足指骨折で外に出ることが少なく家での暮らしで家事の合い間は読書の
時間が多くもてます。ライブラリーでは10冊まで借りることが出来るので、
1度に5~6冊は借りてきます。期間は2週間、読めなかった本は次に返却
の際延長で借りてくることもあります。
居間、寝室、また医院などでの待合時間用にと別々の本を読みます。1冊
を通してと言うのでなく、2~3冊は同時にです。方や小説、方やエッセーと
ジャンルは変えての読書です。
この間から2冊の本でしたが、2冊とも裁判員制度を扱った小説でした。
小杉健治氏 著 「家族」
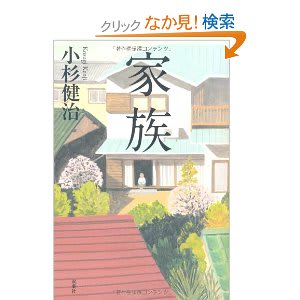
これはホームレスの男が盗み目的で住宅に侵入し、認知症の老女を
殺害したとして逮捕された。男はこの事実を認め、新裁判員制度での裁判
がはじまった。ややサスペンス小説
裁判員のひとり谷口みな子は、自身の経験から、この事件を老女の息子
による嘱託殺人ではないかと疑っていたが・・・・・家族愛を描く、
夏樹静子氏 著 「てのひらのメモ」

広告代理店で働くシングルマザーは、社内でも将来を有望視されている
ディレクターだった。彼女には喘息で苦しむ保育園児がいたが、大切な会議
に出席するため子供を家に置いて出社し、死なせてしまう。子供に傷なども
あり、検察は彼女を「保護責任者遺棄致死罪」で起訴。有罪になれば、三年
以上二十年以下の懲役刑となる。
市民から選ばれた裁判員たちは、彼女をどのように裁くかのサスペンス。
裁判員制度は昨年5月から導入されていますがこの制度は昔もあり、
昭和3年に陪審裁判があり戦中まであったそうです。
人が人を裁くことは容易ではないです。
曽野綾子氏 著 「自分の始末」

人生を楽しく畳む知恵!
「自分の始末」の意図するところは、実はたった一つ、
できるだけあらゆる面で他人に迷惑をかけずに静かにこの世を終わる
ことである。
私たちは一瞬一瞬を生きる他はないのだから、その一瞬一瞬をどう
処理するか、私はずっと考えて来た。 新たな希望が湧いてくる!著者









