
表紙にはタイトルの左に、「紫式部ひとり語り」と表記されている。本書は平成23年(2011)10月に刊行されている。
”「紫式部」。名前ばかりは華々しくもてはやされたものだが、その実この私の人生に、どれだけの華やかさがあったものだあろうか。自ら書いた『源氏の物語』の女主人公、紫の上にちなむ呼び名には、とうてい不似合いとしか言えぬ私なのだ。”という冒頭文から始まり、「ふればかく 憂さのみまさる 世を知らで 荒れたる庭に 積もる初雪」(『紫式部集』113番)を載せ、
”私は人生をふりかえる。思えばいろいろなことがあったものだ。記憶が雲のようにいくつも湧いては心をよぎる。
私は思い出を手繰り寄せる。私の人生、それは出会いと別れだった。” (p3)
というページから始まる。
紫式部が己の人生を振り返りひとり語りを始める。『源氏物語』をなぜ書く気になったのか。何を書きたかったのか。中宮彰子のもとに嫌々女房として宮仕えをすることになり、その思いが中宮彰子と接触していく中でどのように変化し、プロフェッショナルな女房として自らが変身して行ったか・・・・・などを語っていく。「一 会者定離 -雲隠れにし夜半の月」からはじまり、「十三 崩御と客死 ーなほこのたびは生かんとぞ思ふ」までの13章に「終章 到達 -憂しと見つつも永らふるかな」で終わる。
一見、紫式部自身が己を回顧する独白体の小説かな・・・・と思うほど、読みやすい文章で記述されている。読み進めて気づき始めたのだが、これは小説ではない。紫式部のひとり語りの中に、『紫式部日記』、『紫式部集』、『源氏物語』を中核にして、様々な史料が巧みに織り込まれていくのだ。一人語りの裏付けとなる根拠が提示されていく。著者は諸史資料のどこをどのように解釈し、紫式部に語らせたかを示していく。語りと根拠が実に巧みに融合されて回顧が進んで行く。
様々な史料とは何か。本文に引用されている文献を最初の3章の範囲から抽出しご紹介してみよう。『栄花物語』『うつほ物語』『古今和歌集』『後撰和歌集』『大和物語』『類聚符宣抄』『日本紀略』『後拾遺和歌集』『今昔物語集』『公卿補任』『古事談』『小右記』『枕草子』『詩経』という具合である。典拠もその都度明示されているのだが、煩わしいとは感じない。逆に、なるほどという納得感が醸成される。うまくひとり語りに取り込まれている。
最後に「あとがき」を読み、ナルホドと思った。冒頭に”人間紫式部の心を、紫式部自身の言葉によってたどる。本書はその試みです。・・・・・本書は、その彼女の偽らぬ「心の伝記」を目指しました。” (p252)と記されている。
『紫式部日記』と『紫式部集』が伝わっている。「これらは紫式部自身の言葉で書かれた、本人による証言。言わば打ち明け話です。それらが最大の資料である以上、それに依って立つ本書も、本人の独白の形をとらなくてはならないと考えたのです」(p252)と意図を明確にしている。そして、「紫式部作を始め平安時代の文学作品、紫式部をめぐる歴史資料、そして国文学・国史学の研究成果によって、再構成した、紫式部の生涯です。ただ、読む際には読み物として楽しんでいただければと思います。紫式部という人物の息遣いや体温を感じていただければ、心から嬉しく思います」と続けている。
著者の意図とその試みは、私には達成されていると感じる。
瀬戸内寂聴訳『源氏物語』と『ビギナーズ・クラシックス日本の古典 紫式部日記』を読んでから本書を読むという順番になったのだけれど、順序が逆だと、また読み進めるときの印象が違うのではないかという気がする。親しみやすさの距離感という意味で・・・。
まず『源氏物語』に関連して、著者が紫式部に語らせていることの一端をサンプリングで引用しふれておこう。
*私は後になって書いた『源氏の物語』で、登場人物たちを次々に私と同じ目に遭わせた。・・・・光源氏の最初の正妻の息子に至っては、生後数日で母に死なれる。さてどう生きる。母がいなくてあなたたちはどう生きるのだ。 p5-9
*それでも私は、漢学を手放さずにきた。漢学を捨てることは心の骨肉を捨てることであり、私にはあり得なかった。私が漢学素養をひけらかさないと言いながら『源氏の物語』にはふんだんに盛り込むのは、どうしてもそれを抑えられないからだ。『源氏の物語』は、何よりも私自身のために、私が生きる力を取り戻すために創った世界だ。現実を忘れて没頭するために、私は自分の持てる知識と情熱をすべて注ぎ込んだ。そこだけは人の目を遠慮しない世界だと決めて書いた。そうすると自ずと、設定にも文章にも夥しいほど漢学素養が現れた。それが私なのだ。自分の心の世界では、私はどこまでものびのびと私らしくいられた。 p125
*私はなんと様々な境遇の女を見てきたことだろうか。・・・皆の顔が脳裏に浮かぶ。・・・・誰にも心があった。私はそんな女たちの心を、せめて私の『源氏の物語』の中では言葉と声に響かせたい、そう思ったのだ。 p190
*もとはといえば、夫の宣孝の死に遭い現実から目をそむけた私が必死で作り上げた、空中楼閣だ。だがそこに私が投じた、この国の歴史、中国の歴史、古今を超えて実在した多くの人々の情念。欲望、悲嘆、絶望、執着、そう、仏の言う「煩悩」というもの。それらは物語の中に、現実世界に匹敵する世界を造ってしまったのではなかったか。ゆくゆくは現実世界が『源氏の物語』をなぞることもあるかもしれない。『源氏の物語』は、読む人の心の中で、もうひとつの現実世界になってゆく、そうしたとてつもない物語なのかもしれない。 p225
次にもう一つ、この「紫式部ひとり語り」で特徴的なことは、「世」と「身」と「心」という識別をして、自己分析させている点だと思う。
「世」は、まず日常語での「人の一生や寿命を意味する言葉」、限られたある時間ととらえる。さらに別の意味として、”「世の中」や「世間」、また人と人との関係をいう「世」”(p65)ととらえている。
それに「身」を対置する。「身」を「世」に阻まれる私、「世」(世間)という存在に飲み込まれた私、いつかは死ぬ運命を負う私ととらえる。”「身」は「世」という現実から決して逃れられない。現実の中で生きているのだから。現実を振り切って外に出ることは不可能だ。人はそうしたものなのだ。それがどんなに厭わしい現実でも、夢だと言って逃げる訳にはいかないのだ」(p66)と。
その上で、己が忘れていたこととして、己は「身」であるだけではなく、「心」という部分をもつ存在であることに気づく。”心こそが、私を絶望させたり泣かせたりしていたのだ。その時はそれが「身」の現実を拒んでいたからだ。でも心には、現実と向き合い、それに寄り添うという在り方もあったのだ。”と。
女房として宮仕えしながら、この「世」において、「身」と「心」を内省していく紫式部の思いが語られて行く。そして、それが『源氏の物語』にも投影されていると語っている。
この観点を考えると、『源氏物語』の読み方にまた広がりがでてくる思いがする。描き出させた世界の登場人物たちがどのような思いで生きているかというだけで考えるに留めない。紫式部がどのような意図でその人物を物語に登場させ、その人物にどのような思いを投影しているかという次元を介在させて読み解くという視点がありそうだ。
『源氏物語』を読み解いて行く上で、またその著者紫式部に思いを馳せる上で、楽しみながら読める有益な一書だと思う。
ご一読ありがとうございます。
こちらもお読みいただけるとうれしいです。
『ビギナーズ・クラシックス 日本の古典 紫式部日記』 角川ソフィア文庫
『平安人の心で「源氏物語」を読む』 山本淳子 朝日選書
『枕草子のたくらみ』 山本淳子 朝日新聞出版
”「紫式部」。名前ばかりは華々しくもてはやされたものだが、その実この私の人生に、どれだけの華やかさがあったものだあろうか。自ら書いた『源氏の物語』の女主人公、紫の上にちなむ呼び名には、とうてい不似合いとしか言えぬ私なのだ。”という冒頭文から始まり、「ふればかく 憂さのみまさる 世を知らで 荒れたる庭に 積もる初雪」(『紫式部集』113番)を載せ、
”私は人生をふりかえる。思えばいろいろなことがあったものだ。記憶が雲のようにいくつも湧いては心をよぎる。
私は思い出を手繰り寄せる。私の人生、それは出会いと別れだった。” (p3)
というページから始まる。
紫式部が己の人生を振り返りひとり語りを始める。『源氏物語』をなぜ書く気になったのか。何を書きたかったのか。中宮彰子のもとに嫌々女房として宮仕えをすることになり、その思いが中宮彰子と接触していく中でどのように変化し、プロフェッショナルな女房として自らが変身して行ったか・・・・・などを語っていく。「一 会者定離 -雲隠れにし夜半の月」からはじまり、「十三 崩御と客死 ーなほこのたびは生かんとぞ思ふ」までの13章に「終章 到達 -憂しと見つつも永らふるかな」で終わる。
一見、紫式部自身が己を回顧する独白体の小説かな・・・・と思うほど、読みやすい文章で記述されている。読み進めて気づき始めたのだが、これは小説ではない。紫式部のひとり語りの中に、『紫式部日記』、『紫式部集』、『源氏物語』を中核にして、様々な史料が巧みに織り込まれていくのだ。一人語りの裏付けとなる根拠が提示されていく。著者は諸史資料のどこをどのように解釈し、紫式部に語らせたかを示していく。語りと根拠が実に巧みに融合されて回顧が進んで行く。
様々な史料とは何か。本文に引用されている文献を最初の3章の範囲から抽出しご紹介してみよう。『栄花物語』『うつほ物語』『古今和歌集』『後撰和歌集』『大和物語』『類聚符宣抄』『日本紀略』『後拾遺和歌集』『今昔物語集』『公卿補任』『古事談』『小右記』『枕草子』『詩経』という具合である。典拠もその都度明示されているのだが、煩わしいとは感じない。逆に、なるほどという納得感が醸成される。うまくひとり語りに取り込まれている。
最後に「あとがき」を読み、ナルホドと思った。冒頭に”人間紫式部の心を、紫式部自身の言葉によってたどる。本書はその試みです。・・・・・本書は、その彼女の偽らぬ「心の伝記」を目指しました。” (p252)と記されている。
『紫式部日記』と『紫式部集』が伝わっている。「これらは紫式部自身の言葉で書かれた、本人による証言。言わば打ち明け話です。それらが最大の資料である以上、それに依って立つ本書も、本人の独白の形をとらなくてはならないと考えたのです」(p252)と意図を明確にしている。そして、「紫式部作を始め平安時代の文学作品、紫式部をめぐる歴史資料、そして国文学・国史学の研究成果によって、再構成した、紫式部の生涯です。ただ、読む際には読み物として楽しんでいただければと思います。紫式部という人物の息遣いや体温を感じていただければ、心から嬉しく思います」と続けている。
著者の意図とその試みは、私には達成されていると感じる。
瀬戸内寂聴訳『源氏物語』と『ビギナーズ・クラシックス日本の古典 紫式部日記』を読んでから本書を読むという順番になったのだけれど、順序が逆だと、また読み進めるときの印象が違うのではないかという気がする。親しみやすさの距離感という意味で・・・。
まず『源氏物語』に関連して、著者が紫式部に語らせていることの一端をサンプリングで引用しふれておこう。
*私は後になって書いた『源氏の物語』で、登場人物たちを次々に私と同じ目に遭わせた。・・・・光源氏の最初の正妻の息子に至っては、生後数日で母に死なれる。さてどう生きる。母がいなくてあなたたちはどう生きるのだ。 p5-9
*それでも私は、漢学を手放さずにきた。漢学を捨てることは心の骨肉を捨てることであり、私にはあり得なかった。私が漢学素養をひけらかさないと言いながら『源氏の物語』にはふんだんに盛り込むのは、どうしてもそれを抑えられないからだ。『源氏の物語』は、何よりも私自身のために、私が生きる力を取り戻すために創った世界だ。現実を忘れて没頭するために、私は自分の持てる知識と情熱をすべて注ぎ込んだ。そこだけは人の目を遠慮しない世界だと決めて書いた。そうすると自ずと、設定にも文章にも夥しいほど漢学素養が現れた。それが私なのだ。自分の心の世界では、私はどこまでものびのびと私らしくいられた。 p125
*私はなんと様々な境遇の女を見てきたことだろうか。・・・皆の顔が脳裏に浮かぶ。・・・・誰にも心があった。私はそんな女たちの心を、せめて私の『源氏の物語』の中では言葉と声に響かせたい、そう思ったのだ。 p190
*もとはといえば、夫の宣孝の死に遭い現実から目をそむけた私が必死で作り上げた、空中楼閣だ。だがそこに私が投じた、この国の歴史、中国の歴史、古今を超えて実在した多くの人々の情念。欲望、悲嘆、絶望、執着、そう、仏の言う「煩悩」というもの。それらは物語の中に、現実世界に匹敵する世界を造ってしまったのではなかったか。ゆくゆくは現実世界が『源氏の物語』をなぞることもあるかもしれない。『源氏の物語』は、読む人の心の中で、もうひとつの現実世界になってゆく、そうしたとてつもない物語なのかもしれない。 p225
次にもう一つ、この「紫式部ひとり語り」で特徴的なことは、「世」と「身」と「心」という識別をして、自己分析させている点だと思う。
「世」は、まず日常語での「人の一生や寿命を意味する言葉」、限られたある時間ととらえる。さらに別の意味として、”「世の中」や「世間」、また人と人との関係をいう「世」”(p65)ととらえている。
それに「身」を対置する。「身」を「世」に阻まれる私、「世」(世間)という存在に飲み込まれた私、いつかは死ぬ運命を負う私ととらえる。”「身」は「世」という現実から決して逃れられない。現実の中で生きているのだから。現実を振り切って外に出ることは不可能だ。人はそうしたものなのだ。それがどんなに厭わしい現実でも、夢だと言って逃げる訳にはいかないのだ」(p66)と。
その上で、己が忘れていたこととして、己は「身」であるだけではなく、「心」という部分をもつ存在であることに気づく。”心こそが、私を絶望させたり泣かせたりしていたのだ。その時はそれが「身」の現実を拒んでいたからだ。でも心には、現実と向き合い、それに寄り添うという在り方もあったのだ。”と。
女房として宮仕えしながら、この「世」において、「身」と「心」を内省していく紫式部の思いが語られて行く。そして、それが『源氏の物語』にも投影されていると語っている。
この観点を考えると、『源氏物語』の読み方にまた広がりがでてくる思いがする。描き出させた世界の登場人物たちがどのような思いで生きているかというだけで考えるに留めない。紫式部がどのような意図でその人物を物語に登場させ、その人物にどのような思いを投影しているかという次元を介在させて読み解くという視点がありそうだ。
『源氏物語』を読み解いて行く上で、またその著者紫式部に思いを馳せる上で、楽しみながら読める有益な一書だと思う。
ご一読ありがとうございます。
こちらもお読みいただけるとうれしいです。
『ビギナーズ・クラシックス 日本の古典 紫式部日記』 角川ソフィア文庫
『平安人の心で「源氏物語」を読む』 山本淳子 朝日選書
『枕草子のたくらみ』 山本淳子 朝日新聞出版















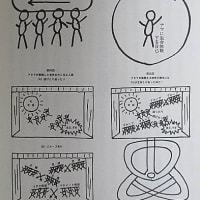




ブログ記事で文庫本の表紙を拝見し、文庫のタイトルが、副題に使われていたフレーズになったのかと思っていました。やはり・・・ですね。
著者の本で最初に読んだのは、『源氏物語の時代 一条天皇と后たちのものがたり』(朝日新聞社、2008年第5刷)でした。ブログを書き始める前です。
私は何年か後にこの単行本を購入した後、書棚に眠らせていたのです。
源氏関連では様々な著者の眠っている本がいろいろありますので、ぼちぼち読み継いでいこうと思っています。
おっしゃる通り、一人称での語りゆえに興味深く読ませるのでしょうね。
この本がタイトルを変えて文庫化された『紫式部ひとり語り』(角川ソフィア文庫)を読み始めました。実は同一本だと気づかずに買い求めたのです。
紫式部に語らせるというのが、ミソでしょうね。説得力が増しますし。いや、著者の研究成果が十分反映されているのでしょうから、もともと説得力はあると思いますが。読みやすいことも魅力だと思います。