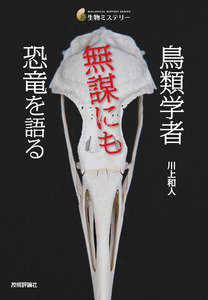『Gene Mapper -full build-』 藤井太洋 (ハヤカワ文庫JA)
電子書籍でNo.1になった話題作の改訂増補版。サブタイトルも、電子版の“core build”に対し、“full build”となっている。
うちの業界だと、フルビルドはゼロからシステム全体をコンパイルし直すという意味で、対義語は差分ビルドとか、部分ビルド。つまり、前回バージョンのオブジェクトを使用しないで作り直したということか。ソースコードが著者の頭の中身で、そこからfull buildされたのが今回のバージョンということ?
まぁ、コアビルドとの対比からすると、システム全体の大きさの違いのことを言っているにすぎないのではないかと思うけれど。でもコアビルドだと、周辺要素のないコアだけって感じで、それじゃシステムは動かないんだけどね。
題材としてバイオテクノロジー、バイオハザードを扱ってはいるが、そのサブタイトルから想像できるように、コンピュータ関係も多くネタが仕込まれている。実際、ウィルスやジーンデザインに関する記述も、イメージ的にはコンピュータウィルスやプログラミングのイメージに近い気がする。
生命活動にインスパイアされた数値計算による最適化手法のひとつであるGenetic Algorithmを、実際にジーンデザインへ適用するという円環を完結させるかのようなネタは笑いどころなのだろうか。
2038年問題の責任について20世紀の技術者を糾弾するジャーナリストというネタも出てくるが、これも笑うところかどうなのかよくわからずに困った。というか、2038年問題の前に2036年問題が来るはずだが、そっちはいいのか。舞台は2037年なんだから、2036年問題はちゃんと乗り越えたんだろうに。それとも、Windowsなんてレガシーなシステムはもはや存在しない設定?
コンピューター関連の大ネタである“ロックアウト”、検索エンジンの暴走(検索結果を吸い上げて、別な情報で上書きする?)によってインターネットが閉鎖され、トルゥーネットが開始されたという設定も、掘ればいろいろなネタは出てきそうな気配なのだけれど、単純に情報の断絶という現象の理由付けにとどまっている。これは、1995年より前の情報がインターネットでは極端に検索しづらい、というか、インターネット上、さらには電子上にも存在しないという、現在もざらにある問題とまったく同じではないかと思う。
設定の矛盾とか不備とかではなく、掘り下げが足りなくって残念な感じ。インターネット上の情報が有用と無用に振り分けられ、有用と判断された情報のみがトルゥーネットに引き継がれたというのはあきらかな情報検閲であり、ネット側から見ると大敗北であり、大きな損失だと思うんだけどな。それこそ、バイオハザードの問題に匹敵するくらいの一大事。
で、最終的にバイオハザードの原因はバイオ兵器の流出で、事件の終息方法はオープンソース化という、コンピュータ業界のネタに戻ってくるわけで、それならばやっぱりインターネット閉鎖問題をもうちょっとクローズアップしてもよかったんじゃないかと思う。
要するに、バイオハザードはとっかかりなだけで、徹頭徹尾、コンピュータの話だったということ。なので、IT関係の仕事をしているひとには興味深く読める小説なのだと思う。
なんだか貶してるだけのように読めるかもしれないが、スピーディーな展開で飽きさせない物語は充分におもしろい。そして、オープンソースの力を信じるという力強いメッセージも、特に情報系の技術者にとっては感動的なんじゃないか。