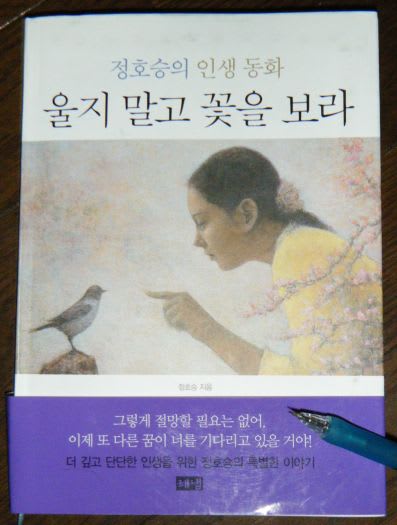
ハリネズミの初恋
明るい昼間の樫の木の森の中を散歩するのが好きな1匹のハリネズミがいました。ハリネズミは夜行性で主に昼は木の根や岩の隙間に隠れて、夜になるとそろそろ動き回るのだが、「コスミ」と呼ばれているハリネズミはそうではありませんでした。
コスミはいつも友達がみな寝ている昼になるとひとりで起きだして小さな耳をぴょこんとたてて鳥の歌を聴きながら樫の木の森の中を散歩しました。そして友達が伸びをしてそろそろ活動する夜になるとひとり平たい石の下に入っていって眠りました。
「コスミ、お前は、おまえ自身をよく知らなければならない。お前はハリネズミだ。ハリネズミはハリネズミらしく生きなければならないのだ。お前はなぜ私たちがみな寝ている昼になると起きて、私たちが起きて仕事をする夜になれば寝るんだ。お前本当にそうやっていてもいいのか。」
「ごめんなさい。だけど、私は夜が嫌いです。明るい風が吹いて、お日様があって、日差しがまぶしい明るい昼が好きです。」
「夜にも月がある。月明かりもあり、それだけではないことを知っているか。星もあって、星明りもある。夜空に落ちる流れ星を見るとどれだけ美しいかわからない。」
「それはそうでしょう。だけど、私は暗いのが嫌いです。薄暗い夜は本当に嫌だ。」
コスミは友達の言葉に少しも耳を傾けず日が昇ると起きて森の中を散歩した。その度にコスミは自分が本当に幸福なハリネズミだという思いがした。
そんなある日のことだった。コスミは森の中のひっそりした小道で1匹のシマリスに会った。ところが、本当に不思議なことだった。朝の散歩道で時々会うには会ったシマリスだったが、コスミはその日に限ってシマリスを見るなり急に胸がどきどき走り始めた。すばやく木の上に這い上がって止まってコスミを見つめるシマリスのキラキラした目に全身がみな解けてしまうようだった。
コスミは勇気を出して黙ってシマリスに近づいて行き言葉をかけた。
「僕は、コスミって言うんだ。君名前はなんていうの。」
「私はタラミよ。」
「タラミ、僕も君のように木の上に上がって行きたい。だけどどうすれば上がっていけるの。その方法をちょっと教えてくれないか。」
「それは教えたからといってできることじゃないわ。自分が努力しなければならないことよ。」
タラミはコスミを見下ろしてにっこりと微笑んだ。
コスミはタラミの近くに行きたくて何とかして気の上に這い上がろうと努力した。しかし、どんなに努力をしてもその都度木から落ちるだけ、どうしても木の上に這い上がることができなかった。
だが、コスミはあきらめなかった。転げ落ちてもまた転げ落ちても一生懸命木の上に這い上がり、日が暮れるころになってやっと木の少し上のほうに上がることができた。しかしすでにタラミは家に帰ってしまいどこにも姿が見えなかった。
その晩、平たい岩の下に帰ってきたコスミは眠れなかった。岩の隙間から見える夜空の星だけをうつろに眺めていた。星という星が全部樫の木の枝の間に見えるタラミの澄んだ黒い瞳のようだった。
翌日の朝、コスミはタラミに会うためにいつもより早く起きて樫の木の森へ行きました。タラミも夜中、コスミに会いたかったのかいつもより早く森に来ていました。コスミは限りなく胸が躍った。コスミがタラミの魅力的な尾を見る度に顔が赤くした。
コスミとタラミはこうやって朝早く森の中のひっそりした道で会って、また会いました。二人が会うたびごとに森はいつも朝露に濡れており、タラミはいつも日差しに光る朝露のようでした。コスミはそんなタラミを眺めていることだけでも幸せでした。
そんなある日、森の中に静かに広がる霧を眺めていたコスミはずっと胸の深くに隠しておいた言葉を言ってしまいました。
「タラミ、僕は絶対にこの言葉を言わないでおこうと思ったけれど、、、僕は君を愛している。」
すると、タラミがすばやく木の下に下りてきながら言いました。
「コスミ、私もあなたを愛しているわ。」
「本当に。」
「もちろん、私は、あなたがその言葉を言ってくれるのをどれだけ待っていたかわからないわ。」
タラミは少しのためらいもなくコスミの胸に飛び込んだ。コスミはあまりにもうれしくて残っている力いっぱい、力の限りタラミを抱きしめた。すると、急に、タラミが「キャァ。離して。離して頂戴。」と悲鳴を上げた。
コスミが驚いて腕の力を抜いた。するとタラミがすばやくコスミの胸から離れて叫んだ。
「あなたの体には何でそんなにとげが多いの。痛くて死ぬところだったわ。」
タラミはすごく怒った顔だった。
「僕たちハリネズミは皆こうだ。僕だけとげだらけなんじゃない。」
「そうならばそうだと前もって話してくれないと。私はとげがあるといやだわ。あなたを愛さないわ。あなたの体にとげがあるとは、本当に思わなかった。」
「タラミ、そう言わないで。僕が誰かを愛したのは君が始めてだ。」
「だけどいや。体にとげがあるかぎり、私はあなたを愛さないわ。私はあなたを抱きしめることも、抱かれることもできない。」
コスミは呆然とした。愛を手にした瞬間急に愛を失ったという考えがして呆然としてタラミだけを見つめた。
「タラミ、愛はそんなものじゃない。私たちが誰かを愛するということはあるがままを愛するという意味だ。僕が少しだめだとしても大目に見てくれることを願う。」
「いいえ、私はあなたのとげがとても痛いの。あなたが少しでも私を愛しているならばこの機会にとげをなくしてしまえばいいわ。」
「とげを、なくせだって。」
「そうよ。愛していたらの話だけど。」
「それは僕にとってはあまりにも無理な要求だ。とげがなくなると僕は死ぬかも知れない。僕が死ねば僕に会えなくなるじゃないか。」
「だけど、そのとげ、いや。」
「タラミ、お願いだ。今あるがままの僕を愛してくれ。」
コスミはやっと気持ちを落ち着けてたどたどしく言葉を続けた。だが、タラミは「とげをなくせなかったら私に会おうと思わないで。」と叫んで後ろも振り向かないでちょこちょこと木の上に上がっていってしまいました。
コスミは悲しかった。
「君の背中にある黒い5本の線あるじゃないか。ある時は僕もその黒い線が見るのもいやだった時があった。だけど、僕はそれのせいで君を嫌いにはならなかった。」
コスミは栗のイガのような体を身を縮めたままタラミが消えた樫の木を見つめて一人で泣き続けました。
コスミはタラミに会うことができなかった。タラミはコスミが樫の木の森の中に来るとどこか遠くへ走っていってしまったりした。
コスミはタラミに会いたくて耐えられなかった。愛がこのように苦しいことだとは思わなかった子隅は毎日涙を流して時間を送った。
そうしていて、ある日よくよく考えた。
「僕がタラミを愛している限りどうすることもできない。僕の体のとげをなくすしか。タラミは僕を愛しながらもとげのせいで僕から離れていっただけだ。僕の体のとげがなくなれば今でも私たちは毎日互いに会って熱く愛しているはずだ。僕はタラミのために体のとげをなくさなければならない、、、」
コスミはその日からとげをなくすために岩の角に体をこすりつけ始めました。1回体をこするたびに全身の血が流れて手足が震えていくようでした。ですが、コスミはタラミを思って我慢して繰り返しました。
「コスミ、お前一体これは何の真似だ。」
「とげをなくすんだ。」
「何。」
「わからなくも、いい。」
「お前、こんなことしていて間違ったら死ぬぞ。とげは我々の生命線のようなものだ。」
「僕も知っているよ。だけどこうするしかないんだ。」
何日も友達が切なく言ってもコスミは聞く振りもしませんでした。
結局コスミは岩ひとつを血で赤く染めてからだのとげを全部なくすことができました。
コスミはそのまま、すぐにタラミを訪ねて言った。
「タラミ、君の言ったとおり体のとげをなくした。」
「何ですって。本当なの。」
「そうだ。僕は君のためならば何だってやることができる。僕を一度抱きしめてみて。もうとげがない。大丈夫だ。」
タラミは驚かないわけにはいかなかった。とげのないコスミはかわいそうにも全身血まみれだった。
タラミはすぐに走ってきてコスミをぎゅっと抱きしめてやりながら言った。
「コスミ、ごめんね。私が悪かったわ。私はあなたが本当にそうするとは思わなかった。許して頂戴。」
タラミはコスミにとげをなくせと言ったことを後悔した。コスミをこのように苦しめた自分を恨んだ。
「コスミ、ごめんね。二度とあんなこと言わないわ。」
「いや。大丈夫だ。僕はこのままで幸せだ。」
愛するタラミの胸に抱かれたコスミは本当に幸せだった。まるで暖かい母の胸に抱かれているようだった。このまま時間が流れないで永遠にとまってしまえばと思った。
どころが、コスミのそんな幸福はごくわずかでした。急にタラミを片思いしていた野ねずみが現れてコスミに攻撃して来ました。
「恐れ多くもハリネズミのくせにシマリスを愛するとは。失せろ。」
こうこうと光る目でコスミを睨む黒い野ねずみの目は恐ろしかった。
「とっとと、失せろ。」
コスミは野ねずみの聞く振りもせず、タラミをぎゅっと抱きしめた。すると、野ねずみが鋭い両足を上げてコスミに攻撃してきた。
コスミも両足を上げてのねずみに飛び掛った。
「やめて。」
タラミが足を踏んで叫んだが争いは簡単には終わらなかった。互いにもつれて地を転がって、時には野ねずみの鋭い歯に噛まれてコスミの体はますます血だらけになった。
体にとげがなくなったコスミは野ねずみの攻撃を防ぐ手立てがなかった。コスミはそのまま愛するタラミを野ねずみに奪われてしまった。
「タラミのためにとげまでなくしたのに野ねずみに奪われるとは。」
コスミはあまりにも悔しくて悲しく泣きました。
何日か樫の木の森の中からコスミの鳴き声が絶えませんでした。
しかし、コスミの体の中から再びとげが少しずつ生えてきたという事実を知っているものは誰もいなかった。
当のコスミ自身さえも、、、。
















