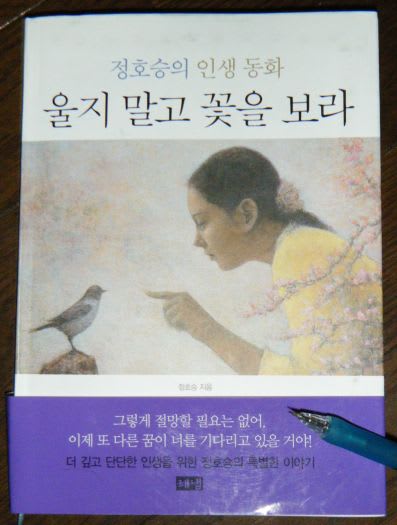待つことのない愛はない
私はヨンジ池です。私は今、釈迦塔と多宝塔を作った阿斯達の妻、阿斯女の話を皆さんに改めて聞かせる必要がある。阿斯女を不幸にしたのは他人の不幸を喜ぶ人々の単純な利己心の現れであるだけ、阿斯女は事実、釈迦塔の影が映るまで待つことができなくて池に身を投げて死んだのではない。待つことのない愛がないという事を、本当に愛には本当に待つことが伴うということを阿斯女もよく知っていた。話は私が始めて阿斯女に会った日からするのがいいようだ。
その日、私は昨夜降った恵みの雨で池が一杯になって心が満たされていた。田んぼに種籾を巻く時が過ぎたのに雨が降らず足をとんとん踏んで心配していた村の人々も一晩ずっと雨が降って限りなく喜んでいた。
ところがその日の夕方ごろだった。村の人々が田んぼに種籾を蒔いて皆家に帰る準備をしている時だった。遠くあぜ道に沿って一人の女性が風呂敷包みを持ってつまづきながら歩いてくるのが見えた。
私ははじめは隣の村の人かと思ってただ黙って見過ごしたが、近くに来るのを見ると見たことのない何と若い女性だった。彼女は長い道のりを来たのか、服は土だらけで今にも倒れるようだった。
「あの、ちょっとお伺いします。この池の他に他の池はありませんか。」
女性は田んぼの出口を塞いでいたキム老人に注意深く近づいて声をかけた。
「そうだ。どうしたのだ。」
「仏国寺の門番の話では、南側に10里離れた所に池がひとつあるといったので訪ねて来ましたが、ここでいいのでしょうか。」
「そうだが、どこから来たのだ。」
「私は、百済の首都、扶餘から来ました。私の夫が今、仏国寺で首長をしているのですが、会いにきたのですが会うことができなくてここに来ました。塔が完成したら池に塔の影が映るというからです。塔ひとつは出来上がって今、池に映ると言います。」
「あ、そうか。あなたはあの有名な首長の阿斯達の奥さんかい。」
「そうです。阿斯女といいます。」
「ほほ、夫を訪ねてこんな遠くまで一人で来たのだね。しっかりしているね。それで、なぜ、夫に会えなかったんだ。」
「女は不浄だといって寺に入ることはできないといいました。」
「それは、それは、長い道のりと苦労してきたのに、、、それならここで待つしかないね。日が明るくなる頃にはここのこの池に多宝塔の影が映るよ。今は日が暮れ始めたので塔の影が消えました。明日の朝日が昇るとまた見えます。」
「はい、教えてくださりありがとうございました。」
女性は頭を下げてキム老人に挨拶をして、またつまづきながら歩いて行った。すると今度はキム老人が割きに女性に声をかけた。
「ちょっと。今、その体でどこへ行くのですか。見ると、どこにも行くあてもないようだが。体も悪いようだし、、」
「池を一回りして見て、池のほとりでどこか眠ろうかと思います。」
「だめです。その体で、本当に病気になりますよ。」
「いいえ。もう気温も暖かくなりましたし、野宿で眠れるようです。」
「いや、そうしたら間違いなく病気になる。春の寒さが人を捕まえるという言葉もある。花嵐に風邪をひく人も一人二人ではない。さあ、うちの家に行きましょう。ちょうど家は皆嫁に行ったり婿になったりして、末の娘が一人残っているから、一緒にいればいい。門番の話通り釈迦塔が完成すればその塔の影も映るだろう。その時まで家で過ごして待つようにしなさい。」
「いいえ、お言葉はありがたいのですが、大丈夫です。」
女性はそう言いながらもキム老人の後ろに従った。キム老人は町内でも豆ひとつでも分けあって食べるほどのよい心を持っているといううわさの出る人だった。
私はその女性が阿斯達の妻だという事実に驚かないではいられなかった。朝が来るたびに水面に長く影が映る多宝塔、風に水面が揺れると度にたくさんの花房が咲くように美しくゆれる多宝塔、そんな多宝塔を作った、首長の妻がまさにその人だったとは。
私はその長い道のりを訪ねてきたその女性が夫にも会うことができず追い出されてしまったという事実がかわいそうだったが心の中ではこっそりとうれしい思いさえした。
阿斯女はその日からキム老人の家で暮らした。毎日のように一日も欠かすことなく日が明ける前に私を訪ねてきて釈迦塔の影が映ることだけを待った。
しかし、夏が過ぎ、秋が来ても釈迦塔の影は映らなかった。肉をえぐれるような風が吹き私がカチカチに凍る冬が来ても釈迦塔の影は映らなかった。
阿斯女は虚しい日を涙で歳月を送った。ある時には多宝塔の影を釈迦塔の影だと思って喜んでみたものの、すぐに塔の影がひとつだけだというのを知ってもっと悲しくなく時もあった。
「池さん、池さん。一日も早く釈迦塔の影を映してください。どうか私の願いを聞いてください。」
阿斯女が私にこんな言葉をする時には私が何か大きな間違いでも犯したようで心が痛かった。事実私も釈迦塔の影が一日でも早く映ることを切実に願っていたが、ただ待っているしか方法がなかった。
「阿斯女さん、もう少し我慢して待ってください。我慢して待っていればいつかは釈迦塔の影が映る日があります。」
阿斯女の心を慰めるために私がこんな言葉、一言でも言うと、阿斯女は「その日がいつごろですか。」と言ってまた涙を流すだけでした。
「あ、いつ再び阿斯達にあることができるのか。」
阿斯女が吐き出すため息の音は毎日トハム山に響き私に響きました。阿斯女の体は日を重ねるごとにやつれていきました。涙で夜を明かす日ももっと多くなりました。しかし、どんなに体がつらくても阿斯女が私を訪ねてこない日はただの一日もなかった。ある日はトハム山に向って泣いて疲れて倒れて起き上がることができない日もあった。
そんな阿斯女を見かねてキム老人が仏国寺に村の人を送ってただ一度でも阿斯女を中に入れてくれと頼んでみました。しかしそれは当てのないことでした。ならば、阿斯達だけでも仏国寺の門の外に一度出てくるようにしてくれと頼んでみました。しかし、それもまた釈迦塔が完成されるまでは決して許されないことでした。
阿斯女を本当の娘のように思っているキム老人の心配は大きくなっていった。阿斯女を姉のように思っているキム老人の末娘のプノの心配も大きくなっていった。それにつれて村の人たちの心配もまた大きくなっていった。
だが、誰も阿斯女の悲しみを慰めることはできなかった。村の誰もが阿斯女を心配して慰めたが、待つことに疲れた阿斯女の心が頼れるところはどこにもなかった。
そんな中、1年が過ぎて、また1年が過ぎたある春の始まる頃の日だった。村の人たちは田んぼに水を入れて代掻きをして種籾を捲こうと騒がしかった。あぜを塞いで水門を開き一生懸命仕事をする村の人たちを見ながら私は今年も豊年になることだけを切実に祈っていた。
ところが、まさにその時だった。急に茶ポン、茶ポンと水の音を出して水の中に歩いて入ってくる人がいた。阿斯女だった。村の人たちが皆種まきに出ている間に阿斯女が私の真ん中に走って入ったのだ。
「あなた、あなた。」
阿斯女は大きな声で泣き叫びながら多宝塔の影に向って走って入った。多宝塔の影を釈迦塔だと勘違いして何回か両手で抱きしめようとした。しかし、塔の影だけがばらばらになるだけ阿斯達の姿はどこにも見えなかった。
「阿斯達、阿斯達。」
ひたすら阿斯達を呼ぶ阿斯女の声だけが悲しいだけだった。
「阿斯女や、阿斯女や。」
その時種まきの籠を投げ捨てて阿斯女のほうに走ってきた一人の人がいた。キム老人だった。キム老人の後ろに村の人々がぞろぞろついてきた。阿斯女は阿斯達を呼びながら水の中にだんだん座り込んでいった。
「あれは、あれは、どうしよう。」
「阿斯女や。阿斯女や。」
キム老人は水の中でもがく阿斯女ヲ見て足をとんとん踏んだ。すると、村の中で泳ぎが上手いと評判のチェさんの婿がすぐに飛び込んで阿斯女を救い出した。チェさんの婿がいなかったら阿斯女歯そのまま死んでいただろう。
阿斯女はそのままキム老人の家に背負われて行き、寝床から起き上がることができなった。
一時はまるで死に行く人のように食べたものをすべて吐いて息遣いが細くなったりもした。しかし、キム老人とプノの真心があまりにも懇切で田んぼに稲がすくすく育つ夏の初めには寝床から起き上がれるようになった。
村の人々は阿斯女が起き上がれるようになると皆自分のことのように喜んでやった。
「これからは、我慢して待っていれば、いつか会える日があるから。」
「そうだ、待たなけりゃ。元々人は待ちながら生きるものだ。」
「そうだ、そうだ。もう、死ぬ勇気で生きなきゃ。」
村の人たちは阿斯女に会うたびに一言ずつ暖かい慰めの言葉をかけた。その度ごとに阿斯女は恥ずかしく耐えることができなかった。阿斯女はやっと自分の間違いを大きく悟ることができた。
「プノさん、人は愛する人がいる限り、死んではならないことを今になって悟りました。」
ある日、庭で蚊取り線香をつけているプノに阿斯女が言いました。心配そうな目で、一時も阿斯女のそばを離れなかったプノでした。
「もう、釈迦塔の影が池の上に映って阿斯達に会える時まで我慢して待つことに心を決めました。もう、私をそんなに心配しないでください。」
「よかったわ。人は愛がある限り生きなければならないと言います。後で阿斯達が訪ねてきた時を一度考えてみてください。その時万一阿斯女が死んでいなかったら阿斯達の心がどんなに悲しいか。おそらく今も、阿斯達は阿斯女が待っていると思って塔を作る仕事に真心のすべてをこめているのです。」
「この間、私はあまりにも愚かでした。許してください。もう、いつまででも待つことができます。」
そしてまた一年が過ぎたある秋の日でした。収穫がちょうど始まったある朝早く。村の子供があぜ道を走ってきて大声で叫びました。
「釈迦塔の影が映っている。」
「池に影が二つだ。」
「え、何だ。何だって。」
「それは本当か。本当。」
その言葉は本当だった。その日の朝タハム山の上に日がぬっと昇ると釈迦塔の影が長く映った。秋の日差しにキラキラ青い水面の上に二つの塔の影が並んで見え隠れしていた。
私はその時どんなに胸が躍ったかわからない。私はその時稲の穂を持って私のほうに走ってくる阿斯女を見た。阿斯女の目からはいつの間にか澄んだ涙が流れていた。
その後、人々は私をヨンジ池と呼んだ。阿斯達と阿斯女は故郷の扶餘に帰らないでここで暮らしました。