
今年は彗星の当たり年だそうで春先にはパンスターズ彗星が太陽系に来てましたね。
そのときは何とか観たいと思ってがんばってみたのですが、わずか2,3回しか、その姿を見ることが出来ませんでした。一応、写真にもそれらしきものを収めることが出来たのですが納得の行く物ではありませんでした。
その時の撮影機材はデジタル一眼に200mm f4.5の望遠レンズでした。
パンスターズ彗星は前評判ほどは明るくならず、観望と撮影には苦労しました。
そこで今度のアイソン彗星は前回の失敗をふまえて、磐石の態勢で望むことにしました。
まずは敵を良く知らなければ攻略できませんので、天文雑誌の特集号を購入。
その雑誌は以下のもの。

とりあえずアイソン彗星に関する知識を一夜漬けで勉強します。
この雑誌にはアイソン彗星の月日ごとの軌跡が載っている星座盤が付録で付いてきます。
この星座盤があれば彗星の見えるおおよその位置を知ることが出来ます。
さらに良いものを見つけました。スマートフォン向けのアプリです。
光学器メーカーのビクセンではアイソン彗星の日付と時間ごとに詳細な位置がわかるアプリを公開していました。
地上からの高度と方角が解るアプリでコメットブックというものです。
アンドロイド版とアイフォン版があります。無料でダウンロードできます。
自分の持っているスマホはアンドロイドなのでgoogle playストア経由でインストールしました。
そのアプリを起動すると次の画面になります。

画面の下に日付と時間のスライドバーがあります。初期設定で当該地域を設定した後、日付と時間を調整しますと高度と方角が出るようになっています。
この画面の例では11月6日、05;06時には方位が117.7度、高度が32.9度の位置に彗星が見えることになります。
この情報をどのように活用するのかは次の器具を使用します。

これまたビクセンで販売しているポーラメーターと言うものです。
これは元々その名が示すように北極軸を簡単に導き出すための道具なのです。
器具の上面には方位磁石の盤面と水準器があります。その側面には角度を示す目盛が刻まれています。


この器具の側面の目盛板の裏側にはつまみがあって緩めると角度の目盛版を可動させることが出来ます。

そしてこれはカメラのアクセサリーシューにはさんで固定出来るようになっています。
カメラに取り付けし、そのカメラを望遠鏡に取り付けて見ました。

高度目盛を32.9度に固定して器具上面の水準器の気泡が中心に来るように望遠鏡の仰角を調整します。
さらにポーラメーター上面の方位磁石の目盛を117.7度になるように望遠鏡の架台を水平方向に可動させると、望遠鏡の光軸は彗星の方角を向くことになります。
これで万全なのですが、一つ心配なことがあります。
それはアイソン彗星がカメラの撮影素子に感光するほどに充分に明るくなるのか、と言うことです。
望遠鏡の接眼レンズの代わりにデジタル一眼カメラをつけているのですから、カメラの撮影素子の感光できないぐらいの明るさではその姿を捉えることが出来ません。
肉眼に拠る観望では接眼レンズを換えてやれば何とか目視は可能です。
その為にはこのポーラメーターを望遠鏡そのものに付ける工夫が必要となります。
そうすれば目視で対象を捉えた後、接眼レンズをカメラに取り替えて撮影が出来ることになります。
もうひと工夫が必要ですね。
それに役立ついいものを見つけましたが、それについてはまた、後日。
 にほんブログ村
にほんブログ村
そのときは何とか観たいと思ってがんばってみたのですが、わずか2,3回しか、その姿を見ることが出来ませんでした。一応、写真にもそれらしきものを収めることが出来たのですが納得の行く物ではありませんでした。
その時の撮影機材はデジタル一眼に200mm f4.5の望遠レンズでした。
パンスターズ彗星は前評判ほどは明るくならず、観望と撮影には苦労しました。
そこで今度のアイソン彗星は前回の失敗をふまえて、磐石の態勢で望むことにしました。
まずは敵を良く知らなければ攻略できませんので、天文雑誌の特集号を購入。
その雑誌は以下のもの。

とりあえずアイソン彗星に関する知識を一夜漬けで勉強します。
この雑誌にはアイソン彗星の月日ごとの軌跡が載っている星座盤が付録で付いてきます。
この星座盤があれば彗星の見えるおおよその位置を知ることが出来ます。
さらに良いものを見つけました。スマートフォン向けのアプリです。
光学器メーカーのビクセンではアイソン彗星の日付と時間ごとに詳細な位置がわかるアプリを公開していました。
地上からの高度と方角が解るアプリでコメットブックというものです。
アンドロイド版とアイフォン版があります。無料でダウンロードできます。
自分の持っているスマホはアンドロイドなのでgoogle playストア経由でインストールしました。
そのアプリを起動すると次の画面になります。

画面の下に日付と時間のスライドバーがあります。初期設定で当該地域を設定した後、日付と時間を調整しますと高度と方角が出るようになっています。
この画面の例では11月6日、05;06時には方位が117.7度、高度が32.9度の位置に彗星が見えることになります。
この情報をどのように活用するのかは次の器具を使用します。

これまたビクセンで販売しているポーラメーターと言うものです。
これは元々その名が示すように北極軸を簡単に導き出すための道具なのです。
器具の上面には方位磁石の盤面と水準器があります。その側面には角度を示す目盛が刻まれています。


この器具の側面の目盛板の裏側にはつまみがあって緩めると角度の目盛版を可動させることが出来ます。

そしてこれはカメラのアクセサリーシューにはさんで固定出来るようになっています。
カメラに取り付けし、そのカメラを望遠鏡に取り付けて見ました。

高度目盛を32.9度に固定して器具上面の水準器の気泡が中心に来るように望遠鏡の仰角を調整します。
さらにポーラメーター上面の方位磁石の目盛を117.7度になるように望遠鏡の架台を水平方向に可動させると、望遠鏡の光軸は彗星の方角を向くことになります。
これで万全なのですが、一つ心配なことがあります。
それはアイソン彗星がカメラの撮影素子に感光するほどに充分に明るくなるのか、と言うことです。
望遠鏡の接眼レンズの代わりにデジタル一眼カメラをつけているのですから、カメラの撮影素子の感光できないぐらいの明るさではその姿を捉えることが出来ません。
肉眼に拠る観望では接眼レンズを換えてやれば何とか目視は可能です。
その為にはこのポーラメーターを望遠鏡そのものに付ける工夫が必要となります。
そうすれば目視で対象を捉えた後、接眼レンズをカメラに取り替えて撮影が出来ることになります。
もうひと工夫が必要ですね。
それに役立ついいものを見つけましたが、それについてはまた、後日。



















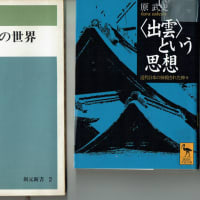








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます