
皆さんは、以下のような問題についてどう考えますか。
数日前、深夜たまたまつけたEテレで、8月17日に行われたサントリーホールのコンサートの模様を放映していました。演奏者はいまや巨匠とも呼ぶべき世界的ピアニスト、マルタ・アルゲリッチと広島交響楽団。曲は、ベートーヴェンのピアノ協奏曲1番。
もう第三楽章も終盤に近い部分だったし、個人的にはアルゲリッチをあまりいいとは思っていないのですが、でもあの軽快で楽しい調子に思わず引き込まれ、貫録を増した彼女の演奏をほんの少し楽しむことができました。曲が終わって会場はやんやの喝采です。
画面が変わり、会場からではなく、局からの説明が入りました。それはアルゲリッチの次の曲とか彼女の演奏実績とかについての説明ではなく、彼女のお嬢さんについての詳しい紹介でした。お嬢さんは、平和活動(NPOでしょうか)をやっているそうです。その彼女がアウシュヴィッツとヒロシマについての詩を作ったので、それを会場で朗読するというのです。
再び画面が変わり、若い男性に続いて可憐な雰囲気のお嬢さんがステージに出てきました。お嬢さんが詩を朗読し始めました。若い男性は通訳でしょうか。聴衆は水を打ったように聞いています。とっさに私はいいようもない不快感を感じ、スイッチを切ってしまいました。もちろん意味を聞きとる以前のことです。
これはひねくれ者の個人的な性分にすぎないかもしれませんが、私は、文化と中途半端な政治的メッセージとを混合したこの種の「あいまいな」イベントが大嫌いです。
たとえばチャリティーコンサートとして売り上げを被災者や難民など、困っている人に寄付するというなら一向にかまいません。しかしこの催しはそれとは違います。一流のホールに世界的ピアニストを招いて一流の演奏を聴かせるという触れ込みで観客を集め、集まったその現場を巧みに利用して「平和活動家」のメッセージを発信する――この企画の中にはずいぶん不純でいいかげんで安っぽい思想がありはしないでしょうか。
アルゲリッチといえば、S席だったらまず二万円は下らないでしょう。それだけの入場料を払って会場に来たお客さんは、95%までは彼女の演奏が聞きたくて集まってきたので、「平和活動」のメッセージなどほんの刺身のつま以下のものとしてしか感じないはずです。
もっとも後で知ったことですが、このコンサートは、初めから「平和の夕べ」と題されていたそうです。演奏会の時期、広島交響楽団との組み合わせという点などと考え合わせると、お客さんの方もそのあたりはもともと織り込み済みではあったのでしょう。ちなみに広島交響楽団は、年一回、広島のフェニックスホールで「平和の夕べ」コンサートを催しているそうですが、楽団の設立趣旨や通常の演奏活動自体は、広島の原爆投下とは何の関係もありません。
いわばこのイベントは、演奏者も観客も善男善女であることを当て込んで仕組まれたもので、ほとんど誰も、アルゲリッチの演奏とそのお嬢さんの詩の朗読行為との間にあるギャップに対して違和感など抱かないのでしょう。
しかし繰り返しますが、私は「善男」ではないので、ここにいくつものおかしな連想ゲームによって成り立っている歪んだ意図を読んでしまいます。私のこの批判的な読みは、けっしてアルゲリッチやそのお嬢さんや、広島交響楽団に対して向けられたものではなく、もっぱらこういう企画を立案して平然としている人、またそれを公共放送の電波を使って全国に平然と流すNHKのプロデューサーに対して向けられたものです。
まず、この企画がどういう順序で進んだのか知りませんが、企画者は、アルゲリッチと親子関係にある人が「平和活動家」であるという「縁」に飛びついたことでしょう。でもこの縁なるもの、じつはクラシックの巨匠の芸術的価値とは何の関係もありません。
それはちょうど、フルトヴェングラーやカラヤンがたまたまナチス・ドイツの体制下で、一見その体制に「協力」しているかのような演奏活動を行なったからといって、彼らを非難するには当たらないのと表裏の関係にあります。音楽に政治的な思想性を求めるのは原理的に無理な話で、アルゲリッチおばさんが別にすぐれた平和思想の持ち主であるわけではありません。企画者は、芸術家の名声と、その子どもの「平和活動」とを安易に結びつけて利用しているのです。
、次に、企画者は、今年は戦後七十年という大きな節目だから、この際、毎年行われている広島交響楽団の「平和の夕べ」に世界的大物を結びつけて、人の集まる首都圏で大々的に平和思想のアッピールをやろうじゃないかと考えたに違いありません。安っぽい興行師精神の見本です。後述しますが、そもそもこの「平和思想」なるものが、現実的な思考回路や歴史への視線を欠落させた陳腐で浅薄きわまるものです。
もっと大事なことを言います。
このお嬢さんの詩は「アウシュヴィッツ」と「ヒロシマ」とを同時に歌い込んだものだということです。その出来栄えがどの程度のものか、聞くのをやめてしまった私に評価する資格はありません。
しかしごく一般的に言って、アウシュヴィッツとは、ナチス・ドイツが初めから抱いていたユダヤ人に対する激しい憎悪・蔑視感情を、一民族絶滅の実践にまで高めていった、その思想を象徴するものです。しかもこの憎悪・蔑視感情は、非ユダヤ系のヨーロッパ人の間にはるか昔から広く(いまもなお)潜在していたものです。それは、第二次大戦におけるドイツの軍事行動とは直接のかかわりをもたないのです(第三帝国完成というプログラムの範囲内には収まるかもしれませんが)。
これに対して、「ヒロシマの原爆投下」は、明白にアメリカの対日軍事行動であって、両者をその非人道性や悲惨さという共通点だけをよりどころに同一視するような情緒的な把握は避けなくてはなりません。この区別をきちんとしないと、思想として残るのは、単なる戦争や殺戮一般という抽象的なものへの忌避を根拠とした抽象的な平和主義・ヒューマニズムだけになってしまいます。
こうした同一視は単純でわかりやすいので、物事を深く考えようとしない多くの人に広まるわけですが、その結果、たとえば「ドイツはあの戦争を反省したが日本は反省していない」といった得手勝手な言い分や、最近の反安保法制の運動に見られる「安保法制は戦争への道」などというバカげた思考停止の感情的な心理基盤が作られるのです。
誤解のないように断っておきますが、アウシュヴィッツとヒロシマを区別せよといっても、アメリカの非人道的行為がナチス・ドイツのそれに比べて軽いとか、かつての連合国の理念のほうが枢軸国のそれに比べればまだましだとか言いたいのではありません。むしろ逆です。個々の歴史事象の質的な相違をしっかり見極めるところから、何に対してどう憤るべきかという正しい指針が生まれてくるのです。情緒的な同一視は、これこれの事態を引き起こしたのは誰かという具体的な問いを封殺してしまいます。
ナチス・ドイツがしたことはもちろんとんでもないことですが、連合国が、これだけを悪魔に仕立て上げることによって、自分たちのしたことを巧妙に正当化し、免罪してきたことも忘れてはなりません。このトリックは、旧ソビエト連邦のユダヤ人虐殺やシベリア抑留者に対する過酷な扱いから最近の中共政府の驚くべき歴史捏造にいたるまで、その隠蔽の構造を連綿と保存し続けているのです。
事実、日本で毎年行われるヒロシマ・ナガサキの追悼・祈念儀式には、「この恐るべき非人道的な行為の直接の下手人は誰か、われわれは誰に対して憤りを向けることが正当なのか」という問いが生まれてくる余地のまったくない欺瞞に満ちたものです。もちろん下手人はアメリカであって、そのことがうやむやにされてきたのは、アメリカが中心となって作り上げた東京裁判史観と、日本の左派が作り上げた自虐史観との合作によるものです。
いろいろと小うるさいことを申しましたが、要するに私が言いたいのは、アウシュヴィッツとヒロシマとをその悲惨さによって同一視するような粗雑なものの見方による限り、何億回平和を祈念してみても、戦争や虐殺はけっしてこの世からなくならないということです。両者を一緒くたに歌い込んだ詩を聞かされたコンサート会場の聴衆のほとんどは、おそらく善意に満ちた素朴な共感を示して拍手の一つもしたのでしょうが、それがいったい何だというのでしょうか。私はむしろ、「今日はアルゲリッチのピアノを聴きに来たので、余計なことはやらないでくれ」と感じた聴衆が少しでも会場にいたことを信じたい。
この企画の担当者およびこれを何の疑いもなく放映したNHKの担当者は、お願いですから、この種の文化と政治をあいまいに混同させる企画が、理性的にものを考えようとする頭脳の働きを麻痺させる作用しかもたらさないということに気づいてほしいと思います。
<追記>その後の調べや読者の方たちからの情報により、この記事には、いくつか訂正すべき点があることがわかりましたので、以下にそれを掲げ、合わせて調査不足であった点についてお詫び申し上げます。しかしこの訂正によって、この記事の主旨そのものを変更する必要はないものと確信しています。
①アルゲリッチ氏のお嬢さんが朗読したのは、自作の詩ではなく、チャールズ・レズニコフの詩であったこと。
②このコンサートのS席のチケット代は、「2万円を下らない」のではなく、1万5千円であったこと。
③コンサートの行われた日付は、8月17日ではなく、8月11日であったこと。
④文中、「若い男性」が通訳ではないかと推測していますが、これは作家の平野啓一郎氏であり、彼が原民喜の「鎮魂歌」を朗読したこと。
最後の点は、筆者にとって別の意味で重要な批判に値する問題を含んでいるのですが、それについては、他の機会に譲ります。
なお、この記事は、ブログ「美津島明編集・『直言の宴』」にも転載されていて、そこでもコメントやりとりがなされています。また美津島明氏のFBでも興味深いやり取りが行われています。ご関心のある方はどうぞ。
ブログ:http://blog.goo.ne.jp/mdsdc568/e/0fa7f7fa539ab5fe1bbac1d07c4a6513
FB:https://www.facebook.com/akira.mitsushima.5












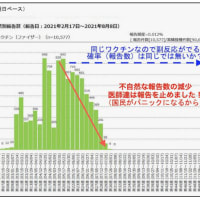

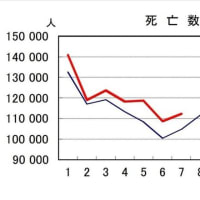
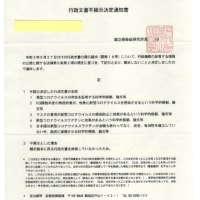
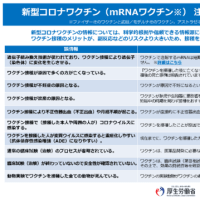

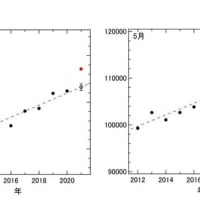

また、かくのごとき縁故によるだけの「盛り合わせ」は論外にしても、政治性について完全にニュートラルであると自称する表現行為はそれこそ胡散臭い。
クラシック音楽ではともかく、ポップスだったら、小説だったら…とりあえずこの論だけ読んだ時点では、「政治と文化」との関わりについて、「善意」の人々がいくらでも口とんがらかす余地はある。
最近、いろんなところで続々と著名人士が「声をあげ」ている。
それは一様に、今更というにも今更すぎる、本人のあきめくらぶりあほうぶりを露呈するばかりのステレオタイプなのだが、きっと大東亜戦争が「歴史」になったのと同様に、「戦後」もまた歴史になったのでしょうね。
冷戦下のサヨク文化のサルマネ、あるいはカリカチュアなのかとすら見える言説や身振りが、ひとによってはオールドスクールを取り入れた新鮮なモードとでも感じられているのであり、そこには「え、いまさら?」というツッコミは無効なのだろう。
それらについて、自分にとって幸運?なことに、「まさかあの人が…」という幻滅を感じる例はほぼない。
もともと「本業」において全然魅力を感じない、ロクな足場を持たないやつだから、そういうしょーもないところにフラフラっとハマるのもむべなるかな…というケースばかり。
幼稚な政治的態度を見たとしても本業に関してはファンであり続けられるというような「政治と文化」の切り分け、割り切りは自分にはできないが、それができなくてもまったく問題なくすんでいる。たまたま、いまのところは。
不幸?にも、ただただどっちらけたアルゲリッチ・ファンはきっと少なからず居たのだろう。
ユダヤの詩はチャールズ・レズニーコフ氏の作品でアニー・デュトワ氏が創作したものでもないですし原爆とユダヤ人を織り込んだ詩でもありません
つまり人の作品を二つ朗読しただけです
難波さんの突き放したスタンスをとても貴重なものに感じますが、う~ん、「戦後」も歴史になったのかなあ。おっしゃる通り、彼らは冷戦時代のサルマネやオールドスクールの取りいれにすぎないものを新鮮だと勘違いしているのでしょうが、歴史健忘症が相変わらず反復されているところを見ると、むしろそれこそがいまだ「戦後」の継続なのではないかと思えて仕方がありません。彼らは「ステロタイプ」に、自分の「若さ」、老いらくの回春の情、インテリという名のアイデンティティを注ぎこむ以外に、もはややることがないのでしょう。
先日もM.K.という「元」脳科学者が一人で「アンポ・ハンタイ、ジユウ・サンセー!」などというラップまがいのバカ踊りをやっている動画を見て、一瞬唖然、世も末、と感じました。
でも私は難波さんと少し違って、本業放棄の元祖・大江健三郎翁やノーベル賞欲しさの国際パフォーマンスに走る村上春樹クンの初期作品群には、いまでも魅力を感じています。このことだけは押さえておきたいと思いました。
しかし、そうであればこそ、なおさら、私はこのイベント企画の胡散臭さを感じます。関連のないはずの二つの詩が、母子の縁を頼りに強引に結びつけられたのは、このイベントにおいてこそだからです。
番組は見ていませんが、私もこの種の平和イデオロギーの押し売りには虫酸が走るので、きっとチャンネルを切ってしまったことでしょう。
昔、LPレコードで、アルゲリッヒと表記されていた頃の彼女の演奏にある種の感銘を受けたことはありますが、好みではありませんでした。しかし周囲には異常なほど入れあげている人がいるので迂闊なことは言えません。
今回の一連の騒動で、私にとってもっとも不愉快な(というほどでもないのですが)人物は音楽家のS.R氏です(はっきり書いてもいいのですが、なにか差し障りが出ると、ご迷惑をおかけするかもしれませんので、小浜さんの流儀に従います)。いつの時代でも、恥知らずに、その時の反政府的正義にコミットすることを知的だとする勘違いから抜けられない人々がいるのだと思います。フランス革命を例に挙げたそうですが、無知にもほどがあります。なにか中学生の歴史知識で止まってしまった人なんでしょう。
S.R.氏は、福島事故で反原発運動が盛り上がった時にも、許し難いバカなことを言っておりました。これについては美津島明さんのブログに投稿したことがありますので、ご笑覧いただければ幸いです。
http://blog.goo.ne.jp/mdsdc568/e/d4e1c312938bccab4344516d46a8617d
この記事では、文芸批評家のボケ谷某人氏(最近は「哲学者」ということになっているらしい!)の言動も批判していますが、そのボケぶりはいよいよ深刻な状態に達しつつあるようで、今回の安保法制問題では、例の国会前のデモに浮かれて、「デモこそは民主主義の本当の姿だ」などと口走っているのを目にしました。「哲学者」先生が、大したことのない政治問題一つ分析できないというのは、まあ、当然なのかもしれませんが。
これら、戦後日本のインテリどもは、批判の対象であるよりは、むしろ精神病理学的対象です。しかし、もはや個別に診断・治療を考えて差し上げるよりは、なぜこのような病気が蔓延することになったのかを「一般病理学」として解き明かすことの方が重要ではないかと愚考いたします。
小浜さんの文章を読むといつもそうですが、同感のあまり、まるで自分がずっと前から同様のことを考えていたかのような、自分はなんでこんなに頭がいいんだろう、というような錯覚に陥り、恥ずかしながら無意識に自惚れてしまいます。しかも痒いところに手が届くような周到な構成と文章によって表現されているので、どこかよそで自説のごとく吹聴してしまいそうです。
批判の対象となっている方々について、日頃から胡散臭く、いわゆる「なんだかなあ、、、」という思いを禁じ得なかったのですが、その明確にならない「なんだかなあ」感が、目の前で平易にして緻密な文章に構成されていくのは爽快です。
これはたった2年半前の文章のはずですが、このころの原発反対運動やデモが、目下展開されている安保法案反対運動やデモと完全に二重写しになりますね。戦後の言語空間では同じ楽派が同じ曲ばかり繰り返すので、これでいったい何度目だ、と溜息が出てきます。déjà-vu という言葉は一回使うからこそ切実感があるのに、これではもう使うのが憚られてきます。デモの特徴を列挙した条りは、あまりにも今のシールズと称する愚かな若者たちにあてはまるので、苦笑を禁じ得ませんでした。
新連載も楽しみにしております。急かすわけではありません。
局所的にはどんな突発的事案が起きるか連中自身わからない。
で、こちら日本側もイザ何かあったときに何をどうするかルールが定まってなければ、
そりゃ鉄砲を預かりもつ現場の人間は、ヘーワケンポーの空念仏唱えるより、そのときその場において「なすべきこと」をするだろう。
そうやって現場の判断をおっかけおっかけ追認するかたちで意図せざる泥沼へ…これぞ「いつか来た道」そのもの。
安保法制整備はまさに焦眉の急。
…というほどのことがわからないやつがいるというのがわからない。
高等教育を受けた人間が「地獄への道は善意で舗装されてる」という超有名な箴言をマンガみたいにそのまんま演じ踊り狂ってるなら
余人は何を言ってやりようがあるのか?
唖然。実に、唖然とさせられます。
これからも、少しでもお役に立てればと思って頑張ります。
まだ「マルタ・アルゲリッヒ」と呼ばれていた、半世紀程昔の彼女は見事に長い黒髪がトレードマークで、音楽自体はともかく憧憬の的でありました。月日が経つのは早いもので、マエストロと呼ばれるに相応しく変容された昨今でありますが、演奏会場で思想的な表現を行うのは「野暮」の一言です。
どういう因縁か私の音楽上の恩師は折り紙付きの左巻き。学生時代には私のことを「反動」呼ばわりしておりました。それでも音楽については寛容で、種々教えを賜って参りましたし、彼女の音楽に対する姿勢は、そのような低次元のものではありませんでした。
この師とは思想的には相容れませんが、音楽的には大変尊敬出来る先生で、最近までお教えを乞うておりました。しかしやはり思想的行き違いから、とうとう破門の憂き目に遭いました。やはり傘寿を迎えられ年齢的に寛容さをなくされてしまったのでしょうね。
繰り返しになりますが、音楽表現の場で思想信条を持ち出すような、薄っぺらなことは絶対にされませんでした。それ以外の場では、公然と左巻き支援を行っているのが周知の事実です。
所謂文化人に左巻きが多いというのも困った現象で、保守的な方にもっと声を上げて頂きたいものです。