倫理の起源13
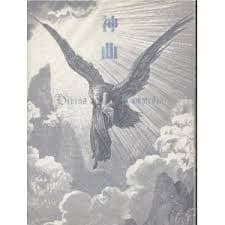
恋を発展させて道徳に転化させる? だがだまされてはいけない。いったい恋の本質としての「狂気性」はどこに消えたのだ?!
プラトンはこの疑問に対して、次のように答えるかもしれない。
いわく、そんなこともわからないのか。恋を成就させるためには、つまり恋する相手と結ばれるまでは狂気性は不可欠のものだが、そのような狂気性を媒介としてこそ、ほんとうの「善いカップル」が生まれるのであって、そうして苦労して勝ち得た恋の成就の暁には、このようなけだかい関係のあり方が必ず訪れてくるのだ。そのとき狂気性そのものは少しも衰えることなく、知への愛という本来的な形態へと昇華されるのだ……。
しかしこんな空手形にだまされてはいけない。お互いに現実感覚を失わないようにして、生の経験豊かなる読者に問いたい。現実には、恋の狂気性は、結ばれたあとも、新しい葛藤の種になりはしないだろうか。あるいは狂気的であったがゆえに、少しの時日が経てばその恋は夢のようにはかなく冷めていくのではないか。あるいは一方が冷めずに他方が冷めてしまえば、そこに生まれるのは、惨めな破局ではないか。狂気が恋する側に残っていればこそ、嫉妬に苦しむことにもなるのではないか。
プラトンには、恋愛における狂気性を動力として結ばれた二人の間にならば、その狂気性をそのまま、知を愛し求める狂気性へと転換することが可能だという信念のようなものがあったように思える。あるいはそうでなければ、常識的に考えて相容れるはずのない二つの道(恋愛の道と知への道、あるいは地上的な狂気とイデアを求める狂気)の隔たりを、それと知りながらごまかして、わざと無視したのではないか。そして私には、このあとの欺瞞的な手つきのほうがありありと見えて仕方がないのだが。
「恋していない者にこそ身をまかせるべきだ」というリシュアスの説を思い出そう。この説はこの説で、てらいすぎのパラドックスだが、エロス神を冒涜するものだといってにべもなくこれを否定した第二のソクラテスには、恋の狂気が、私的関係の平穏な持続や公共性の維持に対して、いかに破壊力を秘めたものであるかという、危険性の認識があっただろうか。まだリシュアスの説のほうに、その感覚が保存されていたのではないか。
ところがソクラテスは、この第二の物語の終わり近くで、リシュアスの説に対して次のような極め付きの批判を行っているのである。
これに対して、恋していない者によってはじめられた親しい関係は、この世だけの正気とまじり合って、この世だけのけちくさい施こしをするだけのものであり、それは愛人の魂の中に、世の多くの人々が徳としてたたえるところのけちくさい奴隷根性を産みつけるだけなのだ。
恋していない者によってはじめられた親しい関係は、けっして善い関係を生まないと言っている。ここで意識されている善い関係とは、単に彼らが二人だけの閉鎖的な幸福を得ることだけを意味しているのではない。そこには、旧世代から新世代に受け継がれるべき善き公共性を維持するにはどうすればよいかという例の問題意識も暗黙のうちに含まれている。
なぜならば、先にも述べたように、プラトンおよび彼の同時代人の知識層が思想的に目指していたのは、明らかに倫理的な課題だったからである。その倫理的な課題とは、年少者と年長者とのプライベートな絆を、ただの肉体的な欲望の発散や私的な恋愛沙汰に終わらせずに、ポリス共同体というパブリックな体制の維持に貢献させることである。言い換えると、エロス的な関係を、個体の有限性を超えた時間的連続性に耐える堅固なものとするためには、いかなる知恵が必要とされるかという問題意識である。
リシュアスの逆説もその倫理的課題の範疇におさまることはいうまでもない。とはいえもちろん、少年が彼を恋していない者に「身をまかす」(性愛関係になる)ことを軸とするような関係のあり方が、この倫理的課題を解き明かすものでないこともまた、あきらかである。好きでもない相手に安易に身を任せれば、相手は彼を軽視して簡単に捨てることになりがちだからだ。
ソクラテスが「この世だけのけちくさい施こしをするだけのもの」「世の多くの人々が徳としてたたえるところのけちくさい奴隷根性」と、口を極めて批判しているのは、そのかぎりではおそらく当たっている。
しかし、では、激しい恋心の結果少年の心身をわがものとするようなアイデアが、右の課題の解決策につながるかと言えば、それもあり得ないことである。激しいエロス感情にもとづいて作られた絆と、知を愛し求める志の共有にもとづく絆とが幸福な一致を見るなどということは、普遍的には成り立たないからである。プラトンは時代の渦中にいて壮大な夢を見ていたのだ。
さてこれまで、ソクラテスが語った二つの物語のうち、あとの「恋の狂気」賛美の物語のほうに、プラトンがほんとうに言いたかったことがもっぱら集約されているという前提で、それを批判することに注意を集中してきた。おそらく『パイドロス』を読んだ多くの読者も、この物語にこそ、恋愛や美についてのプラトン思想の核心が宿っているという事実に疑いをもたないであろう。副題にも「美について」とある。
ところが、『パイドロス』は、以上の「物語」で終わらずに、後半、ほぼ全体の半分に相当するページを、優れた話のあり方とは何かという主題をめぐるソクラテスとパイドロスの対話に当てているのである。それは、リシュアスの書いた話といまソクラテス自身が語ったばかりの二つの話についての反省会といったおもむきである。そしてそのなかにはまた、ソフィストたちの弁論術に対する批判もふんだんに出てくる。
この内容自体は、さほど興味をそそられるものではなく、また本書のテーマからは外れるので、ここでは扱わない。ただ一点引っかかるのは、ソクラテスが、自分の二番目の話には、善き弁論をするための二つの手続きが使われていた、と指摘しているところである。
二つの手続きのひとつは、多様に散らばっているものを綜観して、これをただ一つの本質的な相へとまとめること。もう一つは逆に、さまざまの種類に分割すること。
このいわば「総合」と「分割」の二つの方法を言語に対して用いる技術は、ソクラテス自身によって、「ディアレクティケー」と呼ばれる。そして、自分がエロースとはなんであるかを定義したのは、前者の「総合」に当たり、また、恋の狂気性を、禍をもたらす部分(暴れ馬によって象徴される)と、反対にわれわれに最も善きものをもたらす部分(恋人に対する馭者の畏怖と敬虔の念に相当する)とに分割したのは、後者の「分割」に当たるとされる。
このような一種の楽屋話のような「メタ言論」を聞かされると、私たちは、プラトンの作家的構成能力の複雑高度なあり方に舌を巻かされる思いがする。そして一瞬、ではソクラテスの二番目の「狂気礼賛」の物語は、必ずしもプラトンその人の思想を直接に表現したのではなく、恋やエロースという概念について別の側面からはこういう見方もできるというかたちで、説得力のある言論の見本をひとつ提示して見せたにすぎないのではないかという疑いにとらえられるのである。作品全体は、読者に新しく考えさせるための、一種の教科書のようなものである?
だが、仮にそうだとしても、プラトンは、まずソクラテスにリシュアスの言論の主旨をもっと強調するような演説をさせ、そのあとそれを後悔して、エロス神をたたえる演説をさせているのであるから、私たちは、これまで批判してきたことを引き下げる必要はないであろう。やはりプラトンがソクラテスを使って自分の思想を表現したかった部分は、第二の演説の中に込められていると考えて間違いではなかろう。
つまり、ソクラテスの互いに相反する二つの演説それ自体が、彼のいう「ディアレクティケー」の構造になっていると考えれば、プラトン自身は、やはり、あとの演説のほうが、言論そのものの「最も善きものをもたらす」部分に相当すると考えていたとみなして大過ないだろう。
いうなれば、リシュアスの言論をソクラテスなりに整理して、その論点を強調した第一の演説が、分割の第一番目、すなわち「禍をもたらす部分」を示し、エロス神の礼賛を軸とした第二の演説が、分割の第二番目、すなわち「最も善きものをもたらす部分」を示しているとみなすことができるだろう。私たちのプラトン批判は、だからこそ、この第二番目の部分に集中したのだった。
この推定は、他の作品、『饗宴』『パイドン』『国家』『ゴルギアス』などによって補強される。プラトンは、これらの作品において、はじめから自分の主張を一方的に繰り出すのではなく、ソクラテスを主人公とした「対話(ディアレクティケー)」という両論併記の方法を用いることによって、まず考えられるかぎりの反論を提示しておき、それをあとからゆっくりとひっくり返していくという、弁論のドラマ性を重視した。もちろん最後に勝つのはいつもソクラテスなのだが(『パルメニデス』などは例外)。この弁論のドラマ性は、読者に文学的興味をそそらせるテクニックであると同時に、議論というのはこのようにいつもだれにでも開かれていなくてはならないという彼の思想的態度の表明でもあった。
この思想的態度の表明にかぶれる人は多いが、私はむしろ、そこにもプラトンの狡知を見出す。なぜなら、ソクラテスが登場するほとんどどの作品でも、ソクラテスの発言量が圧倒的に多いし、対話の相手はほとんどの場合、ソクラテスの考えにそのつどただ同調する未熟な若者であり、最終的に議論に決着をつけているのは、いつもソクラテスだからである。ただし、『ゴルギアス』におけるカリクレスと『国家』におけるトラシュマコスはこの言い方には当てはまらない。これらは例外と言っていいかもしれない。つまり「対話」とは、だいたいにおいて、巧妙な見せかけである、と私は言いたい。
ともあれ、『パイドロス』の前半は、表面上「(少年は)恋している者に身をまかせるのと、恋していない者に身をまかせるのと、どちらがよいか」という問いをめぐって展開されており、「美について」という副題が付されてもいるが、じつは、この作品も『饗宴』と同様、「善なる存在として生きるにはどうすればよいか」というプラトンの強い倫理学的な問題意識を底に隠した作品なのである。ここにただの「美」論や恋愛論を読むのは、読みが浅いと言わなくてはならない。
というのは、ソクラテスの第二の演説の結末に見られるごとく、ここには、恋する者どうしの絆を、神に祝福されるべきより高い生のステージにまでもたらすためには、必ず彼らがその絆を利用して、手に手を取って知を愛する精神的な営みに励まなくてはならないという「お説教」が語られているからである。
言い換えると、プラトンの思想的射程の中では、「恋」という最も狂気性のあきらかな、また快楽の奴隷に陥りやすい人間の心身の営みさえもが、その特性ぐるみ愛知や哲学に昇華されなくてはならず、そうした「善」を目指す生き方のうちに包摂されることが要求されているのである。
ハイデガーは、世人の頽落状態から脱してたったひとりで死と向き合うかまえのうちに道徳性の源泉を見ようとした。これに対して『饗宴』と『パイドロス』におけるプラトンは、恋の狂おしい力によって結びついた二人の関係の展開に道徳性がはらまれる可能性を見出そうとした。
なるほど、愛し合った二人が、その二人だけの閉ざされた世界の中でだけ精神性を高め、自分たちは俗情の渦巻く世間から離れて、「善のイデア」に近づいたと主観的に感じ合うことはあるだろう。ことに二人の恋が世間や社会からの迫害にあうとき、そのような精神状態になることはしばしばある。しかしそれは、ちょうどある宗教が、自分たちの教義だけが正しいと主張して他の宗教を異端として斥けるのと同じように、普遍性への回路をもたないものである。
この世での恋がかなわぬものならば、せめてあの世で永遠の愛を、と観念することは、人間のロマン的本質に根差している。たとえば我が国の文学でも、近松の心中ものなどは、そのプロセスを克明にたどろうとする。しかしそれは、その現実的な悲しみと苦しみゆえにこそ人々の共感を誘うのであって、その限りでよく納得できる成り行きである。
だがそのロマン的本質を、「善のイデア」と呼び変えうるかどうかは、また別問題である。私はこのプラトンの手つきにどうしても嘘くさいものを感じる。この嘘くささは、キリスト教道徳の加勢を得て、ヨーロッパの精神史の中に長く根付いて行ったようだ。その好例を、たとえばダンテの『神曲』の構成の中に見出すことができるだろう。美少女ベアトリーチェへの恋心が、天上の至高の輝き、その唯一絶対的な完全性に出会うことで成就しうる? 狂気的なエロスの欲望が、道徳の源泉と最終的には融和する? そんな馬鹿な。












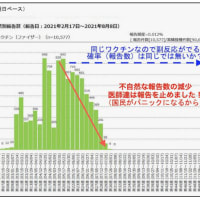

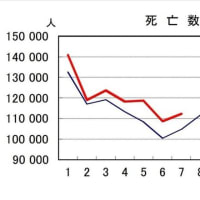
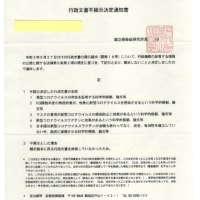
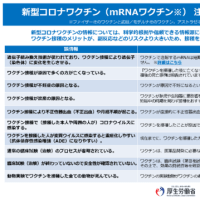

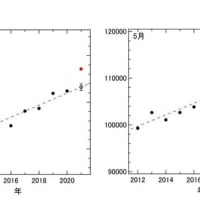

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます