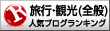秋の風物詩と言えば十五夜。中秋の名月ともいう。稲や芋を収穫するじきでもあり、里芋を供えるので「芋名月(いもめいげつ)」とも呼ばれる。田んぼを歩くと稲がしっかり育っている。夜中は、ボク(小次郎)とのコラボが難しいので月が上る夕方に撮ってみた。これもいいんだな! ちなみに、2021年は9月21日だってさ。過去の、中秋の名月 いつ? 調べてみた。
※ 2021年:9/21、2020年:10/1、2019年:9/13、2018年:9/24、2017年:10/4日、2016年:9/15 ずいぶん差があるねえ!
<2017年10月4日>

◇午後5時56分。田んぼに稲が実り、東の空に中秋の名月が浮かんでいる。夜の十五夜も美しいが、日暮れの残照とのコントラストもキレイ。うむ、小次郎は関心がないようだ。

◇稲穂が頭を垂れている。うむ「実るほど頭を垂れる稲穂かな!」だ。えーと、意味は?
◇人格者ほど謙虚であるというたとえ。 稲が実を熟すほど穂が垂れ下がるように、人間も学問や徳が深まるにつれ謙虚になるものだ。一方、小人物ほど尊大に振る舞うものだということ。 類義として「米は実が入れば俯く(うつむく)、人間は実が入れば仰向く(あおむく)」がある。

◇ まず、これで月見て欲しい。ん? 分かんない? ズームしてみよう

◇ これで分かるだろう? でも、小次郎が入らない。トレードオフだな。知恵を絞ってみよう。

◇ これでバッチリだ。 ま、再度、月をしっかり愛でてみよう。

◇ 夕方の茜色と白い月のコントラストがなんとも言えない。

◇十五夜は満月から2日ズレているのでちょっとかけている。 今度は小次郎とのコラボ。



ちょっと十五夜について勉強しておく。
【十五夜(中秋の名月)】
◇”秋の真ん中に出る月”の意。8月15日(旧暦)の月。この年(2017年)は10月4日
※ “仲秋の名月”という表現もあるが、“仲秋”は、「陰暦8月」を指すので十五夜の日に限定されなくなる。“仲秋”は、秋を初秋(旧暦7月)、仲秋(同8月)、晩秋(同9月)の3つに区分する時に使われるので、旧暦8月全体を指す。対して「中秋」とは「秋の中日」=陰暦8月15日のみを指す。うーむ、ややこしい。
◇月見:平安時代に中国から伝わり貴族の間で広まった。庶民が楽しむようになったのは江戸時代。貴族のように月を眺めるのではなく、稲や芋などの収穫を感謝する意味合いが強かった。
◇ 食べ物やお供えは?
・ススキ(芒):白い尾花が稲穂に似て「神様の依り代」「魔除け」になる。
・月見団子:団子の数はピラミッド状に15個(十五夜)。一番上の団子が月(霊界)との架け橋になる。食べる事で月のパワーをもらう。
・農作物:里芋、栗、枝豆などを供える。里芋を供えることから「芋名月」の異名もある。
ちょっと田植えの頃をふり返ってみよう。
<2017年6月21日ー田植え->

◇梅雨の時期の田植え。ここは、まだ水が張っている状態。

◇ここは、田植えが済んだ直後のようだ。

◇ 田んぼコースの一角。左上にみえるのが美咲が丘の団。

◇ 田んぼをよく見ると苗を植えた直後なのが分かる。

◇ 公民館の近くに「苗代」もあった。
【苗代(なわしろ、なえしろ)】
◇ 苗代は灌漑(かんがい)によって育成するイネの苗床。
◇ もともとは種籾(たねもみ)を密に播いて発芽させ、田植えができる大きさまで育てるのに用いる“狭い田”を指した。
◇ 今の時代は「プラスチック苗代」が主流。
◇ また、高速乗用田植機があるので、腰を痛める事が少なくなったという。
6月21日と10月4日を並べて見てみよう。

◇ 農家の方は、稲の生長を収穫の喜びを感ずるのだろう。
お終い。