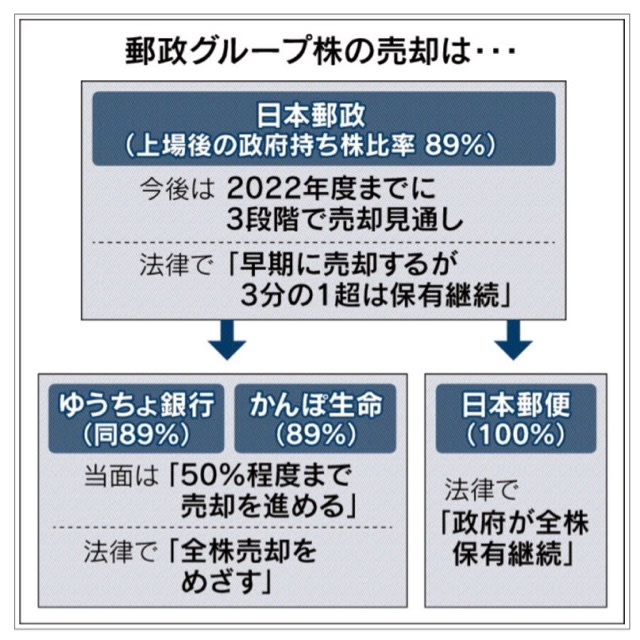日米、安保で新協議機関
自衛隊・米軍、平時も一体運用
2015/11/4 3:30 日経朝刊
【クアラルンプール=田島如生】日米両政府は3日、日米防衛相会談に合わせて自衛隊と米軍を平時から一体的に運用するための新しい協議機関「同盟調整メカニズム」を発足させた。安全保障関連法や4月に改定した日米防衛協力指針を踏まえ、平時から政府機関や自衛隊、米軍の様々なレベルで話し合いの場を持つ。尖閣諸島などをにらんだ共同計画をつくるための新機関も立ち上げた。

外務・防衛局長級の防衛協力小委員会を持ち回りで開いて正式に設置を決めた。新協議機関の設置は新指針に盛り込んでおり、中谷元・防衛相は防衛相会談後、記者団に「新指針の実効性確保のための重要な第一歩だ」と語った。
日米間には、1997年の防衛指針で盛り込んだ自衛隊と米軍の運用を調整する協議機関があった。しかし活用するのは日本有事と、朝鮮半島有事などの周辺事態が起こった場合としており、発動は一度もない。
新設した協議機関は平時から調整するのが特徴だ。このため武装漁民による離島占拠など武力攻撃に至らない「グレーゾーン」事態も対象になる。北朝鮮が人工衛星の名目で弾道ミサイルの発射を示唆する場合も、日本有事や朝鮮半島有事につながるか見通せないため従来の協議機関は使えなかったが、今後は話し合いを持つ。
協議機関は3段階で構成する。(1)国家安全保障会議(NSC)や外務省、防衛省など関係府省が安保政策を擦り合わせる同盟調整グループ(2)自衛隊統合幕僚監部などが自衛隊と米軍の統合運用を話し合う共同運用調整所(3)陸海空それぞれの組織が部隊の運用などを細かく調整するための調整所――の3つだ。

会談を前にカーター米国防長官(左)と握手する中谷防衛相(3日、クアラルンプール近郊)=共同
それぞれの段階で、あらかじめ関係府省や自衛隊、米軍ごとに担当者を決めておき、事態発生時に素早く集まり、連絡を取り合うようにする。関係府省はこれまで外務、防衛両省を想定していたが、必要に応じて国土交通省や厚生労働省も加わり、大規模災害での日米協力なども円滑にする。
自衛隊と米軍の共同作戦計画をつくる新協議機関「共同計画策定メカニズム」も立ち上げた。共同計画は日本有事や周辺事態、グレーゾーン事態などの際の作戦や部隊の展開などを盛り込む。
これまで共同計画は「検討」段階とされてきたが、今後は「策定」段階に入るとしている。中国の海洋進出を踏まえ「有事だけでなく平時から切れ目のない体制を整える必要性が高まっている」(防衛省幹部)ためだ。
具体的には自衛隊と米太平洋軍、在日米軍のそれぞれの代表ら制服組による共同計画策定委員会が詳細な計画をつくり、外交・防衛当局や関係府省などと調整する枠組みを設ける。ただ共同計画は機密情報を含むため、公表しない方針で、日米一体化の実態は不透明な面が残ることになる。
自衛隊・米軍、平時も一体運用
2015/11/4 3:30 日経朝刊
【クアラルンプール=田島如生】日米両政府は3日、日米防衛相会談に合わせて自衛隊と米軍を平時から一体的に運用するための新しい協議機関「同盟調整メカニズム」を発足させた。安全保障関連法や4月に改定した日米防衛協力指針を踏まえ、平時から政府機関や自衛隊、米軍の様々なレベルで話し合いの場を持つ。尖閣諸島などをにらんだ共同計画をつくるための新機関も立ち上げた。

外務・防衛局長級の防衛協力小委員会を持ち回りで開いて正式に設置を決めた。新協議機関の設置は新指針に盛り込んでおり、中谷元・防衛相は防衛相会談後、記者団に「新指針の実効性確保のための重要な第一歩だ」と語った。
日米間には、1997年の防衛指針で盛り込んだ自衛隊と米軍の運用を調整する協議機関があった。しかし活用するのは日本有事と、朝鮮半島有事などの周辺事態が起こった場合としており、発動は一度もない。
新設した協議機関は平時から調整するのが特徴だ。このため武装漁民による離島占拠など武力攻撃に至らない「グレーゾーン」事態も対象になる。北朝鮮が人工衛星の名目で弾道ミサイルの発射を示唆する場合も、日本有事や朝鮮半島有事につながるか見通せないため従来の協議機関は使えなかったが、今後は話し合いを持つ。
協議機関は3段階で構成する。(1)国家安全保障会議(NSC)や外務省、防衛省など関係府省が安保政策を擦り合わせる同盟調整グループ(2)自衛隊統合幕僚監部などが自衛隊と米軍の統合運用を話し合う共同運用調整所(3)陸海空それぞれの組織が部隊の運用などを細かく調整するための調整所――の3つだ。

会談を前にカーター米国防長官(左)と握手する中谷防衛相(3日、クアラルンプール近郊)=共同
それぞれの段階で、あらかじめ関係府省や自衛隊、米軍ごとに担当者を決めておき、事態発生時に素早く集まり、連絡を取り合うようにする。関係府省はこれまで外務、防衛両省を想定していたが、必要に応じて国土交通省や厚生労働省も加わり、大規模災害での日米協力なども円滑にする。
自衛隊と米軍の共同作戦計画をつくる新協議機関「共同計画策定メカニズム」も立ち上げた。共同計画は日本有事や周辺事態、グレーゾーン事態などの際の作戦や部隊の展開などを盛り込む。
これまで共同計画は「検討」段階とされてきたが、今後は「策定」段階に入るとしている。中国の海洋進出を踏まえ「有事だけでなく平時から切れ目のない体制を整える必要性が高まっている」(防衛省幹部)ためだ。
具体的には自衛隊と米太平洋軍、在日米軍のそれぞれの代表ら制服組による共同計画策定委員会が詳細な計画をつくり、外交・防衛当局や関係府省などと調整する枠組みを設ける。ただ共同計画は機密情報を含むため、公表しない方針で、日米一体化の実態は不透明な面が残ることになる。