「小さなナンシイ・ガラス・ハウスをつくってもらって、私はそこの館長さんになりたい。白髪でオカッパの館長さんに。
若い人にガラスの説明をして、おいしいコーヒーをごちそうする。そんなひそかな夢をもっている。
ガラスが私に話しかけてくる。皆さんに、みてもらってほしいと。
人間の意志と人間の知恵を傾けて作り出した、これほど素晴らしい過去の歴史をありのまま語ってくれる歴史的産物は、他にないのだから。」
著者が本「彩蝶」の最後のところに書き記した文章である。
古書店が通路にはみ出して設置した台に、背表紙を向けてぎっしりと並べられている中から、面白そうな本を探し出すのが楽しみになっていたのは、2年前まで母の見守りに通っていた大阪・堺の駅前のことである。
100歳に近くなった母が、1人暮らしをしていたので、毎月10日間程度出かけ、妹たちと交代しながらの見守りであった。
母は、自分のことはほぼできるので、週に3回のデイサービスに、朝出かけるのを見送ってから夕方までの間、買い物に行ったり、掃除をしたり、本を読んだりの毎日である。
最寄りの駅ビルに、天牛という書店が店を開いていて、新刊本と共に古書も扱っている。古書は店の外、通路にはみ出して設置した台の上に並べられていた。
台はいくつかあって、台ごとにジャンル分けした本が並んでいた。私の目当てはチョウ、ガラスなどに関したものであったが、どうしたわけかこの当時、今思えばガラス工芸に関する貴重な本を何冊も見つけることができた。
チョウについては7年ほど前から、学生時代に再び戻ってしまい、写真を撮り歩くようになっていたし、ガラスについては軽井沢でアンティーク・ガラスショップを開こうと計画しはじめていた頃である。
ガラスに関連した本では、由水常雄氏の「ガラスの道」、「ガラス工芸」、「火の贈りもの」や佐藤潤四郎氏の「ガラスの旅」などを見つけていたが、そんな中でふと目に留まったのが「彩蝶」(太田恵子著 1976年 経済界発行)というタイトルの本であった。
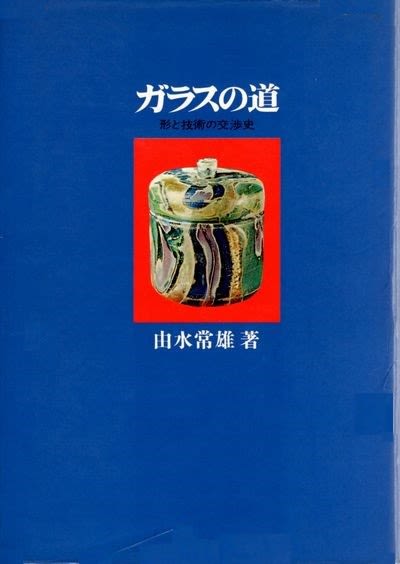
ガラスの道(由水常雄著 1973.6.15発行)
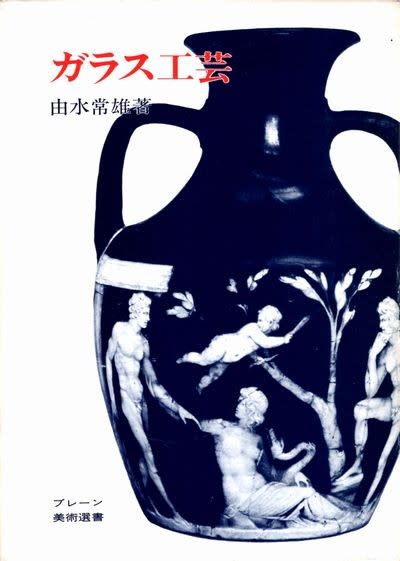
ガラス工芸(由水常雄著 1975.6.30発行)

ガラスの旅(佐藤潤四郎著 1976.4.25発行)
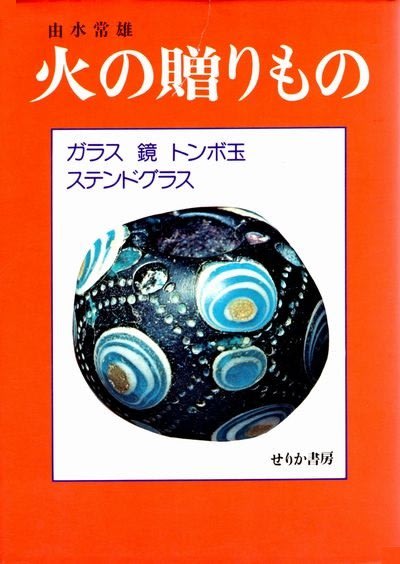
火の贈りもの(由水常雄著 1977.1.20発行)

著書「彩蝶」(太田恵子著 1976.3.31発行)
知らない名前の小説家の本かと思い、箱から出してパラパラと見ていくと、著者は小説家などではなく、まったくの素人の著作で、大阪でバーのマダムをしていた人であると判った。では、蝶とは「夜の蝶」のことかと見ていくと、もちろん全体としては夜の世界を描いているので、その意味合いも含んでのことではあるが、それと共に、ナンシイの蝶、ガレの作品に登場する蝶をも意味していると判った。
内容の大半は著者が過ごした大阪・北新地の「夜の街」のことについてであるが、最終章はガラスの話になっている。チョウとガラス、これは買うしかないということでこの本は今、手元にある。
私自身、学生時代まで大阪で暮らしたが、卒業・就職と共に関東に移り住んだので、大阪のことは意外に知らないことが多い。特に大阪の「夜の街」については当然ながら全く知らない。
この本は1975年に「経済界」に連載されていたものをまとめて単行本としたもので、1976年に同じく株式会社経済界から発行されている。
話の中には関西財界の大物が実名で登場する。私も名前だけは知っている方々も多くみられ、中には私が通っていた大学の関係者も。
著書の内容をざっと紹介すると次のようである。
青春時代:
「私は、大阪湾の青い海が眺望できる大阪市港区で生まれた。大正十四年一月十二日。父は船乗りで、戦前の私はごく平凡な下町娘だった。上陸するごとに成長している私を抱きあげては、『ええ嫁はんになれる』といった。・・・小学校のころから、おけいこごとに通わされた。舞踊をならわせても器用だし、家事を手伝わせてもソツがなかった。このまま世の中が平和でさえあったら、私はええ嫁はんになっていたに違いない。・・・
大東亜戦争に突入したのは、私が女学校四年生の時。当時はまだ戦争といってものんきなもので、日本舞踊のけいこを続けていた。・・・
しかし、運命という彫刻家は、この私を素材に、奇妙な彫刻をきざみはじめた。父が死んだ。運命が、私をきざみあげるために入れた最初のノミといっていい。
女学校を卒業して、船場の大建産業(今の丸紅)に就職した。
昭和二十年三月十三日の大阪大空襲で家も失った。私が二十歳の時。市内は焼夷弾でなめつくされ、たたきつぶされた。
大和の古市に疎開して、そこで二年間過ごした。母は(兵庫県)龍野女学校の出身で、なかなかきかんきの男まさり、バレーボールのキャプテンもしていた。グチひとつこぼさず、父の郷里の広島へ買い出しにでかけては、私たちにみじめな想いはさせなかった。
終戦。疎開先の古市の家は出なければならなかった。・・・終戦の年の夏はこうして終わった。
昭和二十一年の夏のある日、十三大橋を、家財道具を積んだ一台の大八車が渡っていた。私はこの荷車を指図している。和服をつぶしたブラウスを着ていた。老母をつれ、カジ棒をまだ少年だった二人の弟にひかせている。・・・
橋の向こうに、大阪の廃墟が見えていた。
私はその焼けビルの町を遠い目で見た。人には自分の明日を予知する能力がない。十数年後に、いま遠望しているその大阪の街に、どっかりと腰をおちつけて商売する身になろうとは、私自身も予測することはできなかった。・・・」
北新地の城:
「私が初めて水商売に手を染めたのは昭和二十三年のこと。・・・今はパチンコ屋に変わっている、大阪駅前すぐ西の桜橋交叉点北西角。三階建て鉄骨モルタルでじゅうたんを敷きつめた、豪華な会員制クラブ「ツーリスト」が開店し、私は紹介されてそこの女給、いまでいうホステスになった。・・・
私の月給は当時のお金で八千円。しかし何よりも嬉しかったのは、暗いみじめな環境から、一晩中電気の明るい、華やかな場所に出られたことだった。・・・
昭和二十四年、八か月で「ツーリスト」をやめた私は、小さなバー「えんじや」を開店した。
北新地の西寄り、本通りと裏通りを結ぶ小路の東側にある十五坪ほどのお店が、私の最初の”城”となった。・・・
当時は これといったバーも少なく、本当にお茶屋さんばかり。・・・「ああ、自分の店で、自分が働いて、お客さまが来て下さる。それでゴハンが食べられるなんてホンマにありがたいことや」としみじみ実感を味わったものだった。
夜の商工会議所:
「私の店が『夜の商工会議所』といわれるようになったのは、昭和三十四年から。『週刊文春』が『紫苑』(二番目の店)を取材し、記事にしたのが初めてであった。・・・
実は、この『週刊文春』の記事が書かれるにはいきさつがあった。
昭和三十四年、月刊『文芸春秋』が日本を代表するバーのマダムを書き、東京の『エスポアール』、京都の『おそめ』、福岡の『みつばち』を紹介した。
すると文芸春秋社の池島信平さんのところへ、川口松太郎先生が、『太田恵子載ってないじゃないか』と苦情。
また毎日放送の後藤基治さん(故人)からも、『大阪どうして載ってないのや』と相次いで声がかかった。文芸春秋社も、それじゃ『週刊文春』でということになったのだった。」
勇婦ふたり世界旅行:
「『紫苑』を開店してちょうど十年。夜の会頭にしていただき、大阪経済界の後援も得て、商売はうまくゆくのだけれど、永年交際(付き合)っていた彼、Kとの仲はだいぶ前から亀裂が出来ていた。・・・
(このままでは両方ともダメになってしまう)・・・
そして、二か月の世界旅行を思いたった。一人旅は不安なので、博多『みつばち』のマダム武富京子さんに相談すると、『一緒に行こう』と言ってくれた。・・・
最初の海外旅行というので美しい訪問着八枚、それに合わせて帯も三本、東京の呉服店『ちた和』でこしらえた。
お客様が壮行会を催して下さった。壮行会の案内状は・・・・・・。
太田恵子・武富京子を送る会
関西と鎮西に名も高き勇婦ふたりが、いよいよ欧米へ武者修行にゆくことに相成りました。・・・
ご多用の中恐れ入りますが、御寸暇を御割き下さいまして、来る三月二十四日御つどい賜りますよう伏してお願い申します。
代表世話人 今 東光
発起人 山脇義勇 吉原治良 中司清 八谷泰造 松島清重 小林米造
小原豊雲 正田健次郎 平山亮太郎 弘世現 杉道助
場所 クラブ 『井戸』 大阪市北区堂島浜通り」
そしてクラブ「太田」:
「『紫苑』を出てのんびり生きようと考えていた私に思いがけない話が舞い込んだ。『紫苑のすぐ近くに五十五坪の正方形の土地を持っているが、あなたなら売ってもよい』という方が現れた。・・・
大阪経済界の皆様から『やらせてやろう』と暖かい後援をいただいたこと、これがクラブ『太田』を誕生させる一番の力になった。・・・
昭和三十六年二月九日、クラブ『太田』開店。・・・
この日を期して、私は再び、クラブ『太田』に全力投球をはじめた。・・・」
マダムを引退:
「昭和四十八年、私は二十三年間のマダム生活に一応の別れを告げた。
クラブ『太田』は『夜の大阪商工会議所』といわれ、私を『夜の会頭』と呼んで下さる方も多かったが、何といっても引き際が肝心。・・・思い切って幕を引いた。・・・
引退パーティーは・・・大阪一のレストラン『アラスカ』の飯田さんが腕によりをかけてご馳走をつくってくれた。お客様のお土産には、スウェーデン製(コスタ社)のガラス皿に決めた。・・・
マダムをやめるとはいえ、私は『太田』のオーナー。完全にふっきれるといえば嘘になる。
その日、住友金属の日向方斉さん(現会長)からも、
『きみ、二頭政治はよくないよ』と小さな声で注意されていた。・・・
また、鐘淵化学の中司清さん(現相談役)からは、
『院政をしくのじゃないか? きっとそうだよ』と予言されていた。出処進退の難しさを、経済界の方はさすがによくわかっておられる。
しかし、私の新しい仕事ガラスの店はもう歩き始めている。(もうあとへはかえれない)・・・」
キャンドルの灯は消えて:
「私は、決心をした。年内閉店をーーー。
昭和五十年十二月十八日。クラブ『太田』閉店ーーー。
お別れパーティーの時、・・・四百名を上回る方々が、名残りを惜しんできてくださった。
まず、サントリーの佐治敬三社長から、『ママありがとう。ご苦労さん』とのご挨拶を受けたあと・・・パッと、店内の照明がつくと、佐治さんのリードで『星影のワルツ』の斉唱に移る。・・・
いの一番に来られた阪急電鉄の清水雅さん(会長)は、・・・お別れにと、ドーム作のルビー色の美しいガラスの蓋物をくださった。・・・
住友ゴム工業の下川常雄さん(会長)からいただいた、『大阪のひとつの灯が消えたね』という言葉を背にして、私は深夜の北新地を後にした。」
ナンシイの蝶/ガラスに魅かれて
「ガラスとの出合いは、戦後まもなく、まだ街には焼け跡がそのまま残っており、きれいなものも少なかったころのこと。西洋骨とう屋の店先で、ふと眼に入った蝶のカット皿と、ベネチアの赤のグラスに心魅かれたのが始まり。
昭和二十五年にバーを開店しているのだが、北新地の数ある店の中でガラスの灰皿を使ったのは私が初めてだそうで、『紫苑』の店では、ベネチアのシャンデリアを飾り、カウンターにもボヘミアのワイングラスを並べて大切にしていた。・・・
私は数年前、フランスのナンシイに蝶をみた。
この蝶のことは誰にも話さず、大切にあたためてきた。どんな言葉で表現すれば、この蝶にいだいている強烈な印象が判ってもらえるのか、まったく自信がなかったから。
フランスのナンシイ市にあるエコール・ド・ナンシイ・ミュージアムを訪れた時、ガレの家具(ベッド)にはめ込まれた二匹の蝶に心うばわれた。・・・
私は五千年の歴史をもつガラスをみてきて、十九世紀末のガラス工芸にハタと足が止まった。・・・」
パリの休日/美術館めぐり
「昭和五十年五月の連休、いつものように『みつばち』のママ京子さんを誘い、由水先生とヨヨさんと呼んでいる西洋美術のパリ在住の方と四人でガラスを中心に美術館巡りに出かけた。・・・
まずバルセロナに。・・・カーサ・ミラ、カーサ・バリリヨ、サグラダ・ファミリア教会、グエル公園、グエル邸など見て歩いた。
グエル公園の広場にはめ込まれた美しいモザイク模様の中に、私はピンクの蝶をみつけた。グエル邸は、有名なドラゴン・ゲートのみ残して、大部分とりこわされていたが、塀にそって歩いてみると、リラの花が咲き、十九世紀末のよき時代に誘い込んでくれた・・・・
そしてリェージュに。マース側に面したクルチュース美術館の中のガラス館を見る。小さいながら、これだけまとまっているのは珍しい。
エジプトから始まって、ローマ、ササン、ビザンチン、イスラム、そしてアール・ヌーヴォー期のものはティファニー、ガレ、ドーム、マリーノ、デコルシュモン、ワルター、ルソーなど、そして現代のものまでこじんまり入っている。こんな美術館が日本にあってもよいのにと考える。・・・
そこから一時間十五分でケルン着。まっすぐローマ・ゲルマン美術館に。
ここは二年前に新しくできた。ローマ時代のものの展示が中心である。ガラスの量の多いのでは世界一。・・・」
私の夢「ガラス美術館」
「・・・昭和四十五年の万国博で、漠然とマダム引退を考え始めた私は、それまで趣味だったガラスを仕事にする以外に道はないと、考えるようになっていた。
そこで、まず、西洋美術の社長の渡辺朗さんに相談をもちかけた。・・・『ガラスを仕事にしようと思いますのやけど』・・・
ガラスのことについて教えていただき、開店の日には値段から並べ方まで、手にとるようにお世話になった。
現代硝子は、銀座サン・モトヤマの社長茂登山さんに相談した。『ガラス、いいですね。いいと思いますよ』といってくださる。・・・
私は、芦原重義(関西電力会長)にテープカットしていただき、昭和四十八年六月にグラス・ギャラリー『ナンシイ』をロイヤルホテル地下に開店している。・・・
開店のお祝いにきてくださった吉村清三さん(関西電力副会長)は、『太田さん、こんなに高いものばっかり・・・・。何か買おう思うても買うものありませんがな。ネクタイ屋でも開店したら、私かて二本ぐらい買いますよ』・・・浅井孝二さん(住友銀行相談役)も、『高いものですね』とくりかえされる。もっともだと思う。・・・
ある日、松下幸之助さん(松下電器産業相談役)が入ってみえて、ラリックを指さし『これ、おくなはれ』といわれた。・・・
ラリックの香水瓶と、ブランデー・グラスをお買いになった森英恵さん。
金彩入りのアイス・バケツと、にぎりしめたらこわれそうなやはり金彩入りのバカラのグラスを買ってかえられたカルーセル・麻紀さん。
好きで仕入れたものが売れた時はやはり嬉しい。・・・
私はガラスを仕事にして、すぐにガラスがとても重荷になった。趣味にしていた時は、私の思うとおりになると思っていたガラスが、仕事にしてみると、きびしくて簡単に人をよせつけなくなった。私はやせた。・・・
『硝子はひとたび心を許すと、ずるずる引きずり込まれる魔性を持っている』と、美術史家の由水常雄先生は書いておられる。」
大阪にガラス美術館を
「私には、ひそかに育てている夢がある。・・・
若い人の間で、ガラスをつくってみたいという人がふえてきている。よいものをみてないひとに、よいものがつくれるはずがない。
クルチュース美術館のガラス館のようなものがつくれないものか。昨年、皇后様のゆかれたアメリカのサンドウィッチ・ガラス・ミュージアムも決して大規模なものではない。
ガラス、太陽の光線、とくに朝日の時が一番美しい。温度も採光もむつかしくはない。大阪にこじんまりしたものがつくれないものか。・・・
ガラスに対する世の中の評価はまだ低い。いまのうちなら値段もやすい。少しお金をかければ、国際的にははずかしくないものができるように思う。・・・」
「小さなナンシイ・ガラス・ハウスをつくってもらって、私はそこの館長さんになりたい。白髪でオカッパの館長さんに・・・・・・」
彼女の夢はかなえられたのだろうか。
次回に続く。















