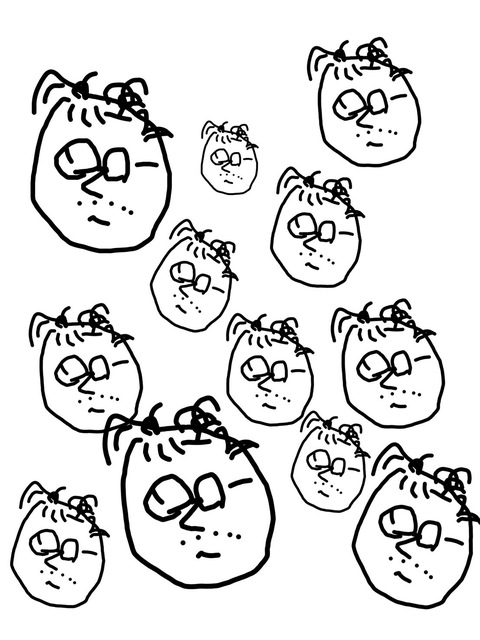待受箱は上段と下段の2段で1セットにした。
基本的に上段・下段ともに巣落ち防止棒は付けなくてよいらしい。
上段は天井板があるので、蜂は直接天井から巣を作るので巣落ちすることはないのだ。
巣が下に伸びてきたらこの上段と下段の間に継ぎ箱(中段)を足していく。
群れにもよるが活動期の巣の成長は早く、うっかりすると1ヶ月余りで下段の下方まで伸びてくる。
このとき巣落ち防止棒があると上段と下段はくっついてしまい、間に継ぎ箱を入れることが出来なくなる。
だから下段にも入れてはいけないのだ。
(この仕様だと仕方がないなぁ)
下段に必要なのは、出入り口と内検用のドアだ。
今回は採蜜後の巣箱(中段)を待受箱の下段に改修することにした。
既に使っていた巣なので、蜜蝋を塗る手間も省けるし、何よりも蜂が安心するのではないかと思う。

まず、巣落ち防止棒をカットする。
棒を入れるのは大変だがカットは簡単だ。あーーもったいない。


木ネジを緩め全面のパネルを外す。

下から7mmでカットし出入り口を作る。


待受箱下段の完成

次は水から出して天井板の取り付けをやらないとなぁ。
どこに置くかも考えないと。
いやー、楽しくてしょうがないゎ。
基本的に上段・下段ともに巣落ち防止棒は付けなくてよいらしい。
上段は天井板があるので、蜂は直接天井から巣を作るので巣落ちすることはないのだ。
巣が下に伸びてきたらこの上段と下段の間に継ぎ箱(中段)を足していく。
群れにもよるが活動期の巣の成長は早く、うっかりすると1ヶ月余りで下段の下方まで伸びてくる。
このとき巣落ち防止棒があると上段と下段はくっついてしまい、間に継ぎ箱を入れることが出来なくなる。
だから下段にも入れてはいけないのだ。
(この仕様だと仕方がないなぁ)
下段に必要なのは、出入り口と内検用のドアだ。
今回は採蜜後の巣箱(中段)を待受箱の下段に改修することにした。
既に使っていた巣なので、蜜蝋を塗る手間も省けるし、何よりも蜂が安心するのではないかと思う。

まず、巣落ち防止棒をカットする。
棒を入れるのは大変だがカットは簡単だ。あーーもったいない。


木ネジを緩め全面のパネルを外す。

下から7mmでカットし出入り口を作る。


待受箱下段の完成

次は水から出して天井板の取り付けをやらないとなぁ。
どこに置くかも考えないと。
いやー、楽しくてしょうがないゎ。