城見小学校に行っていたころ、学校の先生が言っていた。
「糠を食べると脚気にならん」と。
わが家の糠は、すべて牛にやっていた。
いくら先生が言うことでも、牛のエサを食おうとは思わなかった。
・・・・・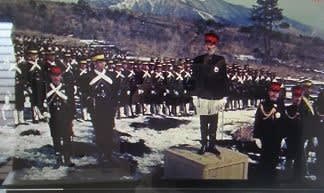
(新東宝映画「明治天皇と日露大戦争」)
・・・・・・
「知っておきたい和食の秘密」 渡辺望 勉誠出版 202年発行
かつてこの国に、「脚気(かっけ)」という恐ろしい病気があった。
全身に倦怠感が訪れ、やがて下半身が浮腫みはじめ、ついには感覚麻痺を引き起こし、最悪の場合心不全にいたって命を失う。
この脚気は肺結核と共に、若くて体力のある人にも容赦なくしかも不意に襲いかかる死病だった。
江戸時代、あまりに江戸内で、富裕層に多くみられる病だったため「江戸患い」とも呼ばれた。
ところが、地方や貧困層にいる人々には、この恐ろしい病は一向に縁がないのである。
江戸時代、漢方医が麦飯や雑穀を主食とする人たちに脚気がないことに気づき、麦飯治療法を主張した。
しかし蘭方医から「我が国の食文化を代表する米食が病気の原因であるはずがない」と激しく退けた。
しかし軍隊兵士に脚気が大流行し、これをなんとかしないと軍事力の停滞を招きかねないことになった。
森鴎外たち陸軍軍医グループと、高木兼寛たち海軍軍医グループの華々しい論争が始まった。
「麦飯問題=脚気論争」は解決を見ないまま、日清戦争と日露戦争に突入した。
その結果、麦飯と洋食を取り入れていていた海軍には脚気にによる死病者はほとんどゼロであった。
もし、敗戦という事態であったなら、その主原因の一つの森鴎外たち軍医グループも追及されていたに違いない。
・・・・・
日本食物史・吉川弘文館
「食べる」行為は、動物的、醜い行為ととらえられ、羞恥心からも食べる行為を見せたくない、話題にしないという考えが生じる。
いっぽうで一定の階層、儀式などに共通した食事作法が生まれた。
脚気
明治12年、5.000人の4割が脚気にかかり、57人が死亡した。
海軍軍医はパン食と野菜を多くした、死者は7人に減った。(陸軍軍医・森林太郎は細菌説だった)
・・
脚気
明治期に入ると国民病といわれるほど患者数が増加した。
とりわけ、
産業化につれて都市に集中するようになった貧困層に羅患者が多くみられ、その病因は副食が乏しい白米中心の食生活にあった。
症状が急転し、死に至ることも稀でなかった。
伝染病ととらえ怖れる人も少なくなかった。
1878年、患者は陸軍の1/3にのぼり、軍部内の深刻な問題になった。
陸軍に米麦混食が普及し、その結果、脚気の発生は低下傾向に向かった。
1910年鈴木梅太郎が玄米にオリザニン(ビタミンB1)があろことを発見、第一次大戦後、
恐ろしい伝染病とされていた脚気は、栄養に配慮することによって克服できる病気へと変わった。
・・・・・
「日本食物史」 江原・石川・東四共著 吉川弘文館 2009年発行
白米志向と脚気論争
栄養学に関する知識は、明治から大正時代にかけて急速に発展することになる。
アジアのように米を主食とする国に多発したのは脚気である。
古くは平安時代に脚気の文字がある。
米が精白されるとビタミンB1が取り去られる。
おかずにB1の豊富なものをとっていれば避けられるが、おかずの占める比率は低かった。
日本でビタミンB1の合成に成功し発売されたのは昭和13年のことであった。
・・・・・
(Wikipedia 森鴎外)
・・・・・
「満州事変から日中全面戦争へ」 伊香俊哉著 吉川弘文館 2007年発行
戦争栄養失調症
1938年春の徐州会戦に参加した兵士の中から、下痢症状が長くつづいたあげくに死亡するというケースが多発した。
軍医らが死亡原因の特定に努めた。
見解は、アメーバ赤痢が原因とするものと、実質的な餓死であるとするものに分れた。
「戦争栄養失調症」という病名に落ち着いた。
中国戦線においてもかなりの餓死者が出ていたのである。
O軍医は「当時私たちが栄養失調と呼んだ病気のなかのあるものは重症脚気であり、又あるものは全身の機能の衰えであった。
激しい労働と、偏った食糧、その絶対量の不足によったのは言うまでもない」
・・・・・
「日本の歴史 15巻」 大門正克著 小学館 2009年発行
戦病死とはなんなのか。
戦病死とは食糧不足による栄養失調とマラリア、脚気などの病気、行軍による心身消耗が重なって餓死することである。
日本の軍人・軍属の戦没者230万人のうち約6割が餓死だったとする研究を明らかにした。
・・・・・
「日本医療史」 新村拓著 吉川弘文館 2006年発行
戦時体制下の医療
「世界に冠絶する大和民族天賦の優良素質を今日ここまで低下せしめたるは衛生軽視の政治、行政機構に存するのである」として、
中央行政機関の整備を強調した。
1937年首相に就任した近衛文麿は、新しい省の腹案を提示した。1938年、厚生省が誕生した。
明治以来の内務省衛生局は新省の衛生・予防のほかに体力局によって担われることになった。
戦時体制下の健康問題
未熟練工が長時間労働に従事したため、機械による外傷や指の怪我などが増え、結核や脚気の羅患者も増大した。
・・・・・

















このラッパが音楽的に誠に上手で、これ以上のラッパ「君が代」を聞いたことがありません。しみじみとした曲でした。
信号ラッパであるため、下手でも士気を高める吹奏のほうが戦争映画らしいとも感じました。