氷とサトウキビーーカリブ海のヴォネガット
越川芳明
カート・ヴォネガットは、ヨーロッパ的というか、より正確に言えばドイツ的なコンテクストで語られ易い作家かもしれない。中西部インディアナポリスのドイツ人コミュニティで生まれ育ち、母方の家はビール醸造家として財を築いたが、第一次大戦が勃発すると国内は反ドイツのムードに染まり、禁酒法が母方の家を廃業に追い込む。第二次大戦のときに、ヴォネガットは軍隊に志願入隊しヨーロッパに向かうが、ドイツ軍の捕虜になりドレスデンに送られ、そこで連合国の空軍による空襲に遭遇する。かれ自身は屠畜場の地下室で運よく命拾いするが、地上では13万人ものドイツの民間人が黒焦げになっていた。そうしたヨーロッパでの戦争がヴォネガット家やかれ自身に引き起こした不条理な出来事ゆえに、またかれがそれらを出世作『スローターハウス5』に書いたために、ヴォネガットがドイツ的なコンテクストで語られるのは少しも不思議ではない。
だが、その後、冷戦時代の朝鮮戦争やヴェトナム戦争、さらに大儀なき戦争であることが次第に判明してきているイラク戦争を推し進めるなど、世界の「裸の王様」になったアメリカ合衆国の現在を考える参照点として、ヴォネガットはいち早く非ヨーロッパ的な地点に到達していたと見なすことはできないだろうか。
非ヨーロッパ的な地点とは、米国のすぐ南に位置するカリブ海である。カリブ文学の研究者、山本伸がいうように、これが加わることでカリブ文学がそれまで以上のポテンシャルを帯びたという「ディアスポラの視点」(1)をヴォネガットに期待するのは一見無謀に見えるかもしれないが、カイブ海を参照点にすることで、アメリカ作家ヴォネガットが何を成し遂げたか、わたしたちにどのような思考を促すのか、この小論で検討を加えてみたい。
原爆と特殊アイス
『猫のゆりかご』(1963年)は、ヴォネガットにしてはめずらしくカリブ海を舞台にした小説だ。しかも、原爆を開発した科学者のひとりとその子孫に焦点を当てるというフィクショナルな設定によって、この小説は原爆をトピックにした先駆的なアメリカ小説といえるかもしれない。確かに原爆を扱ったポストモダン小説は一例を挙げるだけでも、トマス・ピンチョンの『重力の虹』、ロバート・クーヴァーの『火刑』、ジェラルド・ヴィゼナーの『ヒロシマ・ブギ』、スティーヴ・エリクソンの『真夜中に海がやってくる』、リチャード・パワーズの『囚人のジレンマ』など、枚挙に暇がないが、ヴォネガットのSF的想像力は、原爆にとどまることなく、さらに脅威である化学物質を持ち出てくる。
原爆より脅威である化学物質とは、実のところ、ヴォネガットの考案によるものではない。ニューヨーク州にあるジェネラル・エレクトリック社の広報部に勤めていたときに、英作家のH・G・ウェルズが会社に訪ねてきて、接待をまかされたノーベル賞受賞学者のアーヴィング・ラングミュアが小説家にこんなSFのネタはいかがかでしょうか、と語ったものであり、当事者のふたりが亡くなったということで自分が拝借することにした、とヴォネガット自身告白している(2)。
ヴォネガットは、室温で水に混ぜるとたちどころに水を凍らせてしまうという、その致死的な化学物質に<アイス9>という名称を与えた。小説の中で、この物質の発明者の同僚だった老科学者が語り手に打ち明ける。発明者のところにいろいろな軍人が訪ねてきたが、とりわけ海兵隊の将軍が訪ねてきて、泥ぬかるみを解消する物質を発明してほしい、と依頼していたことが印象に残っている、と。
「エヴァーグレーズに完全装備の師団がはまりこんでも、救出にむかう海兵隊員は一人ですむように」(3)と、将軍は言ったという。
この化学物質を一滴でも垂らせば、フロリダの湿地帯をたちどころに凍らすことができる。海兵隊の将軍の目は、フロリダの湿地帯の彼方に、文字通り合衆国がはまりこんでいくヴェトナムの湿地帯を幻視していたかもしれないが、それはともかく、ここでヴォネガットは一国の軍隊が最先端の科学の成果を強力な兵器に変えることの脅威についての寓話を語っているのだが、なぜわざわざフロリダの湿地帯を例に挙げたのだろうか。
周知のように、フロリダの南部の湿地帯エヴァーグレーズthe Evergladesは、北のオキチョビー湖から南のフロリダ湾まで約100マイル、東西に60マイルもつづき、米国の亜熱帯の原野としては最大級のものであり、国立公園としてもイエローストーンに次ぐ規模を誇る。そこは、人間のよって飼いならされない自然の宝庫であり、絶滅の危機にあるアメリカン・クロコダイルやバンドウイルカ、マナティ、シラサギ、禿鷲などの奇種が生息。しかも、そこかしこにアリゲーターが潜んでいることで知られる。
フロリダに住むセミノール族は1817年より合衆国政府軍と3度の戦争を繰り返すが、政府軍にとって一番厄介なのはまさにその湿地帯だった。また、1898年の米西戦争でフロリダが合衆国の手に渡るまで、深南部の奴隷がフロリダの湿地帯に逃げのび、セミノール族に保護をもとめていた。合衆国の海兵隊にとって地獄と思えるところは、逃亡奴隷やセミノール族にとっては天国だった。そんな湿地帯を干上がらせたいという、小説の海兵隊の将軍の望みは、奇しくも湿地帯を農地に変えるという農業改革によって半ば実現しまった。現在はエヴァーグレーズの周辺にサトウキビ畑が広がり、と同時に運河を通じて畑の農薬がエヴァーグレーズの水を汚染するという公害が発生している。
1872年頃にエヴァーグレーズに生まれたというセミノール族のサム・ハフは、アメリカ人の人類学者に向かって、すでに1952年にこう語っていた。
「エヴァーグレーズじゃ、蒸気シャベルが運河を作り始めた。蒸気シャベルがフォート・ローダーデイルやディアフィールドからやってきて、オキチョビーのほうへ向かっていった。『蒸気シャベルがオキチョビー湖にたどり着いたら、すぐにエヴァーグレーズの水は干上がるぞ。そしたらプランテーションを始める』??そう白人たちが言った。・・・(中略)わたしはそのことを信じなかった。だが、水は実際に干上がった。オキチョビーでもだ。エヴァーグレーズは小さくなり、木がどんどん大きくなった」(4)
この小説を執筆中のヴォネガットの脳裡に、19世紀以降フロリダの湿地帯エヴァーグレーズを舞台にディアスポラ体験をしているセミノール族や逃亡奴隷のことが浮かんでいたとは考えにくい。しかし、ヴォネガットは海兵隊の将軍の目を通して、フロリダの湿地帯の彼方に、やがてアンクル・サムが文字通りはまり込んでいくヴェトナムの泥沼を幻視し、化学兵器の犠牲になるヴェトナムの人民のことに思いを馳せたかもしれない。小説に挟まれた海兵隊の将軍の野望にまつわる些細な一節がわたしたちをそんな奇想へと誘う。
脱走海兵隊員とディアスポラ黒人
海兵隊といえば、この小説の後半の舞台となっている、カリブ海のサン・ロレンソ共和国は、1922年にハイチに進駐した米海兵隊から脱走したアール・マッケイブ伍長という男が流れついたカリブ海の小島に作った国ということになっている。
マッケイブ伍長が作りあげた国は、首都の名がボリバールという、南米の植民地独立の英雄の名前にあやかっていながら、悪魔を絞め殺す大蛇ボアの絵が子供っぽいタッチで機体に描かれているプロペラ式戦闘機6機が米国から贈られたと語られるように、合衆国の完全な属国である。
1898年の米西戦争はカリブ海の覇権がヨーロッパからアメリカ合衆国へと移る象徴的な出来事であった。この年、合衆国は太平洋のグアム島、フィリピン諸島とならんで、カリブ海のプエルト・リコを軍事占領する。これ以降、キューバも1902年にスペインから独立後、アメリカ合衆国によって保護国化を余儀なくされ、ドミニカ共和国は1916年に軍事占領される。このように、二〇世紀の幕開けからカリブ海を軍事・経済戦略のひとつの拠点とするアメリカ合衆国の覇権主義が展開され、その先兵に立ったのが海兵隊だった。
サン・ロレンソ共和国のもう一人の立役者は、ボコノンという名の、トバーゴ出身でイギリス国籍をもつ黒人だ。二十世紀初頭にロンドンに渡り、高等教育を受けるが、そのとき第一次大戦が勃発して徴兵され、ヨーロッパの戦場で負傷を負う。その後も、ヨーロッパの起こす戦争に翻弄され世界各地を放浪。故郷に戻るもスクーナー船を建造して、気ままに航海していたが、ハリケーンを逃れてポルト・プランスに寄ったさいに、マッケイブ伍長に出会ったという次第。ボコノンこと、洗礼名ライオネル・ボイド・ジョンスンは、このようなイギリス植民地の支配を受けた周縁人でありながら、半分根こそぎのディアスポラの数奇な人生を送った黒人だった。
サン・ロレンソ共和国を樹立したふたりは、この島の住民の悲惨な状況を見るや、マッケイブは専制君主の<悪の権化>として振る舞い、ボコノンは地元宗教を創始し、人びとの<救世主>となる。
「政治や経済をいくら改革しても、人びとの暮しがすこしも楽にならないとわかってきて、ボコノン教だけが希望をつなぐ手段となった・・・ボコノンが自分とその宗教を追放してくれとマッケイブに頼んだんだ。人びとの宗教生活により熱がでるように、はりが出るように」(118)
宗教迫害にまつわる逆説を語ったこの一節は、ベネズエラのチャベス大統領のように、どうして中南米やカリブ海の国ぐにに人々によって愛される「独裁者」が誕生するのか、という疑問への小説家の想像力による解答になっているかもしれない。
サトウキビ畑のユダヤ人
『猫のゆりかご』には、サン・ロレンソのジャングルで肌の色の違う地元の人たちに無料の病院を建設し、ここ20年間人のために尽くしているらしいジュリアン・キャッスル(60歳を越えている)という名のアメリカ人砂糖成金が登場する。
サトウキビはコロンブスがニューギニアからエスパニョーラ島に導入したことから始まるといわれる。17世紀後半からプランテーション型の砂糖生産がはじまり、イギリス領バルバドスやフランス領マルチニーク、グアドループなどがその主な生産地だった。その後、イギリス領ジャマイカや、フランス領サン=ドマングが加わり、19世紀以降はキューバが最大の生産地となった。もちろん、そうしたプランテーションを支えていたのは奴隷制であった。
とはいえ、カリブ海は一括りに論じられない。サトウキビのプランテーション制でも島と島のあいだに差異があることを、人類学者のシドニー・W・ミンツは語っている。
「プエルト・リコには、スペイン人の植民者とアフリカ奴隷(多くがプエルト・リコの植民地史の比較的早い時期に自由民となった)の両方が定住したが、プランテーション制はイギリス領のジャマイカ(1655年以降)やフランス領のサン=ドミニーク(1697年以降)のようにプエルト・リコには根づかなかったが、そのことはプエルト・リコの小作人と、他のカリブ海の国のそれを区別する社会的特徴を決定する一助となるかもしれない」(5)
さらにミンツが別の著書で語るように、「カリブ海域全体にとって、そのほとんど全史を通じて着実な需要に恵まれたのは砂糖であった」(6)とすれば、ここにイベリア半島から追われたマラーノ(キリスト教に改宗した隠れユダヤ人)の商人の関与があっても不思議ではない。はたして十六世紀後半から世界最大の砂糖供給地になったブラジルでマラーノたちが関与していたのである。プランテーションが行われたのは、アフリカ奴隷の輸入先でもある北東部海岸地方のペルナンブーコとバイーア地方だった。オランダがバイーアでは1624年から、ペルナンブーコでは1630年から西インド会社を設立して砂糖の生産に乗り出す。増田義郎はマラーノたちの砂糖生産への関与についてこのように述べている。
「ペルナンブーコの『新オランダ』における砂糖産業の成功の陰には、ユダヤ系の『新キリスト教徒』の協力があった。ブラジルの有力な商人は、ポルトガルから移住してきた新キリスト教徒であった。彼らは、イベリア本国の宗教的圧迫のゆえにキリスト教に改宗したユダヤ人、またはその子孫であり、経済的実力をたくわえていたが、ユダヤ人ということで、つねに社会的に冷たい目で見られ、活動をはばまれていた。ところが、新教徒のオランダ人がはいってきたので、彼らはかつてない行動の自由を得、新来者に協力して、産業の発展に貢献したのである」(7)
ヴォネガットはカリブ海サトウキビ農業や砂糖生産において、ディアスポラのユダヤ人の果たした役割について触れてなどいない。だが、この小説には、広島に原爆が落とされた日に合衆国の著名人たちが何をしていたかという本を語り手が書こうとしている、といった設定があり、ヴォネガットは手段を選ばず植民地主義的な世界進出を行なうアンクル・サムや資本家に批判的だった。だから、狂気の慈善家キャッスルには、奴隷制プランテーションに加担したマラーノ商人ではなく、むしろ中南米やカリブ海で先住民の側に立った改宗ユダヤ人の神父ラス・カサスの影がちらつくのである。
註
(1)山本伸『カリブ文学研究入門』世界思想社、2004年、18頁。
(2)カート・ヴォネガット『ヴォネガット、大いに語る』飛田茂雄訳、ハヤカワ文庫、1988年、150-151頁。
(3)Kurt Vonnegut, Jr., Cat’s Cradle (New York: Dell, 1963), p.73.
(4)Patsy West, The Enduring Seminoles: From Alligator Wrestling to Ecotourism (Gainsville: UP of Florida, 1998), p.7.
(5)Sidney W. Mintz, Caribbean Transformations (Chicago: Aldine Publishing Company, 1974), p.141.
(6)シドニー・W・ミンツ『甘さと権力--砂糖が語る近代史』川北稔・和田光弘訳、平凡社、1988年、14頁。
(7)増田義郎『略奪の海 カリブ--もうひとつのラテン・アメリカ史』岩波新書、1989年、138頁。
(『英語青年』2007年8月号、8-10頁)
越川芳明
カート・ヴォネガットは、ヨーロッパ的というか、より正確に言えばドイツ的なコンテクストで語られ易い作家かもしれない。中西部インディアナポリスのドイツ人コミュニティで生まれ育ち、母方の家はビール醸造家として財を築いたが、第一次大戦が勃発すると国内は反ドイツのムードに染まり、禁酒法が母方の家を廃業に追い込む。第二次大戦のときに、ヴォネガットは軍隊に志願入隊しヨーロッパに向かうが、ドイツ軍の捕虜になりドレスデンに送られ、そこで連合国の空軍による空襲に遭遇する。かれ自身は屠畜場の地下室で運よく命拾いするが、地上では13万人ものドイツの民間人が黒焦げになっていた。そうしたヨーロッパでの戦争がヴォネガット家やかれ自身に引き起こした不条理な出来事ゆえに、またかれがそれらを出世作『スローターハウス5』に書いたために、ヴォネガットがドイツ的なコンテクストで語られるのは少しも不思議ではない。
だが、その後、冷戦時代の朝鮮戦争やヴェトナム戦争、さらに大儀なき戦争であることが次第に判明してきているイラク戦争を推し進めるなど、世界の「裸の王様」になったアメリカ合衆国の現在を考える参照点として、ヴォネガットはいち早く非ヨーロッパ的な地点に到達していたと見なすことはできないだろうか。
非ヨーロッパ的な地点とは、米国のすぐ南に位置するカリブ海である。カリブ文学の研究者、山本伸がいうように、これが加わることでカリブ文学がそれまで以上のポテンシャルを帯びたという「ディアスポラの視点」(1)をヴォネガットに期待するのは一見無謀に見えるかもしれないが、カイブ海を参照点にすることで、アメリカ作家ヴォネガットが何を成し遂げたか、わたしたちにどのような思考を促すのか、この小論で検討を加えてみたい。
原爆と特殊アイス
『猫のゆりかご』(1963年)は、ヴォネガットにしてはめずらしくカリブ海を舞台にした小説だ。しかも、原爆を開発した科学者のひとりとその子孫に焦点を当てるというフィクショナルな設定によって、この小説は原爆をトピックにした先駆的なアメリカ小説といえるかもしれない。確かに原爆を扱ったポストモダン小説は一例を挙げるだけでも、トマス・ピンチョンの『重力の虹』、ロバート・クーヴァーの『火刑』、ジェラルド・ヴィゼナーの『ヒロシマ・ブギ』、スティーヴ・エリクソンの『真夜中に海がやってくる』、リチャード・パワーズの『囚人のジレンマ』など、枚挙に暇がないが、ヴォネガットのSF的想像力は、原爆にとどまることなく、さらに脅威である化学物質を持ち出てくる。
原爆より脅威である化学物質とは、実のところ、ヴォネガットの考案によるものではない。ニューヨーク州にあるジェネラル・エレクトリック社の広報部に勤めていたときに、英作家のH・G・ウェルズが会社に訪ねてきて、接待をまかされたノーベル賞受賞学者のアーヴィング・ラングミュアが小説家にこんなSFのネタはいかがかでしょうか、と語ったものであり、当事者のふたりが亡くなったということで自分が拝借することにした、とヴォネガット自身告白している(2)。
ヴォネガットは、室温で水に混ぜるとたちどころに水を凍らせてしまうという、その致死的な化学物質に<アイス9>という名称を与えた。小説の中で、この物質の発明者の同僚だった老科学者が語り手に打ち明ける。発明者のところにいろいろな軍人が訪ねてきたが、とりわけ海兵隊の将軍が訪ねてきて、泥ぬかるみを解消する物質を発明してほしい、と依頼していたことが印象に残っている、と。
「エヴァーグレーズに完全装備の師団がはまりこんでも、救出にむかう海兵隊員は一人ですむように」(3)と、将軍は言ったという。
この化学物質を一滴でも垂らせば、フロリダの湿地帯をたちどころに凍らすことができる。海兵隊の将軍の目は、フロリダの湿地帯の彼方に、文字通り合衆国がはまりこんでいくヴェトナムの湿地帯を幻視していたかもしれないが、それはともかく、ここでヴォネガットは一国の軍隊が最先端の科学の成果を強力な兵器に変えることの脅威についての寓話を語っているのだが、なぜわざわざフロリダの湿地帯を例に挙げたのだろうか。
周知のように、フロリダの南部の湿地帯エヴァーグレーズthe Evergladesは、北のオキチョビー湖から南のフロリダ湾まで約100マイル、東西に60マイルもつづき、米国の亜熱帯の原野としては最大級のものであり、国立公園としてもイエローストーンに次ぐ規模を誇る。そこは、人間のよって飼いならされない自然の宝庫であり、絶滅の危機にあるアメリカン・クロコダイルやバンドウイルカ、マナティ、シラサギ、禿鷲などの奇種が生息。しかも、そこかしこにアリゲーターが潜んでいることで知られる。
フロリダに住むセミノール族は1817年より合衆国政府軍と3度の戦争を繰り返すが、政府軍にとって一番厄介なのはまさにその湿地帯だった。また、1898年の米西戦争でフロリダが合衆国の手に渡るまで、深南部の奴隷がフロリダの湿地帯に逃げのび、セミノール族に保護をもとめていた。合衆国の海兵隊にとって地獄と思えるところは、逃亡奴隷やセミノール族にとっては天国だった。そんな湿地帯を干上がらせたいという、小説の海兵隊の将軍の望みは、奇しくも湿地帯を農地に変えるという農業改革によって半ば実現しまった。現在はエヴァーグレーズの周辺にサトウキビ畑が広がり、と同時に運河を通じて畑の農薬がエヴァーグレーズの水を汚染するという公害が発生している。
1872年頃にエヴァーグレーズに生まれたというセミノール族のサム・ハフは、アメリカ人の人類学者に向かって、すでに1952年にこう語っていた。
「エヴァーグレーズじゃ、蒸気シャベルが運河を作り始めた。蒸気シャベルがフォート・ローダーデイルやディアフィールドからやってきて、オキチョビーのほうへ向かっていった。『蒸気シャベルがオキチョビー湖にたどり着いたら、すぐにエヴァーグレーズの水は干上がるぞ。そしたらプランテーションを始める』??そう白人たちが言った。・・・(中略)わたしはそのことを信じなかった。だが、水は実際に干上がった。オキチョビーでもだ。エヴァーグレーズは小さくなり、木がどんどん大きくなった」(4)
この小説を執筆中のヴォネガットの脳裡に、19世紀以降フロリダの湿地帯エヴァーグレーズを舞台にディアスポラ体験をしているセミノール族や逃亡奴隷のことが浮かんでいたとは考えにくい。しかし、ヴォネガットは海兵隊の将軍の目を通して、フロリダの湿地帯の彼方に、やがてアンクル・サムが文字通りはまり込んでいくヴェトナムの泥沼を幻視し、化学兵器の犠牲になるヴェトナムの人民のことに思いを馳せたかもしれない。小説に挟まれた海兵隊の将軍の野望にまつわる些細な一節がわたしたちをそんな奇想へと誘う。
脱走海兵隊員とディアスポラ黒人
海兵隊といえば、この小説の後半の舞台となっている、カリブ海のサン・ロレンソ共和国は、1922年にハイチに進駐した米海兵隊から脱走したアール・マッケイブ伍長という男が流れついたカリブ海の小島に作った国ということになっている。
マッケイブ伍長が作りあげた国は、首都の名がボリバールという、南米の植民地独立の英雄の名前にあやかっていながら、悪魔を絞め殺す大蛇ボアの絵が子供っぽいタッチで機体に描かれているプロペラ式戦闘機6機が米国から贈られたと語られるように、合衆国の完全な属国である。
1898年の米西戦争はカリブ海の覇権がヨーロッパからアメリカ合衆国へと移る象徴的な出来事であった。この年、合衆国は太平洋のグアム島、フィリピン諸島とならんで、カリブ海のプエルト・リコを軍事占領する。これ以降、キューバも1902年にスペインから独立後、アメリカ合衆国によって保護国化を余儀なくされ、ドミニカ共和国は1916年に軍事占領される。このように、二〇世紀の幕開けからカリブ海を軍事・経済戦略のひとつの拠点とするアメリカ合衆国の覇権主義が展開され、その先兵に立ったのが海兵隊だった。
サン・ロレンソ共和国のもう一人の立役者は、ボコノンという名の、トバーゴ出身でイギリス国籍をもつ黒人だ。二十世紀初頭にロンドンに渡り、高等教育を受けるが、そのとき第一次大戦が勃発して徴兵され、ヨーロッパの戦場で負傷を負う。その後も、ヨーロッパの起こす戦争に翻弄され世界各地を放浪。故郷に戻るもスクーナー船を建造して、気ままに航海していたが、ハリケーンを逃れてポルト・プランスに寄ったさいに、マッケイブ伍長に出会ったという次第。ボコノンこと、洗礼名ライオネル・ボイド・ジョンスンは、このようなイギリス植民地の支配を受けた周縁人でありながら、半分根こそぎのディアスポラの数奇な人生を送った黒人だった。
サン・ロレンソ共和国を樹立したふたりは、この島の住民の悲惨な状況を見るや、マッケイブは専制君主の<悪の権化>として振る舞い、ボコノンは地元宗教を創始し、人びとの<救世主>となる。
「政治や経済をいくら改革しても、人びとの暮しがすこしも楽にならないとわかってきて、ボコノン教だけが希望をつなぐ手段となった・・・ボコノンが自分とその宗教を追放してくれとマッケイブに頼んだんだ。人びとの宗教生活により熱がでるように、はりが出るように」(118)
宗教迫害にまつわる逆説を語ったこの一節は、ベネズエラのチャベス大統領のように、どうして中南米やカリブ海の国ぐにに人々によって愛される「独裁者」が誕生するのか、という疑問への小説家の想像力による解答になっているかもしれない。
サトウキビ畑のユダヤ人
『猫のゆりかご』には、サン・ロレンソのジャングルで肌の色の違う地元の人たちに無料の病院を建設し、ここ20年間人のために尽くしているらしいジュリアン・キャッスル(60歳を越えている)という名のアメリカ人砂糖成金が登場する。
サトウキビはコロンブスがニューギニアからエスパニョーラ島に導入したことから始まるといわれる。17世紀後半からプランテーション型の砂糖生産がはじまり、イギリス領バルバドスやフランス領マルチニーク、グアドループなどがその主な生産地だった。その後、イギリス領ジャマイカや、フランス領サン=ドマングが加わり、19世紀以降はキューバが最大の生産地となった。もちろん、そうしたプランテーションを支えていたのは奴隷制であった。
とはいえ、カリブ海は一括りに論じられない。サトウキビのプランテーション制でも島と島のあいだに差異があることを、人類学者のシドニー・W・ミンツは語っている。
「プエルト・リコには、スペイン人の植民者とアフリカ奴隷(多くがプエルト・リコの植民地史の比較的早い時期に自由民となった)の両方が定住したが、プランテーション制はイギリス領のジャマイカ(1655年以降)やフランス領のサン=ドミニーク(1697年以降)のようにプエルト・リコには根づかなかったが、そのことはプエルト・リコの小作人と、他のカリブ海の国のそれを区別する社会的特徴を決定する一助となるかもしれない」(5)
さらにミンツが別の著書で語るように、「カリブ海域全体にとって、そのほとんど全史を通じて着実な需要に恵まれたのは砂糖であった」(6)とすれば、ここにイベリア半島から追われたマラーノ(キリスト教に改宗した隠れユダヤ人)の商人の関与があっても不思議ではない。はたして十六世紀後半から世界最大の砂糖供給地になったブラジルでマラーノたちが関与していたのである。プランテーションが行われたのは、アフリカ奴隷の輸入先でもある北東部海岸地方のペルナンブーコとバイーア地方だった。オランダがバイーアでは1624年から、ペルナンブーコでは1630年から西インド会社を設立して砂糖の生産に乗り出す。増田義郎はマラーノたちの砂糖生産への関与についてこのように述べている。
「ペルナンブーコの『新オランダ』における砂糖産業の成功の陰には、ユダヤ系の『新キリスト教徒』の協力があった。ブラジルの有力な商人は、ポルトガルから移住してきた新キリスト教徒であった。彼らは、イベリア本国の宗教的圧迫のゆえにキリスト教に改宗したユダヤ人、またはその子孫であり、経済的実力をたくわえていたが、ユダヤ人ということで、つねに社会的に冷たい目で見られ、活動をはばまれていた。ところが、新教徒のオランダ人がはいってきたので、彼らはかつてない行動の自由を得、新来者に協力して、産業の発展に貢献したのである」(7)
ヴォネガットはカリブ海サトウキビ農業や砂糖生産において、ディアスポラのユダヤ人の果たした役割について触れてなどいない。だが、この小説には、広島に原爆が落とされた日に合衆国の著名人たちが何をしていたかという本を語り手が書こうとしている、といった設定があり、ヴォネガットは手段を選ばず植民地主義的な世界進出を行なうアンクル・サムや資本家に批判的だった。だから、狂気の慈善家キャッスルには、奴隷制プランテーションに加担したマラーノ商人ではなく、むしろ中南米やカリブ海で先住民の側に立った改宗ユダヤ人の神父ラス・カサスの影がちらつくのである。
註
(1)山本伸『カリブ文学研究入門』世界思想社、2004年、18頁。
(2)カート・ヴォネガット『ヴォネガット、大いに語る』飛田茂雄訳、ハヤカワ文庫、1988年、150-151頁。
(3)Kurt Vonnegut, Jr., Cat’s Cradle (New York: Dell, 1963), p.73.
(4)Patsy West, The Enduring Seminoles: From Alligator Wrestling to Ecotourism (Gainsville: UP of Florida, 1998), p.7.
(5)Sidney W. Mintz, Caribbean Transformations (Chicago: Aldine Publishing Company, 1974), p.141.
(6)シドニー・W・ミンツ『甘さと権力--砂糖が語る近代史』川北稔・和田光弘訳、平凡社、1988年、14頁。
(7)増田義郎『略奪の海 カリブ--もうひとつのラテン・アメリカ史』岩波新書、1989年、138頁。
(『英語青年』2007年8月号、8-10頁)










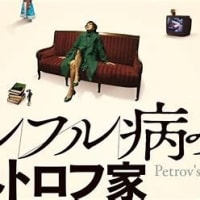
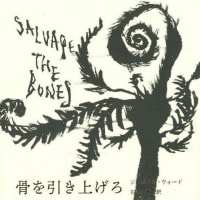

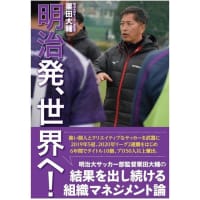












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます