11月27日 木曜日
●「和紙」が無形文化遺産に登録。
おめでとうございます。
昨年の「和食」につづき日本の職人芸がみとめられてスゴクうれしい。
●わが家は、ついこないだの、22日のブログでも書いたが「大麻商」だった。
この地方では「麻屋」という。
わたしの麻屋与志夫はペンネームなのだ。
注 ついこないだ。ついこのあいだ。つい昨日のように。
●鹿沼は日本一の昔は「麻」の産地だった。
わたしが家業をついだ昭和27年頃すでに斜陽産業だった。
その麻を精麻に引いて、芯縄やロープにしていた。
●前置きが長くなったが、その芯縄をつくる際の、切っ先――4,5センチの切りはしを和紙の産地に買っていただいていた。
すなわち、麻紙(まし)の原料となった。
●だから、和紙が無形文化遺産として登録がきまり、慶賀のいたりだ。
●ああ、早く「野州大麻」を書き出したいなぁ。
鹿沼の最後の麻屋としてがんばっていたころのことをぜひ、書き遺したい。
わたしにしか、書けない作品だ。
●いまは、栃木に数軒当時の同業者がのこっている。
鹿沼では絶滅。
滅びてしまった商売を、古いことばや、因習に囚われていた業界のことを書き残して置きたいのだが、なんども考えているのだがリアリズム文学を書く文体をもたないわたしに可能なのだろうか。
●試してみる価値はある。
●滅びてしまった、わたしの心の中では、生き続けている無形文化遺産のような「職業」である「野州大麻商」のことを書きたい。
●努力してみる価値はありそうだ。
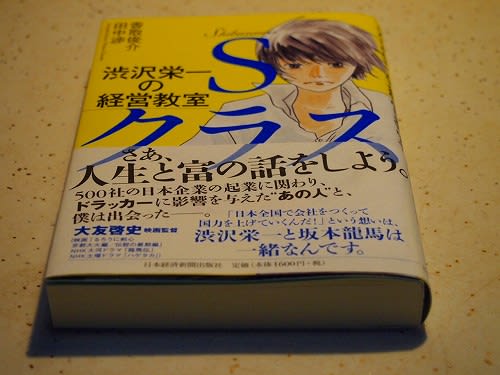
日本経済新聞出版社刊。
親友香取俊介氏の作品です。わたしはいま再再読しています。
おもしろいですよ。いろいろな読み方のできる懐の広い作品です。
学生には、道徳の書としても読めると思います。
各紙の書評欄で好評です。ぜひご高読下さい。
今日も遊びに来てくれてありがとうございます。
お帰りに下のバナーを押してくださると…活力になります。
皆さんの応援でがんばっています。
 にほんブログ村
にほんブログ村
●「和紙」が無形文化遺産に登録。
おめでとうございます。
昨年の「和食」につづき日本の職人芸がみとめられてスゴクうれしい。
●わが家は、ついこないだの、22日のブログでも書いたが「大麻商」だった。
この地方では「麻屋」という。
わたしの麻屋与志夫はペンネームなのだ。
注 ついこないだ。ついこのあいだ。つい昨日のように。
●鹿沼は日本一の昔は「麻」の産地だった。
わたしが家業をついだ昭和27年頃すでに斜陽産業だった。
その麻を精麻に引いて、芯縄やロープにしていた。
●前置きが長くなったが、その芯縄をつくる際の、切っ先――4,5センチの切りはしを和紙の産地に買っていただいていた。
すなわち、麻紙(まし)の原料となった。
●だから、和紙が無形文化遺産として登録がきまり、慶賀のいたりだ。
●ああ、早く「野州大麻」を書き出したいなぁ。
鹿沼の最後の麻屋としてがんばっていたころのことをぜひ、書き遺したい。
わたしにしか、書けない作品だ。
●いまは、栃木に数軒当時の同業者がのこっている。
鹿沼では絶滅。
滅びてしまった商売を、古いことばや、因習に囚われていた業界のことを書き残して置きたいのだが、なんども考えているのだがリアリズム文学を書く文体をもたないわたしに可能なのだろうか。
●試してみる価値はある。
●滅びてしまった、わたしの心の中では、生き続けている無形文化遺産のような「職業」である「野州大麻商」のことを書きたい。
●努力してみる価値はありそうだ。
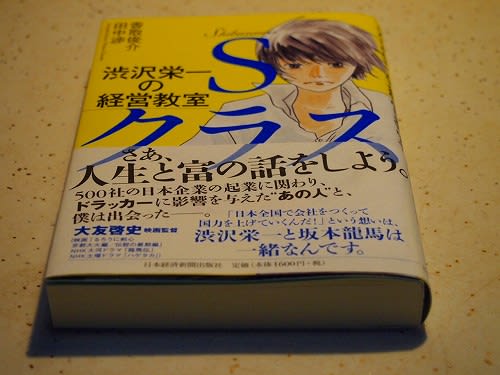
日本経済新聞出版社刊。
親友香取俊介氏の作品です。わたしはいま再再読しています。
おもしろいですよ。いろいろな読み方のできる懐の広い作品です。
学生には、道徳の書としても読めると思います。
各紙の書評欄で好評です。ぜひご高読下さい。
今日も遊びに来てくれてありがとうございます。
お帰りに下のバナーを押してくださると…活力になります。
皆さんの応援でがんばっています。










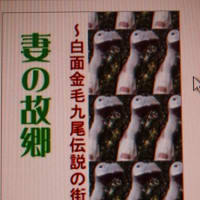
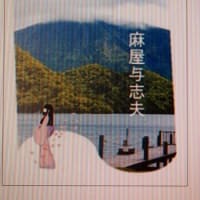
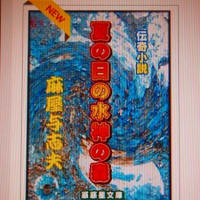
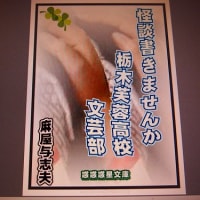






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます