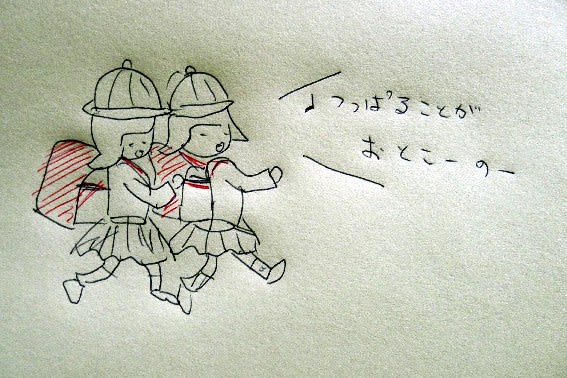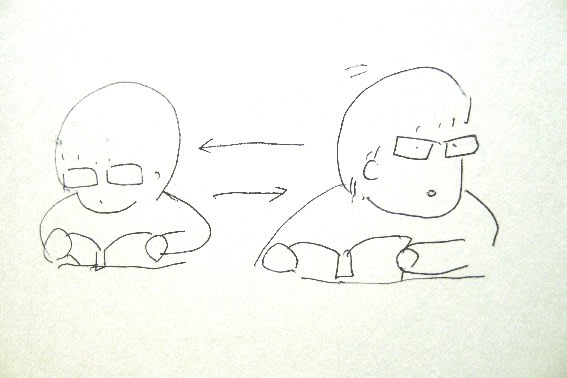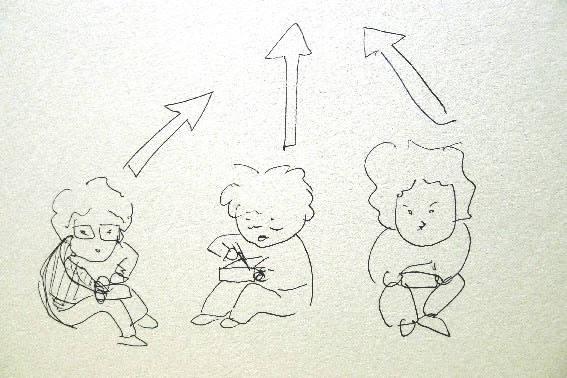それは十月にしてはひどく蒸し暑い夜だった。人々が行き交う。何がおかしいのかにやけた愛想笑いを浮かべたスーツがもう一人のスーツをへつらう。男の腕にぶら下がる様に歩く女の視線は冷ややかだ。私はめったに訪れない都会の喧噪にうんざりしながら依頼人の指定したバーを目指した。その店は知らなければ到底到達できないであろう路地の奥にあった。
私に依頼をする人種は大抵がろくな物じゃない。やくざの集金代行か、ストーカーの手助け、はたまたゆすりの証拠集め。今夜はどんなトラブルに首を突っ込む羽目になるのか自分でも分からない。
重みのある木製の扉を押し開ける。初老のマスターがグラスを拭き上げている姿が目に入る。カウンターの端にちょこんと座る女の怯えるような瞳と目があった。栗色の短髪。フォーマルな服装の美しい女性だ。胸のポケットには目印である紫色のスカーフが見えた。私は店内に身を滑り込ませた。女?俺に何の依頼をするつもりだ。
「あなたが連絡をくれた方ですか」私は女のそばで立ち止まった。
「そうです」
私は女の隣に座りふただび口を開いた。
「私は裏の世界の住人なのですが、ご存じですか」
「存じ上げています。そして敵が多いことも存じ上げています」
「敵が多いのは自分でも十分承知しているが、あなたと何の関係がありますか」私はいつでも立ち上がれる様にイスから重心を半分ずらした。
「今夜ある賭けが行われます」
女は質問には答えずそうつぶやいた。
「勝者には敗者の身につけている金品を奪うことが許されます。スポンサーはあなたに恨みを持つ物達です」
内容は聞こえたが、穏やかでは無い内容にオウム返しで聞き返しそうになった。
戸外の熱気と共にドアが勢いよく開いた。ずっしりとしたロングコートの男が懐から両手を引き出すのが見えた。
まさか
素早く引き出される男の両手には鈍く光るオートマチックがあった。銃口がまっすぐこちらに向きつつあった。
私は女をひきずり降ろして向かいのイス席に転がり込んだ。閃光と銃声が店内を支配する。マスターの右肩が跳ね上がり、崩れ落ちた。全弾打ち尽くした銃のスライドが後退したまま止まる気配を感じる。馬鹿めアマチュアめ。二丁とも同時に弾を打ち尽くすとは、拳銃を二丁持っている意味が無い。私はそう思いながらボックス席から飛び出し男に突進する。男は二丁の空マガジンは排出したが、同時にマガジンチェンジが出来ない事実に呆然としながら二丁の拳銃を放り投げた。男は腰を落としながら自分のブーツのすねに手をつっこもうとしている。ナイフかそれともバックアップのコンシールド銃か。私はカウンターから落ちたであろうジャックダニエルの瓶を男に投げつける。ジャックダニエルは回転しながら男の手に当たる。ブーツから取り出したナイフが手から落ちる。私は懇親のフットスタンプを男の顔面に両足でお見舞いしてやった。カエルを踏んだような声を出して男は昏倒した。
男を見下ろしながら用心深く私は立ち上がった。
いやな気配を首筋に感じた。
私は後ろを振り向くように身をよじりながらその場にかがんだ。頭上に一陣の風が通り向けた。
私の後頭部を狙ったであろう瓶が空を切ったのだ。ジョニ黒だった。瓶が当たるべき衝撃を感じられず体を崩すマスターがそこにいた。なぜ?
次の瞬間、負傷している老マスターは大声をあげ、カウンターの氷に刺さっていたアイスピックを握りしめ私に襲いかかる。一突き目をかわしながら私はマスターの足をねらって刈る。マスターはくるりと半円を描いてマスターは転んだ。私は一人目の男が放り出した銃を拾い、二丁とも転んだマスターの顔面に投げつける。一丁は手で払いのけたが、二丁目は腕をかいくぐりマスターの鼻頭にまともに当たった。ネズミを踏みつけたような声を出してマスターは昏倒した。
次の瞬間、私は背後から針金状のものを首にひっかけられて背負われた。針金のハンガーを延ばしたものだな。危険な状況だったが、どこか余裕を感じていた。これこそがまさに危険だった。余裕では無くパニックに陥っているのだ。シャンプーのいい匂いがする。まさか、依頼人だと言っていたあの女か。私は狭い店内の壁を思い切り蹴った。女共々床に倒れ込む。自分の後頭部を思い切り振りかぶって女の後頭部をぶんなぐる。首にめりこむ針金がゆるむ。私は針金の隙間に両手を入れながら強引に立ち上がる。再び懇親の力を込めて女の顔面にフットスタンプをお見舞いした。今度はモグラを踏んだような感触を残して女が気絶した。
結局なんだったのか。
昏倒している三人のポケットにはそれぞれ百万円の束が二つずつあった。私は無言で六つの札束を回収してその場を後にした。
無論、実況中継していたであろうカメラシステムを可能な限り店内で破壊していくことを忘れなかった。
まあ、金も入ったし、結果的にいい夜になったと自分に言い聞かせた。
私に依頼をする人種は大抵がろくな物じゃない。やくざの集金代行か、ストーカーの手助け、はたまたゆすりの証拠集め。今夜はどんなトラブルに首を突っ込む羽目になるのか自分でも分からない。
重みのある木製の扉を押し開ける。初老のマスターがグラスを拭き上げている姿が目に入る。カウンターの端にちょこんと座る女の怯えるような瞳と目があった。栗色の短髪。フォーマルな服装の美しい女性だ。胸のポケットには目印である紫色のスカーフが見えた。私は店内に身を滑り込ませた。女?俺に何の依頼をするつもりだ。
「あなたが連絡をくれた方ですか」私は女のそばで立ち止まった。
「そうです」
私は女の隣に座りふただび口を開いた。
「私は裏の世界の住人なのですが、ご存じですか」
「存じ上げています。そして敵が多いことも存じ上げています」
「敵が多いのは自分でも十分承知しているが、あなたと何の関係がありますか」私はいつでも立ち上がれる様にイスから重心を半分ずらした。
「今夜ある賭けが行われます」
女は質問には答えずそうつぶやいた。
「勝者には敗者の身につけている金品を奪うことが許されます。スポンサーはあなたに恨みを持つ物達です」
内容は聞こえたが、穏やかでは無い内容にオウム返しで聞き返しそうになった。
戸外の熱気と共にドアが勢いよく開いた。ずっしりとしたロングコートの男が懐から両手を引き出すのが見えた。
まさか
素早く引き出される男の両手には鈍く光るオートマチックがあった。銃口がまっすぐこちらに向きつつあった。
私は女をひきずり降ろして向かいのイス席に転がり込んだ。閃光と銃声が店内を支配する。マスターの右肩が跳ね上がり、崩れ落ちた。全弾打ち尽くした銃のスライドが後退したまま止まる気配を感じる。馬鹿めアマチュアめ。二丁とも同時に弾を打ち尽くすとは、拳銃を二丁持っている意味が無い。私はそう思いながらボックス席から飛び出し男に突進する。男は二丁の空マガジンは排出したが、同時にマガジンチェンジが出来ない事実に呆然としながら二丁の拳銃を放り投げた。男は腰を落としながら自分のブーツのすねに手をつっこもうとしている。ナイフかそれともバックアップのコンシールド銃か。私はカウンターから落ちたであろうジャックダニエルの瓶を男に投げつける。ジャックダニエルは回転しながら男の手に当たる。ブーツから取り出したナイフが手から落ちる。私は懇親のフットスタンプを男の顔面に両足でお見舞いしてやった。カエルを踏んだような声を出して男は昏倒した。
男を見下ろしながら用心深く私は立ち上がった。
いやな気配を首筋に感じた。
私は後ろを振り向くように身をよじりながらその場にかがんだ。頭上に一陣の風が通り向けた。
私の後頭部を狙ったであろう瓶が空を切ったのだ。ジョニ黒だった。瓶が当たるべき衝撃を感じられず体を崩すマスターがそこにいた。なぜ?
次の瞬間、負傷している老マスターは大声をあげ、カウンターの氷に刺さっていたアイスピックを握りしめ私に襲いかかる。一突き目をかわしながら私はマスターの足をねらって刈る。マスターはくるりと半円を描いてマスターは転んだ。私は一人目の男が放り出した銃を拾い、二丁とも転んだマスターの顔面に投げつける。一丁は手で払いのけたが、二丁目は腕をかいくぐりマスターの鼻頭にまともに当たった。ネズミを踏みつけたような声を出してマスターは昏倒した。
次の瞬間、私は背後から針金状のものを首にひっかけられて背負われた。針金のハンガーを延ばしたものだな。危険な状況だったが、どこか余裕を感じていた。これこそがまさに危険だった。余裕では無くパニックに陥っているのだ。シャンプーのいい匂いがする。まさか、依頼人だと言っていたあの女か。私は狭い店内の壁を思い切り蹴った。女共々床に倒れ込む。自分の後頭部を思い切り振りかぶって女の後頭部をぶんなぐる。首にめりこむ針金がゆるむ。私は針金の隙間に両手を入れながら強引に立ち上がる。再び懇親の力を込めて女の顔面にフットスタンプをお見舞いした。今度はモグラを踏んだような感触を残して女が気絶した。
結局なんだったのか。
昏倒している三人のポケットにはそれぞれ百万円の束が二つずつあった。私は無言で六つの札束を回収してその場を後にした。
無論、実況中継していたであろうカメラシステムを可能な限り店内で破壊していくことを忘れなかった。
まあ、金も入ったし、結果的にいい夜になったと自分に言い聞かせた。