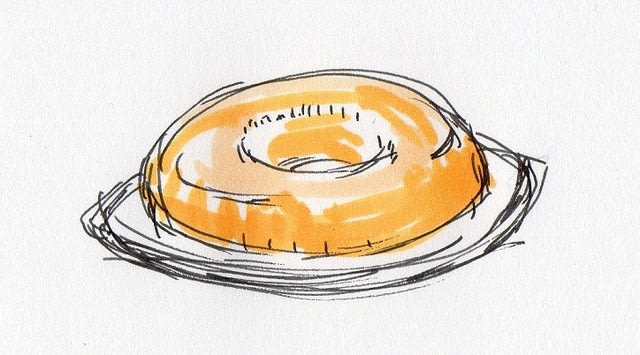対応する男
約束の時間はとうに過ぎている。和宏は待ちきれずに、とうとう玄関の前に立っていた。うららかな休日の午後。今日は和宏にとってクリーム色のスポーツセダンが納車される特別な日だった。
和宏はそわそわしながら通りを見ている。昨夜なかなか寝付けなかった。布団の中で、新車のステアリングを握る自分。助手席に座る妻。桜並木を駆け抜ける景色を想像すると、俺もなかなか捨てたもんじゃ無いなと興奮を覚えた。
和宏が通りを見ているのには訳があった。和宏の住まいは一方通行の多い、奥まった場所にある。ここに車で到着するにはちょっとしたコツが必要だった。ディーラーの営業マンには地図を渡して説明した。
「了解しました」
調子のいい若者だったが、和宏は一抹の不安を感じていた。
その時、クリーム色のセダンが通りの逆を走っていくのが見えた。
「ああ、その道は違う」
家に来るためにはもう一度大通りに出て、別の道に入り直す必要がある。
「これは時間がかかるな」
そう一人つぶやいて和宏は居間に戻る。
アクシデントを乗り越えて無事納車された。
納車後一週間が過ぎた。科学者である和宏にはある発見があった。ハンドルを握ると不思議と思考のまとまりを感じていた。
十年目、セダンの調子が悪くなった。買い換えか修理か。悩んだ和宏は修理に出した。
二十年目、ふらふらするセダンの足まわりと排気漏れがうるさいマフラーを交換した。
三十年目、ゴム関係の部品在庫があるうちに出来るだけ交換した。
和宏はある夜、時間路線図なるものを発明する。現在の時間に接続して乗り入れたものがいる場合、履歴として表示されるものだった。
半ば冗談でつくったものだった。なぜなら、時間旅行の出来るものなどいないとふんでいたためだ。しかし、和宏を中心に十年、二十年、三十年に一回づつ何者かが乗り入れてた。
和宏にはぴんとくるものがあった。クリーム色のセダンと関係があるのでは無いだろうか。
和宏はガレージに向かう。
少々くたびれてはいるが愛車のセダンがそこには止まっている。もう少しで四十年、この車と一緒にいることになる。
ドアを開けて車内に入る。ライトで照らしながら和宏は痕跡を探す。普段はあまり開けない後部座席の小物入れを開けてみる。丸まった状態の紙屑があった。延ばしてみると、それは見に覚えの無い飲み屋のレシートだった。日付をみて驚愕する。今から十年後の未来の日付が印刷されている。
和宏はある仮説を立てる。
十年の節目ごとにセダンが調子を崩し、修理をした。
これは、調子の悪くなったセダンと共に過去に遡り、車を交換する。状態の良いセダンを未来に乗っていく。この行為を繰り返したのか?
こんな事をする人物は一人しかいない。
和宏は、平行宇宙の自分は作ることに成功したはずだと確信して、タイムマシンの開発に着手する。
約束の時間はとうに過ぎている。和宏は待ちきれずに、とうとう玄関の前に立っていた。うららかな休日の午後。今日は和宏にとってクリーム色のスポーツセダンが納車される特別な日だった。
和宏はそわそわしながら通りを見ている。昨夜なかなか寝付けなかった。布団の中で、新車のステアリングを握る自分。助手席に座る妻。桜並木を駆け抜ける景色を想像すると、俺もなかなか捨てたもんじゃ無いなと興奮を覚えた。
和宏が通りを見ているのには訳があった。和宏の住まいは一方通行の多い、奥まった場所にある。ここに車で到着するにはちょっとしたコツが必要だった。ディーラーの営業マンには地図を渡して説明した。
「了解しました」
調子のいい若者だったが、和宏は一抹の不安を感じていた。
その時、クリーム色のセダンが通りの逆を走っていくのが見えた。
「ああ、その道は違う」
家に来るためにはもう一度大通りに出て、別の道に入り直す必要がある。
「これは時間がかかるな」
そう一人つぶやいて和宏は居間に戻る。
アクシデントを乗り越えて無事納車された。
納車後一週間が過ぎた。科学者である和宏にはある発見があった。ハンドルを握ると不思議と思考のまとまりを感じていた。
十年目、セダンの調子が悪くなった。買い換えか修理か。悩んだ和宏は修理に出した。
二十年目、ふらふらするセダンの足まわりと排気漏れがうるさいマフラーを交換した。
三十年目、ゴム関係の部品在庫があるうちに出来るだけ交換した。
和宏はある夜、時間路線図なるものを発明する。現在の時間に接続して乗り入れたものがいる場合、履歴として表示されるものだった。
半ば冗談でつくったものだった。なぜなら、時間旅行の出来るものなどいないとふんでいたためだ。しかし、和宏を中心に十年、二十年、三十年に一回づつ何者かが乗り入れてた。
和宏にはぴんとくるものがあった。クリーム色のセダンと関係があるのでは無いだろうか。
和宏はガレージに向かう。
少々くたびれてはいるが愛車のセダンがそこには止まっている。もう少しで四十年、この車と一緒にいることになる。
ドアを開けて車内に入る。ライトで照らしながら和宏は痕跡を探す。普段はあまり開けない後部座席の小物入れを開けてみる。丸まった状態の紙屑があった。延ばしてみると、それは見に覚えの無い飲み屋のレシートだった。日付をみて驚愕する。今から十年後の未来の日付が印刷されている。
和宏はある仮説を立てる。
十年の節目ごとにセダンが調子を崩し、修理をした。
これは、調子の悪くなったセダンと共に過去に遡り、車を交換する。状態の良いセダンを未来に乗っていく。この行為を繰り返したのか?
こんな事をする人物は一人しかいない。
和宏は、平行宇宙の自分は作ることに成功したはずだと確信して、タイムマシンの開発に着手する。
新商品見本市にて
おい。そこの青年。そのカメラの説明をしてもらおうか。心配せずとも、お金なら持っているぞ青年。気に入れば何台でも買うぞ。
ほう、ファインダーに小さなテレビ画面がはめこまれていて、レンズを通して見えるものが、映像として見えるのだな。それはすばらしいな。
ほう、センサーというものがフルサイズなのか。
ほう、一秒で十四コマ連写できるのか。
ほう、暗闇でも7、5段分の手ぶれ補正か。
しかし、ワシの持つ物の方が高性能じゃ。購入は来年の新作だ。なに、ワシが持っている物の機種は何だって。言ったろう。ワシはお金と暇は持て余しておる。自分で開発したんじゃ。走っていても目の前の景色は揺れもせず鮮明じゃ。暗闇でもしばらく待っておればかなり見える。ビタミンAも採っておる。ブルーベリーなんかもいいらしい。まだまだ、現行のカメラに負けないくらい、ワシの目の方が高性能じゃ。ちなみにカメラはこれが最高じゃ。
レンズ付きカメラのフラッシュが瞬く。
後学の為に、カメラとレンズ、一通りのパンフレットくれるか。お金はあるんじゃぞ。
おい。そこの青年。そのカメラの説明をしてもらおうか。心配せずとも、お金なら持っているぞ青年。気に入れば何台でも買うぞ。
ほう、ファインダーに小さなテレビ画面がはめこまれていて、レンズを通して見えるものが、映像として見えるのだな。それはすばらしいな。
ほう、センサーというものがフルサイズなのか。
ほう、一秒で十四コマ連写できるのか。
ほう、暗闇でも7、5段分の手ぶれ補正か。
しかし、ワシの持つ物の方が高性能じゃ。購入は来年の新作だ。なに、ワシが持っている物の機種は何だって。言ったろう。ワシはお金と暇は持て余しておる。自分で開発したんじゃ。走っていても目の前の景色は揺れもせず鮮明じゃ。暗闇でもしばらく待っておればかなり見える。ビタミンAも採っておる。ブルーベリーなんかもいいらしい。まだまだ、現行のカメラに負けないくらい、ワシの目の方が高性能じゃ。ちなみにカメラはこれが最高じゃ。
レンズ付きカメラのフラッシュが瞬く。
後学の為に、カメラとレンズ、一通りのパンフレットくれるか。お金はあるんじゃぞ。
勝負喫茶
店員「いらっしゃい」
客「アイスコーヒー一つ」
店員「かしこまりました。で、勝負されますか?」
客「は?」
店員「私と勝負する事によっていろいろな特典がございます。どうされますか」
客「得なことがあるんなら何だってするよ」
店員「では少々お待ちください」
しばらくすると店員はアイスコーヒーを二つ持ってきた。テーブルに並べる。
店員「ではアイスコーヒー早飲み勝負スタートです」
客「いやだよ。アイスコーヒーなんてその気になったらすぐ飲み終わっちゃうよ」
店員「いやですか」
店員は向かいの席に座る。アイスコーヒーにガムシロップとミルクを入れて、飲み出す。
客「君、飲んだね。そのアイスコーヒーの代金はどうなってるの?」
店員「もちろんお客様のお会計に入れさせていただいてます。勝負に勝てばただだったんですけどねえ」
客「じゃあ、勝負するよ」
店員「では将棋でどうですか」
客「いいよ」
客も自分のアイスコーヒーにガムシロップとクリームを入れる。
一時間後。
店員が勝利する。
客「あんた強いね。今回はおごる。でも次は勝ちますよ」
店員「毎度」
客は悔しげに店を後にする。
店員は、最強将棋ソフトからの指示を受けていたインカムを自分の耳から外す。この店の勝負はすべてイカサマで店員が勝利するシステムになっている。
店員「いらっしゃい」
客「アイスコーヒー一つ」
店員「かしこまりました。で、勝負されますか?」
客「は?」
店員「私と勝負する事によっていろいろな特典がございます。どうされますか」
客「得なことがあるんなら何だってするよ」
店員「では少々お待ちください」
しばらくすると店員はアイスコーヒーを二つ持ってきた。テーブルに並べる。
店員「ではアイスコーヒー早飲み勝負スタートです」
客「いやだよ。アイスコーヒーなんてその気になったらすぐ飲み終わっちゃうよ」
店員「いやですか」
店員は向かいの席に座る。アイスコーヒーにガムシロップとミルクを入れて、飲み出す。
客「君、飲んだね。そのアイスコーヒーの代金はどうなってるの?」
店員「もちろんお客様のお会計に入れさせていただいてます。勝負に勝てばただだったんですけどねえ」
客「じゃあ、勝負するよ」
店員「では将棋でどうですか」
客「いいよ」
客も自分のアイスコーヒーにガムシロップとクリームを入れる。
一時間後。
店員が勝利する。
客「あんた強いね。今回はおごる。でも次は勝ちますよ」
店員「毎度」
客は悔しげに店を後にする。
店員は、最強将棋ソフトからの指示を受けていたインカムを自分の耳から外す。この店の勝負はすべてイカサマで店員が勝利するシステムになっている。
マジック・ラーメン
客「マジックとラーメンの融合。本日開店か……」
店員「いらっしゃいませ」
表情の読めない仮面をかぶり、シルクハット、タキシード姿の店員がぽつんと立っている。
客「ラーメン屋さんで合ってますよね」
店員「はい。本日開店のマジック・ラーメンでございます。ただいまイスとテーブルをお出しします」
店員が指をパチンと鳴らすと、炎が目の前の空間を舞う。いつの間にか一人用のテーブルとイスが出現している。
店員「どうぞこちらへ。メニューをどうぞ」
店員は客に手を見せる。直後、炎があがる。メニューがあらわれた。
客はいちいち立ち上ぼる炎を内心嫌いながらメニューを広げる。
客「つけ麺と餃子」
店員「かしこまりました」
店員が厨房に下がる。
しばらくするとポール・モーリアの曲にのせて、先ほどの店員と女性助手が大きな縦長の箱を客の近くまで運んでくる。ちなみに女性助手はパートのおばちゃんだ。
店員は箱の扉を開けて、客を中に入るように促す。
客「入るの?」
店員は無言でうなずく。
客が箱の中に入ると、扉は閉められる。その場で箱がくるりと一回転する。
箱の外で、硬質な刃を打ち付けあう音が真っ暗な空間にいる客の耳に届く。
客「何するんですか」
店員「安心してください。今から二十本の刀を差します。脱出ショーです。無事外に出ることはできるのでしょうか」
客「全然、安心ではありません」右から左から、前から後ろから、刀を差し込む気配が響く。
ドラムロールが鳴った。
じゃーん
客は無傷で外に出る。テーブルには、つけ麺と餃子が出来上がっていた。
客「マジックとラーメンの融合。本日開店か……」
店員「いらっしゃいませ」
表情の読めない仮面をかぶり、シルクハット、タキシード姿の店員がぽつんと立っている。
客「ラーメン屋さんで合ってますよね」
店員「はい。本日開店のマジック・ラーメンでございます。ただいまイスとテーブルをお出しします」
店員が指をパチンと鳴らすと、炎が目の前の空間を舞う。いつの間にか一人用のテーブルとイスが出現している。
店員「どうぞこちらへ。メニューをどうぞ」
店員は客に手を見せる。直後、炎があがる。メニューがあらわれた。
客はいちいち立ち上ぼる炎を内心嫌いながらメニューを広げる。
客「つけ麺と餃子」
店員「かしこまりました」
店員が厨房に下がる。
しばらくするとポール・モーリアの曲にのせて、先ほどの店員と女性助手が大きな縦長の箱を客の近くまで運んでくる。ちなみに女性助手はパートのおばちゃんだ。
店員は箱の扉を開けて、客を中に入るように促す。
客「入るの?」
店員は無言でうなずく。
客が箱の中に入ると、扉は閉められる。その場で箱がくるりと一回転する。
箱の外で、硬質な刃を打ち付けあう音が真っ暗な空間にいる客の耳に届く。
客「何するんですか」
店員「安心してください。今から二十本の刀を差します。脱出ショーです。無事外に出ることはできるのでしょうか」
客「全然、安心ではありません」右から左から、前から後ろから、刀を差し込む気配が響く。
ドラムロールが鳴った。
じゃーん
客は無傷で外に出る。テーブルには、つけ麺と餃子が出来上がっていた。
エンジニアの思い
太郎はズボンのポケットに手を入れながら歩いている。ポケットの中には大小二つのビー玉があった。骨董市で手に入れたものだった。時代は大正の物で、身分の高い家の主が文鎮として使うためにわざわざ作らせたものであると、骨董市のおやじは言っていた。太郎は古い物が好きだった。手の中でガラス玉をもて遊びながら、太郎は骨董市のおやじとのやり取りを思い出す。
商品の写真を撮影しても良いかと太郎はおやじに聞いた。
「いいよ、どんどん撮ってよ、あんちゃん」
太郎は並べられているアンティーク時計や、銀食器、などにカメラを寄せて撮る。
「あんちゃん、もしかしてプロかい」
太郎はフリーのカメラマンだった。
「ええ」
太郎はうなずいた。
「すごいね、あんちゃん。カメラは現代のカメラだけど、古いレンズを使ってるね」
昭和初頭のレンズで撮ったものが不思議と評価されていた。
「あんちゃんの好きそうな玉がある店、おいら知ってるよ」
おやじはうれしそうに紙と鉛筆を取り出して住所と簡単な地図を書いた。
太郎が今歩いているのは、そのとき紹介された街だ。この先の路地を曲がると店があるはずなのだが、それらしき店はまだ見あたらない。取り出した地図と目の前の景色を何度も見返しながらうろうろと歩く。
太郎は室内にある水槽に目が止まる。窓から差し込む光がメダカを照らしている。太郎は、たすきがけしているカメラを背後から取り出して、ファインダーをのぞく。ピントを合わせていると、水槽の背後にある顔と太郎の目があった。声にならない声を出して、太郎は思わずカメラを下ろす。その店が骨董市のおやじが言っている店だった。太郎は引き戸を開けて店内に入る。こじんまりした店の中にはずらりとレンズが並んでいる。
「びっくりさせてすみません。お客様のカメラに興味があったもので」白色のカッターシャツにうぐいす色のエプロンをしている店主がすまなそうに頭を下げる。
「こちらこそ勝手に撮ってすいません」
「ごゆっくりごらんください」
店主は自分の作業スペースに戻って、レンズを磨きだす。オーバーホールしたものを店頭に並べていると骨董市のおやじから聞いていた。太郎は夢中でショーウインドーをのぞき込む。
数本のレンズを購入した。そのうちの一本に太郎の記憶には無い、メーカー純正のレンズがあった。どうやらメーカーのエンジニアが試作したものらしい。写りは素晴らしいのだが、意図しないものが写る場合がるということだった。
(意図しないゴーストとか、光線とかのたぐいだろう)太郎はそう解釈して帰路についた。
幻のレンズ(太郎は先日のレンズをそう名付けた)を付けたカメラを携えて太郎は街にいた。目の前を人々が歩いていく。ゆっくりとした歩みのおばあさんに太郎は目が止まる。おばあさんには雰囲気があった。カメラを構えて数枚シャッターを切る。手応えを感じる。太郎が名刺を差し出しながらおばあさんに声をかける。雑誌掲載の許可をもらい、おばあさんの住所を聞いた。
編集作業をしていた太郎はパソコンの前で首をひねっている。画面には、あでやかな和装にはえる横顔のおばあさんの全身が写っている。
「こんな猫いたかな?いたんだろうな…」
おばあさんに寄り添うように黒猫が足下にいた。黒猫はおばあさんを見上げている。構図は悪くないと判断した太郎は、データを雑誌社に納品した。
数ヶ月後、オフィスの電話が鳴った。
「先日、撮影してもらった者なのですが」太郎は声のトーンを思い出す。
「ああ、あのご婦人ですね。先日は、ありがとうございました。送った雑誌見ていただけましたか、賞もいただきました」
「それはおめでとうございました。ところであの写真に写っている猫なんですけど」
「ええ、かわいらしい猫でしたね。私も写真を見て気づきました。いましたかね」
「チャーなんです」
「チャー?」
「チャーは私の飼い猫でして、数年前に亡くなりました。長生きしましてね、私が出かけると、猫にはめずらしく、一緒に外まで付いてきましてね。とてもかわいい猫でした……」涙声になる婦人の声を聞きながら、太郎の頭にはある単語が浮かんでいた。
ゴースト……
太郎はズボンのポケットに手を入れながら歩いている。ポケットの中には大小二つのビー玉があった。骨董市で手に入れたものだった。時代は大正の物で、身分の高い家の主が文鎮として使うためにわざわざ作らせたものであると、骨董市のおやじは言っていた。太郎は古い物が好きだった。手の中でガラス玉をもて遊びながら、太郎は骨董市のおやじとのやり取りを思い出す。
商品の写真を撮影しても良いかと太郎はおやじに聞いた。
「いいよ、どんどん撮ってよ、あんちゃん」
太郎は並べられているアンティーク時計や、銀食器、などにカメラを寄せて撮る。
「あんちゃん、もしかしてプロかい」
太郎はフリーのカメラマンだった。
「ええ」
太郎はうなずいた。
「すごいね、あんちゃん。カメラは現代のカメラだけど、古いレンズを使ってるね」
昭和初頭のレンズで撮ったものが不思議と評価されていた。
「あんちゃんの好きそうな玉がある店、おいら知ってるよ」
おやじはうれしそうに紙と鉛筆を取り出して住所と簡単な地図を書いた。
太郎が今歩いているのは、そのとき紹介された街だ。この先の路地を曲がると店があるはずなのだが、それらしき店はまだ見あたらない。取り出した地図と目の前の景色を何度も見返しながらうろうろと歩く。
太郎は室内にある水槽に目が止まる。窓から差し込む光がメダカを照らしている。太郎は、たすきがけしているカメラを背後から取り出して、ファインダーをのぞく。ピントを合わせていると、水槽の背後にある顔と太郎の目があった。声にならない声を出して、太郎は思わずカメラを下ろす。その店が骨董市のおやじが言っている店だった。太郎は引き戸を開けて店内に入る。こじんまりした店の中にはずらりとレンズが並んでいる。
「びっくりさせてすみません。お客様のカメラに興味があったもので」白色のカッターシャツにうぐいす色のエプロンをしている店主がすまなそうに頭を下げる。
「こちらこそ勝手に撮ってすいません」
「ごゆっくりごらんください」
店主は自分の作業スペースに戻って、レンズを磨きだす。オーバーホールしたものを店頭に並べていると骨董市のおやじから聞いていた。太郎は夢中でショーウインドーをのぞき込む。
数本のレンズを購入した。そのうちの一本に太郎の記憶には無い、メーカー純正のレンズがあった。どうやらメーカーのエンジニアが試作したものらしい。写りは素晴らしいのだが、意図しないものが写る場合がるということだった。
(意図しないゴーストとか、光線とかのたぐいだろう)太郎はそう解釈して帰路についた。
幻のレンズ(太郎は先日のレンズをそう名付けた)を付けたカメラを携えて太郎は街にいた。目の前を人々が歩いていく。ゆっくりとした歩みのおばあさんに太郎は目が止まる。おばあさんには雰囲気があった。カメラを構えて数枚シャッターを切る。手応えを感じる。太郎が名刺を差し出しながらおばあさんに声をかける。雑誌掲載の許可をもらい、おばあさんの住所を聞いた。
編集作業をしていた太郎はパソコンの前で首をひねっている。画面には、あでやかな和装にはえる横顔のおばあさんの全身が写っている。
「こんな猫いたかな?いたんだろうな…」
おばあさんに寄り添うように黒猫が足下にいた。黒猫はおばあさんを見上げている。構図は悪くないと判断した太郎は、データを雑誌社に納品した。
数ヶ月後、オフィスの電話が鳴った。
「先日、撮影してもらった者なのですが」太郎は声のトーンを思い出す。
「ああ、あのご婦人ですね。先日は、ありがとうございました。送った雑誌見ていただけましたか、賞もいただきました」
「それはおめでとうございました。ところであの写真に写っている猫なんですけど」
「ええ、かわいらしい猫でしたね。私も写真を見て気づきました。いましたかね」
「チャーなんです」
「チャー?」
「チャーは私の飼い猫でして、数年前に亡くなりました。長生きしましてね、私が出かけると、猫にはめずらしく、一緒に外まで付いてきましてね。とてもかわいい猫でした……」涙声になる婦人の声を聞きながら、太郎の頭にはある単語が浮かんでいた。
ゴースト……