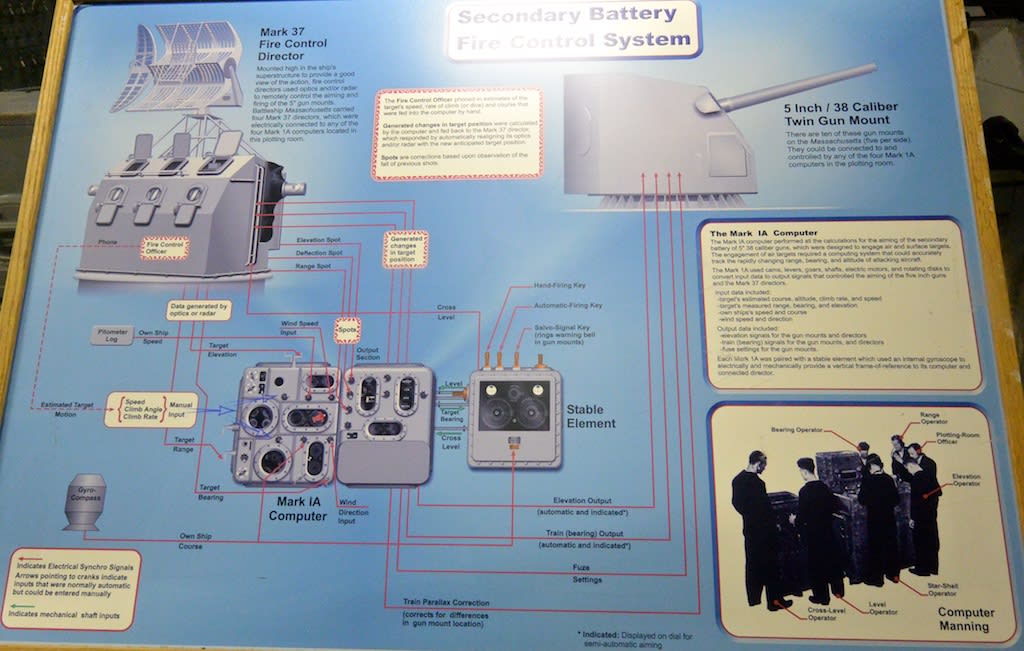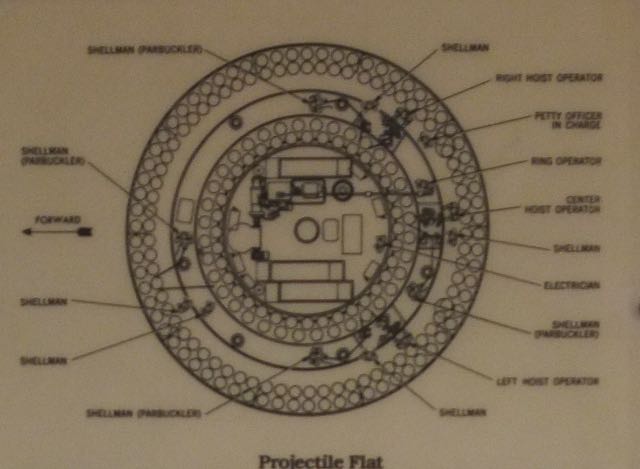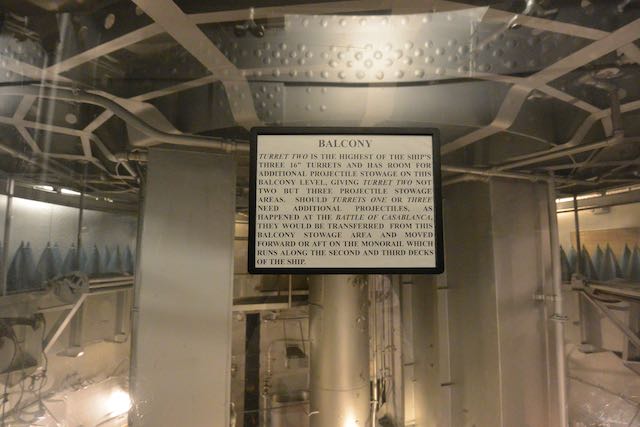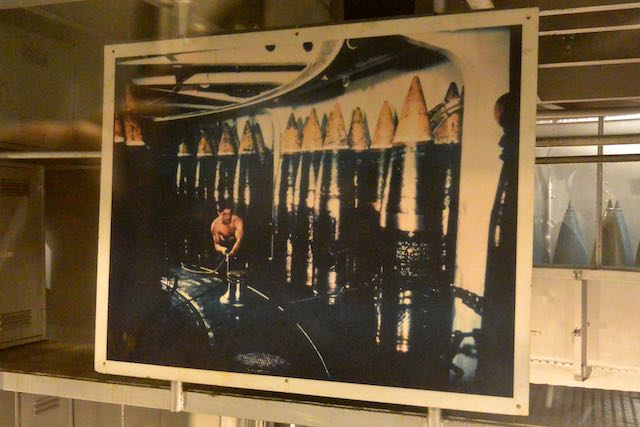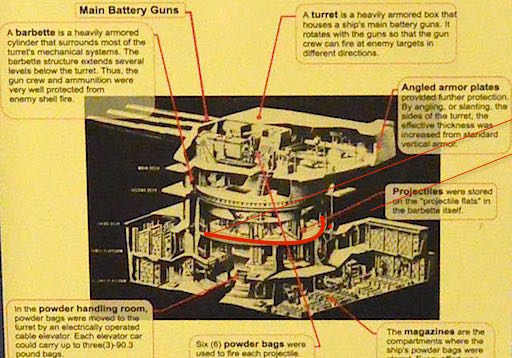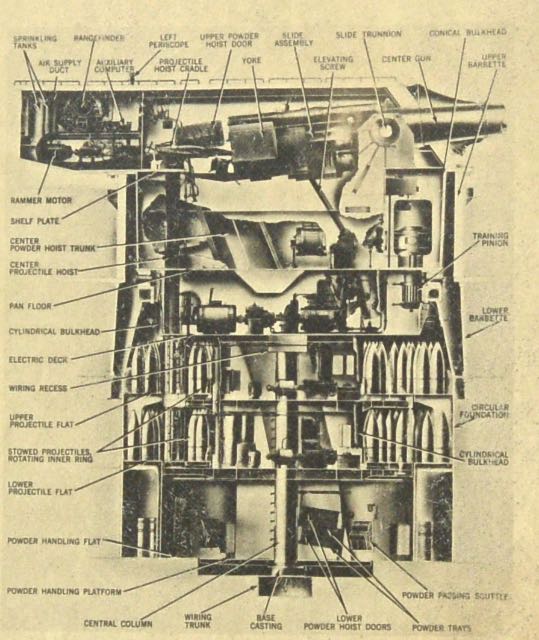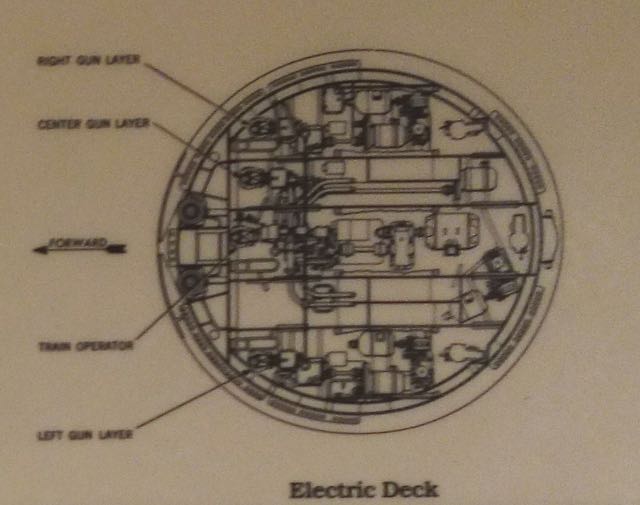本日、着払いで航空自衛隊の遺失物取得係から、
11月3日入間で紛失したカメラが戻ってきました。
本体をストラップのついたケースごとプチプチで包み、
さらにそれを内側が緩衝材の封筒に入れて送るという
非常にリーズナブルでかつ安心安全な梱包です。
おそらく何万人もの落し物を関東一円に送るのは、何人もの隊員が
膨大な量の荷物の山と格闘する作業となると思われます。
今回たまたま落し物をしたおかげで、毎年「祭りのあと」に必ず
繰り返されるこのような煩雑な仕事を行ったり、
わたしをそこまで遠路はるばる連れて行ってくれた自衛官のように、
イベントの運営を最初から最後まで円滑に行うための
あらゆる分野で彼らが任務を果たしていることを知りました。
何度かかけた電話の対応も大変丁寧なものでしたし、こういうことがあると
一層自衛隊という組織に対し安心というか信頼感が増します。
さて、今日はシリーズ最終回として、却って来たカメラの画像を元に
当日の朝からもう一度お話ししてみます。

基地に入る門は大きく2箇所に分かれます。
稲荷山公園駅を降りてバス停のほうに行けば北門(と特設門)、
反対側に行っても稲荷山門という(正門らしい)入り口があります。
わたしは招待者用の受付が近いかと思い去年と同じく
稲荷山門から入ることにしました。
しかし、去年と比べてだいたい2分の1くらいしか並んでいないような気がしました。
3年前にテレビドラマの影響で大変な人出となったときは32万人、
だいたい平均が22万人、この日はなんと13万人だったそうですから、
2分の1と体感したのはほぼ正確だったということになります。
総火演もそうですが、一度行けばまず「人間航空祭」といわれるくらいの
うんざりするほどの人で入退場の辛さに懲りてしまう人も多いでしょう。
関係者・招待者・隊員家族以外ではカメラが趣味の人以外はほとんどが
「ご新規さん」なのかもしれないと思います。
今年は前日が雨で、朝方も雨天が予想されていたため、そのため
人出が大幅に少なくなったのかと思われました。
開門前にフェンス沿いの人たちは門の前に移動させられ、
そこで約1時間くらいを待つことになりました。

形だけ鞄の中を隊員に歩きながら(荷物検査台などはない)チェックしてもらい、
すぐに中に入るのですが、入った途端走り出す人多し。
「走らないでください!」危険ですので走らないでください!」
自衛官がそこここで叫ぶも皆聞く耳持たず。
やっぱりブルーインパルスのウォークダウンが見られる場所などは
限られていますので、のんびりしている場合ではないのでしょう。

稲荷山門から入ると、もう一度入間基地内の踏切を
渡ることになるのですが、ここにお立ち台の上から注意を喚起し、
挨拶をしてついでに笑いを取る係の自衛官がいます。
わたしはここを通るのは去年に続き2回目。
去年はたまたまそういうキャラの人だったのかと思ったら・・、

なんとお立ち台に「DJ自衛官」という幕がかかっていました。
2015年度の動画が上がっていましたのでどうぞ。
DJ自衛官! 2015入間基地航空祭
今年は3人投入です。

実は、今回紛失騒ぎを起こしたカメラ、SONYRX-100は、2代目です。
アメリカで買った先代はアメリカ滞在中にレンズが引っ込まなくなり、
奇しくも購入地のカリフォルニアで息を引き取ってしまいました。
RX-100はその後新しいバージョンがM4まで出ているのですが、
いろいろ調べたところ、あとから加わった機能はたいして意味がなく、
それならいまだに売られている1代目で十分じゃないかと思い、
総火演前に3万円台という超リーズナブルな値段で同じのを買いました。
使い方も慣れているし、それにやはり新しいと画像も綺麗です。

開始前のエプロンの様子。
最前列には向こうから人が座りだしていますが、ガラガラです。

そしてブルーインパルス開始前の同じところ。
混んではいますが、やはり去年ほどではない気がします。
coralさんもおっしゃっていましたが、今年の見学は皆楽だったのではないでしょうか。

望遠レンズでは撮れない空挺降下の傘が10個並んだところ。
隣の白レンズカメラのおじさんは
「これは広角がもう一台必要ですなあ」
といっていました。

さて、それでは格納庫で行われたレセプションについて。
招待者はで受付の際、レセプションパーティに参加するかどうか聞かれ、
参加費用を払って入場チケット(テーブルの番号が書いてある)を貰います。
わたしは去年参加しているのでどんなものかわかっていましたが、
ここでご報告する義務があるため(笑)あえて参加を申し込みました。
あえて、というのは主にコストパフォーマンスの問題です。

最初に入間基地司令が挨拶をしました。
これを空自らしいというのかたまたまこの空将がそうなのか知りませんが、
しょっぱなから笑いを取りに来るスピーチでした。
ただし残念なことに、スピーカーの位置の関係で、わたしのいたところでは
何を言っているのか最初から最後まで全くわかりませんでした。
(来賓席の前の最前列のテーブルだったのに・・)

地元に選曲を持つ議員の先生方が名前を呼ばれて返事だけしました。
スピーチは幸いなことにありませんでした。
はい、と大きな声で返事しながら手を挙げているのは
自民党の柴山昌彦議員。
柴山議員の後ろはヒゲの隊長佐藤正久議員(比例)。
先日呉でご挨拶したばかりの宇都議員は空自出身です。

始まる前にテーブルの上の料理を撮ってみました。
陸自の式典にはまだご縁がなくて参加したことはないのですが、
どうしても海自のパーティと比べてしまいますね。

唐揚げ肉団子シューマイカキフライ餃子、というメニューは
もちろん海自でも出るのかもしれませんが、問題はこの料理を
食べるために払う3000円というお金なんですなあ。
進水式や命名式など、企業が絡む場合はもちろんのこと、
海自の宴会料理では必ずテーブルを彩る船盛の刺身は絶対にここではでません。
料理の内容の割に高いのは、業者を入れているからではないのか、
とわたしは思うのですが、その辺はわかりません。
今まで出た海自基地での宴会では調理した隊員の紹介がありましたが、
ここではそういう人の姿すらなかったのでそう思ったのですが。

カレーと焼き鳥、そしてうどんそばの屋台があって、
むしろ卓のものよりこちらがメインという感じです。
カレーはまあ普通に美味しかったです。

焼き鳥屋台も皆首から入館証を下げているので業者ですね。

宴たけなわのころ、自衛官にエスコートされたミス航空祭の
皆さんが台上に上がって一人ずつ紹介を受けます。
台の前には家族らしい人々がどっと群がっていました。
このミス航空祭、毎年妙齢の娘を持つ関係者に声をかけて
出場者を集めるのだそうです。
自衛官の娘や姉妹あり、関連業者の娘あり。
元自衛官の娘さんなどというのも結構多いそうですね。
着物を着ないといけないので、成人式でせっかく誂えたから、
と出場する方もいるそうです。
選考で落とされたりする人もいるのかどうかはわかりませんでした。

テーブルの上は瞬時にしてこのような状態になり、しかも追加なし。
乾杯後、卓の周りに陣取っていた人たちが取った後も場所を移動せず、
その場で食べだしたので人垣の外で立ち尽くしていると、一人が
「とる?」
といかにも鷹揚な様子で()前に入れてくれました。
そりゃとるさ。朝から何も食べてなくて眩暈してるくらいなんだから。
が、わたしが食べ物を取った後遠慮して外に出ると、ナチュラルにまた
最前列を占領してしまいました。
そういえば、会場に入ったとき、まだ乾杯もしていないのに
すでに料理を食べまくっているテーブルがあってあらら、と思ったのですが、
「お金払ったんだから(しかも3000円)」というのが念頭にあるとこうなるのかな。

昼からのブルーインパルス演技は望遠で撮りましたが、
フォーメーションが広がるとデジカメの出番です。
上向き空中開花。

まだ上向き空中開花のスモークが残っている中、
スタークロスが始まっています。

この日は風もそこそこしかなく、綺麗にシェイプが残りました。
なんでもあまり風がなさすぎてもスモークが消えないので
それもあんまり良くないということを聞いたことがあります。

レインフォール。

1機で描くレターエイト。(途中)

そしてバーティカルキューピッドです。
最高に美しいハートシェイプが真っ青な空に描かれます。

5番機と6番機が描いたハートに向かって、
4番機(スロット)が矢となって進んでいきます。

きっちりと後ろからスモークを出すには、どこかで
指令が出ているとしか思えないのですが、そうなんでしょうか。

さて、ブルーが全機着陸するのを見届けてから、わたしは荷物をまとめ、
早々に出口に向かいました。
招待席の近くで撮影会みたいになっているので何かと思ったら
米空軍の軍人さんを皆が取り囲んで順番に一緒に撮ってもらっていました。
この後、500mくらいの距離をシャトルバスが往復しているのですが、
歩くのを選んだことが裏目に出て、途中でカメラを落としたのです。
ないと気づいてすぐに来た道を戻ったのですが、今にして思えば
地面にカメラが落ちているのを見つけた人がすぐさま拾って
近くの自衛官に届けたってことだったんでしょうね。
この時拾ってくれた方にも、どなたかは存じませんがお礼を申し上げます。
それにしても肩にかけていたものが落ちても気づかないわたしって。
終わり