般若寺(コスモス寺)を出て、秋篠寺を訪れた。
秋篠寺は私にとっては想い出のある寺で、そもそもは父が学生時代にここを訪れたことがあったのか、古い写真の裏に詠んだ句が記されていて、それでこの寺に惹かれたのだが、私の学生時代は広島で過ごしたので、訪れる機会はなかった。結婚後しばらくして妻と一緒に訪れたのだが、もう50年ほども昔のことで、当時は鄙びた感じで訪れる人の姿はほとんどなかった。受付には木の板が掛けてあり、それを木槌で叩くと、係りの僧が出てくるのというのが気に入った。妻と静かな境内をゆっくり歩いたことや、この寺の本堂にあった、仏像の一つの技藝天像に非常に感動を覚えたことが思い出される。
境内は今回は昔に比べるとだいぶ整備されていたが、この寺門(東門)は質素である。

門から入る。緑が美しい。楓が多いので紅葉が見事だろう。

香水閣(こうずいかく) 霊水が湧いている。明治維新までは、この井戸で汲まれた水が宮中行事に使われたとのこと。日頃は門が閉じられている。毎年6月6日には公開されるとのこと。

金堂跡。厚く生えたコケ(蘚類)が美しい。



この寺は宝亀7年(776年)に、光仁天皇の勅願により善珠僧正が薬師如来を本尊とする寺を造営したのが始まりとされている。宗派はもとは法相宗と真言宗を兼学し、浄土宗に属した時期もあったが、現在は単立(独立した宗教法人)で、山号はない。
本堂(国宝)。創建時には講堂として建立されたが、保延元年(1135年)に兵火によって一山の伽藍がほとんど消失した中で残り、鎌倉時代に大修理を受けて以来、本堂と呼ばれている。本尊は薬師如来(重文)。

伝・技藝天像。像高205.6センチメートル。本堂仏壇の向かって左端に立つ。瞑想的な表情と優雅な身のこなしは見飽きない。頭部のみが奈良時代の脱活乾漆造で、体部は鎌倉時代の木造による補作。「技藝天」の彫像の古例は日本では本像以外にほとんどなく、本来の尊名であるかどうかは不明とされている。残念ながら堂内は写真撮影禁止なので、技藝天像の写真は、販売されているものをスキャンした。


技藝天は女人で、衆生の吉祥と芸能を主催し、諸技諸芸の祈願を納受したまうと言われていて、その出生については次のような伝えがある。
「あるとき天上で、大勢の天女たちに囲まれて音楽や踊りを楽しんでいた大自在天王(シバ神)の髪の生え際から忽然と一天女が生まれ出た。その容姿端麗なことはもとより、技芸に秀でていることは、並みいる天女たちの遠く及ぶところではなかった。居合わせた天人天女たちは一斉にその勝れた才能を称えて、この天女を技藝天と呼んだ」
鐘楼

大元堂。大元帥明王を安置する。秘仏で6月6日のみ公開される。憤怒の形相をしている。軍事組織での「元帥」という肩書きの由来と言われている。


開山堂。開山(創立者)の像や位牌を祀る。秋篠寺の開山は奈良時代の法相宗の僧・善珠とされている。














 Wikipediaより
Wikipediaより Wikipediaより
Wikipediaより


























 葛
葛 板藍根
板藍根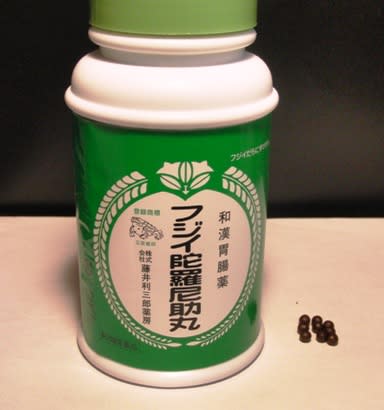
 奈良県吉野で
奈良県吉野で



