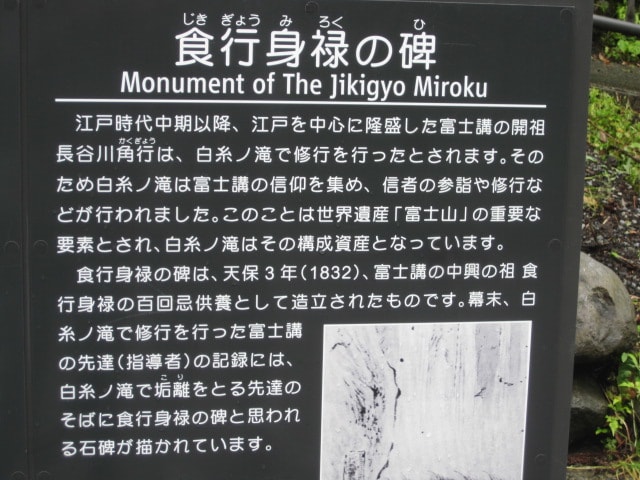「東京駅高速バス・2番のりば(東京駅八重洲口)」
木更津・君津(京成バス・日東交通)。三井アウトレットパーク木更津行(京成バス・日東交通)。安房鴨川行「アクシー号」(京成バス・日東交通・鴨川日東バス)。勝浦・御宿行・安房小湊行(小湊鐵道・鴨川日東バス)。
元々は、バス停のみで発券窓口がなかったが、京成バスでは2014年7月ー2番のりばと3番のりばのほぼ中間にあたる八重洲ロータリービル1F・2Fに乗車券類の発売窓口や待合所等の設備を兼ねた「京成高速バスラウンジ」を開設。
京成バス・安房鴨川行に乗車

慢性的渋滞の発生していた箱崎ジャンクション・江戸橋ジャンクション・首都高速1号羽田線の渋滞緩和と共に、開発の進められていた
東京臨海副都心と既存都心部を結ぶために建設された。
橋梁としては芝浦側アプローチ部1465m(陸上部439m+海上ループ部1026m)+吊り橋部918m+台場側アプローチ部1367m(海上部905m+陸上部462m)が
一体で建設された。
海とビル群の景色や夜景などの眺望が良好な事から週末のドライブコースとしての人気があり、それが要因で渋滞となることもあると云う。
レインボーブリッチ(芝浦)

「羽田空港 新国際線」
世界17都市への就航が予定される羽田空港は、首都圏からのアクセスがよく、地方空港との乗り継ぎもしやすいと人気。
新国際線オープンにあわせ、京浜急行、東京モノレールの新駅も開業し、国際線ターミナルエリアに直接アクセスできる。
また、海外ブランドから日本ブランドまで幅広く揃う免税店、24時間営業のダイニングや、世界各国の味が楽しめる飲食店なども。

「東京湾アクアライン」
トンネルを抜けると、そこは、千葉県であった。
川崎側の9.6kmがアクアトンネルと呼ばれるトンネル、木更津側の4.4kmがアクアブリッジと呼ばれる橋になっている。
その境の人工島には海ほたるPAが、アクアブリッジは、日本第1位の長さの橋梁、アクアトンネルは、山手トンネル・関越トンネル・飛騨トンネルに次ぐ、日本第4位の長さの道路トンネルである。
「バスは、千葉県外房へ」
県南部,房総半島 南西端の洲崎から勝浦市にいたる太平洋に面した海岸地方。
海食台地が広く露出し, 磯浜が続き,アワビ,サザエ,テングサの産地でもある。また無霜地帯で,花卉栽培が 盛んである。
太平洋に面した外房に(鴨川・小湊・勝浦・御宿・大原)

「ロシア人来航の地」
鎖国下にあった江戸時代の元文4年の1739年、
天津村(現鴨川市天津)の沖合いに日本探検を目的として日本沿岸を訪れたロシアの探検隊が来航し布入の地に上陸。
この上陸はわが国(北海道を除く)で初めてのロシア人の上陸であり、日本の歴史・外交史上でも重要な出来事。
「オホーツク探検事業の一つで」-シュバングルグ率いる船団の一隻の
ヴアリトン大尉(ガヴリエル号)の乗組員が上陸。今でもロシア人が訪れると云う。

「天津城」
鴨川の中世は、治承4年の1180、石橋山の合戦で敗退した源頼朝は安房に逃れ、安房の武士団を集めて再起を。
当事、安房の在地領主としては、丸氏・安西氏・神余氏などが知られ、在地領主には、東条氏と長狭氏がいた。
「吾妻鏡」治承4年・頼朝は、上総権介平広常のもとへ行こうとしたところ、長狭六郎常伴に襲撃され、三浦義澄の機転と奮闘により、
長狭六郎常伴は討ち取られ危機を脱し、市域に「一戦場」という地名が残っている。
この出来事の場所であるとする伝承が。東条七郎秋則は、頼朝に従って協力したため、のちに長狭郡一円の支配をみとめられた。
鎌倉幕府執権北条氏の家臣である工藤氏の一族とされる工藤吉隆が、天津を領有していたといわれ、小松原で東条景信に襲われた日蓮上人を救い、討ち死に、中世後期になると、安房に基盤をもった里見氏が、在地武士の内紛を巧みに利用して安房を統一する。
長狭郡に勢力を広げていた東条氏は、1445年、に安西氏とともに丸氏を滅ぼし、その後、里見氏に攻撃され、市内田原の太田学にあった金山城に追い詰められ滅亡。
以後、里見氏が旧勢力に代わって、当地を支配し、市域の村々の形成があらましできあがったのは、このころといわれている。
城のあった山


「メキシコ大統領がやってきた」-メキシコとの交流記念碑が。
1978年「ホセ・ロペス・ポルティーリョ・メキシコ大統領」が御宿町に来町した。
大統領は「エルマーノ!(兄弟)」と声をかけながら若者が担ぐみこし上から、日の丸の扇子を開いて音頭を取ったと云う。
今から、400年前に御宿の村民が当時スペイン領メキシコの難破船乗組員を助けたことに始まる、御宿町、大多喜町とメキシコとの交流が、
(御宿は勝浦の隣)。
山頂から見た海岸

千葉県鴨川市は、県南部、古代豪族「加茂氏」の名、房総丘陵を南北に分け、加茂川が東西に流れている。源頼朝の家臣東条氏が金山城を築城し
支配している。江戸初期「里見氏」転封後は、幕府直轄地に、海岸前原で、紀州漁民「イワシ・まかせ網」を伝え漁業が発達した。
現在5漁港で、イワシ・サバの沖漁業が盛んである。
沿岸の畑地では、大正から「切り花栽培」が江見中心に広がっている。
鴨川と云えば、シーワールドのアシカ・イルカショー・白クジラ・ラッコ等が人気

JR千葉内房線・外房線
千葉市から東京湾沿いに房総半島を南下し、太平洋沿岸の鴨川に至る路線。
蘇我駅で外房線から分岐し、安房鴨川駅で再び外房線に接続する。
千葉駅から安房鴨川駅までの距離(営業キロ)は、内房線経由より外房線勝浦経由のほうが距離が29.9km短い。
千葉駅 - 君津駅間は複線区間となっており、列車の本数も比較的多く東京方面からの快速電車も乗り入れているが、一方、君津駅以南は単線区間となり、約一時間に一本と云う本数は、極端に少なくなる。
千葉市蘇我駅ー安房鴨川駅で

次回は、安房鴨川駅から館山駅より一つ手前「仁右衛門島の太海駅」へ。