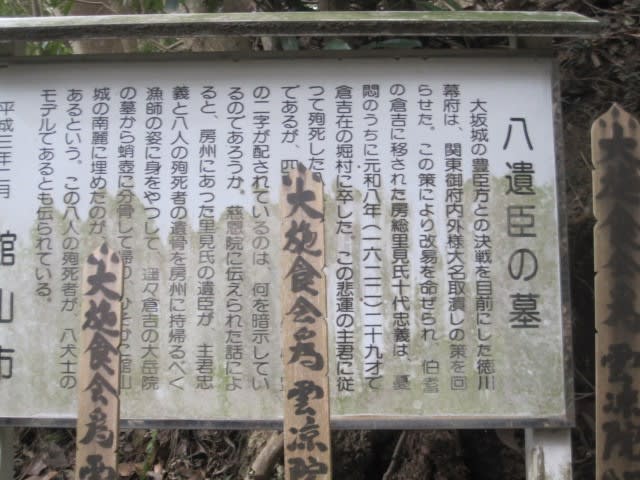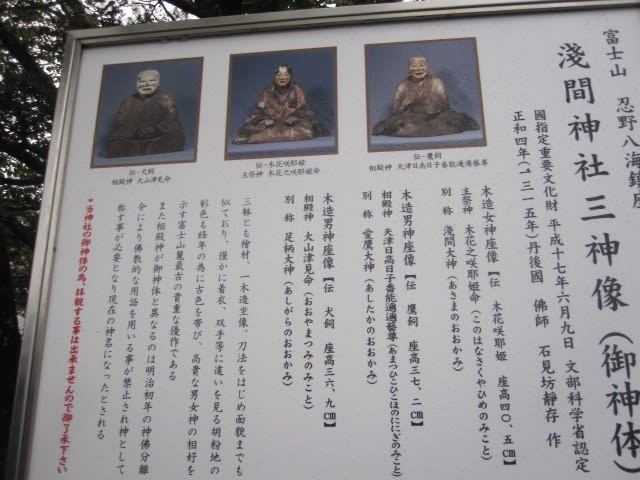明治中期以降「第一艦隊の停泊地」であった。海軍砲術学校などが設置され軍部の都市館山で栄えた。
戦後、海上自衛隊が引き継ぐ、現在温暖の気候を生かし花卉栽培・花つみ園・イチゴ狩りなど観光農業が盛ん。
館山湾の北条海岸は古い、洲崎灯台・平砂浦海岸など「南房総国定公園」に属している。

館山航空基地は、千葉県館山市に所在する海上自衛隊の軍用飛行場である。艦載哨戒ヘリSH-60J・SH-60Kと救難ヘリUH-60Jを運用する第21航空群の航空基地となっている。
館山航空基地は、もともと関東大震災によって隆起した浅瀬を旧海軍が埋め立てて飛行場を建設し、1930年(昭和5年)に館山海軍航空隊が置かれた。東京湾の防備を担当する海軍航空部隊の重要基地であり、横須賀鎮守府に所属している艦載機や水上飛行機、飛行艇も運用されていた。基地周辺には、本土決戦に備えて多数の地下壕や掩体豪が建設され、現在も残っている。基地の近隣には赤山地下壕があり見学可能な戦跡となっているほか、旧海軍の建造物は現在も司令部庁舎や国旗掲揚台として使用されており、基地専用の水源地も旧海軍が建設したものをそのまま使用している。基地の内外には、旧軍関係の石碑や史跡が数多く点在している。
戦後は海上保安庁の海上警備隊から保安庁警備隊となって館山航空隊が編成され、海上自衛隊航空部隊の発祥の地ともなった。現在は海上保安庁の羽田基地所属ヘリも、離着陸訓練のため頻繁に使用する。
ヘリコプター専用飛行場としては日本最大規模のヘリポートであり、毎年10月に行なわれる基地祭「ヘリコプターフェスティバルIN館山」で、厚木航空基地からは、アメリカ海軍のUH-60、木更津駐屯地からは陸上自衛隊のUH-60J、浜松基地からは航空自衛隊のUH-60が飛来して、日本国内のすべてのUH-60シリーズのヘリコプターを見ることができる。
滑走路のタイトルバックが有名なTVドラマ「Gメン'75」の撮影はここで行われた[4]。
一般見学者用に基地内に史料館があり、山本五十六元帥の揮毫のプロペラや零戦の栄エンジンのセルモーター、二式小銃などが展示されている。見学には事前の予約が必要。












城山公園近くのレストランでランチ、ちょっとした手作りのお惣菜が嬉しいお店。