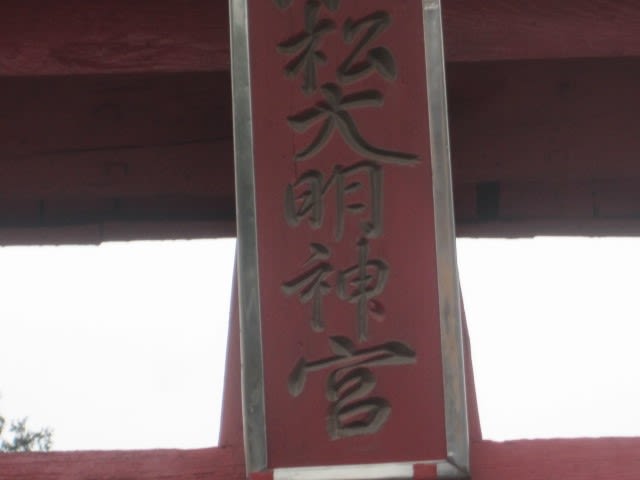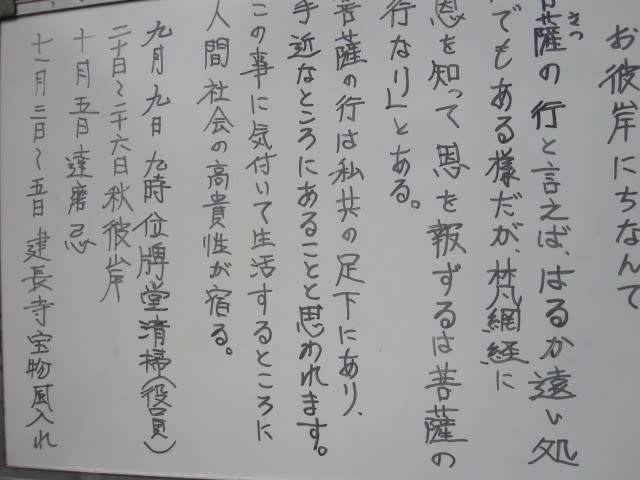「岩殿城」-大月市の岩殿山城、連郭式山城(634m)・堀切・虎口・井戸・土橋など。
築城主小山田氏ー城主小山田氏・武田氏・廃城は17世紀初頭。
相模川水系の桂川と葛野川とが合流する地点の西側に位置。
頂上の南側直下は鏡岩と呼ばれる礫岩が露出した約150メートルの高さの崖で、狭い平坦地を挟んで、さらに急角度で桂川まで落ち込んでいる。
山頂までは大月駅から徒歩で約1時間で、山頂からは富士山が望め、「山梨百名山、秀麗富嶽十二景」にも選定。
山の南側と桂川の間の狭い場所に中央自動車道が、1972年、岩殿山で大規模な地滑りが発生、同年3月、から中央自動車道の相模湖ICと大月ICの間が全面通行止めとなった。解除されるまで、通行止めは123日間に及んだと云う。
岩殿山城は東西に長い大きな岩山をそのまま城にして、全方面が急峻で、南面は西から東までほとんどが絶壁を連ね、北面も急傾斜である。
東西から接近できるが、それも厳しい隘路を通らなければならない。
各種の防御施設が配されたが、天然の地形のせいで郭も通路も狭く、大きな施設の余地はなく、周囲には集落や武家館が点在していたと云う。
「信長公記・甲陽軍鑑・甲乱記」によれば、
天正10年の1582年、3月ー織田・徳川連合軍の武田領侵攻に際して、武田家臣・小山田信茂は新府城(韮崎市中田町中條)から武田勝頼を岩殿山城へ迎えるが、勝頼一行が郡内領へ向かう途中で信茂は勝頼から離反し、勝頼一行は、天目山(甲州市大和町)で自害した(天目山の戦い)。
「理慶尼記」では、信茂が勝頼に籠城を薦めた岩殿山城を「みつからか在所」と記している。
小山田信茂は、勝頼滅亡後に織田氏に出仕しているが、甲斐善光寺において処刑され、郡内小山田氏は滅亡する。
その6月には「本能寺の変」により甲斐・信濃の武田遺領を巡る「天正壬午の乱」が発生。
都留郡では本能寺の変が伝わると土豪や有力百姓などの「地衆」が蜂起し、甲斐国を統治していた織田家臣・河尻秀隆の家臣は追放された。
こうした状況から、後北条氏では相模津久井城主・内藤綱秀が都留郡へ侵攻し、岩殿城を確保した。
後北条氏はさらに都留郡一帯を制圧・「天正壬午の乱」において甲府盆地において三河国の徳川家康と北条氏直が対峙するが、徳川・北条同盟の成立により後北条氏は甲斐・郡内領から撤兵し、甲斐国は徳川家康が領した。
江戸に武家政権を成立させた徳川家康は、幕府の緊急事態の際に甲府への退去を想定していたといわれ、江戸時代にも岩殿山城は要塞としての機能を。。
JR中央本線~上野原ー四方津ー梁川ー鳥沢ー「猿橋駅・大月駅」ー初雁ー笹子

山梨県大月市「猿橋」-橋脚がなく結木という木が橋桁を造っている。
山口県「錦帯橋」-錦川に小島の橋台を作り、アーチで架けていく。
富山県「愛本橋」-63mのはねhasi はね橋。
「三奇橋」の一つ「猿橋」

「猿橋」
桂川とその支流・葛野川の合流地点の付近に位置・甲斐国と武蔵国・相模国の交通拠点である。
江戸時代には猿橋村が成立し、甲州街道の宿駅である猿橋宿が設置されたと云う。
猿橋が架橋された年代は不明だが、地元の伝説によると、
古代・推古天皇610年頃(別説では奈良時代)に百済の渡来人で造園師ある志羅呼が、猿が互いに体を支えあって橋を作ったのを見て造られたと言う伝説がある。(猿橋の名は、伝説に由来)
室町時代には、「鎌倉大草紙」-関東公方の足利持氏が敵対する甲斐の武田信長を追討し、持氏が派兵した一色持家と信長勢の合戦が「さる橋」で行われ、信長方が敗退したという。
1487年、の聖護院道興「廻国雑記」ー道興が小仏峠を越えて当地を訪れ、猿橋の伝承と猿橋について詠んだ和歌・漢詩を記録している。
戦国時代ー「勝山記」永正17年の1520年、都留郡の国衆・小山田信有(越中守)が猿橋の架替を行っている。
この信有による架替は、小山田氏の都留郡北部への支配が及んだ証拠とも評価されている。
猿橋は、1533年、にも焼失し、1540年、再架橋されていると云う。
勝山記ー大永4年の1524年、甲斐守護・武田信虎は同盟国である山内上杉氏の支援のため猿橋に陣を構え、相模国奥三保(神奈川県相模原市)へ出兵し相模の北条氏綱と戦い、「小猿橋」でも戦闘があったという。
戦国期に小山田氏は武田氏に従属し、「勝山記」によれば享禄3年の1530年、越中守信有は当地において氏綱と対峙している。
勝山記によれば、留守中の3月には小山田氏の本拠でる中津森館(都留市中津森)が焼失し、4月23日に越中守信有は矢坪坂の戦い(上野原市大野)において氏綱に敗退しているとある。また、猿橋には、国中の永昌院(山梨県山梨市矢坪)の寺領も存在していた。
1676年、以降に橋の架け替えの記録が残り、少なくとも1756年(宝暦6年)からは類似した形式の刎橋である。
江戸時代には猿橋が最も有名で、「日本三奇橋」の一つと。
甲州街道沿いの要地(宿場)にあるため往来が多く、荻生徂徠「峡中紀行」、渋江長伯「官遊紀勝」など多くの文人が訪れ紀行文や詩句を。

1817年、「葛飾北斎・北斎漫画 七編 甲斐の猿橋」描いている。

猿橋神社

名勝・猿橋は桂川に架かる橋

谷の両岸から三本のハネギを4段にくみ、せり出して架けてある。

高さ約31m・幅3.3m・長さ30.9m。

現在の橋は、1984年に架け替えた。





追われる身となった忠治は猿橋の「大黒屋」に滞在した。
居場所を突き止められ、食べ慣れた野鳥の肉入りそばを平らげて外へ。猿橋両岸から迫った追っ手を避け、橋から約32メートル下の桂川に飛び込んだ。かっぱと三度がさを下流に流して行方をくらまし、猿橋上流の阿弥陀寺に隠れたという。

国定忠治も食した大黒屋の「モリ蕎麦」

甲州街道・国道20号線 「大月宿」

旧郷社「三嶋神社・大明神」ー642坪ー
平安の初め此地方が開拓され、村落が生まれつつある頃大同元年の806年、伊予国(愛媛県)大三島の大山祇神社より勧請された。
富士山の噴火続き田畑山林の荒廃厳しいため、富士即木花咲耶姫命の御怒りを鎮むべく、父神に坐す大山祇命をお迎へし、復興の精神的よりどころとしたと言ふ。
御神体は大松山の大松を三段に伐つて作つた。中段の御神像と伝へられる。甲斐南部氏奥州出向の折参詣、霊現あらたかにより彼の地に三島神社を起す。中世度々の戦に武将の祈願あり名刀景光、延元元年銘の大石灯籠など残す。
小山田氏と縁深く本社を守護神と仰ぎ、備中守の面と言ふ鬼面石等の伝ありと云う。
江戸時代になり甲州街道開くと共に、従来の者多く参詣交通安全を祈り興深き伝へを残す。
明治8年第八区の郷社に、大正2年供進指定神社に列せられ、この地方中心の神社に発展、戦後三回の整備事業により、輪奐の美備はつて参詣者も多い。
祭神ー9月25日ー

三嶋神社の大ケヤキを「大槻」と呼んぶ、市の地名を「大月」に。(槻は、ケヤキの古い名)
境内

市の80%が山林・中心市街地に桂川・笹川が合流で川沿いに発達し、富士信仰の入口として発展。現在は交通の拠点で、大月駅から私鉄富士急行が河口湖
線が乗り入れている。大月ー河口湖までⅠ時間乗車する。
年々都心への通勤者が増えていると云う。
市内から見た「岩殿山」

山梨市の「西沢渓谷」
国内屈指の渓谷美を誇る景勝地。変化に富んだ西沢渓谷の中でも、七ツ釜五段ノ滝は圧巻・
新緑・紅葉の時期はさらに際だった美しさを見せる。
巨大な花崗岩を清流が削ってできた見事な景観と紅葉はよく合う。


市内の宿場 駒橋宿ー大月宿ー花咲宿ー初狩宿ー白野宿ーーーーー。

登山ー上野原、八重山530.7m・四方津、高柄山733.2m・梁川、倉岳山990.1m・鳥沢、扇山1137.8m・猿橋、百蔵山1003.4m
大月、岩殿山634m・初狩、高川山975.7m・笹子雁ヶ腹摺山、1357.7m・・・・。(5~6時間コースが多い)