哲学チャンネルより ニヤーヤ学派【インド哲学解説】を紹介します。
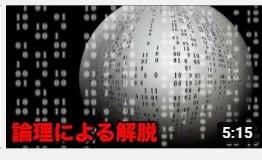
ここから https://www.youtube.com/watch?v=r572XrejVq0&t=2s
※関連した過去動画 インド哲学解説はじめます https://youtu.be/P0IviccxpDc インド哲学の始まり【ヴェーダ〜ウパニシャッド】【インド哲学解説】 https://youtu.be/ZFhM3bnWI00 ウパニシャッド哲学【インド哲学解説】 https://youtu.be/JChzdoXiyoQ ヴァイシェーシカ学派【インド哲学解説】 https://youtu.be/i_GX0qVq6rc サーンキヤ学派【インド哲学解説】 https://youtu.be/61TwcvOe660 ヨーガ学派【インド哲学解説】 https://youtu.be/MW8fHuUq-Xs ヴェーダーンタ学派【インド哲学解説】 https://youtu.be/AzDLJILjTMQ 六師外道【インド哲学】【沙門の思想】 https://youtu.be/Eusrb8UCpdM ジャイナ教【インド哲学解説】【六師外道】 https://youtu.be/YyhdGUOKBMA 原始仏教【インド哲学解説】 https://youtu.be/0NKsFFNIbMI ※書籍 ニヤーヤとヴァイシェーシカの思想―インド六派哲学 https://amzn.to/36YgHFi
動画の書き起こし版です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ニヤーヤ学派はインド六派哲学の一つであり インドを代表する論理学でもあります。 経典はアクシャパーダ・ガウタマが著したとされる【ニヤーヤ・スートラ】 2世紀ごろが成立時期だとされています。 その他、新ニヤーヤ学派とされる哲学の経典である【タットヴァ・チンターマニ】 5世紀に著されたヴァーツヤーヤナの【論証学入門】などが有名です。 インド思想では解脱への方法として瞑想や苦行を挙げるものが多いのですが ニヤーヤ学派はそれらを否定し、論理の追及による解脱を目指しました。 彼らは苦しみの原因を『誤った認識』に求めます。 誤った認識があるからこそ執着が生まれ それを源泉として妬みや欺きや貪りが生まれる。 解脱に役立つものを正確に把握し、 誤った認識を滅することで苦を消滅させることができると考えたのです。 そして、真理の認識が必要な対象を12個定義します。 それが 『アートマン(自我)』『身体』『感覚器官』『対象』『意識』『思考器官』 『活動(業)』『欠陥』『転生』『結果』『苦』『解脱』 です。 これら全てを正確に『知る』ことによって 苦しみが滅すると考えたわけですね。 とは言え、ここで問題が発生します。 12個の把握すべき真理のうち『アートマン(自我)』は直接認識することができません。 なぜならば、認識を可能にしている主体がアートマンであり、 西洋哲学で散々議論されたとおり、認識方法自体を認識することはできないからです。 ニヤーヤの哲学者たちも同様の問題に悩まされたようですが 彼らは理性によってアートマンを推論しうると考えます。 例えば、欲求という感情を考えたときに。 ある事柄に欲求が生まれるということは 過去に同種の快楽を感じているはずです。 何かを得たいということは、その何かを得ると得をすることが 『あらかじめ分かっている』からだと言うんですね。 そして、そう感じるからには過去と現在において同一の主体が必要であり それそのものがアートマンだと推論することができるとします。 至極当たり前の議論な気がします。 そこまでして『自分』という主体を推論しなくても そりゃ自分は過去も現在も同一の存在だよなと考えても良さそうです。 しかし【アートマン】という概念は非常に厄介な存在でして。 アートマンを単に自我とか心として断定できれば楽なのですが 厳密にはどの言葉も100%アートマンに対応することができません。 仮にアートマンが自我なのだとしたら 輪廻によって次に生まれ変わった生命に宿る自我が 連続性を帯びていることを説明できないからです。 もっと魂よりの意味なのですが、魂ともまた違う。 同じように、私たちは過去に経験したことがないようなことにも 欲求を感じることがあります。 これを前世の経験からくる欲求だと仮定して考えると 輪廻を超えた同一性を持つものの存在を想像することができます。 それがアートマンだと言うわけですね。 このようにして理性を論理的に発揮することで 解脱に必要な真理に到達することができると考えるのがニヤーヤ学派の立場です。 ヴァイシェーシカ学派の解説でも触れましたが ニヤーヤ学派も非常に分析哲学的な要素を持っています。 例えば、仏教などにおいては対象は観念の構造物であると考えます。 一方でニヤーヤ学派は認識や言語は現実世界に完全に対応するという 実在論的なものの見方をします。 白い馬の【白】と【馬】はどちらも現実世界に実在すると考えるのです。 だからこそ、世界に対応した言語や認識を論理的に研究することで 真理に近づくことができると考えたのです。 まさに分析哲学的姿勢です。 そのような立場のニヤーヤ学派ですから、 論理的根拠のない思想を大変嫌いました。 例えば、六派哲学の一つに数えられるヨーガ学派においては 解脱のための瞑想を推奨していました。 そして、解脱によって永遠の幸せを手に入れられると考えたのです。 ニヤーヤ学派は瞑想で解脱に至る根拠が一切ないと、これを否定します。 同時に永遠に幸福が続くなんてことはなく、 論理的に考えたら永遠に続かないと考える方が自然だとし もっと言えば、幸せを求めている段階ですでに執着が発生していて その愛着は束縛となり解脱を阻害する要因となる。 つまり幸せを目的とする解脱は矛盾していると言いました。 解脱が目指すものは無であり、決して幸福ではない。 あくまでも論理的に、事実を冷静に認識した上で 知識と論理によって解脱にたどり着くという姿勢を誇示したのです。 一方で、論理的な推論よりも、信頼できる言葉である神の言葉 すなわちヴェーダに書かれた言葉の方が正しい。 とする宗教的な要素も持ち合わせており この若干のこる曖昧さが西洋哲学との大きな違いであり インド哲学特有の面白さではないかと思います。 とは言え、ニヤーヤ学派の論理は その後様々なインド哲学や思想に取り入れられることとなります。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー









