昨日は、第366回社楽の会を開催しました。
特別ゲストは、修文大学の太田昌孝先生、テーマは『文学と民俗学の出会うところ』

西脇順三郎について、熱く語っていただきました。

ノーベル文学賞候補に3回もなった西脇順三郎の思考の源泉が、若い頃と途中一時期住んでいた新潟県小千谷にあるというお話を、作品を例にしてお話ししていただきました。
太田先生自身、この9年間で小千谷に32回通っているそうです。
我が師・三宅正彦が、安藤昌益の思想を研究するために、大館や八戸に通い詰めたのと同じです。
そして次の書を残しました。
三宅正彦『安藤昌益の思想的風土 大館二井田民俗誌』そしえて出版
太田昌孝先生の著書を紹介します。
『西脇順三郎と小千谷―折口信夫への序章』風媒社
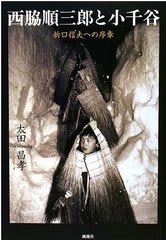
Amazonより商品の説明
内容(「BOOK」データベースより)
詩語に宿る母胎としての“故郷”。詩人のなかに、潜むように隠されてきた小千谷―。香気たかく、豊かな民俗にポエジーの源泉を求め、折口信夫との相関を捉えた、新たなる西脇像の到来を告げる論考。
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
太田 昌孝
1959年12月、愛知県生まれ。静岡大学大学院教育学研究科修士課程(国文学)から、名古屋市立大学大学院人間文化研究科博士後期課程(日本文化・民俗学)。愛知県立高校教諭、静岡産業大学非常勤講師等を経て、一宮女子短期大学専任講師。名古屋市立大学人間文化研究所特別研究員。「西脇順三郎を偲ぶ会」研究委員。主な所属学会等に昭和文学会、日本現代詩研究者国際ネットワーク、日本民俗学会、西脇順三郎を偲ぶ会、宮沢賢治学会、三田文学会、静岡大学国語教育学会、日本詩人クラブ、日本未来派同人、沃野同人(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
特別ゲストは、修文大学の太田昌孝先生、テーマは『文学と民俗学の出会うところ』

西脇順三郎について、熱く語っていただきました。

ノーベル文学賞候補に3回もなった西脇順三郎の思考の源泉が、若い頃と途中一時期住んでいた新潟県小千谷にあるというお話を、作品を例にしてお話ししていただきました。
太田先生自身、この9年間で小千谷に32回通っているそうです。
我が師・三宅正彦が、安藤昌益の思想を研究するために、大館や八戸に通い詰めたのと同じです。
そして次の書を残しました。
三宅正彦『安藤昌益の思想的風土 大館二井田民俗誌』そしえて出版
太田昌孝先生の著書を紹介します。
『西脇順三郎と小千谷―折口信夫への序章』風媒社
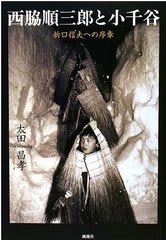
Amazonより商品の説明
内容(「BOOK」データベースより)
詩語に宿る母胎としての“故郷”。詩人のなかに、潜むように隠されてきた小千谷―。香気たかく、豊かな民俗にポエジーの源泉を求め、折口信夫との相関を捉えた、新たなる西脇像の到来を告げる論考。
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
太田 昌孝
1959年12月、愛知県生まれ。静岡大学大学院教育学研究科修士課程(国文学)から、名古屋市立大学大学院人間文化研究科博士後期課程(日本文化・民俗学)。愛知県立高校教諭、静岡産業大学非常勤講師等を経て、一宮女子短期大学専任講師。名古屋市立大学人間文化研究所特別研究員。「西脇順三郎を偲ぶ会」研究委員。主な所属学会等に昭和文学会、日本現代詩研究者国際ネットワーク、日本民俗学会、西脇順三郎を偲ぶ会、宮沢賢治学会、三田文学会、静岡大学国語教育学会、日本詩人クラブ、日本未来派同人、沃野同人(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)










それから貴会の存在は稀有であり、貴重です。「先生に学ぶ姿勢がなければ生徒はついてこない。」というのが高校教師時代からの私の信条です。また教師はたくさんの引き出しを持ち、その中から自分の『決め球』を絞り込んでゆくと、厳しい現実を目の前にしても挫けることはないはずです。特に参加して下さった若い先生方、どうかいつまでも学ぶ心を失わず、ご自分をupdateし続けて下さい。同じことの繰り返しという日常は意識を「冬眠状態」に陥らせます。そんな時、『西脇順三郎詩集』を紐解き、脳髄にショックを与えてみるのも良いかもしれませんよ。(笑い)
最後に僭越ですが、宮沢賢治の教え方等でお悩みの時は遠慮なく私にご連絡下さい。また、出張授業も大歓迎です!連絡先は管理人様にお聞き下さい。
「研究とは、小さなことでもいいから、誰も言っていないことを見つけること。それが人類への貢献になる」
いつも三宅先生が言っていた言葉です。学生の卒論でも一切の妥協を許さず、オリジナルを求められました。
その世界の一端が参加者に伝わったと思います。
来年は、「やまなし」の模擬授業をぜひお願いします!
『やまなし』は研究者泣かせの作品です。私自身、授業の経験は有りませんが、長年賢治と関わってきた経験を生かして是非、がんばりたいと思います、