週刊日本の100人 松尾芭蕉
シリーズ第44号は松尾芭蕉です。
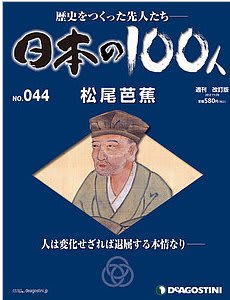
ご存じ、俳聖・松尾芭蕉の登場です。
江戸時代を代表する俳人です。
1644年(正保元年)伊賀(現在の三重県)上野に生まれます。
1675年に江戸へ出ます。
1684年に旅に出ます。
1694年(元禄7年)体調を崩し、大坂にて病没しました。
「野ざらし紀行」、「鹿島紀行」、「笈の小文」、「更科紀行」、「奥の細道」などの俳諧紀行を残しました。
さて、松尾芭蕉といえば「忍者説」
出生地が伊賀で名字を持っていたこと、何度も旅に出られる経済力があったこと、移動距離と曽良の記録との違い、などが根拠ですが、この「日本の100人」ではどう解釈しているのでしょうか。
実は結論は出していません。いろいろな説が紹介されており、疑問がさらにふくらみます。
以前、色丹島を訪問したときに、ロシアの子どもたちが松尾芭蕉について調べ学習をしていたのが印象に残っています。
世界で最も短い定型詩。
どう理解したのでしょうか・・・。
目次です。
■特集
松尾芭蕉
人は変化せざれば退屈する本情なり
■ライフ&タイム
旅に生き旅に死す漂泊の俳聖の50年
迷い多き伊賀時代/江戸の人気俳諧師の転機
隠棲生活のなかで/「奥の細道」の旅路へ
ついに確立した新境地
■ヒューマンエピソード
俳諧一筋に生き抜いた自然体の世捨て人
■クローズアップ
悟りの道か、隠密行か?「奥の細道」の旅を徹底検証
■人物スクランブル
松尾芭蕉 人物相関図
与謝蕪村/杜甫/宝井其角/R・H・ブライス
■後世への遺産
俳諧からHAIKUへ 蕉風は世界を駆け巡る
■評伝アラカルト
松尾芭蕉考
黛まどか/芥川龍之介/養老孟司
正岡子規/上田秋成/中上健次
■ビジュアル人物事典
佐佐木信綱/佐竹義宣/佐藤一斎/佐藤栄作
佐藤賢了/佐藤忠信/佐藤継信/サトウハチロー
■日本の100人ミュージアム
このシリーズでの100人は・・・
織田信長
徳川家康
豊臣秀吉
坂本竜馬
伊達政宗
平清盛
勝海舟
真田幸村
源 義経
武田信玄
西郷隆盛
明智光秀
上杉謙信
石田三成
徳川家光
前田利家
高杉晋作
徳川慶喜
聖徳太子
徳川吉宗
近藤勇
黒田官兵衛
足利尊氏
吉田松陰
空海
大久保利通
東郷平八郎
徳川光圀
東条英機
北条早雲
山内一豊
土方歳三
田中角栄
福沢諭吉
宮本武蔵
加藤清正
毛利元就
吉田茂
源頼朝
山本五十六
直江兼続
平賀源内
伊藤博文
松尾芭蕉
白州次郎
徳川綱吉
千利休
細川幽斎
大石内蔵助
木戸孝允
島津義弘
足利義満
渋沢栄一
井伊直弼
大友宗麟
福島正則
松下幸之助
伊能忠敬
板垣退助
後醍醐天皇
平将門
乃木希典
南方熊楠
大隈重信
日蓮
ジョン万次郎
野口英世
大村益次郎
山本勘助
田沼意次
松平容保
菅原道真
北条時宗
藤堂高虎
榎本武揚
島津斉彬
二宮金次郎
後藤新平
手塚治虫
岩崎弥太郎
本田宗一郎
親鸞
津田梅子
藤原道長
山田長政
上杉鷹山
原敬
森鴎外
葛飾北斎
岩倉具視
芥川龍之
新渡戸稲造
犬養毅
黒澤明
日野富子
豊臣秀長
今川義元
本居宣長
高橋是清
夏目漱石
シリーズ第44号は松尾芭蕉です。
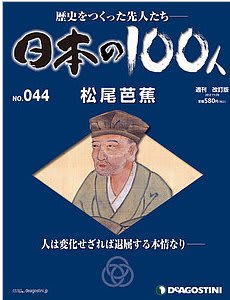
ご存じ、俳聖・松尾芭蕉の登場です。
江戸時代を代表する俳人です。
1644年(正保元年)伊賀(現在の三重県)上野に生まれます。
1675年に江戸へ出ます。
1684年に旅に出ます。
1694年(元禄7年)体調を崩し、大坂にて病没しました。
「野ざらし紀行」、「鹿島紀行」、「笈の小文」、「更科紀行」、「奥の細道」などの俳諧紀行を残しました。
さて、松尾芭蕉といえば「忍者説」
出生地が伊賀で名字を持っていたこと、何度も旅に出られる経済力があったこと、移動距離と曽良の記録との違い、などが根拠ですが、この「日本の100人」ではどう解釈しているのでしょうか。
実は結論は出していません。いろいろな説が紹介されており、疑問がさらにふくらみます。
以前、色丹島を訪問したときに、ロシアの子どもたちが松尾芭蕉について調べ学習をしていたのが印象に残っています。
世界で最も短い定型詩。
どう理解したのでしょうか・・・。
目次です。
■特集
松尾芭蕉
人は変化せざれば退屈する本情なり
■ライフ&タイム
旅に生き旅に死す漂泊の俳聖の50年
迷い多き伊賀時代/江戸の人気俳諧師の転機
隠棲生活のなかで/「奥の細道」の旅路へ
ついに確立した新境地
■ヒューマンエピソード
俳諧一筋に生き抜いた自然体の世捨て人
■クローズアップ
悟りの道か、隠密行か?「奥の細道」の旅を徹底検証
■人物スクランブル
松尾芭蕉 人物相関図
与謝蕪村/杜甫/宝井其角/R・H・ブライス
■後世への遺産
俳諧からHAIKUへ 蕉風は世界を駆け巡る
■評伝アラカルト
松尾芭蕉考
黛まどか/芥川龍之介/養老孟司
正岡子規/上田秋成/中上健次
■ビジュアル人物事典
佐佐木信綱/佐竹義宣/佐藤一斎/佐藤栄作
佐藤賢了/佐藤忠信/佐藤継信/サトウハチロー
■日本の100人ミュージアム
このシリーズでの100人は・・・
織田信長
徳川家康
豊臣秀吉
坂本竜馬
伊達政宗
平清盛
勝海舟
真田幸村
源 義経
武田信玄
西郷隆盛
明智光秀
上杉謙信
石田三成
徳川家光
前田利家
高杉晋作
徳川慶喜
聖徳太子
徳川吉宗
近藤勇
黒田官兵衛
足利尊氏
吉田松陰
空海
大久保利通
東郷平八郎
徳川光圀
東条英機
北条早雲
山内一豊
土方歳三
田中角栄
福沢諭吉
宮本武蔵
加藤清正
毛利元就
吉田茂
源頼朝
山本五十六
直江兼続
平賀源内
伊藤博文
松尾芭蕉
白州次郎
徳川綱吉
千利休
細川幽斎
大石内蔵助
木戸孝允
島津義弘
足利義満
渋沢栄一
井伊直弼
大友宗麟
福島正則
松下幸之助
伊能忠敬
板垣退助
後醍醐天皇
平将門
乃木希典
南方熊楠
大隈重信
日蓮
ジョン万次郎
野口英世
大村益次郎
山本勘助
田沼意次
松平容保
菅原道真
北条時宗
藤堂高虎
榎本武揚
島津斉彬
二宮金次郎
後藤新平
手塚治虫
岩崎弥太郎
本田宗一郎
親鸞
津田梅子
藤原道長
山田長政
上杉鷹山
原敬
森鴎外
葛飾北斎
岩倉具視
芥川龍之
新渡戸稲造
犬養毅
黒澤明
日野富子
豊臣秀長
今川義元
本居宣長
高橋是清
夏目漱石









