昨日(2017年6月10日)、第25回 授業実践フォーラム へ行ってきました。
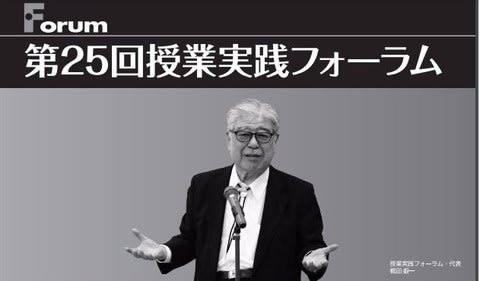
会場の不二羽島文化センターは満員御礼。
テーマ「新しい学習指導要領が目指すもの~各教科等における見方・考え方と授業実践~」
開会あいさつでは、
勝見先生が、教育観の「観」とは哲学。
今日は、how-to ではなく、「観」をお土産に持ち帰ってほしい。
流行を見据えつつ変わらぬこと、変えてはならないことを気づかせてくれる
ただし、教育の哲学や理念は、具体的な実践になってこそ価値がある。
この言葉が印象的でした。
岐阜市教委の服部先生のあいさつ。
「AIにできない教員の仕事の部分を大切にしたい。」
その通りです。
文部科学省 白井 俊 先生
「育成すべき資質能力と各教科等における見方・考え方」
白井先生は、OECD パリで勤務。キーコンピテンシーを考える仕事で、カリキュラム、教授法、マネジメントの研究の専門家です。
何ができるようになるか、コンピテンシー(資質・能力)を育成すべきかが、これが国際的なトレンド。
内容(コンテンツ)か資質・能力(コンピテンシー)か。
今回の指導要領では、全者から、後者重視に転換する。
知識より、思考力判断力が重視したら、知識がおろそかになり、思考力も減ってしまった。
基本的な知識・技能も大切。
見方・考え方は教科によって違う。
この後、鼎談
加藤 明
白井 俊
角屋重樹
午後からは、社会科、算数科、小学校英語の講座に出ました。
最後の梶田先生の講演は、やや聞き苦しいものでした。
新学習指導要領は、今までの10年とそんなに変わらない。
その前が変わった。
前々回。
子供に任せればうまくいく。
指導しない方がうまく育つ、といっていた。
しかし、大人が責任を持って指導しなければ子どもは育たない。
指導は、小うるさく言うものではない。
場づくり、課題の設定、・・・、これが教師の専門性。
2000年の指導要領は禍根を残した。
恥ずかしいものだった。
いつものように、ゆとり教育の悪口で、前回の指導要領を自画自賛です。
今回、戦後最大の大改訂と言われていますが、
「新学習指導要領は、今までの10年とそんなに変わらない。」と言ったことには驚きました。
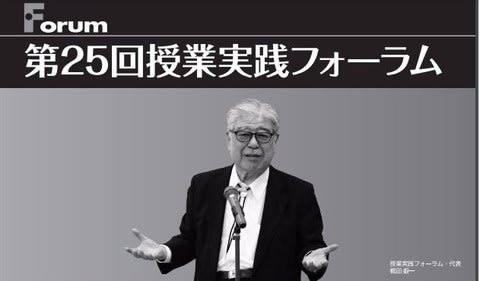
会場の不二羽島文化センターは満員御礼。
テーマ「新しい学習指導要領が目指すもの~各教科等における見方・考え方と授業実践~」
開会あいさつでは、
勝見先生が、教育観の「観」とは哲学。
今日は、how-to ではなく、「観」をお土産に持ち帰ってほしい。
流行を見据えつつ変わらぬこと、変えてはならないことを気づかせてくれる
ただし、教育の哲学や理念は、具体的な実践になってこそ価値がある。
この言葉が印象的でした。
岐阜市教委の服部先生のあいさつ。
「AIにできない教員の仕事の部分を大切にしたい。」
その通りです。
文部科学省 白井 俊 先生
「育成すべき資質能力と各教科等における見方・考え方」
白井先生は、OECD パリで勤務。キーコンピテンシーを考える仕事で、カリキュラム、教授法、マネジメントの研究の専門家です。
何ができるようになるか、コンピテンシー(資質・能力)を育成すべきかが、これが国際的なトレンド。
内容(コンテンツ)か資質・能力(コンピテンシー)か。
今回の指導要領では、全者から、後者重視に転換する。
知識より、思考力判断力が重視したら、知識がおろそかになり、思考力も減ってしまった。
基本的な知識・技能も大切。
見方・考え方は教科によって違う。
この後、鼎談
加藤 明
白井 俊
角屋重樹
午後からは、社会科、算数科、小学校英語の講座に出ました。
最後の梶田先生の講演は、やや聞き苦しいものでした。
新学習指導要領は、今までの10年とそんなに変わらない。
その前が変わった。
前々回。
子供に任せればうまくいく。
指導しない方がうまく育つ、といっていた。
しかし、大人が責任を持って指導しなければ子どもは育たない。
指導は、小うるさく言うものではない。
場づくり、課題の設定、・・・、これが教師の専門性。
2000年の指導要領は禍根を残した。
恥ずかしいものだった。
いつものように、ゆとり教育の悪口で、前回の指導要領を自画自賛です。
今回、戦後最大の大改訂と言われていますが、
「新学習指導要領は、今までの10年とそんなに変わらない。」と言ったことには驚きました。









