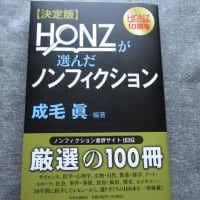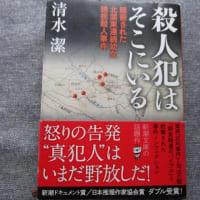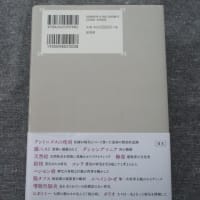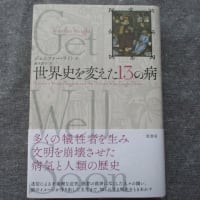TVメディアの機能「注目を集める」について
中でも政治参加を促す面のあるプレス(報道)について。
スポンサーは、番組の合間に流れるCM時間枠(広告媒体)を広告代理店を通じて買取(言わば代理店は手数料をいただくブローカー)、その金でTV放送会社は成り立っている。メインは、番組ではなくCMなのである。このような収益モデルのために、報道番組でさえこのビジネスモデルの影響から免れることができなくなってしまった。高い視聴率を獲得する。つまり、できる限り多くの注目を集めなければ、放送会社にとって、スポンサーが減少することは収入減を意味し、それが続けば事業として成り立たなくなり、倒産するからである。視聴率の過当競争がこのような現実を生み出した。
「公器としてのメディア」とか誰かが言っていたが、上場していれば、その上場企業にとっての公とは誰を指すかといえばそれは当然株主である。
だから現実は、まじめな内容(社会の悪い面をどう解決するか)を追求するような番組は、大衆の興味外にあるために作成されず、大衆がほっとする、癒される、笑える番組に駆逐され、報道さえも大衆迎合的な、劇のような放送となってしまうのである。例えば選挙でマニフェストより刺客騒動を報道番組が大きく扱ったのは記憶にあたらしい。
こうしたスポンサー(TVをプロモーションに利用する企業)、広告代理店、広告媒体企業(TV放送会社)の悪しき三角形に割って入ったのがインターネット・サイトである。インターネットでは個人(プロ・アマ問わず)が自分の考え(あるいはニュース)をまるで放送局のように、しかも直接的に全国(ブロード)、団体・グループ(ナロー)、個人(ポイント)に発信することが可能となったのである。能動的な個人は多数の選択肢の中からあるいは選択肢を組み合わせてその発信されるサイトにアクセスすることで情報を得る機会を得ることができたのである。これは、個人にとってマスメディアという媒介者を通じて情報を分かりやすい説明を流してもらうという唯一の権力とは違った形の媒介者を手に入れたことを意味するのである。
このようなものを市民メディアと呼ぶとすれば、この市民メディアの発達こそが、既存のメディアに揺さぶりをかけ、健全な報道を復活させる手段となる可能性を秘めているのである。