京都府埋蔵文化財調査研究センターは19日、長岡京市下海印寺西条の下海印寺遺跡で、平安末期(11世紀末~12世紀前半)に築造された、堀で方形に区画された屋敷地の中心建物とみられる掘立柱跡が出土した、と発表した。同センターは「在地領主の主殿と考えられる」としている。
京都第二外環状道路建設に伴い2年前から調査。昨年、方形区画の南西角に当たる堀跡を確認し、以後も発掘を続けていた。
中心建物跡は、昨年に堀跡が出た場所から東方約30メートルの地点で、掘立柱の柱穴計10基(各70センチ四方)が見つかった。範囲は南北9メートル、東西10メートルに及び大型であることから、主殿と判断した。
さらに、中心建物跡から南東約10メートルの地点で、方形区画の南東角とみられる「L」字状に曲がる堀跡(幅9・5メートル、深さ1・6メートル)を新たに確認。南西角の堀跡までは50メートルで、この結果、区画の東西幅は50メートルと特定した。先の調査では、南西角の堀跡から直線で25メートル北の地点に土橋の跡を検出、正門とみられることで、南北幅はその倍の東西幅と同じ50メートルと推定され、方形区画の全範囲がこれで特定できたとしている。
遺構からは、奈良-平安期に朝廷が順次発行した12種類の銅銭「皇朝十二銭」の8番目に当たる「饒益神宝(にょうえきしんぽう)」が1枚、9番目の「貞観永宝(じょうがんえいほう)」が17枚の計18枚も発見。重なった状態だったことから、地鎮のため埋められた可能性が高い。
同センターは「平安末期の、都から離れた地域の実態解明につながる希少な例」としている。現地説明会は、22日午後2時から。問い合わせは現地事務所の携帯電話080(5324)7920。

京都第二外環状道路建設に伴い2年前から調査。昨年、方形区画の南西角に当たる堀跡を確認し、以後も発掘を続けていた。
中心建物跡は、昨年に堀跡が出た場所から東方約30メートルの地点で、掘立柱の柱穴計10基(各70センチ四方)が見つかった。範囲は南北9メートル、東西10メートルに及び大型であることから、主殿と判断した。
さらに、中心建物跡から南東約10メートルの地点で、方形区画の南東角とみられる「L」字状に曲がる堀跡(幅9・5メートル、深さ1・6メートル)を新たに確認。南西角の堀跡までは50メートルで、この結果、区画の東西幅は50メートルと特定した。先の調査では、南西角の堀跡から直線で25メートル北の地点に土橋の跡を検出、正門とみられることで、南北幅はその倍の東西幅と同じ50メートルと推定され、方形区画の全範囲がこれで特定できたとしている。
遺構からは、奈良-平安期に朝廷が順次発行した12種類の銅銭「皇朝十二銭」の8番目に当たる「饒益神宝(にょうえきしんぽう)」が1枚、9番目の「貞観永宝(じょうがんえいほう)」が17枚の計18枚も発見。重なった状態だったことから、地鎮のため埋められた可能性が高い。
同センターは「平安末期の、都から離れた地域の実態解明につながる希少な例」としている。現地説明会は、22日午後2時から。問い合わせは現地事務所の携帯電話080(5324)7920。














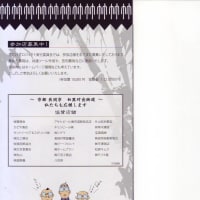
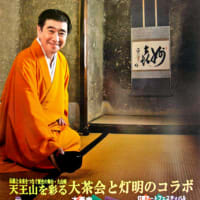

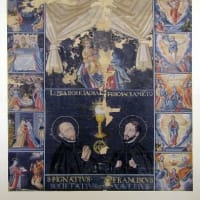
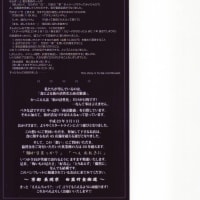
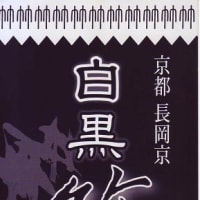
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます