 奈良時代の高僧、行基(668~749年)が建てた京都府大山崎町大山崎の「山崎院」の跡地で見つかった銅塊が、奈良・東大寺の大仏鋳造用だった可能性が高まったのを受け、「大山崎ふるさとガイドの会」は18日、同町円明寺の町立中央公民館で学習会を開いた。発掘を担当した町職員を招き、会員約40人が説明に耳を傾けた。
奈良時代の高僧、行基(668~749年)が建てた京都府大山崎町大山崎の「山崎院」の跡地で見つかった銅塊が、奈良・東大寺の大仏鋳造用だった可能性が高まったのを受け、「大山崎ふるさとガイドの会」は18日、同町円明寺の町立中央公民館で学習会を開いた。発掘を担当した町職員を招き、会員約40人が説明に耳を傾けた。銅塊が24日から町歴史資料館で展示されるのを前に、ガイドとして来館者に説明できるように事前に学習しようと企画した。
発掘を担当した町経済環境課(前町教委)の林亨主幹は、円盤形の銅塊6枚がまとまって出土した点に触れ、「行基が大仏造立に貢献した褒美として、鋳造後に余った銅が山崎院に下賜されたのでは」と推測した。
会員からは「銅が東大寺へ運ばれる途中で留め置かれた可能性はないか」という質問が出た。出席した町教委職員は「造立を前に良質の銅を早く集めたい時期に、山崎院に留める理由が考えにくい」と答えた。
学習会では、銅塊2枚が展示された。ガイドたちはお好み焼きに似た大仏ゆかりの銅塊を興味深そうに眺め、はっきり記憶に残るよう、その色や大きさを頭にインプットしていた。
【 2011年05月19日 11時13分 】
 | 民衆の導者 行基 (日本の名僧) |
| クリエーター情報なし | |
| 吉川弘文館 |













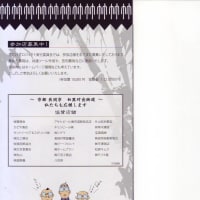
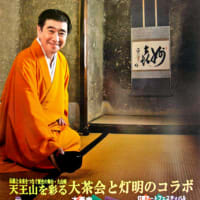

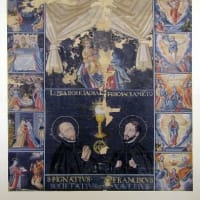
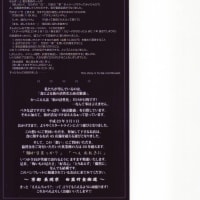
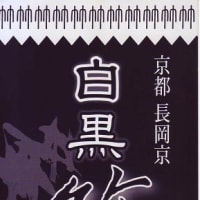
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます