皆さん、こんにちは!
当館のある石炭記念公園には、近代化遺産として、先日ご紹介した竪坑櫓とともに、田川のシンボルである巨大な二本の煙突がそびえています。
三井田川鉱業所の伊田竪坑建設にともない、1908年に完成したこの煙突は、高さ45.45m、直径上部3.1m、同下部5.8mと、現存する明治期の煙突としては最大級のもので、使用された耐火煉瓦はなんと213,000枚、そのうち181,000枚はドイツ製のものと言われています。
東側の、根元に張出のない「第一煙突」は、下部の煉瓦はフランドル積みで、途中からイギリス積みに変わっております。
西側の、根元に張出のある「第二煙突」の煉瓦は全てイギリス積みで造られています。

フランドル積みは明治中期に流行った積み方で、一段に長い辺と短い辺が交互になる様に煉瓦を置き、イギリス積みでは、長い辺だけを並べた段と、短い辺だけを並べた段を交互に積みます。
イギリス積みの方が強度は高いと言われ、明治後期以降に主流となります。
二本の煙突を作っている最中に、流行が変わってしましたのですネー。
煙突の下には、現在は残っていませんが、12基の大型ボイラーが据え付けられた汽缶場(ボイラーハウス)という建物がありました。
蒸気機関車に積まれているものによく似たボイラーで、石炭を燃やして水を沸騰させ、大量の蒸気を作り、竪坑櫓のケージを上げ下げする『巻上機』及び付属設備の動力用蒸気エンジンに送っていました。
つまり、煙突は燃やした石炭の排煙のために建造されたという訳ですネ!
この炭坑の選炭場で生まれた「炭坑節」の歌詞に「あんまり煙突が高いので、さぞやお月さん煙たかろ♪」と歌われています。
当時の人々にとっては、今までに見たこともないほど巨大なものに感じたのでしょうネ!
筑豊炭田の最盛期、規模は様々ですが、各炭坑には煙突があり、それがシンボルになっていました。
坑夫の間で歌われていた「ゴットン節」には「赤い煙突目当てに行けば、米のマンマが暴れ食い♪」という歌詞がありますが、これは『赤い(煉瓦)の煙突(炭坑)のある所へ行けば、白いご飯が沢山食べられるほど稼げるゾ!』といったような意味です。
炭坑の動力は徐々に電気に切り替わり、伊田坑の巻上機も1952年に電化されます。しかし、それ以降もボイラーは病院や炭鉱住宅の給湯用として使われ、煙突は一本のみ煙を上げていましたが、1964年の閉山でついにその役目を終えます。
田川の上に出たお月さんも、ようやく煙突の煙りから開放されたのですね~。
このような大型煉瓦煙突は、老朽化により解体されたりして世界的にも少なくなっており、貴重なものになっています。
ぜひ、この貴重な煙突を見に、田川に遊びに来てください!
最新の画像[もっと見る]












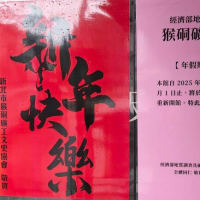





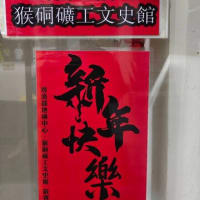

第一立坑・第二立坑はイギリス式ですしね。