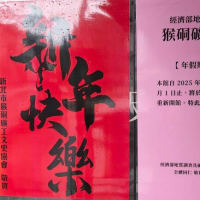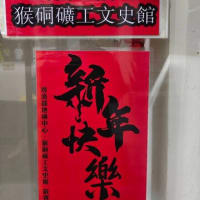市博物館では、山本作兵衛コレクションがユネスコ世界記憶遺産に登録された2011年から、
IPM(総合的有害生物管理)という考え方にならって、生物被害防除を単に薬剤を使って行うのではなく、
さまざまな方法を総合的・合理的に組み合わせることでその数・出現範囲を管理し、自然と共存していくという思いを持って館運営を行っています。
勿論、薬剤も必要な場面では、適切な量を使用します。
市美術館Facebookでも以前取り上げていましたが、博物館でもこの夏、資料の燻蒸を行いました。
博物館では、炭坑資料や民俗資料、古書をご寄贈いただくことがあります。
それ自体は大変ありがたいことなのですが、個人宅や蔵の中に長年置かれていた場合、
あまりの居心地の良さに居つき、資料・書籍を食害していたり糞をしていたり、はたまた虫が眠っていたり
虫に居心地がいいということはカビも生えていたり・・・
ご寄贈していただいたままの状態で収蔵庫に保管もしくは展示室で展示公開するには、さまざまなリスクが考えられます。
ですので、博物館では資料・書籍をご寄贈いただいた場合、必要に応じて燻蒸等の作業を行っています。
旧収蔵場所の情報から目視観察のみで収蔵可能と判断し、燻蒸を行わない場合もあります。

◆燻蒸に用いる薬剤は人体にも影響があるものなので、閉館後~休館日に実施しました。
安全確保の為、立入禁止区域を設け、ガスマスクも装着


◆目張りを行い、ガス漏れ防止+ガス漏れが無いか常時チェック
燻蒸はやったら安心・終わりという訳ではなく、終了後、資料についた虫や糞を払ったり、安全な場所へ移動させたりする必要があります。
現在も天気のいい日に資料をめくり、そこに付いた異物を払う作業を行っています。
・・・燻蒸実施から日にちがかなり経っていますが、これがとても地味で終わりの見えない作業
・・・頁を捲ると虫糞がポロポロしていたり、虫に食害された穴があったり、資料の健康状態を知るには欠かせない大切な作業です。
そして先日、燻蒸業者さんから業務実施報告書が届きました。

◆燻蒸を実施する際、燻蒸室内・室外にテストサンプル(生きている虫+生きている菌)を設置
燻蒸作業終了後速やかに、このテストサンプルを公益財団法人文化財虫菌害研究所へ送付し、
それらの生存・孵化・培養結果(約1か月)によって、同研究所から燻蒸の効果判定書が届きます。
当館がこの夏実施した燻蒸は、殺虫殺卵・殺菌効果 それぞれ100%との判定をいただきました。
それぞれ100%との判定をいただきました。
このような流れを経て、収蔵資料は安全に収蔵され、展示公開の日を待つのです。
・・・私は燻蒸後の資料をめくる・払う作業をもう少し頑張ります
IPM(総合的有害生物管理)という考え方にならって、生物被害防除を単に薬剤を使って行うのではなく、
さまざまな方法を総合的・合理的に組み合わせることでその数・出現範囲を管理し、自然と共存していくという思いを持って館運営を行っています。
勿論、薬剤も必要な場面では、適切な量を使用します。
市美術館Facebookでも以前取り上げていましたが、博物館でもこの夏、資料の燻蒸を行いました。
博物館では、炭坑資料や民俗資料、古書をご寄贈いただくことがあります。
それ自体は大変ありがたいことなのですが、個人宅や蔵の中に長年置かれていた場合、
あまりの居心地の良さに居つき、資料・書籍を食害していたり糞をしていたり、はたまた虫が眠っていたり

虫に居心地がいいということはカビも生えていたり・・・
ご寄贈していただいたままの状態で収蔵庫に保管もしくは展示室で展示公開するには、さまざまなリスクが考えられます。
ですので、博物館では資料・書籍をご寄贈いただいた場合、必要に応じて燻蒸等の作業を行っています。
旧収蔵場所の情報から目視観察のみで収蔵可能と判断し、燻蒸を行わない場合もあります。

◆燻蒸に用いる薬剤は人体にも影響があるものなので、閉館後~休館日に実施しました。
安全確保の為、立入禁止区域を設け、ガスマスクも装着


◆目張りを行い、ガス漏れ防止+ガス漏れが無いか常時チェック
燻蒸はやったら安心・終わりという訳ではなく、終了後、資料についた虫や糞を払ったり、安全な場所へ移動させたりする必要があります。
現在も天気のいい日に資料をめくり、そこに付いた異物を払う作業を行っています。
・・・燻蒸実施から日にちがかなり経っていますが、これがとても地味で終わりの見えない作業

・・・頁を捲ると虫糞がポロポロしていたり、虫に食害された穴があったり、資料の健康状態を知るには欠かせない大切な作業です。
そして先日、燻蒸業者さんから業務実施報告書が届きました。

◆燻蒸を実施する際、燻蒸室内・室外にテストサンプル(生きている虫+生きている菌)を設置
燻蒸作業終了後速やかに、このテストサンプルを公益財団法人文化財虫菌害研究所へ送付し、
それらの生存・孵化・培養結果(約1か月)によって、同研究所から燻蒸の効果判定書が届きます。
当館がこの夏実施した燻蒸は、殺虫殺卵・殺菌効果
 それぞれ100%との判定をいただきました。
それぞれ100%との判定をいただきました。このような流れを経て、収蔵資料は安全に収蔵され、展示公開の日を待つのです。
・・・私は燻蒸後の資料をめくる・払う作業をもう少し頑張ります