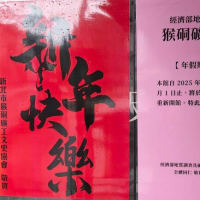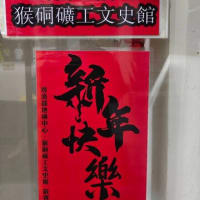みなさん、こんにちは!
先月のブログでのお約束通り、今回からは、『山本作兵衛コレクション』の「価値」と「魅力」につきまして紹介させていただきます。
『山本作兵衛コレクション』は、炭坑記録画589点と日記、雑記帳、その他の原稿と記念品類、合わせて697点の資料で構成されておりますが、その魅力の核心は、なんといっても墨絵と水彩画で構成される『炭坑記録画』にあります。
この記録画の題材は、山本作兵衛(明治25年-昭和59年)が実際に経験した、明治32年頃から大正時代中期(作兵衛7歳から青年期)にかけての、中小の炭坑における手掘り採炭の詳細な様子と、当時の炭坑労働者の生活が中心になっています。
昭和期の機械化された炭坑の様子を題材にした記録画は少ないのですが、作兵衛氏の言葉を借りれば「(その時代なら)写真がありますモン」ということです。
そう、明治から大正時代の炭坑の記録で、特に坑内の写真はほとんどありません。
世界で最初に産業革命の起こったイギリスにおいても、炭坑の外観や坑外での炭坑労働者を写した写真は結構ありますが、初期の坑内作業に関しては画家による絵の例がいくらかあるだけです。
なぜならば、暗い坑内でのカメラ撮影にはフラッシュが不可欠ですが、当時の粉末マグネシウム主体の閃光粉を燃やすフラッシュでは、ガス爆発や炭塵爆発を招く恐れがありましたし、電池式のストロボが出来てからも、カメラの防塵ケースなど無い時代ですので、炭塵が詰まってカメラが使用不能になることもしばしばでした。
このような理由もあり、山本作兵衛コレクションのような、「実際に坑内で働いた経験者による視覚的で具体的な記録」は、他にあまり例のない、世界的に見ても極めて貴重なものなのです。
産業革命を支え、近代化の文字通り燃料となった石炭採掘現場の当時のありのままの姿を知ることのできる重要なのです。
次回は、山本作兵衛コレクションの特徴と魅力について、もう少し詳しくご紹介させていただきます!