朝日新聞4月25日(土)、土曜日の別刷りbeの連載「はてなスコープ」から

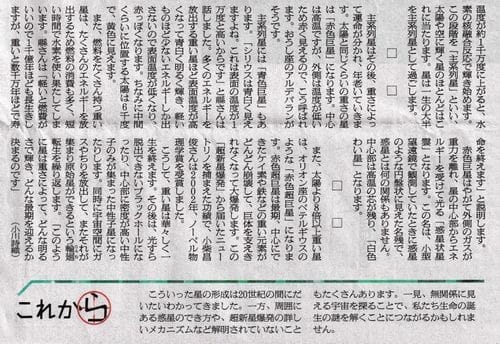
(はてなスコープ)
星の誕生から最期まで
生まれた重さが運命の岐路
2020年4月25日
夜空に輝く星たちにも、私たち人間と同じようにいろいろな人生があります。輝かし
い一生なのか、静かに終えるのか――。星はどうやって生まれて、どう年老いていく
のでしょうか。
一般的に星の寿命は約100億年と言われています。私たちがすむ太陽系にある
太陽は、誕生してから46億年経っています。「寿命が100年の人間で例えると、
今の太陽は働き盛りで、とても安定した状態といえます」と国立天文台の縣秀彦准教授。
私たちがいる太陽系の外は、ほとんど真空に近い状態ですが、ところどころに水素
やヘリウムのようなガスやちり(星間物質)が多く集まっている場所があります。
そこで星は誕生します。ガス同士の重力で互いに引っ張り合い、収縮により温度が上
がり、「原始星」という星の赤ちゃんが生まれます。原始星は周囲の星間物質を重力
によって引きつけて成長していきます。こういった星の誕生の場面はいくつも見つか
っています。例えば、オリオン大星雲やわし星雲、オメガ星雲などです。
その後、原始星が成長し、中心温度が約1千万度に上がると、水素の核融合反応で
輝き始めます。この段階を「主系列星」といい、太陽や空に輝く星のほとんどはこれ
に当たります。星は一生の大半を主系列星として過ごします。
□ □
主系列星はその後、重さによって運命が分かれ、年老いていきます。太陽と同じく
らいの重さの星は「赤色巨星」になります。中心は高温ですが、外側は温度が低いた
め赤く見えるので、こう呼ばれます。おうし座のアルデバランがそうです。
主系列星には「青色巨星」もあります。「シリウスは青白く見えますよね。これは
表面の温度が1万度と高いからです」と縣さんは話しました。多くのエネルギーを
放出する重い星ほど表面温度が高くなって青白く明るく輝き、軽いものほど少ない
エネルギーしか出さないので表面温度が低くなり、赤っぽくなります。ちなみに中間
くらいに位置する太陽は6千度で、黄色に見えます。
また、燃料をたくさん持つ重い星は、たくさんのエネルギーを放出するため燃料の
消費も多く、短い時間で水素を使い果たしてしまいます。縣さんは「軽いと燃費が
いいので1千億年ほども長生きしますが、重いと数千万年ほどで寿命を終えます」
と説明します。
赤色巨星はやがて外側のガスが重力を離れ、星の中心部からエネルギーを受けて
光る「惑星状星雲」となります。この名は、小型望遠鏡で観測していたときに惑星
のような円盤状に見えた名残で、惑星とは何の関係もありません。中心部は高温の
芯が残り、「白色わい星」となります。
□ □
また、太陽より8倍以上重い星は、オリオン座のベテルギウスのような「赤色超
巨星」になります。赤色超巨星は最期、中心にできたケイ素や鉄などの重い元素が
どんどん崩壊して、巨体を支えきれなくなって大爆発します。この「超新星爆発」
から届いたニュートリノを捕まえた功績で、小柴昌俊さんは2002年、ノーベル
物理学賞を受賞しました。
こうして、重い星は華々しく一生を終えます。その後は、光すら脱出できない
ブラックホールになったり、中心部に密度が高い中性子のみが集まった中性子星に
なったりします。同時に宇宙空間にガスやちりを放出して、またそれが集まり原始
星ができるという輪廻転生を繰り返します。「このように星は重さによって、どん
な明るさで輝き、どんな最期を迎えるか決まるのです」(小川詩織)
■これから
こういった星の形成は20世紀の間にだいたいわかってきました。一方、周囲に
ある惑星のでき方や、超新星爆発の詳しいメカニズムなど解明されていないことも
たくさんあります。一見、無関係に見える宇宙を探ることで、私たち生命の誕生の
謎を解くことにつながるかもしれません。
★最近、天文講話の依頼が少なく(無くなり)ました。
星の誕生から最期まで(星の一生)は定番のネタです。
・ブラックホールについては、昨年直接撮影されました。
・赤色超巨星のオリオン座ベテルギウスの超新星爆発問題等
・星仲間Iさんのベテルギウスの光度変化等
話のネタはたくさんあります。

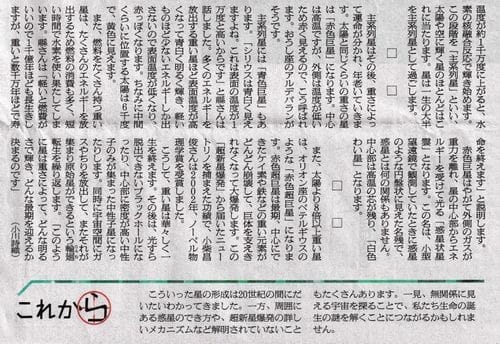
(はてなスコープ)
星の誕生から最期まで
生まれた重さが運命の岐路
2020年4月25日
夜空に輝く星たちにも、私たち人間と同じようにいろいろな人生があります。輝かし
い一生なのか、静かに終えるのか――。星はどうやって生まれて、どう年老いていく
のでしょうか。
一般的に星の寿命は約100億年と言われています。私たちがすむ太陽系にある
太陽は、誕生してから46億年経っています。「寿命が100年の人間で例えると、
今の太陽は働き盛りで、とても安定した状態といえます」と国立天文台の縣秀彦准教授。
私たちがいる太陽系の外は、ほとんど真空に近い状態ですが、ところどころに水素
やヘリウムのようなガスやちり(星間物質)が多く集まっている場所があります。
そこで星は誕生します。ガス同士の重力で互いに引っ張り合い、収縮により温度が上
がり、「原始星」という星の赤ちゃんが生まれます。原始星は周囲の星間物質を重力
によって引きつけて成長していきます。こういった星の誕生の場面はいくつも見つか
っています。例えば、オリオン大星雲やわし星雲、オメガ星雲などです。
その後、原始星が成長し、中心温度が約1千万度に上がると、水素の核融合反応で
輝き始めます。この段階を「主系列星」といい、太陽や空に輝く星のほとんどはこれ
に当たります。星は一生の大半を主系列星として過ごします。
□ □
主系列星はその後、重さによって運命が分かれ、年老いていきます。太陽と同じく
らいの重さの星は「赤色巨星」になります。中心は高温ですが、外側は温度が低いた
め赤く見えるので、こう呼ばれます。おうし座のアルデバランがそうです。
主系列星には「青色巨星」もあります。「シリウスは青白く見えますよね。これは
表面の温度が1万度と高いからです」と縣さんは話しました。多くのエネルギーを
放出する重い星ほど表面温度が高くなって青白く明るく輝き、軽いものほど少ない
エネルギーしか出さないので表面温度が低くなり、赤っぽくなります。ちなみに中間
くらいに位置する太陽は6千度で、黄色に見えます。
また、燃料をたくさん持つ重い星は、たくさんのエネルギーを放出するため燃料の
消費も多く、短い時間で水素を使い果たしてしまいます。縣さんは「軽いと燃費が
いいので1千億年ほども長生きしますが、重いと数千万年ほどで寿命を終えます」
と説明します。
赤色巨星はやがて外側のガスが重力を離れ、星の中心部からエネルギーを受けて
光る「惑星状星雲」となります。この名は、小型望遠鏡で観測していたときに惑星
のような円盤状に見えた名残で、惑星とは何の関係もありません。中心部は高温の
芯が残り、「白色わい星」となります。
□ □
また、太陽より8倍以上重い星は、オリオン座のベテルギウスのような「赤色超
巨星」になります。赤色超巨星は最期、中心にできたケイ素や鉄などの重い元素が
どんどん崩壊して、巨体を支えきれなくなって大爆発します。この「超新星爆発」
から届いたニュートリノを捕まえた功績で、小柴昌俊さんは2002年、ノーベル
物理学賞を受賞しました。
こうして、重い星は華々しく一生を終えます。その後は、光すら脱出できない
ブラックホールになったり、中心部に密度が高い中性子のみが集まった中性子星に
なったりします。同時に宇宙空間にガスやちりを放出して、またそれが集まり原始
星ができるという輪廻転生を繰り返します。「このように星は重さによって、どん
な明るさで輝き、どんな最期を迎えるか決まるのです」(小川詩織)
■これから
こういった星の形成は20世紀の間にだいたいわかってきました。一方、周囲に
ある惑星のでき方や、超新星爆発の詳しいメカニズムなど解明されていないことも
たくさんあります。一見、無関係に見える宇宙を探ることで、私たち生命の誕生の
謎を解くことにつながるかもしれません。
★最近、天文講話の依頼が少なく(無くなり)ました。
星の誕生から最期まで(星の一生)は定番のネタです。
・ブラックホールについては、昨年直接撮影されました。
・赤色超巨星のオリオン座ベテルギウスの超新星爆発問題等
・星仲間Iさんのベテルギウスの光度変化等
話のネタはたくさんあります。





























