本日6月22日、夏至、快晴です。(筆者は関東地方在住)。晴れの夏至を経験するのは珍しい、昨年の夏至6月23日は雨でした。
最新作「氷の接吻」を紹介しています。
前回前々回では妻明子とコタロウ少年を車ごと谷底に落とした「和久井峠の逆さ落とし」を紹介しました。その続きの「南千本駅ホーム」です。
>二人は明子のメール予告とおりに駅ホームに現れる。以下は原文で<
人影の途絶えたただだだっ広いだけの空疎な地下鉄ホーム。
煩いアナウンスはもう聞こえない。発進した下り電車は地下鉄路を静かに遠ざかる。その走行音も徐々に減衰し、レール音はいつの間にか聞こえなくなった。ホームは無音になったのだ
無音のホームの照明が暗くなった。陰気な空間が地下鉄ホームに出現した。
「ねえ何かおかしいわね、急に静かになってしまって。そのうえ暗いわ、気味が悪い」
「俺にもへんな感じがしている。無人の状態は前兆かもしれない。サキ、時刻を教えてくれ」
「ホームの時計がいまゼロ分に移動したわ、きっちり午後の一時」
明子が知らせた約束の時間だ。その時間にあわせて不気味な様に変様した駅ホーム。イクオとサキは周囲をうかがう。もう一人がホームに居残った。尾行中の山本刑事である。
尾行者の本能として。とっさにベンチ下に潜り込みその姿を隠した。イクオ達は山本に気づかなかった。
イクオは語る。
「いまが指定の時間だ。何かが起こるぞ、それは明子コタロウの降臨に違いない」
「コタロウは義理がたい、約束通りにきっと現れるのよ」とサキ。
「二人の姿を見守るのは我々だけ。誰もいなくなったホームだから発見もたやすい。彼らはここから楽園に向かうはずだから、追跡にも好都合だ」
「サキ、お前にはこの沈黙が聞こえているか。空間がさらに無口になった、いまこそ死者が登場するぞ」
「私たち以外一人の姿も見えない。乗客全てを電車が吸い取って、下りた客は全員がはき出された。小うるさいあの案内員すら消えた。なんだか怖い」
サキは弱気になった。
「この薄気味い無人ホームが永く続くわけがない。すぐに人が戻ってくるさ。押し込むなのアナウンスが煩い、雑音の空間にもどるさ。
しかしそれまでの数秒が約束の時間なのだ。この無人空間に明子と少年が現れるのだ。
ホームをぐるりと見渡し、彼らを発見しなければならない。私がホームを右から、そしてサキ、お前は左から見回してくれ。
何かを見つけたら、静かに声を上げてくれ。大声を上げるのでないぞ、静かに合図を入れるのだ」
「分かったわよ、私って地声は静かだから安心して」
用心深く少しずつ、決して見逃してはならない。だからゆっくりとしかし機敏に見渡すのだ。
サキとイクオはホームを見回し始めた。するとある角度でイクオの目が止まった。怪しい影を見たのである。左手斜め前方、距離にして二十メートルほど離れている地点、そこは下りホーム先端となる箇所なのだが、その先端の角にうっすらと、今にも消え入る人影が二人、目に入ったのだ。
イクオがひそひそと、とても小さな声で注意を入れた。
「サキ、私が聞こえるか」
「聞こえるわ。ホームには他に音がないから、もっと小さな声でも聞こえるわ」
「見えたぞ」イクオは一段と声を落とした。
「うっすらと影が、女の影、そして男の影だ。ホームの先端だ」
イクオが見つけた空間に浮かぶ陰、それは灰色の浮遊する女の姿であり、影の形状としてはたたずむ和服姿である。
真水から泡が湧き出るように、その二人の影も空間からにじみ出たに違いない。
ホームはすっかり薄暗くなっているので、影が灰色の暗い背景と入り交じり、輪郭は溶け入るようだ。背景は灰色の霞みにうっすらと女の、そして男の立ち姿が認められるのだ。
「ホームの先端で見えたのね。私は目線をゆっくりと回していく」
サキは目線をぶらさず、慎重に首を回していく。そして弱い声で
「見つけた」
小さな歓声だった。小さくも心が弾む明るい響き、サキらしい声が聞こえた。
イクオは和服の女を明子とみとめた。サキはその横の男にコタロウの外観を見た。二人影はたがいに支えあい、寄り添っていた。
その姿はぼんやりとした様は中空に浮かぶまぼろしとも見えた。
明子が前方に視線を落としているのは、考え悩みにふけるのか、灰色の影でこそあるが、そのうなじの白さは匂うほどの色気が覗える。
イクオは叫んだ。
「私がなんであのうなじの細さ白さを忘れられようか、あれは絶対に明子だ。明子が約束の時間に違わず、ホームに現れたのだ」
「私にも明子さんの影姿が見える。生きていた時よりもすらりとしている。今にも歩き出しそう。あのすらり姿がうらやましいわ」
「何言ってるのだ、あれは人ではないのだぞ。霊なのだ。大体霊になればほっそりはするさ。己の肉付きを霊と比べてもどうにもならないぞ」
「もう一人の姿はもっとぼんやりしているけれど、ほっそりとした姿、そして白い、真っ白な詰め襟服を着ている。コタロウだわ」
しかし影はあまりにも薄くかすみ、今にも地下鉄路の暗がりに消え入りそうだ。もう数秒も経過すれば、二人の影は消滅するだろう。
「二人はまだ見えている、消えていくまでの今がチャンスよ。走って、明子さんのすぐそばにいくのよ」
サキがイクオに指示した。
「走りながらも呼びかけるのよ。「アキコー」って。そして彼女のあの手、下向きに下ろしているあの左手を取り、「この世にいてくれ」と乞い願うのよ。そうしてこそあの世行きを引き留められる。
今しかない、さあ走って」
しかしイクオはサキに答えず、走らず、ただ黙って影を見ていた。鼓動が早くなったのか、息も荒らぶっていた。
イクオ、走るのだ。妻の楽園行きを止めるのだ。イクオは生唾をごくりと呑んだ。第一歩を踏み出した。しかしなぜか足が動かない。
(下に続く)
最新作「氷の接吻」を紹介しています。
前回前々回では妻明子とコタロウ少年を車ごと谷底に落とした「和久井峠の逆さ落とし」を紹介しました。その続きの「南千本駅ホーム」です。
>二人は明子のメール予告とおりに駅ホームに現れる。以下は原文で<
人影の途絶えたただだだっ広いだけの空疎な地下鉄ホーム。
煩いアナウンスはもう聞こえない。発進した下り電車は地下鉄路を静かに遠ざかる。その走行音も徐々に減衰し、レール音はいつの間にか聞こえなくなった。ホームは無音になったのだ
無音のホームの照明が暗くなった。陰気な空間が地下鉄ホームに出現した。
「ねえ何かおかしいわね、急に静かになってしまって。そのうえ暗いわ、気味が悪い」
「俺にもへんな感じがしている。無人の状態は前兆かもしれない。サキ、時刻を教えてくれ」
「ホームの時計がいまゼロ分に移動したわ、きっちり午後の一時」
明子が知らせた約束の時間だ。その時間にあわせて不気味な様に変様した駅ホーム。イクオとサキは周囲をうかがう。もう一人がホームに居残った。尾行中の山本刑事である。
尾行者の本能として。とっさにベンチ下に潜り込みその姿を隠した。イクオ達は山本に気づかなかった。
イクオは語る。
「いまが指定の時間だ。何かが起こるぞ、それは明子コタロウの降臨に違いない」
「コタロウは義理がたい、約束通りにきっと現れるのよ」とサキ。
「二人の姿を見守るのは我々だけ。誰もいなくなったホームだから発見もたやすい。彼らはここから楽園に向かうはずだから、追跡にも好都合だ」
「サキ、お前にはこの沈黙が聞こえているか。空間がさらに無口になった、いまこそ死者が登場するぞ」
「私たち以外一人の姿も見えない。乗客全てを電車が吸い取って、下りた客は全員がはき出された。小うるさいあの案内員すら消えた。なんだか怖い」
サキは弱気になった。
「この薄気味い無人ホームが永く続くわけがない。すぐに人が戻ってくるさ。押し込むなのアナウンスが煩い、雑音の空間にもどるさ。
しかしそれまでの数秒が約束の時間なのだ。この無人空間に明子と少年が現れるのだ。
ホームをぐるりと見渡し、彼らを発見しなければならない。私がホームを右から、そしてサキ、お前は左から見回してくれ。
何かを見つけたら、静かに声を上げてくれ。大声を上げるのでないぞ、静かに合図を入れるのだ」
「分かったわよ、私って地声は静かだから安心して」
用心深く少しずつ、決して見逃してはならない。だからゆっくりとしかし機敏に見渡すのだ。
サキとイクオはホームを見回し始めた。するとある角度でイクオの目が止まった。怪しい影を見たのである。左手斜め前方、距離にして二十メートルほど離れている地点、そこは下りホーム先端となる箇所なのだが、その先端の角にうっすらと、今にも消え入る人影が二人、目に入ったのだ。
イクオがひそひそと、とても小さな声で注意を入れた。
「サキ、私が聞こえるか」
「聞こえるわ。ホームには他に音がないから、もっと小さな声でも聞こえるわ」
「見えたぞ」イクオは一段と声を落とした。
「うっすらと影が、女の影、そして男の影だ。ホームの先端だ」
イクオが見つけた空間に浮かぶ陰、それは灰色の浮遊する女の姿であり、影の形状としてはたたずむ和服姿である。
真水から泡が湧き出るように、その二人の影も空間からにじみ出たに違いない。
ホームはすっかり薄暗くなっているので、影が灰色の暗い背景と入り交じり、輪郭は溶け入るようだ。背景は灰色の霞みにうっすらと女の、そして男の立ち姿が認められるのだ。
「ホームの先端で見えたのね。私は目線をゆっくりと回していく」
サキは目線をぶらさず、慎重に首を回していく。そして弱い声で
「見つけた」
小さな歓声だった。小さくも心が弾む明るい響き、サキらしい声が聞こえた。
イクオは和服の女を明子とみとめた。サキはその横の男にコタロウの外観を見た。二人影はたがいに支えあい、寄り添っていた。
その姿はぼんやりとした様は中空に浮かぶまぼろしとも見えた。
明子が前方に視線を落としているのは、考え悩みにふけるのか、灰色の影でこそあるが、そのうなじの白さは匂うほどの色気が覗える。
イクオは叫んだ。
「私がなんであのうなじの細さ白さを忘れられようか、あれは絶対に明子だ。明子が約束の時間に違わず、ホームに現れたのだ」
「私にも明子さんの影姿が見える。生きていた時よりもすらりとしている。今にも歩き出しそう。あのすらり姿がうらやましいわ」
「何言ってるのだ、あれは人ではないのだぞ。霊なのだ。大体霊になればほっそりはするさ。己の肉付きを霊と比べてもどうにもならないぞ」
「もう一人の姿はもっとぼんやりしているけれど、ほっそりとした姿、そして白い、真っ白な詰め襟服を着ている。コタロウだわ」
しかし影はあまりにも薄くかすみ、今にも地下鉄路の暗がりに消え入りそうだ。もう数秒も経過すれば、二人の影は消滅するだろう。
「二人はまだ見えている、消えていくまでの今がチャンスよ。走って、明子さんのすぐそばにいくのよ」
サキがイクオに指示した。
「走りながらも呼びかけるのよ。「アキコー」って。そして彼女のあの手、下向きに下ろしているあの左手を取り、「この世にいてくれ」と乞い願うのよ。そうしてこそあの世行きを引き留められる。
今しかない、さあ走って」
しかしイクオはサキに答えず、走らず、ただ黙って影を見ていた。鼓動が早くなったのか、息も荒らぶっていた。
イクオ、走るのだ。妻の楽園行きを止めるのだ。イクオは生唾をごくりと呑んだ。第一歩を踏み出した。しかしなぜか足が動かない。
(下に続く)














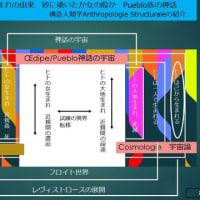













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます