
前回の写真をそのまま再び掲載いたしました。古村第二水雷戦隊司令官と原矢矧艦長です。
丹治様からのコメントにもございますが、古村啓蔵司令官は第二水雷戦隊司令官着任の前は戦艦武蔵艦長でもございました。
武蔵艦長時代は髭を蓄えた艦長でした。以前もお話いたしましたが、渾名は「ゴリラ」でございました。
久しく、この話題から遠ざかっておりました。ほぼ一か月が経ちました。
本来「くだまき」は笑いを意識いたしました「語り」としておりました。が、この戦艦大和と祖父を語るに当たりまして、これは当然な事なのですがどうしても「人の死」と言うものに直面せざるを得ません。一話の中で「一体何人の人がこの世から去っていったのだろう」とふと考えてしまった酔漢です。
「一度頭をリフレッシュする必要があるのではないか」そう考えました。
戦争を語るわけです。今更ながら「重いテーマを選択したものだ」と自責の念に駆られました。
そんなとき、父のアルバムを開いたわけでございます。
あの「坊の岬沖海戦」からご生還された方々、そして父を含めたご遺族の方々。皆様それぞれの思いを背負っての戦後を生きた人達でした。徳之島での慰霊祭の写真は全体像を含めまして今後公開いたします。まだ幼い顔も見られます。酔漢より明らかに若い彼女たちにはどのように映った慰霊祭だったのでしょうか。
私も昭和53年に慰霊祭に参加しておりますが、ようやく「あの人が清水芳人さんで大和副砲長だった人だ」と知った年頃でしたので、「おじいいちゃん達がいっぱいいるなぁ」だったのだと思います。
ですが、このおじいちゃん達がどのような人生を送り、そして生前に「僕らに何かを伝えたかった」。これは事実なのです。
「その現場にいて、その記憶が整理され、そして表現が出来る」
これは、その時の集合写真を見ましても(酔漢も写っております)自身の仕事ではないか。
再びこう考えるに至りました。
中村ハルコさんの死の報に接し、一度は止めかけました。が、上記の思いが再び強くなりました酔漢です。
「このまま中途半端ではいけない」これは思いました。しかし、語る事がプレッシャーとなっていたことは事実です。
大和は傾斜が収まらず。次回は「総員上甲板」のジャッジの経緯を語らなければなりません。これは相当語られておりますし、「今更自分が何も」とも思いかけました。
ですが、ですが、やはり酔漢自身の目で確かめた事は整理し公開するのが筋であろうと再び意を決して、今日、今、キーボードに向かっております。
前置きが長くなりました。
矢矧その後です。
「黄色い煙!火薬庫火災!火薬庫火災!」
一番火薬庫が火災を起こしました。
矢矧艦橋上防空指揮所にいる原艦長です。
「危ない!応急班員退去!離れるんだ!」
壊れた伝声管にありったけの声で叫びます。
「危ない!」と思った瞬間発令所から八田中尉(矢矧発令所長 八田謙二中尉)が、
「艦長!火薬庫危険、注水します。」
と報告して火薬庫の注水弁を大急ぎで全開注水せしめ、辛じて自爆を未然に防止し得たが、発令所長八田中尉以下十五名は、退去に遅れて、艦と運命を共にした。
(原為一 矢矧艦長手記より抜粋)
この八田中尉の事は多くの書に書かれております。再び原手記を見てみます。
四月六日艦長訓示、作戦命令発令時の事です。
原艦長はこのときこう話されておられます。
殊更にに軽率に死を求ることなく、生命の存する限り、強靭なる闘魂を奮い起こし、精根の限りを尽くして敵を撃砕することこそ、皇国に忠誠なる所以である。と私の信念を述べた。
(中略)純心な八田中尉が直ぐ手を挙げて、私に質問した。(中略)海軍軍人として貴重な艦を、死をもって守る強烈なる責任感を堅持することは当然だが、限られた主従間の小乗的武士道の封建時代と異なり、現代のような国家国防機構においては、我が国我が国民の存する限り、これと運命を共にすることこそ、我が武士道の真髄であって、逆境にたって闘志を失い自らを卑下し、過早にみずから死を求めたり、自責の念にのみとらわれて高所大局にたって将来を考えず、無用無益な死によって、大切な人的資源を失うことは、むしろ敵の欲するところであり、我が海軍にとっては甚大な損失であることなど、つぶさに所懐を披歴して諭すと、八田中尉は晴々した面持ちで「よく解りました」と云って立ち去った。
(原為一 矢矧艦長 証言手記より抜粋)
上記記載は二度目ではありますが、八田中尉は若くして亡くなられておられます。優秀な方であったと皆様(ご生還された方々)は申しておられます。矢矧においては丁度大和の臼淵大尉のような存在ではなかったかと思います。
「八田中尉以下六名、暗黒。主砲発令所!」
「脱出は・・・脱出は可能なのか!」
つい今しがた、艦の自爆を防止する為、発令所へ戻った八田中尉です。
応急班員からの伝令です。
「発令所内、満水!脱出は不可能です」
原艦長は昨日、八田中尉と話した事を思い出しております。
火薬庫からの黄色い煙は消えておりました。
雷撃機は魚雷庫の腹を開けたまま、艦の上空を縦横無尽に飛び回っていた。艦は傾斜が激しくなり、ついに左舷の上甲板まで海水につかってしまった。いつの間にか押し流された多くの部下が左舷近くの海中で泳いでいる。
(矢矧機銃群指揮官 安達耕一 証言より抜粋 軍艦矢矧海戦記より)

この直前の顛末は前々回に語っております。この写真も(しつこいなどと思わんで下さい)再び登場させます。
重油まみれで奮戦中の矢矧です。
あるホームページを紹介いたしましたが、そのHPについての史観を述べさせていただきます。酔漢の私見です。
海上はうねりにうねっていた。なにを血迷ったか古村司令官らは空襲の最中内火艇で磯風に乗り移ろうとたくらんだ。(兵にはそう見えた)。誰もが逡巡した。
特攻艦隊大和 戦後60年目の真実。 軽巡矢矧 第二水雷戦隊の通信兵は見た。
上記HPよりの抜粋です。
これには酔漢は異を唱えます。
古村司令官、原艦長とも逃亡をたくらんだわけではないというのが酔漢的私見です。
旗艦の移乗は作戦中多々あります。
航行不能になった矢矧からは作戦の目的である「沖縄突入」が不可能と判断された場合、作戦遂行の為には旗艦を変更し、あくまでも作戦の遂行を行うことが指揮官としての正しいジャッジです。過去の海戦を見ても(この事例は割愛いたしますが)頻繁に行われている行為です。その際、艦長と司令官が共に行動することもあり、副長が艦長の役目を果たさなければなりません。
「たとえ矢矧を失おうとも、わが水雷戦隊は大和と共にあくまで沖縄突入を敢行すべし」
古村司令官はこう話しておられます。あくまで初心を貫徹しようとしたのです。
短艇をおろそうとその指揮をとりましたのが、池田武邦中尉でした。
その短艇は機銃でこなごなになります。これは祖父・海軍そして大和 奮戦スレド徒死スルナカレ 矢矧 三
で語りました。
またどうHPにはこうも記述されておられます。
その時、原艦長は内野副長を叱りつけ、非常食の持ち出しを命令した。沈もうとしているのに非常食の持ち出し命令は正常でないと感じた。停電し真っ暗な艦内はいくら内部事情に精通しても歩けるものではない。
副長は艦内巡検が日課とされております。艦内どこに何があるのか一番詳しい人物です。暗い艦内でもおそらく歩けただろうと推察いたします。また主計長も同行しておりますが、食糧庫内の管理は主計長の仕事です。これもあり得る艦長の判断だと考えます。
非常食持ち出しは、艦を移乗する際または、艦が沈没するという時間的に確実な段階で乗員を出来るだけ多く救出しようとした原艦長の判断なのです。木材搭載の件も語りましたが、原艦長は作戦遂行と乗員救出を同時にシュミレーションしていたのです。
上記HPの見方に対しては、酔漢自身疑問を持たずにはいられません。
しかしながら、同HPの数値的分析には頭が下がります。今後大和他この作戦を整理検証するには大変必要な事実を公開しております。東海大学鳥飼先生のHPと共に、素晴らしい分析結果であることは否定いたしておりません。ここに補足いたします。
矢矧に近づく「磯風」です。(写真右上の艦)磯風前田艦長。敵機の攻撃を掻い潜りながら矢矧に接近しようと試みます。
ヨークタウンのヘルダイバー。パイロットは「ハリー・ウオーリー大尉」磯風からの対空砲により戦死されておられます。磯風の抵抗が激しかったことを物語る事実です。が、磯風は撃沈されます。
そして一四○五。矢矧はついに力尽きます。
原艦長は総員退艦を命じます。
「おいあのクルーザーの写真を撮っておけ」
「奴の最期ですからね」
「小っちゃい奴(磯風)が近づいていきますぜ」
ブリュワー少尉はシャッターを切りました。
「ついでだ、機銃をお見舞いしてやろう」
ヘルダイバーが海上へ降ろそうと準備している矢矧の短艇を破壊しました。
嗚呼、もう終わりか!
不肖未熟の身を持って矢矧艦長となり、忠誠なる乗員一千名と共に、勇戦敢闘の甲斐もなく、ついに敗れた、例えに不徳の致すところ誠に申し訳ない。艦長の心はまさに断腸の思いであった。
最上甲板の一角には、いつの間にか古村少将と私とただ二人が取り残されていた。海面がグッツと盛り上がってきたかと思うと、もう靴が水に浸ってきた。
「さあ行こう。」
「行きましょう。」
靴だけ脱いで二人並んで海中に飛込んだ。残るは白濁々たる渦流のみ。水深五百米、九州南方会場、坊の岬の二百六十度九十浬、時に昭和二十年四月七日午后二時六分。空には爆音なお轟々。
(原為一 矢矧艦長 手記より抜粋)
フネが沈んだというより、海水がドーッと押し寄せてきて、飲み込まれたという感じでした
(池田武邦 矢矧測的長 証言手記より抜粋)
矢矧沈没地点
鹿児島県坊津の南南西九○カイリの東シナ海
北緯三○度四八分
東経一二八度八分の東シナ海
戦死 副長内野信一大佐以下、四四六名
戦傷 一三三名
確認戦果 撃墜一九機
主砲 二一八発
高角砲 三六五発
機銃 三万二九八○発
上記消費弾数。
わが矢矧はその船体に、魚雷七本以上、大型爆弾二十発以上を射込まれ、大小の至近弾、およそ数千発をあび、骨も肉も、皮膚までも完全にボロボロにひきちぎられながら、なお平然と、すわったままの巨人のごとく、しずかに沈没し、大往生をとげつつあった。(中略)
思うに、わが矢矧の犠牲的精神によって、大和以下友軍の損害を、いくぶんたりとも軽くしえたことは、私の最大の念願であり、またよろこびであった。
戦後、アメリカ海軍のカリング大佐は、
「大和隊の被害が、比較的軽少であったことは、矢矧の犠牲的行為に負うところが大であった」と激賞している。
矢矧の戦死者数四四六名、もって冥すべきであろう。
(原為一 矢矧艦長 手記より抜粋)
「水上部隊としてこのような任務を付与されるとは全く想定していない。必ず沈む覚悟で奉公しなければならない。これから私が言うことを急速に準備せよ」
当時、大坪寅次郎中尉は甲板士官。今でもこのときの原為一艦長の言葉を忘れないでいると聞きました。
「乗員を出来るだけ助けるのだ」
「矢矧の乗員が多数助かったのは搭載した角材のおかげなのです」
平成十八年洋上慰霊祭(酔漢父塩竈実家へは案内が届いておりました。父の健康上の理由、そして私の仕事の都合が合わず欠席の返事を投函しました)での事です。
原艦長、古村司令官は作戦を諦めることなどなく奮戦し、そして多くの人命を生かす作戦を立案していたのです。
元矢矧測的長、原艦長をして「優秀なるケブガン」と言わしめた「池田武邦中尉」です。
長崎はハウステンボスのシンボル「ドムトルーン」を眺めております。
建築家として世界的な評価を得ております。
祖父と同じあの日におられた方とは知りませんでした。
池田武邦元矢矧中尉と建築家池田武邦先生と同一人物として一致しましたのはこの夏のことだった酔漢です。
「僕らの世代には、いくら言っても伝わらないというあきらめがある。明日死ぬかもしれない、ああ今日は生きていた。そういう毎日を体験したことのない人に、実感を伝えることは無理だ」
「敗戦後、何千年も続いてきた伝統文化が紙くずのように捨てられた。現代の日本人は、日本人の顔をしていても、日本人ではない」
あるインタビューでの池田先生の言葉です。
重いものを感じます。
後悔しました。無理をしても平成十八年の洋上慰霊祭に参加すべきだったと。
矢矧の戦後はまだ終わってなかったのでした。
丹治様からのコメントにもございますが、古村啓蔵司令官は第二水雷戦隊司令官着任の前は戦艦武蔵艦長でもございました。
武蔵艦長時代は髭を蓄えた艦長でした。以前もお話いたしましたが、渾名は「ゴリラ」でございました。
久しく、この話題から遠ざかっておりました。ほぼ一か月が経ちました。
本来「くだまき」は笑いを意識いたしました「語り」としておりました。が、この戦艦大和と祖父を語るに当たりまして、これは当然な事なのですがどうしても「人の死」と言うものに直面せざるを得ません。一話の中で「一体何人の人がこの世から去っていったのだろう」とふと考えてしまった酔漢です。
「一度頭をリフレッシュする必要があるのではないか」そう考えました。
戦争を語るわけです。今更ながら「重いテーマを選択したものだ」と自責の念に駆られました。
そんなとき、父のアルバムを開いたわけでございます。
あの「坊の岬沖海戦」からご生還された方々、そして父を含めたご遺族の方々。皆様それぞれの思いを背負っての戦後を生きた人達でした。徳之島での慰霊祭の写真は全体像を含めまして今後公開いたします。まだ幼い顔も見られます。酔漢より明らかに若い彼女たちにはどのように映った慰霊祭だったのでしょうか。
私も昭和53年に慰霊祭に参加しておりますが、ようやく「あの人が清水芳人さんで大和副砲長だった人だ」と知った年頃でしたので、「おじいいちゃん達がいっぱいいるなぁ」だったのだと思います。
ですが、このおじいちゃん達がどのような人生を送り、そして生前に「僕らに何かを伝えたかった」。これは事実なのです。
「その現場にいて、その記憶が整理され、そして表現が出来る」
これは、その時の集合写真を見ましても(酔漢も写っております)自身の仕事ではないか。
再びこう考えるに至りました。
中村ハルコさんの死の報に接し、一度は止めかけました。が、上記の思いが再び強くなりました酔漢です。
「このまま中途半端ではいけない」これは思いました。しかし、語る事がプレッシャーとなっていたことは事実です。
大和は傾斜が収まらず。次回は「総員上甲板」のジャッジの経緯を語らなければなりません。これは相当語られておりますし、「今更自分が何も」とも思いかけました。
ですが、ですが、やはり酔漢自身の目で確かめた事は整理し公開するのが筋であろうと再び意を決して、今日、今、キーボードに向かっております。
前置きが長くなりました。
矢矧その後です。
「黄色い煙!火薬庫火災!火薬庫火災!」
一番火薬庫が火災を起こしました。
矢矧艦橋上防空指揮所にいる原艦長です。
「危ない!応急班員退去!離れるんだ!」
壊れた伝声管にありったけの声で叫びます。
「危ない!」と思った瞬間発令所から八田中尉(矢矧発令所長 八田謙二中尉)が、
「艦長!火薬庫危険、注水します。」
と報告して火薬庫の注水弁を大急ぎで全開注水せしめ、辛じて自爆を未然に防止し得たが、発令所長八田中尉以下十五名は、退去に遅れて、艦と運命を共にした。
(原為一 矢矧艦長手記より抜粋)
この八田中尉の事は多くの書に書かれております。再び原手記を見てみます。
四月六日艦長訓示、作戦命令発令時の事です。
原艦長はこのときこう話されておられます。
殊更にに軽率に死を求ることなく、生命の存する限り、強靭なる闘魂を奮い起こし、精根の限りを尽くして敵を撃砕することこそ、皇国に忠誠なる所以である。と私の信念を述べた。
(中略)純心な八田中尉が直ぐ手を挙げて、私に質問した。(中略)海軍軍人として貴重な艦を、死をもって守る強烈なる責任感を堅持することは当然だが、限られた主従間の小乗的武士道の封建時代と異なり、現代のような国家国防機構においては、我が国我が国民の存する限り、これと運命を共にすることこそ、我が武士道の真髄であって、逆境にたって闘志を失い自らを卑下し、過早にみずから死を求めたり、自責の念にのみとらわれて高所大局にたって将来を考えず、無用無益な死によって、大切な人的資源を失うことは、むしろ敵の欲するところであり、我が海軍にとっては甚大な損失であることなど、つぶさに所懐を披歴して諭すと、八田中尉は晴々した面持ちで「よく解りました」と云って立ち去った。
(原為一 矢矧艦長 証言手記より抜粋)
上記記載は二度目ではありますが、八田中尉は若くして亡くなられておられます。優秀な方であったと皆様(ご生還された方々)は申しておられます。矢矧においては丁度大和の臼淵大尉のような存在ではなかったかと思います。
「八田中尉以下六名、暗黒。主砲発令所!」
「脱出は・・・脱出は可能なのか!」
つい今しがた、艦の自爆を防止する為、発令所へ戻った八田中尉です。
応急班員からの伝令です。
「発令所内、満水!脱出は不可能です」
原艦長は昨日、八田中尉と話した事を思い出しております。
火薬庫からの黄色い煙は消えておりました。
雷撃機は魚雷庫の腹を開けたまま、艦の上空を縦横無尽に飛び回っていた。艦は傾斜が激しくなり、ついに左舷の上甲板まで海水につかってしまった。いつの間にか押し流された多くの部下が左舷近くの海中で泳いでいる。
(矢矧機銃群指揮官 安達耕一 証言より抜粋 軍艦矢矧海戦記より)

この直前の顛末は前々回に語っております。この写真も(しつこいなどと思わんで下さい)再び登場させます。
重油まみれで奮戦中の矢矧です。
あるホームページを紹介いたしましたが、そのHPについての史観を述べさせていただきます。酔漢の私見です。
海上はうねりにうねっていた。なにを血迷ったか古村司令官らは空襲の最中内火艇で磯風に乗り移ろうとたくらんだ。(兵にはそう見えた)。誰もが逡巡した。
特攻艦隊大和 戦後60年目の真実。 軽巡矢矧 第二水雷戦隊の通信兵は見た。
上記HPよりの抜粋です。
これには酔漢は異を唱えます。
古村司令官、原艦長とも逃亡をたくらんだわけではないというのが酔漢的私見です。
旗艦の移乗は作戦中多々あります。
航行不能になった矢矧からは作戦の目的である「沖縄突入」が不可能と判断された場合、作戦遂行の為には旗艦を変更し、あくまでも作戦の遂行を行うことが指揮官としての正しいジャッジです。過去の海戦を見ても(この事例は割愛いたしますが)頻繁に行われている行為です。その際、艦長と司令官が共に行動することもあり、副長が艦長の役目を果たさなければなりません。
「たとえ矢矧を失おうとも、わが水雷戦隊は大和と共にあくまで沖縄突入を敢行すべし」
古村司令官はこう話しておられます。あくまで初心を貫徹しようとしたのです。
短艇をおろそうとその指揮をとりましたのが、池田武邦中尉でした。
その短艇は機銃でこなごなになります。これは祖父・海軍そして大和 奮戦スレド徒死スルナカレ 矢矧 三
で語りました。
またどうHPにはこうも記述されておられます。
その時、原艦長は内野副長を叱りつけ、非常食の持ち出しを命令した。沈もうとしているのに非常食の持ち出し命令は正常でないと感じた。停電し真っ暗な艦内はいくら内部事情に精通しても歩けるものではない。
副長は艦内巡検が日課とされております。艦内どこに何があるのか一番詳しい人物です。暗い艦内でもおそらく歩けただろうと推察いたします。また主計長も同行しておりますが、食糧庫内の管理は主計長の仕事です。これもあり得る艦長の判断だと考えます。
非常食持ち出しは、艦を移乗する際または、艦が沈没するという時間的に確実な段階で乗員を出来るだけ多く救出しようとした原艦長の判断なのです。木材搭載の件も語りましたが、原艦長は作戦遂行と乗員救出を同時にシュミレーションしていたのです。
上記HPの見方に対しては、酔漢自身疑問を持たずにはいられません。
しかしながら、同HPの数値的分析には頭が下がります。今後大和他この作戦を整理検証するには大変必要な事実を公開しております。東海大学鳥飼先生のHPと共に、素晴らしい分析結果であることは否定いたしておりません。ここに補足いたします。
矢矧に近づく「磯風」です。(写真右上の艦)磯風前田艦長。敵機の攻撃を掻い潜りながら矢矧に接近しようと試みます。
ヨークタウンのヘルダイバー。パイロットは「ハリー・ウオーリー大尉」磯風からの対空砲により戦死されておられます。磯風の抵抗が激しかったことを物語る事実です。が、磯風は撃沈されます。
そして一四○五。矢矧はついに力尽きます。
原艦長は総員退艦を命じます。
「おいあのクルーザーの写真を撮っておけ」
「奴の最期ですからね」
「小っちゃい奴(磯風)が近づいていきますぜ」
ブリュワー少尉はシャッターを切りました。
「ついでだ、機銃をお見舞いしてやろう」
ヘルダイバーが海上へ降ろそうと準備している矢矧の短艇を破壊しました。
嗚呼、もう終わりか!
不肖未熟の身を持って矢矧艦長となり、忠誠なる乗員一千名と共に、勇戦敢闘の甲斐もなく、ついに敗れた、例えに不徳の致すところ誠に申し訳ない。艦長の心はまさに断腸の思いであった。
最上甲板の一角には、いつの間にか古村少将と私とただ二人が取り残されていた。海面がグッツと盛り上がってきたかと思うと、もう靴が水に浸ってきた。
「さあ行こう。」
「行きましょう。」
靴だけ脱いで二人並んで海中に飛込んだ。残るは白濁々たる渦流のみ。水深五百米、九州南方会場、坊の岬の二百六十度九十浬、時に昭和二十年四月七日午后二時六分。空には爆音なお轟々。
(原為一 矢矧艦長 手記より抜粋)
フネが沈んだというより、海水がドーッと押し寄せてきて、飲み込まれたという感じでした
(池田武邦 矢矧測的長 証言手記より抜粋)
矢矧沈没地点
鹿児島県坊津の南南西九○カイリの東シナ海
北緯三○度四八分
東経一二八度八分の東シナ海
戦死 副長内野信一大佐以下、四四六名
戦傷 一三三名
確認戦果 撃墜一九機
主砲 二一八発
高角砲 三六五発
機銃 三万二九八○発
上記消費弾数。
わが矢矧はその船体に、魚雷七本以上、大型爆弾二十発以上を射込まれ、大小の至近弾、およそ数千発をあび、骨も肉も、皮膚までも完全にボロボロにひきちぎられながら、なお平然と、すわったままの巨人のごとく、しずかに沈没し、大往生をとげつつあった。(中略)
思うに、わが矢矧の犠牲的精神によって、大和以下友軍の損害を、いくぶんたりとも軽くしえたことは、私の最大の念願であり、またよろこびであった。
戦後、アメリカ海軍のカリング大佐は、
「大和隊の被害が、比較的軽少であったことは、矢矧の犠牲的行為に負うところが大であった」と激賞している。
矢矧の戦死者数四四六名、もって冥すべきであろう。
(原為一 矢矧艦長 手記より抜粋)
「水上部隊としてこのような任務を付与されるとは全く想定していない。必ず沈む覚悟で奉公しなければならない。これから私が言うことを急速に準備せよ」
当時、大坪寅次郎中尉は甲板士官。今でもこのときの原為一艦長の言葉を忘れないでいると聞きました。
「乗員を出来るだけ助けるのだ」
「矢矧の乗員が多数助かったのは搭載した角材のおかげなのです」
平成十八年洋上慰霊祭(酔漢父塩竈実家へは案内が届いておりました。父の健康上の理由、そして私の仕事の都合が合わず欠席の返事を投函しました)での事です。
原艦長、古村司令官は作戦を諦めることなどなく奮戦し、そして多くの人命を生かす作戦を立案していたのです。
元矢矧測的長、原艦長をして「優秀なるケブガン」と言わしめた「池田武邦中尉」です。
長崎はハウステンボスのシンボル「ドムトルーン」を眺めております。
建築家として世界的な評価を得ております。
祖父と同じあの日におられた方とは知りませんでした。
池田武邦元矢矧中尉と建築家池田武邦先生と同一人物として一致しましたのはこの夏のことだった酔漢です。
「僕らの世代には、いくら言っても伝わらないというあきらめがある。明日死ぬかもしれない、ああ今日は生きていた。そういう毎日を体験したことのない人に、実感を伝えることは無理だ」
「敗戦後、何千年も続いてきた伝統文化が紙くずのように捨てられた。現代の日本人は、日本人の顔をしていても、日本人ではない」
あるインタビューでの池田先生の言葉です。
重いものを感じます。
後悔しました。無理をしても平成十八年の洋上慰霊祭に参加すべきだったと。
矢矧の戦後はまだ終わってなかったのでした。















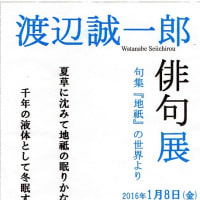

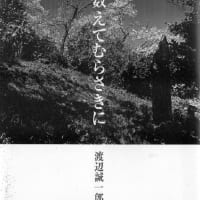








古村さんが沈みかかっている矢矧から脱出しようとしたとすれば、「旗艦変更」が目的のはずです。
古村さんの職務は「水雷戦隊司令官」です。指揮する艦艇は「旗艦」矢矧のみではありません。
たとえ矢矧が沈んでも、部下の駆逐艦が一隻でも残っていれば、
古村さんには司令官としての職務を遂行する義務があります。
ミッドウェーで赤城が被弾した際、
南雲中将と一航艦司令部は旗艦を長良に移しました。
マリアナ沖海戦で大鳳がやられた時、
小澤中将は旗艦を瑞鶴に変更しました。
エンガノ岬沖海戦で瑞鶴がやられた時も、
旗艦を変更しています(移した先の艦は失念)。
また二艦隊がレイテに向う途中、パラワン水道で旗艦愛宕が潜水艦の魚雷攻撃を受けて沈みました。
その際、二艦隊司令長官の栗田中将は旗艦を大和に変更しました。
坊之岬沖海戦で矢矧がやられた時に古村さんが取ろうとした行動を「逃亡」というなら、
これらの例はすべて逃亡ということになってしまいます。
戦闘中に指揮官が旗艦を「見捨てた」となれば、これは「敵前逃亡」ということになります。
よくて「予備役編入の即日召集」。
悪くすれば、軍法会議にかけられて死刑ということすらあり得ます。
ここに例を挙げた南雲中将、小澤中将、栗田中将は、そのような処分を受けていません。
第一次ソロモン海戦の帰途で、加古は米潜の魚雷を受けて沈みます。
艦長の高橋大佐は生還しますが、
処分の対象にはならず、最終的には少将に進んでいます。
古村さんも矢矧艦長の原さんも生還しますが、
やはり処分の対象にはなっていません。
これは海軍当局が二人の取った行動を「逃亡」と認識していなかった
明白な証拠だと思います。
先のコメントを投稿した後で思い出しました。
古川司令官、原艦長は結局、旗艦移乗できず、海上漂流となり、大和爆沈を目撃。沖縄特攻は儚く消える。
更には敵飛行艇まで現れて、彼らが捕虜になるかもしれない状況となったわけですが・・。
古川司令官と原艦長がこの状況で生存し続ける正当性があったんですかね。
危険極まりない戦闘中に減速接舷までやらせて、結局、磯風も敵機にやられて最終的に沈没してしまう。
彼らは責任というものを感じなかったのか疑問です。
逆に、捕虜になって超機密文書を盗られた福留、勝手な理屈で抗命し敵前逃亡した栗田。これらも処分らしい処分は受けていません。というか、ある階級以上は、どんなヘマをしても処分しなかった。これが旧海軍ではないでしょうか?
敵の米海軍との大きな差がこの点にもあります。
さらに繰り返しですが、司令官の旗艦移乗はわかりますが、艦長は責任を取って艦と運命を共にするのが、当時の海軍の倫理的行動ではないでしょうか?
下っ端の兵隊に「逃亡」と思わせるような情けない姿を晒すこと自体が断罪ものと思うのですが。