
「ひーさんの散歩道」
6月24日更新「多賀城の散歩道」でした。
そのときの記事が「伏石/多賀城市市川」です。
多賀城市市川にあります「伏石」の紹介記事でございました。
「くだまき」の前に上記をリンクしてみてください。
酔漢は自転車での散歩(ポタリング・・って言ってたなぁ)が趣味でございましたので、多賀城あたりはくまなく回りました。
「伏石」も知るには知っていたのですが、この石(石碑)がどうして、横になったままなのか、その理由までは知りませんでした。
これは「ひーさんの散歩道」で知ったところなのですが、時宗がからんでいたのですね。
尤も、自身が自転車散歩の頃には理由を説明している「看板」などなかったのですし、「なしてねてんだべ」位にしか思わなかった、歴史音痴ですので。
はたして、上記の記事を拝読しまして・・・
「なんだや!(時宗→総本山→遊行寺→藤沢→自宅より徒歩4分)」と頭の中で連想発想したわけです。
すかさず、ひーさんにコメントしましたところ
「是非、アップを!」
と相成りました、本日の「くだまき」でございます。
すぐさま、遊行寺へとまいりました。
そうそう、遊行寺というのは通称でございまして正式な名称は「藤沢山 無量光院 清浄光寺」と申します。
この開山には複雑な歴史がございまして、酔漢も詳しくは存じておりません。
遊行寺境内の案内版をご紹介いたします。

この案内板の通り、遊行寺が出来ましたのが、1325年とされており、多賀城伏石は1287年となってます。
「遊行寺の方が新しいんだべ」
などと、考えておりますが、その多賀城になぜ時宗の僧侶が大勢訪れていたのか、これは疑問に思いました。
そこで遊行寺境内にあります、ガイドさんに聞いてみました。
見事な答えでした。
一編上人は愛媛県のお生まれ、豪族の息子だったそうです。
(これはしゃねかった!)
ところが、祖父が追われる立場となり陸奥まで逃げたそうで、奥州江刺、そこで絶命。
一編の「踊念仏」は1279年、信濃で初めて行われたとされ、その後、各地を回ります。奥州へ向かったとされるのが1280年(弘安三年)で、陸奥国江刺の祖父の墓前へ向かう途中に「松島へ立ち寄る」との記録があるそうです。
最終的には「平泉へも立ち寄る」とされております。
この間、布教活動にも熱心に取り組んだともあります。
再び、ひーさんの記事を見てみましょう。
そこには「西阿弥陀仏という僧が三十四名でもって碑を建立」とございます。
その名に一編は出てまいりません。
「別働隊がいたのか!」
これは単純に疑問でございます。
ここで、一編の死が1289年。
一編50歳、場所は摂津(現兵庫)。栄養失調との話もあります。
これを考えますと、「伏石にはやはり一編は関わっていない」と言えます。
ここに登場いたします「西阿弥陀仏」という僧ですが、時宗では略して「西阿」(せいあ)と呼ばれていたと、推察します。
記録では「他阿」と呼ばれる僧が、諸国を回っておりますが、これは一編の死後、1290年の頃ですし、北関東中心の布教活動でしたから、奥州へは向かっておりません。
この「西阿弥陀仏他三十余名の僧」は遊行寺にも記録は残されておりませんでした。

一編上人の像です。
「踊念仏」の姿を見たいとは思いますが、果たして、そのような元気はあったのかなぁ、とも思いました。
藤沢は門前町、そして宿場町として発展してまいりました。
江の島、そして遊行寺と、昔の宿場の残りが歴史として多く残されております。
正月三が日は、この遊行寺の坂で箱根駅伝を観戦。そしてその後に遊行寺へ初詣にまいります。
恒例行事としてます。
多賀城と藤沢。
時宗を通じて繋がった細い糸をたぐることはたやすい事ではございませんが、「また故郷と繋がったものもあった」と感じました。
ひーさんばりに頑張った?「くだまき」でした。
久しぶりに歴史を考えました。
「知恵熱が出そう・・・・・」
追伸
ご心配をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
おなかも方はほぼ治っておるとの事。
足は痛みはなく、今はギブスをはめたまま仕事をしてます。
コメントを頂戴しておりますが、後程、お返事致しますね。
暖かいお言葉の数々、ありがとうございました。
6月24日更新「多賀城の散歩道」でした。
そのときの記事が「伏石/多賀城市市川」です。
多賀城市市川にあります「伏石」の紹介記事でございました。
「くだまき」の前に上記をリンクしてみてください。
酔漢は自転車での散歩(ポタリング・・って言ってたなぁ)が趣味でございましたので、多賀城あたりはくまなく回りました。
「伏石」も知るには知っていたのですが、この石(石碑)がどうして、横になったままなのか、その理由までは知りませんでした。
これは「ひーさんの散歩道」で知ったところなのですが、時宗がからんでいたのですね。
尤も、自身が自転車散歩の頃には理由を説明している「看板」などなかったのですし、「なしてねてんだべ」位にしか思わなかった、歴史音痴ですので。
はたして、上記の記事を拝読しまして・・・
「なんだや!(時宗→総本山→遊行寺→藤沢→自宅より徒歩4分)」と頭の中で連想発想したわけです。
すかさず、ひーさんにコメントしましたところ
「是非、アップを!」
と相成りました、本日の「くだまき」でございます。
すぐさま、遊行寺へとまいりました。
そうそう、遊行寺というのは通称でございまして正式な名称は「藤沢山 無量光院 清浄光寺」と申します。
この開山には複雑な歴史がございまして、酔漢も詳しくは存じておりません。
遊行寺境内の案内版をご紹介いたします。

この案内板の通り、遊行寺が出来ましたのが、1325年とされており、多賀城伏石は1287年となってます。
「遊行寺の方が新しいんだべ」
などと、考えておりますが、その多賀城になぜ時宗の僧侶が大勢訪れていたのか、これは疑問に思いました。
そこで遊行寺境内にあります、ガイドさんに聞いてみました。
見事な答えでした。
一編上人は愛媛県のお生まれ、豪族の息子だったそうです。
(これはしゃねかった!)
ところが、祖父が追われる立場となり陸奥まで逃げたそうで、奥州江刺、そこで絶命。
一編の「踊念仏」は1279年、信濃で初めて行われたとされ、その後、各地を回ります。奥州へ向かったとされるのが1280年(弘安三年)で、陸奥国江刺の祖父の墓前へ向かう途中に「松島へ立ち寄る」との記録があるそうです。
最終的には「平泉へも立ち寄る」とされております。
この間、布教活動にも熱心に取り組んだともあります。
再び、ひーさんの記事を見てみましょう。
そこには「西阿弥陀仏という僧が三十四名でもって碑を建立」とございます。
その名に一編は出てまいりません。
「別働隊がいたのか!」
これは単純に疑問でございます。
ここで、一編の死が1289年。
一編50歳、場所は摂津(現兵庫)。栄養失調との話もあります。
これを考えますと、「伏石にはやはり一編は関わっていない」と言えます。
ここに登場いたします「西阿弥陀仏」という僧ですが、時宗では略して「西阿」(せいあ)と呼ばれていたと、推察します。
記録では「他阿」と呼ばれる僧が、諸国を回っておりますが、これは一編の死後、1290年の頃ですし、北関東中心の布教活動でしたから、奥州へは向かっておりません。
この「西阿弥陀仏他三十余名の僧」は遊行寺にも記録は残されておりませんでした。

一編上人の像です。
「踊念仏」の姿を見たいとは思いますが、果たして、そのような元気はあったのかなぁ、とも思いました。
藤沢は門前町、そして宿場町として発展してまいりました。
江の島、そして遊行寺と、昔の宿場の残りが歴史として多く残されております。
正月三が日は、この遊行寺の坂で箱根駅伝を観戦。そしてその後に遊行寺へ初詣にまいります。
恒例行事としてます。
多賀城と藤沢。
時宗を通じて繋がった細い糸をたぐることはたやすい事ではございませんが、「また故郷と繋がったものもあった」と感じました。
ひーさんばりに頑張った?「くだまき」でした。
久しぶりに歴史を考えました。
「知恵熱が出そう・・・・・」
追伸
ご心配をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
おなかも方はほぼ治っておるとの事。
足は痛みはなく、今はギブスをはめたまま仕事をしてます。
コメントを頂戴しておりますが、後程、お返事致しますね。
暖かいお言葉の数々、ありがとうございました。















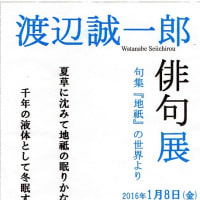

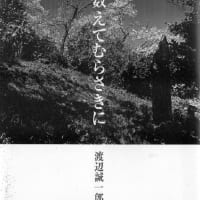








河野氏の紋章は正八角形の中に漢数字の三。
瀬戸内海の大三島神社は河野氏の氏神ですが、
この神社の紋章が正八角形の中に漢数字の三。
北鎌倉にやはり時宗のお寺がありますが(海蔵寺だったでしょうか)、
この寺の紋章が、やはり正八角形に漢数字の三でした。
それにしても時衆(時宗の信者をこう呼ぶそうです)の足跡が
東北地方にも記されているのですね。
明らかに陸奥との関係がわかりましたね。
追記して、酔漢さんの記事へのリンクと掻い摘んで、この話しをまとめてみたいと思います。
丹治さんもお元気のようですね。
大三島は行ったことがございます。しかしその頃は全く興味がありませんでした。
海蔵寺は臨済宗のお寺です。
時宗は、光照寺、光触寺とかがあります。
他にもあるかもしれません。
何せ執権「時宗」から「鎌倉に入るな」と言われておりますので、その影響もあるかもしれませんね。
全国へ散った時衆なんですね。
各地で伝説が残っているようです。
またいつか、遊行寺がらみで紹介したいと思ってます。
御指摘、有難うございます。
光照寺で頂いた御朱印に「一遍上人法難の霊場」とありました。
御住職に御尋ねしたところ、
鎌倉への入府を拒まれたのだとか。
これからは事実関係は確認して投稿するようにしたおと思います。