
戦後1945年9月29日新聞紙上で公開された大和の沖縄突入では,総特攻のさきがけとしてではなく,「沖縄救援の途上」「米機の巨(大爆)弾」を受けて「海上砲台の猛威を果たさず」撃沈された,としている。「沖縄へ最期の逆襲」をする無謀な敵泊地,上陸地点への突入は失敗し,「この世の終わりかと」悲惨な末路を記事にしている。
「戦艦大和」が広く国民の目にさらされ、その存在が明らかとなったのは新聞記事からでございます。
上記はリンク先、下記「東海大学 鳥飼 教授研究室 HP」より抜粋いたしました。
父はその新聞の記憶は全くなく、「大和」の存在を知ったその瞬間ということも記憶しておりませんでした。
鳥飼先生のHPの存在は父が入院する直前に私が父に知らせたのでした。
「東海大学の鳥飼先生の論文(HP)によれば、昭和20年9月29日の新聞で、初めて『軍艦大和』が広く知らされたとあるけれど、親父はどこで知った?」
「さぁなぁ、ただ、どっからともなく耳さぁ入ぇって来た。どっかだ読んだとかは、記憶がねェなや。んだども、なんでも世界一でけぇ戦艦があって、それが沖縄さぁ特攻した。っては聞いた。そいっつぁ親父が乗ってたかどうかしゃねぇ。でも、親父の最期の言葉さぁ思い出したのっしゃ。『今度乗る艦(ふね)さぁぜってい沈まねぇ艦だから安心すろ』って・・・。そいずがあったからっしゃ『親父は大和さぁいたんでねぇべか』って、兄貴が言ったのっしゃ。まだ、公報さぁつかねぇべ。んだって、戦争が終わったのに、まだ帰ってこねぇのも不思議だっちゃ。まず、そうでねぇかって・・」
「海軍省、鎮守府にいたら、早く連絡があったって思う?」
「なぐてもや、後始末で忙しいんでねぇかって、そうおふくろは言ってたべ。んでも、遅そすぎっちゃ。んだから、多分、兄貴がそう話したんでねぇかな・・」
帰りを待つ、特に、祖母がどのように生活をしていたか、それは前回に少しだけお話いたしました。
やはり、公報を見るまでは、「生きて帰ってくる」そう信じていたに違いないのです。
さて、「大和」「武蔵」を知った多くの人達は、どのように感じたのでしょうか。
「日本が、世界一大きい軍艦を作り、それを二隻も保有していた」この事実は、二隻ともこの世からなくなってから知った事となります。
また「多くの、事実が公表され始めると同時に、多くの話が一人歩きいたします」
「一億特攻のさきがけとなれ」
この言葉は、「天一号作戦」が下令された際、連合艦隊が使ったとされる言葉でした。
しかしながら、「特攻のさきがけ」とするには、「大和」の存在自体が知らされていない。この事実がある以上無理な話ではないかと、酔漢は考えます。
大和が壱號艦として、その存在が誕生したときから、国民にしらされていれば、納得もしうる「言葉」であり、効果的(誤解なさらないでください。この話の運用上そうした、話にいたしております。酔漢の本意ではございません)なことだったと考えます。
ですが、戦後しかも終戦して一カ月以上たってからの情報公開(それもマスコミからの)であれば、「事実と違うことが一人歩き」しても致し方がないとなります。
逆な見方をいたしますれば選局不利な状況で「なぜ、大和を使わないのか」「大和はどうした」という世論が発生していたかもしれません。
「実は動かす為に燃料がない」
「飛行機がなければ戦闘海域に向かえない」
これは、軍として隠す事実なのでしょうが、「国民から頂戴した貴重な税金をムダに使っているようだ」とか、海軍としては国民に申し開きが出来ない状況が露呈するのが時間の問題だったのかと、斯様に推察する次第です。
天一号作戦の中で「水上部隊の沖縄本島行き」は、航空部隊を有効に活用する為の「囮」であり、「囮」であるが故、艦隊自体、大きな被害を被る。それは「特攻」という言葉にかき消され、問題の本質を替えられ、「一億総特攻のさきがけ」となる。
しかしながら、「囮作戦」を正面に出せば、(最後の水上部隊をみすみす手放すとなれば)日本海軍の誇り(変なプライド)をも作戦の段階で失うこととなる。
作戦の矛先を「殴り込み」に変えれば、「誰しもが納得するのではないか」そうした意図がGF作戦令を読み返すごとに現れてまいります。
「親父はじいちゃんの戦死を特攻と思ってない?」
「だれ、最初から思わねがった」
「理由は?」
「一つは、生きて帰ってきた艦があるってこった。途中の作戦中止は特攻にはありえねえべ。少なくても特攻に関しては、そうだべ。最後の一隻になっても、沖縄さぁいぐ事が特攻でねぇかってそう思うのっしゃ。それとや、こいずは俺の思うことなんだけんど・・」
「何っしゃ?」
「おめぇ、回天って兵器知ってか?」
「知ってる」
「あれは、一人乗りだべ。しかも、一度入ったら外から鍵かけられてや、二度とでられなぇんだど。まさしく、生き地獄だべ。そうした人が親父と一緒にされたら、回天で死んでいった人に申し訳ねぇべ」
「どういう事?」
「親父の艦には三千名がいたんだ。三千名が特攻と言っても・・零戦や回天は一人。一人で敵さぁ突っ込む。並の精神力ではそうはいがねぇ。しかも、『やめろ!』いう命令が出てんだべ。したら、おらいの気持ちとしたらだど。回天さぁ乗ってた人と同じ『特攻隊員』だったとは、言う資格がねぇんでねェかって・・・そう思うのっしゃ」
最後の親父の言葉が「特攻」という言葉を使いたくなかった酔漢の一番の理由だったのかもしれません。
「戦艦大和」が広く国民の目にさらされ、その存在が明らかとなったのは新聞記事からでございます。
上記はリンク先、下記「東海大学 鳥飼 教授研究室 HP」より抜粋いたしました。
父はその新聞の記憶は全くなく、「大和」の存在を知ったその瞬間ということも記憶しておりませんでした。
鳥飼先生のHPの存在は父が入院する直前に私が父に知らせたのでした。
「東海大学の鳥飼先生の論文(HP)によれば、昭和20年9月29日の新聞で、初めて『軍艦大和』が広く知らされたとあるけれど、親父はどこで知った?」
「さぁなぁ、ただ、どっからともなく耳さぁ入ぇって来た。どっかだ読んだとかは、記憶がねェなや。んだども、なんでも世界一でけぇ戦艦があって、それが沖縄さぁ特攻した。っては聞いた。そいっつぁ親父が乗ってたかどうかしゃねぇ。でも、親父の最期の言葉さぁ思い出したのっしゃ。『今度乗る艦(ふね)さぁぜってい沈まねぇ艦だから安心すろ』って・・・。そいずがあったからっしゃ『親父は大和さぁいたんでねぇべか』って、兄貴が言ったのっしゃ。まだ、公報さぁつかねぇべ。んだって、戦争が終わったのに、まだ帰ってこねぇのも不思議だっちゃ。まず、そうでねぇかって・・」
「海軍省、鎮守府にいたら、早く連絡があったって思う?」
「なぐてもや、後始末で忙しいんでねぇかって、そうおふくろは言ってたべ。んでも、遅そすぎっちゃ。んだから、多分、兄貴がそう話したんでねぇかな・・」
帰りを待つ、特に、祖母がどのように生活をしていたか、それは前回に少しだけお話いたしました。
やはり、公報を見るまでは、「生きて帰ってくる」そう信じていたに違いないのです。
さて、「大和」「武蔵」を知った多くの人達は、どのように感じたのでしょうか。
「日本が、世界一大きい軍艦を作り、それを二隻も保有していた」この事実は、二隻ともこの世からなくなってから知った事となります。
また「多くの、事実が公表され始めると同時に、多くの話が一人歩きいたします」
「一億特攻のさきがけとなれ」
この言葉は、「天一号作戦」が下令された際、連合艦隊が使ったとされる言葉でした。
しかしながら、「特攻のさきがけ」とするには、「大和」の存在自体が知らされていない。この事実がある以上無理な話ではないかと、酔漢は考えます。
大和が壱號艦として、その存在が誕生したときから、国民にしらされていれば、納得もしうる「言葉」であり、効果的(誤解なさらないでください。この話の運用上そうした、話にいたしております。酔漢の本意ではございません)なことだったと考えます。
ですが、戦後しかも終戦して一カ月以上たってからの情報公開(それもマスコミからの)であれば、「事実と違うことが一人歩き」しても致し方がないとなります。
逆な見方をいたしますれば選局不利な状況で「なぜ、大和を使わないのか」「大和はどうした」という世論が発生していたかもしれません。
「実は動かす為に燃料がない」
「飛行機がなければ戦闘海域に向かえない」
これは、軍として隠す事実なのでしょうが、「国民から頂戴した貴重な税金をムダに使っているようだ」とか、海軍としては国民に申し開きが出来ない状況が露呈するのが時間の問題だったのかと、斯様に推察する次第です。
天一号作戦の中で「水上部隊の沖縄本島行き」は、航空部隊を有効に活用する為の「囮」であり、「囮」であるが故、艦隊自体、大きな被害を被る。それは「特攻」という言葉にかき消され、問題の本質を替えられ、「一億総特攻のさきがけ」となる。
しかしながら、「囮作戦」を正面に出せば、(最後の水上部隊をみすみす手放すとなれば)日本海軍の誇り(変なプライド)をも作戦の段階で失うこととなる。
作戦の矛先を「殴り込み」に変えれば、「誰しもが納得するのではないか」そうした意図がGF作戦令を読み返すごとに現れてまいります。
「親父はじいちゃんの戦死を特攻と思ってない?」
「だれ、最初から思わねがった」
「理由は?」
「一つは、生きて帰ってきた艦があるってこった。途中の作戦中止は特攻にはありえねえべ。少なくても特攻に関しては、そうだべ。最後の一隻になっても、沖縄さぁいぐ事が特攻でねぇかってそう思うのっしゃ。それとや、こいずは俺の思うことなんだけんど・・」
「何っしゃ?」
「おめぇ、回天って兵器知ってか?」
「知ってる」
「あれは、一人乗りだべ。しかも、一度入ったら外から鍵かけられてや、二度とでられなぇんだど。まさしく、生き地獄だべ。そうした人が親父と一緒にされたら、回天で死んでいった人に申し訳ねぇべ」
「どういう事?」
「親父の艦には三千名がいたんだ。三千名が特攻と言っても・・零戦や回天は一人。一人で敵さぁ突っ込む。並の精神力ではそうはいがねぇ。しかも、『やめろ!』いう命令が出てんだべ。したら、おらいの気持ちとしたらだど。回天さぁ乗ってた人と同じ『特攻隊員』だったとは、言う資格がねぇんでねェかって・・・そう思うのっしゃ」
最後の親父の言葉が「特攻」という言葉を使いたくなかった酔漢の一番の理由だったのかもしれません。















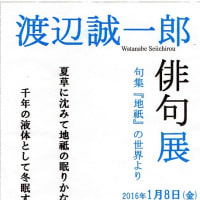

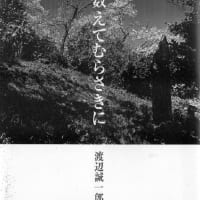








大和が「特攻」だったというのは、昔の書物では呼んだ記憶がありませんし、「特攻」だと思ったこともありませんでした。
が、最近出版された本がやみくもに「特攻」という言葉を使うものだから、「大和は特攻だったの?」というくらいの認識です。
飛行機の援護もなくて「無駄死にだった。」と考える人たちが勝手に「特攻」だと言ってるだけだと思います。
大和は決して「特攻」ではなかったと思います。
当時の新聞は、日本の負け戦を正直に書いていなかったと聞きます。
しかし、この記事では事実を述べているようですね。
当時、どの家も新聞を読んでいたとは考えられませんので、噂は伝染病のように国民に伝わったのでしょう。
ご実家は新聞をとっていたと思いますが、お父上も新聞の記事より人の話が印象深く残っていたのでしょう。
それに、大和=父では無かったでしょうから。
自分で答えを出したいと、ブログで語っておりますが、改めて重いテーマだったと感じております。
自身でも「特攻でななかった」という結論ですが。
父は驚いておりましたが、「遺族への知らせ」はもっと後なのです。
情報の流れのむずかしさを感じました。
父と話した時間が短かったのか、十分だったのか。
まだ整理できない自分がおります。
昭和33年に亡くなった叔父(父兄)と話ができたらと思うこのごろです。
少なくとも二艦隊乗員の意識では特攻でなかったと思います。
戦争というと、その悲惨さや有効性が強調されがちです。
有効性・・・負け戦の場合、有効性のなさが声高に主張されます。
後世の我々は、当時の人たちよりも圧倒的に多くの情報を持っています。
当然のことながら作戦の結果も知っています。
これは歴史を語る時に注意しなくてはならないことですが、
現在の情報をすべて動員して過去を批判するということは慎まなくてはならないと思うのです。
吉田俊雄さんの著書に『戦艦大和・その生と死』(PHP研究所)があります。
この本の冒頭には、吉田さんが呼ばれた大和会の様子が紹介されています。
出席者は戦争を生き抜いた大和乗組の下士官兵と特務士官です。
彼らの発言を読む限り、第二艦隊の出撃を「沖縄特攻」だと意識していたとは思えません。
「沖縄が危ないから、自分たちが助けに行くのだ」
というのが彼らの思いだったようです。
彼らの意識の中にあったのは
「特攻か特攻でないか」
というよりはむしろ
「任務に邁進する」ということだったのではないでしょうか。
但し当時の関係者と残された御遺族の考えを同列に置くことはできません。
「第二艦隊の乗組員は三千人だったが、零戦や回天は一人乗りで脱出不可能。
天一号作戦を特攻と言ったら、特攻機や回天で戦死した人たちに申し訳が立たない」。
酔漢さんのお父様の言葉には、考えさせられました。
だから、二階級特進でないのが当然だと。そう思っておりました。
昨今、「そうではない」とのご意見が多数であるように感じます。
しかして、私は祖母、父の考えを知る者としてはたして祖父は特攻ではなかったとそう感じるようになりました。
暗号室は最後には鍵をかける。
祖父はその中にいたんだと考えます。
これは「任務」なのです。