身近な植物図鑑(夏編)名前?黄色の花2種(改定
よく見かけるけれど名前に分からない植物2種類です。
改定です。
お陰様で教えて頂いて、2種類とも名前がわかりました
まずは、この植物からです。
1・5メートルぐらいの崖の上に際に沿って生えています。以前は他でも、よくみかけたのですが・・
葉と見えるところを押しつぶすと、水分が少しでました。
先端には、花がつ。黄色の花弁としべがわかりました。
多肉植物だと思うのですが・・・名前まではちょっとわかりません。
お陰様で、名前がわかりましたよ
花が、たくさんの星に見えるメノマンネングサ

次も、よく見かけるのですが、名前が分かりません。・・・ただ、雑草だねと、と一言で言われてしまう植物です
黄色の菊のような花が咲いています。咲き終わるとすぐに、綿毛がでています。
丈は、短いのから、長いのまであるようなのです。
似たような植物がたくさんあるようです
こちらも名前が分かりました。
種の冠毛が特徴のオニタラビコ

ここまで書いて、ずっと、投稿を保留していたの
最初の植物は、マンネングサ属の仲間・・・なのかしら?・・マンネングサ((万年草)はこういう漢字でこう書きます
いつも、見させて頂いている林の子さんの「HAYASIーNOーKO Ⅱ」に、似たのが載っているのを。。。。たぶんというか、ねっ これですよね
マンネングサ・・・・ここをクリックして見比べてみてくださいね。
マンネングサと 名前が分かったので、調べてみました
アジア、ヨーロッパ、北米大陸など世界各地に分布し、岩盤面の隙間のような、乾燥かつ貧栄養状態にあるわずかな土壌でも生育可能な丈夫な植物である
日本では石垣などの被覆に使われたこともあり、また多肉植物として栽培されるものも多い。園芸方面では学名仮名読みでセダムという呼び名が通用する。また、乾燥、高低温、塩害、アルカリ性に強く、近年は屋上緑化に適した植物としても注目・利用されている
セダムで調べてみると、また違った一面が見えるかも。。。
園芸方面では学名仮名読みでセダムという呼び名が通用する。また、乾燥、高低温、塩害、アルカリ性に強く、近年は屋上緑化に利用されています。。。
なるほど、これからもっと、利用されていく植物ですね。
投稿してからすぐに、教えて頂いて2種の黄色の花の名前がわかりました。
写真の上の方・・・マンネングサの仲間の「メノマンネングサ」
写真の下の方・・・ 「オニタラビコ」 鬼田平子
投稿してすぐに、「花紀行」のとんちゃんさんと、「HAYASI-NO-KO」の林の子さんから、コメントあり二種類の名前を教えて頂けました。
とんちゃんさん、林の子さん、ありがとうございます。
ブログの写真を見てすぐに、知識のある方から返事がもらえたり、教えてもらえるからインターネットは、ありがたいですね。















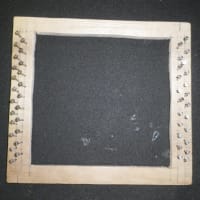




マンネングサの色々はよく見ます。
ただなにマンネングサなの?ということになるといつでも分からなくて・・・
たったひとつだけ「タイトゴメ」はコロコロしている形からなんとなく分かるようになりました。
これはメノマンネングサによく似ていますね。
お星様の形のマンネングサは大好き!
野原で見てもつい笑顔になれます!
下の花は左はオニタビラコかもしれない
右はヤブタビラコ?
いつもよく見ていてもいざ名前となるとこの類も迷ってどうしようもない
いつかははっきりさせたいと思っている花
検索したり図鑑で見たりしているときはなるほど!って思っても実際目にするととってもやっかい
ちゃんとポイントをつかんでいないからだと反省ばっかりです。
一緒に勉強させてくださいね。
秋には秋の野の花ですから、夏編は今のうちに。
マンネングサ、乾燥にも強く水不足で枯れていても少しの水で復活するのですが、
さすがに殆ど水気を貰えない場所なのでしょうか、茎がかなり徒長気味ですね。
緑と言うより黄味が強くなったメノマンネングサ、辺りでしょうか。
下の画像は、左右ともにオニタビラコでしょうね。とんちゃんの推測されるヤブタビラコは種子に冠毛(綿毛)がつかないのですが、
画像では両方共に冠毛があるように見えます。
ヤブタビラコの画像をご参考までに貼っておきますね。↓
http://blog.goo.ne.jp/ken328_1946/e/7dd1934c658819719320c45a1bfed81b
これでひとつ頭に入ったかもしれないです。
来年にはまた元通りの空っぽになるかもしれませんが・・・
何度も繰り返し いっぱい見る いっぱい間違えたり勘違いしたり
同じようなことでも少しずつの進展につながると思います。
改めてよく調べた見ると、マンネングサの仲間の、メノマンネングサだと思います。
これで、あの崖の縁に沿ってに毎年、生えているのは「メノマンネングサ」と、判明しました。
残念ながら、上からは、見られないのですが、黄色の星が一面に広かっているのでしょうね。
おにたらびこ・・鬼田平子・・こう書くようです。田畑にたくさん広がって抜くのが面倒な植物だったのでしょうね。
同じように見えるのが結構・図鑑にのっているのですが・・・冠毛が特徴だったのですね。
そういえば、両方とも、綿毛がついていました
たくさんの情報をキチンと把握していないと、間違った結果になってしまうのですね。人に伝えるのはむずかしいですね。
あ、これって、実生活とおなじですね。
いつも、応援ありがとうございます
もう一度、確認してみました。
メノマンネングサと、オニタラビコで、決定ですね。
ヤマタラビコの写真をみてきました。自分の撮った写真のは植物とはやはり、ちがいますね。
葉の色とか形とか・・見比べてみて、わかりました。
ありがとうございました。
今年の夏は、異常に暑かったので、見つけていたのですが写真を取りに行くのに、二の足を踏んでいるうちに、九月も下旬になってしまってしみました。
でも、自然は正直で、もう、秋の植物が咲き始めてしましました。
このところの天気では、どこから、秋でどこまでが夏か分からなくなってしまっています。
でも、「角虎の尾」が咲いて散ってしましまいた。
秋になっているのですね。
夏の植物と思っていた物も秋にも続けて咲いているし区別がつかなくなってしまっています。
盛りのとき、旬のときが、季節なのでしょうが、いまいちよくわかりません。
彼岸過ぎたら一気に秋、二度の台風で早く葉が落ち始めているようです。
花壇の花は、人の都合で時期を違えることは余り無いのでしょうが、
勝手に広がっている雑草は、根を張った土の温度や種子の育ち方次第で、
勝手に花をつけるようですから、カタバミなどは年中咲いている。
年中咲いているので、その葉を食草としているヤマトシジミなども、
いつでも卵を産めるし、年中飛び回れる。
四季のある日本なので、桜が秋に咲くと「狂い咲き」と揶揄されるようですが、
サクラでも秋に咲きまた春に咲く種類もある訳で、人間の生活環境とは違っているのでしょう。
雑草類を見ていると、やはりワイルドだと思います。
彼岸花が咲き始めたというので、お墓参りがてら、隅田公園を歩いてみました。
もう、花期が終わってしまったと思っていた植物がまだまだたくさん出そろっていました。
雑草は、環境に適応して、自分の気分次第に生きて生きていくのだ!!
図鑑の生育期なんて、糞くらえ!
ぐらいの勢いで頑張っていました。
季節とか、環境がどうのとか。。。関係なく生きていく・・・・
それに連れて、昆虫たちも、
いままで、雑草がたくさん生えている。ぐらいの感覚で雑草を見てきたのですが、
最近、見る目が変わって来て、世界が広がった気がします。
植物って人間の感覚や、区分けしたがる人々とは、関係なく生き生きとして、ワイルドなものなんですね。