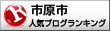昨日ブログに書いたように、
ただいま決算審議の準備のため、身動きが取れない状態が続いてはいるのですが、
それでもこれは行かなくちゃ!と思って今日顔を出したのが、
こちら。

辰巳地区で新しく始まる「安心生活見守り支援事業」に関する集会です。
この事業は、地域の見守りの目で高齢者の孤立や孤独死を防ごうというものです。
町会や民生委員、社会福祉協議会などが協力しあい、地域住民による「見守り支援員」が月1回ぐらいのペースで一人暮らしなどの高齢者宅を訪問し、声掛けによる安否確認などを行います。
辰巳地区では、この事業を始めるにあたって、町会の役員さんや民生委員さんが高齢者のお宅を全て訪問し、見守り支援をしてほしいかどうか、アンケート調査をして回りました。
その結果、対象者883名中174名・約20%の高齢者が、見守り支援を希望していることがわかりました。
問題は、ここからです。
「174名ものニーズに対応する支援員の確保が、自分たちにできるのか??」
会議では、町会役員の負担増などを理由に、時期尚早との意見も続出しました。
無理もありません。
そもそも、町会の組織率や加入率の低下や役員の高齢化など、地域コミュニティの維持すら困難という地域も多いのが現状なのです。
それでも、
「見守ってほしいというお年寄りがいる以上、とにかく今始めなければ!」という声に、
地域福祉の希望が見えた気がしました。
ただいま決算審議の準備のため、身動きが取れない状態が続いてはいるのですが、
それでもこれは行かなくちゃ!と思って今日顔を出したのが、
こちら。

辰巳地区で新しく始まる「安心生活見守り支援事業」に関する集会です。
この事業は、地域の見守りの目で高齢者の孤立や孤独死を防ごうというものです。
町会や民生委員、社会福祉協議会などが協力しあい、地域住民による「見守り支援員」が月1回ぐらいのペースで一人暮らしなどの高齢者宅を訪問し、声掛けによる安否確認などを行います。
辰巳地区では、この事業を始めるにあたって、町会の役員さんや民生委員さんが高齢者のお宅を全て訪問し、見守り支援をしてほしいかどうか、アンケート調査をして回りました。
その結果、対象者883名中174名・約20%の高齢者が、見守り支援を希望していることがわかりました。
問題は、ここからです。
「174名ものニーズに対応する支援員の確保が、自分たちにできるのか??」
会議では、町会役員の負担増などを理由に、時期尚早との意見も続出しました。
無理もありません。
そもそも、町会の組織率や加入率の低下や役員の高齢化など、地域コミュニティの維持すら困難という地域も多いのが現状なのです。
それでも、
「見守ってほしいというお年寄りがいる以上、とにかく今始めなければ!」という声に、
地域福祉の希望が見えた気がしました。











































 k
k