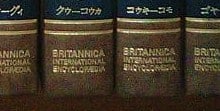平沼 赳夫( ひらぬま たけお )
1939年(昭和14年) 8月3日 生まれ
衆議院議員(10期)。
運輸大臣(第70代)、通商産業大臣(第66代)、経済産業大臣(初代・第2代)を歴任。養父は第35代内閣総理大臣の平沼騏一郎。
2010年(平成22年)4月 新党たちあがれ日本を結成し、代表に就任。
座右の銘は、「天命を信じ人事を尽くす」。
わが郷の記事
2010 04 09 自分の足で 「たちあがれ日本」 【わが郷】
☆☆
☆
Wikipedia よりの、メモ
平沼 赳夫(ひらぬま たけお、1939年(昭和14年)8月3日 - )は、日本の政治家。衆議院議員(10期)。
運輸大臣(第70代)、通商産業大臣(第66代)、経済産業大臣(初代・第2代)を歴任。養父は第35代内閣総理大臣の平沼騏一郎。
2010年(平成22年)4月、与謝野馨らとともに新党たちあがれ日本を結成し、代表に就任した。
座右の銘は、「天命を信じ人事を尽くす」。
生い立ち [編集]東京市渋谷区代々木大山町にて、中川恭四郎・節子夫妻の長男として生まれる。父・恭四郎は群馬県知事、特許庁長官などを歴任した内務官僚中川友次郎の四男で、農林中央金庫に勤めていた。その後、三井生命、学校経営、大協石油と職を変え、大協石油の特約店・朝日商販の社長となった。母・節子は早稲田大学総長を務めた平沼淑郎(平沼騏一郎の兄)の孫娘であった[1]。
赳夫が2歳のとき、子供のいない騏一郎は、恭四郎・節子夫妻を一家養子として迎えた[2]。
立候補 [編集]佐藤栄作、中川一郎の秘書を経て、1976年(昭和51年)の第34回衆議院議員総選挙、1979年(昭和54年)の第35回衆議院議員総選挙に立候補するが、連続して落選。落選の最大の理由は、当時タブーとされた憲法改正を前面に掲げて戦ったためである。
また、戸別訪問をした際には「騏一郎には実子がなかったはずだが…」といぶかしがられ、関係を問い質される苦労もあったという[5]。
自由民主党時代 [編集]1980年(昭和55年)の第36回衆議院議員総選挙にて、旧岡山1区で立候補して初当選する。以後10回連続当選。この間、石原慎太郎、亀井静香、中川昭一といった中川一郎に近い保守派の議員らと行動をともにする。村山改造内閣で運輸大臣として初入閣。その後も第2次森内閣で通商産業大臣に、第2次森内閣 (中央省庁再編)で初代経済産業大臣に、第1次小泉内閣でも再び経済産業大臣に任命された。派閥は中川一郎率いる自由革新同友会に所属し、中川一郎の死後は石原らとともに清和会へ合流した。清和会を離脱した亀井静香らのグループと中曽根康弘が率いていた政策科学研究所が合流し、志帥会が発足。名称は初代事務総長である平沼の命名による。
清和会の創始者である福田赳夫は、自身と同じ名前を持ち、長男・福田康夫の中学・高校の3年後輩である平沼を公私に渡って可愛がった。
なお、政治家の年金未納問題が注目された際に年金の未納が発覚している。
郵政民営化法案に反対 [編集]ポスト小泉(小泉退陣後の後継総理)の有力候補として注目されていたが、小泉内閣後期では拉致問題や政治手法の違いから徐々に溝が生じ、2005年(平成17年)7月5日、郵政民営化法案の衆議院本会議採決で反対票を投じた。このため同年9月11日の第44回衆議院議員総選挙では自民党の公認を得られず、無所属で出馬。自民党公認の阿部俊子を破り、9回目の当選を果たした。特別国会の首班指名選挙では、小泉純一郎に投票したが、郵政法案の衆議院再採決では反対票を投じた。解散総選挙で自民党を非公認になり、無所属で当選した13人のうち再び反対票を投じたのは平沼一人であった(野呂田芳成は欠席)。
自民党からの離党勧告 [編集]郵政と選挙における行動によって、自民党から平沼に対して離党勧告処分が下った。ただ、法案に再び反対した平沼には除名処分が確実といわれていたが、首班指名選挙では小泉純一郎に投票したため離党勧告処分にとどまった(野呂田は首班指名選挙で国民新党代表の綿貫民輔(当時)に投票したため、除名処分となった)。自民党党紀委員長の森山眞弓(当時)は、平沼が他の造反無所属衆議院議員と同じ離党勧告という処分だったことについて「自民党の行動にすべて反対しているわけではない。『政治的信念を変えられない』ということで、理解できないこともない」と説明した。
平沼 騏一郎(ひらぬま きいちろう、慶応3年9月28日(1867年10月25日) - 昭和27年(1952年)8月22日)は、日本の司法官僚、政治家。位階は正二位。勲等は勲一等。爵位は男爵。学位は法学博士。号は機外。
大審院検事局検事総長(第8代)、大審院長(第11代)、日本大学総長(第2代)、大東文化学院総長(初代)、財団法人大東文化協会会頭(第3代)、司法大臣(第26代)、貴族院議員、枢密院副議長(第11代)、枢密院議長(第17・21代)、内閣総理大臣(第35代)、国務大臣、内務大臣(第62代)などを歴任した。