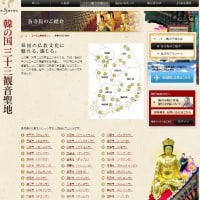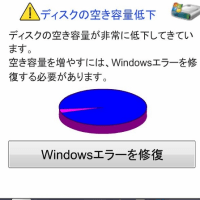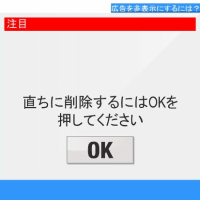「にっぽん縦断 こころ旅」という番組に、しばしば目を奪われている。六十半ばの火野正平さんが息を切らして自転車を漕いでの旅である。
小生も古希である、自転車での遠出は如何に大変か身にしみて判るのである。
今や電動自転車の時代である。決して若くない火野正平さんに息を切らせて電動自転車の旅をさせるのも良いが、歳が重なると近い将来限界が来ることも間違いない。
将来、人力サイクリングの方を若手に譲り、電動自転車での方を火野正平さんに担当してもらうような時期が来るように思える。そうすれば、七十歳を過ぎても、彼がこの番組を続けることができるだろうと思ったからである。
息を切らし汗水垂らしてこそ意味があるという反論は、十分に承知している。かつて、登山は足でするものだ、ケーブルカーでする登山など邪道だと山男達が声高に叫んだ時代があった。
しかし、ケーブルカーなどの交通機関による登山がもたらしたものは、頑健な山男や山女に占有されていた登山を高齢者や子供達を含む庶民に開放したという歴史があるのである。庶民のものになってこそ、本物の登山だと思う。
そんなことがきっかけで、こんなことを考えた。
人力走行の方は将来若い人に譲り、年寄りは年寄りの味で電動自転車を利用して旅をするという番組ができても良いような気がしている。NHKのご検討を期待する。
自転車や電動自転車を列車で運べるのかということに疑問が湧いたので少し調べた。そこで「輪行」という聞きなれない言葉に行き着いた。
参考(Wikiによる);
1.輪行(りんこう)とは、自転車の乗員が自転車を公共交通機関(鉄道~船~飛行機など)を使用して運ぶこと。サイクリストや自転車旅行者が、行程の一部を自走せず省略するために使う手段。
公共交通機関を利用しない自走以外の移動(例えば自家用車積載)は輪行とは呼ばない。
2.公共交通を利用する理由としては以下のような点があげられる。
* 走行コースが周回ルートを取らないように設定できる。
* 同じ期日で自走より遠方に移動できる。
* 道路が通行止、自転車通行禁止となっている区間を避けられる。
* 旅程のなかで気象・日没・道路状況・体調・けが等により自走が危険、あるいは楽しくないルートをキャンセルできる。駅があればどこでも走行を中止して帰投できる。
* 自転車が故障した場合。
* 公道走行を禁じられている自転車の場合。(競技場やタンデム車の走行が許されている県までの移動など)
3.許可条件
* 自転車の分解(少なくとも折りたたむか、ホイールを取り外す)。(渡し舟、一部のロープウェイ等で自転車が走行可能な状態では輪行とはみなされない。)
* 乗員による持ち込み。(鉄道利用時に自転車の乗員に限り許される)
* 専用の袋に収納する。
4.語源は、競輪の選手が競輪場まで自走してレースに参加することを、自転車で行く=「輪行」と称していたことに由来する。競技場への移動は主に列車を使ったが、その際に分解して袋に入れれば有料手回り品扱いとするという取り決めがされた。この自転車収納用の袋を業者が「輪行」にちなんで「輪行袋」と言う名前で呼び、やがて輪行袋を使用する事を「輪行」と言うようになった。
輪行は競技自転車選手および自転車愛好家で用いられる用語である。運送主体となる旅客運輸業者各社の運送約款および営業規則には「輪行」という表現はない。大概の自転車は分解しても旅客運輸業者が定める「手回り品」の規格を上回るが、特例として袋に入った自転車は「手回り品」として認められている。現在JR各社などでは競輪選手対象には別の条件を定めている。
以下略。