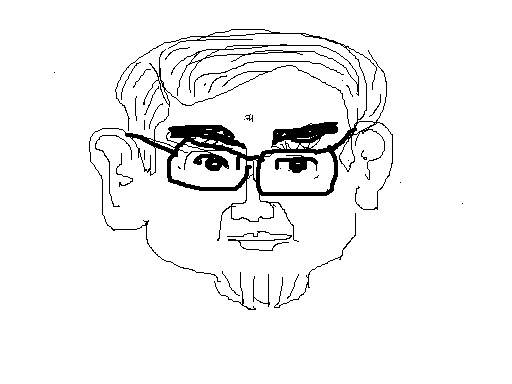今年もまた立派な「ムラサキ山芋」を頂いた。カボスも落花生も生姜も入っていた。
平川さん毎年本当にありがとうございます。今年も全ておいしく楽しみに頂きます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ブログに最初に登場したムラサキ山芋のエントリー
⇒2011年12月18日のブログ「ムラサキヤマイモには独特のパワーがある!」
大分県国東半島にある「ひらかわファーム」から送ってもらった「ムラサキヤマイモ」。
いよいよ満を持して「とろろ」をつくった。この陶器セラミックの大根下おろし器は、歯の文様が大根よりヤマイモに向いている。
大家族の場合はやはりすり鉢でないと量的に間に合わないが、少人数になった今はこの隠し道具をとろろ作りに重宝している。
なお、大根オロシ用には同じ陶器セラミック製ながら歯の文様が微妙に違う別のものを使っている。
皮をむく時からその粘りを感じたが、下しだすと驚きの粘度だった。この粘度は特別だ。
試にだし汁を加える前に口に含んでみると、かすかな甘味とイモそのものの味が立ち上がった。
香りも感じた。出来上がったとろろをご飯にかけて混ぜようとしたが粘度が高くて、並みのまぜ方ではまざらない。
時間をかけて丁寧に混ぜた。まさに太古からの自然薯の流れを引くイモのコクと太地のパワーを感じながら大満足で頂いた。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ダイジョ/大薯/台湾山芋:特徴や産地と旬 引用元。
●ダイジョとは
◆ヤマノイモ科ヤマノイモ属

ダイジョまたはダイショと呼ばれるものは長芋や自然薯と同じヤマノイモ属の仲間でヤムイモの一種です。
アフリカからアジア、オセアニアに至る熱帯から亜熱帯地域で広く栽培されており、原産地には諸説あるようですが、インドから熱帯アジアという説が有力なようです。
日本には台湾から沖縄を経て九州に伝わったとされ、「台湾山芋」や「沖縄山芋」とも呼ばれています。また、九州各地ではこのダイジョを「つくね芋」と呼んでいます。
◆ダイジョの特徴

ダイジョには白いタイプと紫色のタイプがあり、紫色の物にも表皮とその付近だけ紫色の物と、中まで紫色をしているタイプがあります。沖縄では中まで紫色の物が多いようですが、九州では白い物の方が多くみられます。

形は不規則で、大きいものだと10キロ以上にもあることがあるそうです。通常1株に一塊の芋が出来き、長芋や自然薯などとは違いムカゴは出来ません。
すりおろすと長芋とは比較にならないほど強烈な粘りで、味も濃く感じます。紫色の色素はアントシアニンで、中まで紫のものはすりおろすと淡い紫色のとろろになります。
収穫のタイミングが早過ぎたり、栽培環境によっては断面やすりおろした時に空気に触れ、茶色く変色するものがあります。
●ダイジョの主な産地と旬
◆ダイジョの主な産地
国内では沖縄県を中心に九州南部で作られています。ダイジョは低温に弱く、本州では種イモが寒さで越冬できないためあまり栽培されていません。種イモを越冬させるには常に15度以上に保つ必要があるとされています。
◆ダイジョの収穫時期と旬
収穫時期は産地にもよりますが、霜の影響を受けない温かい地域では12月頃に行われ、霜の影響を受けるところでは、霜が降りる前の11月辺りから収穫が始まります。
|
『現在でも、天体力学で数値計算か特殊な方法を使わずに三体以上の物体の間の運動を計算することは困難である。 この調和こそが地球上の世界そのものなどを解き明かすための究極の鍵であるとの錯覚を抱かせてしまった。 (工学ではこれをフィードバックシステムが効いているという。) これは自由放任が一番よいという思想になる。 各惑星は自由な軌道変更を選択する権利を有していると言えるからである。 あとは望むものをすべて手に入れることができたのである。 他の世界は彼らに抗すべくもなかった。 個人絶対主義も市場万能主義も最も宇宙の摂理に適ったことだということになり、その障害となるものは「悪」だということになるだろう。 一方経済社会を太陽系型に近づけていくことは、要するにそれらの糸をどんどん切ってその経路を単純化していくことに他ならない。 昔は町の経済は商店街が担って地域社会と二人三脚の形で街を支えていたのだが、現在では多くの場合、巨大店舗がその経済機能をまるごと奪い取る形で商店街を壊滅に追い込んだ。 結局はその良し悪しは相対的だとの理屈をいう人も多い。 どうやら一般に「自然と社会を劣化(縮退)させるとその過程で儲けが生まれる」ということが言えるようだ。 要するに勝ち組と負け組の差が指数関数的に拡大して前者が後者を凄まじい勢いで食い殺して行ってしまう。これこそが格差問題の本質である。 (工学ではフィードバックがきかなくなったという。) ところが縮退が進むと、社会の中の資金の流れが次第に巨大企業と巨大機関投資家の間だけで短絡した経路を作って、その狭い世界の中だけを高速で回転するようになり、 血液が回らなくなったその外側の世界はだんだん壊死していく。 もはやモノを作ったり買ったりする世界自体を外側に取り残してさらに内側のコア、つまりコンピューターの中の瞬間的な売買で自己増殖を行なえる 投機市場の世界の中だけを回り始めてしまったのである。 世界経済の本来のサイズの実に数倍に膨れ上がっていた。 そしてそれまでの全ての錯覚の終曲のように、それは最後に自身を超新星のように大爆発させ、すでに半ば壊死していたその外側の世界をも爆風で襲って世界の全ての人々を巻き込んでしまった。 発散して、カタストロフィーをおこす可能性が多いことを予測していたにもかかわらず、社会に警告を発しなかったのは何故か?
2009年に上出さんから送って頂いたものです。再掲載) |
「真夜中のドア〜stay with me」/ 松原みき Official Lyric Video
学生時代から、もう60年ほどのつきあいになる友人に「山 内 庸 行」さんがいます。彼は大阪富田林市に住んでいます。
山内さんは3年前に大阪狭山市の混声合唱団(さやこん)clickに入りました。
以下の文章は混声合唱団の7月の機関誌に山内さんが投稿した寄稿文です。彼の許可を得て本ブログに転載しました。
※※※※※※
※※※※※
『2023年 定演を迎えるに辺り思うこと』 Bass 山 内 庸 行
私は今回2回目の定演を迎えさせて頂きます。先生方の熱意と、団員の皆さんとの実力の格差にある時は励まされ、ある時は怯(ひる)むような日々を送っています。
同時に、声を出すことの快(こころよ)さ、そして何より良い曲を歌わせて頂ける喜びを感じています。
実は私の父は銀行員でしたが約60年間に渡り、北原白秋の流れをくむ短歌作りと、毎朝の般若心経の写経を日課にしていました。
2009年、白寿直前に亡くなった時、なんと、四国88ヶ寺の納経用の写経(本堂と太子堂用) 計176枚を私名義で書き遺して逝ったのです。
他方、戦中生まれのガキ大将だった私は、中学生の頃人生問題に出くわし、大学時代には、坐禅のクラブに入り禅寺から学校に通いました。
それ以来『比較する能力がないと社会では生きれないが、比較の中には自分はいない、つまりは社会生活や文明構築には、不可欠な言葉や概念は、
比較でしか成り立たないと言う大きな落とし穴があることに、人類で最初に気付かれた釈迦の気付きの私なりの追体験』に努めてきましたので、
各宗各派に分かれた既成の仏教やご利益宗教は大嫌いで、あの世とか神様とか仏様とか空海さんとか四国遍路とかの比較を抜けきらないコトにも、
全く関心がありませんでした。
しかし、父の想いを無視する事も出来ず「写経」を配達する事も親孝行だと割り切り、父の初盆前の2010年5月に歩き切る自信もないままに、
68歳の年に大阪から青森までの距離にあたる約1200Kmの四国遍路の道を歩き始めました。そして、何とか42日間で歩き切ることが出来ました。
一度に四国88ヶ寺全てを回る遍路を『通し遍路』と言いますが、今迄4回の『通し遍路』を、毎回はぼ、40数日で回ることが出来ました。
88歳の米寿での6回目の『通し遍路』で打止めにしたいと思っています。
四国遍路の由来を調べていて『四国遍路は空海さんが開いたと、一般には信じられているが、本当は仏教伝来以前から紀伊半島の山岳修験者が、
四国に行って拓いた修行場が元になっている』らしいと知り、それなら、四国遍路の元祖を歩きたいと思い立ち、72歳の時に吉野から熊野迄、
約100Km続く険しい大峰山系を時には鎖に頼り行く縦走の道『大峰奥駆修験道』に、何度となく挑戦しました。その折に平安時代に『蟻の熊野詣』と言われるほど、
熊野本宮詣でが盛んであった事や、その道の1つに 大峰奥駆 に次いで、厳しい、千メートルを越える4つの峠を越えて熊野本宮へ至る『小辺路』があることを知り、
予てより歩きたいと思っていましたが、この7月初めに、4泊5日で歩く事が出来ました。
私がそもそも『歩く事』にここまで惹かれるようになったのは、亡き父に無理矢理背中を押され、最初の四国遍路に行った時『お寺参りには、
大して意味があるようには思えないが、お寺とお寺の間を歩く事に意味がある』と感じさせてくれたのは、3つの体験があったからだと思います。
先ずこの話からさせてください。と言うのも今回の定演で歌う歌が、それらの体験に深く繋がっていると感じられてならないからです。
1つ目は7キロの荷物を背負い毎日30Km近く歩くのですから、歩き始めて直ぐに身体中、痛くない所はとこにもないという状態になります。
宿につく頃には「もう、明日はアカン」とまで追い込まれます。でも、風呂に入り、ご飯を食べて一晩寝たら、自分は何もしていないのに、
翌日には気力と体力が回復しているではありませんか。『自分はいのちだった』と時間させられる日々でした。
2つ目は、40日以上歩く事以外に何の目的もなく一人で只、歩き続けていると、さすがに鈍感な私もハッキリ気付かされることがありました。
それは、鳥の声は、聞こうとせずとも、耳に、木々の緑は見ようとせずとも、眼に、勝手に入って来ていると言う事実です。
また、呼吸は寝ていても勝手になされていますが起きている時も、山道では山道の、平地では平地の息が勝手になされていると言う事実です。
例えば遍路の場に、もし妻が居てくれたとしても、私のナマのこの(この挿入)実感は、たとえ妻であっても、共有出来ないのです。
それは、私だけのモノなのです。しかも実感である限り、常にマッサラなこの一瞬だけのモノなのです。
『自分は、自分の意思とは無関係に働いている自分を超えたいのちに生かされている。
なのにいのちの実感の世界では、他との比較・代替不能な、自分だけの世界を生きている』と言う『生きる事の不思議さ』を気付かされたような気がしています。
そして、言葉や概念で表現された他人との比較の中の自分は、言わば社会を生きる為の方便に過ぎず、比較・代替不可能なこのナマの実感の世界の自分こそが
本当の自分ではないのか!と思わざるを得ない日々を続けていたのです。
私は定年後、知的障がい者施設『金剛コロニー』の入所者の親が亡き後の支えとなる『法人成年後見人』の受け皿としてのNPO法人『かんなびの丘』の設立支援が縁で、
10年以上理事や理事長として関わってきましたので、果たして社会的に役に立つ事や知的能力だけが『人間の価値』なのだろうか?と考えさせられたのでした。
考えてみますと、人生100年時代とは誰もが寝たきりになったり、認知症になったり、中途障がい者になったりする事もあり得る時代と言えます。
そんな時、親やきょうだいや自分には、生きる価値はないとでも言うのでしょうか?
同時にAI時代が本格的にやって来ます。データを集めて・比較して・処理すると言う意味での知的能力では、もう、機械に訂正)には敵わない時代なのです。
そんな時でも、知的能力だけが、人としての価値だと言うのでしょうか?
今こそ、社会に役に立つかどうかや、知的優秀さなどの、他人との比較ではなく、『取り替えのできないいのちに生かされ、言葉や概念の前に在る、
自他超えた自分だけのナマの実感そのもの』と言う誰もが授かっている『いのちの不思議』を、その人の天賦の人権の根拠としてみる人間観・生命観への転換が必要なのではないでしょうか。
今回の定演で第二部男声合唱で歌う『昴』は、谷村新司自身が『(「昴」は古来、物質の豊かさのシンボルであり)この歌は物質文明に別れを告げようという意味を込めて作曲した』と、
自著で延べています。物質的繁栄は、主に知的能力、つまり言葉や概念の力と考えると、私は谷村新司も『さらば昴』の歌詞で『言葉や概念で創られた世間的価値と言う、
比較の世界の中の自分』とは決別し『言葉や概念の前に在る比較・代替不可能な自分だけのナマの実感の世界』( つまり、『世間的価値観でないという意味では「荒野」』)に向かって
人間観・生命観の転換を図ろうと言おうとしたのではないかと思われてなりません。
又、第三部『いのちの木を植える』として、谷川俊太郎の作詞4曲を歌いますが、『でも、木は、いつも木と言う言葉以上のものだ』の歌詞に見られるように、
この四曲は、まるで谷川俊太郎が、谷村新司の『昴』に呼応するかの様に『人間が信じて疑う事のない、言葉や概念、
つまり、知性が織り成している社会生活や文化生活が、いかに底の浅いものか「比較・代替不可能な自分だけのいのちを、比較・相対の世界に貶(おとしめ)る、
言葉や概念の落とし穴に気付いて欲しい!」と警鐘を鳴らしている』様に聞こえてなりません。
梨の木も羊も、一匹の蝿も、自然界の全ては自分だけの真実とも言える実感の世界、自然と一体となって生きています。
それは人間だけなのです。言葉や概念と言った比較の中に自分の価値や生きる真実を見出そうとして、見出せなく焦っているのは・・・。
『ただ私たちだけが、本当でなかった(『梨の木』)真実に気付き、その意味を考えて欲しい』 これこそが
谷川俊太郎のメッセージではないでしょうか?
そして、第一部で歌う歌は、中原中也の2つの詩に混声合唱団の男声指導者の安田先生が作曲したものですが、その1つ『汚れつちまつた悲しみ』は、
自分だけのナマの実感と自分が選んだ言葉とのギャップに戸惑い・苦しみ・それを自分の『汚れ』として感じた中也の詩人としての(挿入)感性の鋭さが、
生み出した歌ではないかと私は受け取っています。中也は結構生活が乱れ、人付き合いもかなり邪険だったようです。
それは、日常の言葉や概念に満足して底の浅さに気付こうとせず、自分の感性が展開しているイキイキとしたナマの世界ではなく、
映像に過ぎない言葉や概念の世界を、本当の世界と思い込んで、何の違和感も感じない、人々への嫌悪感と軽蔑の思いのなせる技ではと、想像しています。
遍路歩きで3つの体験があったと書きましたが、その3つ目の体験とは「遍路とは道に迷う事なり」と言いたいくらい道に迷った時の体験です。
本当に困った時に、偶然出会った見知らぬ人から助けを受けると、感謝とも喜びともつかぬ、得も言われぬ熱い思いが、込み上げてくるのを、何度となく体験しました。
この体験で『「有難う」は言葉なんかに在るのではなく、言葉の前に在るこの実感こそが、本当の「有難う」だったのだ』と思い知らされました。
「言葉や概念の有難うの世界」では、間違いなく、自分は自分、他人は他人ですが「自分のナマの実感の有難うの世界」では、確かに自分だけの世界なのですが、
その自分だけのナマの実感は、自分だけでは決して生まれ得ないと言う当たり前の事実にも気付かされるのです。
つまり、自分が 『何気なく、いつも自分の外に在ると信じて疑わないコトやモノこそが、自分の人生の実感の中身を作ってくれている』と言う不思議な、
しかし、当たり前の事実が見えてくるのです。 イヤ、むしろ『全てを自分の外に在るとして認識させてしまう言葉や概念の落とし穴』を見過ごして来た
自分の迂闊さに気付かされるのかも知れません。
ここまで書くと、第九の『フロイデ』の後の初めての合唱“D”の部分を思い出します。『世の習わしが隔てた』を『言葉や概念が創り出す自他を分ける比較の思いが隔てた』と捉え
『自分の外側の世界こそが自分の世界を創り出してくれている「いのちの実感」の世界に抱かれる時、そんな比較の思いは消え、自他の隔ても自ずと消え、
人々は全て自分の人生の中身、つまり友となる』と読めない事もありません。
いや、ここを作曲していた時「シラーの詩のフロイデと言う言葉や概念」を通り越して言葉や概念以前の「フロイデの実感』がベートーベンの心の底から溢れ出してと
私には思われてならないのです。
私は、第九にしても、混声合唱にしても『歌う(声を出す)』事は、『歩く』と言う行為と、何か共通点があるように感じます。そして、そこに歌う事の魅力を感じています。
練習中、上田先生は時折『どんな音程でも、先ずは、自分の声を出して!』と仰います。この言葉を聞く度に、
最初の遍路の後に、地域の先輩に 『遍路して、結局どうやったんや?』 と聞かれ、思わず、『どんなにしんどくても、今の一歩を踏み出す以外はない事を、
遍路は教えてくれたように思います』と答えたのを思い出します。
今の一声も一歩も、歳と共に当然の事ながら、短く、弱いものになります。しかし歳をとっても常に自分の今の一声・一歩が問われ続けているのではないでしょうか。
そして、その一声・一歩以外には、自分の歌も人生もなく、踏み出した時の自分だけにしか分からない、ナマに実感にこそ、自分が生きる意味の全てがあるのではないでしょうか!
混声合唱の醍醐味は、ハーモニーにあると言われ、私もそこに惹かれます。それは何故でしょうか。
ハーモニーは、自他の比較を超えた自分もいない、自分に出逢えるからこそ、美しさと喜びを感じさせてくれるとは言えないでしょうか。
合唱のハーモニーは 『ナマの実感の世界は、自分だけの世界なのに、そこは自分すらもない、自他分離不可能な世界でもある』と言う『いのちの不思議さの実証であり
、追体験なのではないでしょうか。
坐禅は 『無念無想』 と言われますが、一度でも坐禅をされたら分かると思いますが、坐禅の時の方が言葉や概念や思いは余計浮かんで来ます。
植物人間にならない限り、思いは止められません。 何故ならば、思いとは胃が胃液を分泌するのが胃の仕事である様に、思いを浮かべるのが、脳の仕事だからです。
しかし、坐禅を続けていると『思いは湧き起こり続け、外の景色の音も入ってきますが、気付いていながら気にならない』 状態がやって来ます。
更に、自分と自分の思い自分と外の景色や音と、全ては自分と対立的に在るものではなく、全てが自分の中身であると感じられる状態が現れます。
何故ならば全ては自分の五感と意識が展開している世界に過ぎないからです。
しかし、坐禅中に意識が昇ってくることは絶対に在りません。何故なら、『眠る』のと同様に『考え事』を追っていては坐禅にならないからです。
父も70歳頃2回、歩き遍路していました。『60年続けていた短歌が人生の宝と思っていたが、歩き遍路こそが宝であり、歩く坐禅(歩禅)だった!』と書き遺していました。
私にとって歩き遍路は、坐禅の時に生じていた状態を意識に昇らせてくれたと、今では父に感謝しています。
定演のアンコール曲の『ひとつしかない輝き』は、中原、谷村、谷川の思いを凝縮した様な曲で、今回の定演のフィナーレを飾るのに最適な曲だと私は思っています。
しかし『ひとつ』を、一つ二つの ひとつ と言う、比較と捉えてしまうとこの3人の真意とかけ離れたものになるのではないでしょうか。
『日々是好日』と言う言葉があります。『一期一会』と同義語と私は受け取っていますが『自他の違い・比較は見えながら、比較・代替不可能な自分すらも無い自分を生きる。
繰り返しの日々を、マッサラに生きる』の意味ではないかと受け取っています。そして、17年ほど保護司をさせて頂いておりました時、自省の思いをこめて
『比較が分からない人間は愚かだが、比較でしか見れない人間は、もっと愚かだ!。何故ならば、比較の中には自分も他人も人生も存在しないのだから!』と、
保護観察対象者に、話してきました。何故ならば彼らの多くが、比較の中で、自分を見失い、犯罪に手を染めてしまっている様に思えたからです。
そして、釈迦が生老病死の四苦に悩まれ、出家された時も、比較の中で生きる意味を求められたからではないか・・・と想像しています。
『いのちの実感の世界での比較を超えたひとつ』として、初めて『ひとつしかない輝き』は、今回の定演に最適な曲と思われてなりません。皆さまは、どう思われますか。
『生きる事』、『釈迦の気付き』、『坐禅』、『歌う事』、『ハーモニー』・・・みんな、底では「繋がっているんだなぁ~」と、
脳が分泌しただけの、つれづれの思いを、又又、長々と雑文を書き連ねてしまいました。
勝どきの住人森山さんからメールが届きました。
⇒「勝どき橋」から撮った写真です。
築地市場跡の写真です。(手前の「勝どき橋資料館」の建物は築地市場跡地外です)
最後の建物の駐車場を壊しているところです。
これで更地になり、アト色々な建築物が出来るのでしょうね。この写真の遠方のビルの間に「東京タワー」が見えます。
返信しました。
⇒「森山さん 貴重なショットですね。ありがとうございます。
こうして森山さんが撮影した写真を見ると築地市場が位置した土地は
ゼネコンや大手デベロッパー業界に狙われて当然のことがよくわかりますね。」

「人間として、何もせず、何も言わず、不正に立ち向かわず、抑圧に抗議せず、また、自分たちにとってのよい社会、よい生活を追い求めずにいることは、不可能なのです。 」
ネルソン・マンデラ
だが、日本では「和を以て貴しとなす」が金科玉条で、「沈黙は金」で、「みなさまのおっしゃる通り」が強制される。
あの東条英機ですら「私が開戦を決めたのではない。下から上がってきたことだ。」と責任無しを正当化する。
最初は「まだ誰も戦争するなんて言っていないのに、反対を叫ぶなんて」と言い、
過程では「空気を読め、場違いな発言はするな」と言い、
最後には「決まったことにとやかく言うな。従うのが当然だ。」と押し付けられる。
「ムラ政治の安定」と「差別」とはセットだったのではないか。多数派にくっついていないと自分がイジメられるという理屈か。
農村の宮座の村方三役と地主小作水飲のムラ秩序は企業そのものとなり、社内の派閥となり、役人のセクト主義となり、原子力ムラになり、対米従属ムラとなった。
網野善彦は土地に縛られた農民とは別に海の民、山の民、の存在の大きさに注目し、「百姓=農民」ではないと主張した。
「村八分を恐れた」社会だけが日本の流れの全てではないはずだ。
「普天間基地の県外移設は出来ないと20年前から決まっている」って、いったい誰が決めたんだ。
山本スイカ メールマガジン「 少数異見 聞いても聞かない、見えても見ない」 No.196(2022.6.5)から引用。
赤銅色に見える種類は「ツタンカーメン」/紫えんどう豆。宅急便を開いたらたっぷり頂いたのでおすそ分けにも回そうとおもう。
早速卵とじにしてもらって食べたが、新鮮でなんともおいしい。


平川ファームさん、いつもありがとうございます。


おすそ分けした一家から写真が届きました。5/22 追記

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
会社で平川さんが所属した事業本部は東京・田無にあり、私も自分が所属した事業本部が東京・神田だったせいか、
大阪支社の各営業部の社内配置では 二人が所属したそれぞれの営業部は フロアーのはしっこの隣同士になった。
二人は 出会ってすぐに互いに話をかわすようになり 定時過ぎに在社していて目が合えば 隣のビルの地下にある「小ぼけ」で飲むようになった。
他の人と飲む時より平川さんと飲む時は結構な量の日本酒を飲んでいたような気がする。薩摩人である平川さんは酒も強かった。
呑み助同士ということで知り合ったが、彼も私も会社の「久富さん」という方をリスペクトしていたのも共通していた。
1997年に阿智胡地亭は大阪支社から広島の中国支社に転勤になったので、現役時代に一緒に飲むのはその時点で終わった。
初めて飲みだしてから30年近く経ったが、互いにその後 退職してからも連絡を取り合って、機会があれば神戸、大阪、東京と一杯やるご縁が続いているのはありがたい。
(栗山英樹・著 『稚心を去る』より再構成)
「稚心」とは「子どもっぽい心」のこと。
それを捨て去らない限り、何をやっても決して上達はしない、とても世に知られる人物となることはできない。
まずは「稚心を去る」ことが、立派な武士になるための第一歩である。
幕末に生き、わずか25年という短い生涯を駆け抜けた武士・橋本左内は、数え年で15歳のときに、このようなことを書いている。
いまも読み継がれる『啓発録』は、彼がこれから生きていく上での指針、強い決意のようなものをしたためたものだ。
時代が違うとはいえ、これが、いまでいう中学生が打ち立てた「志」かと思うと、心から感服する。
そしてこの「稚心を去る」が、人の能力を引き出すためにはとても重要な意味を持ってくると、最近、強く感じている。
成長を妨げているのは「子どもっぽい心」、要するに「わがまま」であるケースが多い。
みんな心の中に「大人の心」と「子どもっぽい心」が共存していて、うまくいかないと、すぐに「子どもっぽい心」が出てきて、人を「わがまま」にさせる。
そして、余計なことまで考えて、いつもイライラしている。はっきり言って時間の無駄、何もいいことがない。
これはいま、日本という国が抱えている多くの問題にも直結しているのではないだろうか。
様々なニュースに触れるたび、よくそのことを思う。心が子どもであるがゆえ、大人になり切れていないがゆえのトラブルはあとを絶たない。
そういう自分も、まだ子どもだ。
でも、この7年間(編集部注:本稿はファイターズ監督8年目に執筆した)で、大人になるスピードは間違いなく加速させてもらっていると思う。
自分を捨てて、人のために尽くすということを、まだまだできてはいないけれど、真剣に向き合えるようにはなってきている。
だからこそ「子どもっぽい心」を出させてしまったときは、いつも責任を感じてしまう。
どうして「大人の心」を引き出してあげられなかったのか、と。
結果が出ていれば、自然と「大人の心」が出てきて、誰でも「チームのために」となる。
プロの世界は、特にそう。結果が出て、みんなが気分良くやれているときは、驚くほど「大人の集団」。
難しいのは、結果が出ていないときにどうやって「大人の心」を引き出すか。
きっとそれを引き出すのが、監督の仕事なんだと思う。
「稚心を去る」、これがすべてだ。
作品のモチーフになった「真柏」は 小豆島八十八ヶ所霊場54番札所宝生院にあります。
:境内には応神天皇御手植と言われる大真柏がある。この大真柏は高さ二十四メートル、幹の周囲十六メートルもあり、
樹令二千年という世界一の折紙がついている。大正十五年に特別天然記念物となっている。島の観光客は一年を通じて多数見物にやって来る。
(朱鷺書房発刊の『小豆島八十八ヶ所』より抜粋)




会場の風景

今年の大賞

面白いなと思った作品

長谷川さんの画の他作品との「構成」の違いに気が付いた。
そして毎年の作品に通底する「継続する一つの生命に対する畏敬の念」が今年も胸に迫った。
やはり長谷川さんは目には見えないイノチの「生老病死」を彼の創造の基底に置いていると思う。
しばらくじっと観賞したが どの位置のどの部分の細部を見ても 全く彼の送筆の結果はゆるぎなく変わらない。
57年前に愛媛県新居浜市の工場独身寮でおなじ時空を過ごした「ちょーさんこと長谷川さん」がいま上野の東京都美術館で作品を掲示している。
それを自分が上野で観賞することが出来るご縁はありがたく嬉しい。
2021年に日中水墨大賞を授与された長谷川さんの作品「北限アコウの生命力」 click→関連エントリー

昨年3月11日掲載エントリーの一部
上野の東京都美術館はぼちぼち人の姿があった。


長谷川さんの作品は 穏やかな画面に阿蘇の湧水が豊かに流れていて 眺めていると気持ちが落ち着いた。
やはり構成がいい。細心の送筆の緻密さがもたらす完成度の高さに今回も感嘆した。

昨年は長谷川さんの作品clickが日中水墨大賞を取った。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
杉本さん ご教示いただきありがとうございました。
友人の森山さんから勝どきのタワーマンションの地上40階の展望室から眺望した写真を送ってもらいました。
⇒「手前が隅田川、左から浜離宮→中央やや左の白くて広い面のビルが今ウワサの電通ビル<現在売却済み>
そこから右に 茶色の朝日新聞社→がんセンター→白くて高いビルの歌舞伎座が見えます。そのあたりから銀座です。
そして大きな土地が現在の築地市場跡です。」
◎このような位置からの眺望は初めてです。 にしても築地市場跡の広大な面積には驚愕します。
貴重で歴史的な、ある意味日本という国の施設を、ある時期に在籍した都庁の幹部公務員が売却を計画し 実行したという事実を目の当たりにする景色ですね。
いずれ築地市場の跡地は新しい高層ビルが林立する街になるでしょうから貴重な記録写真でもあります。
丸い大根は青皮紅心大根・紅芯大根(あおかわこうしんだいこん)か?

ムラサキ山芋は 見るたびに土の持つ強烈なエネルギーが凝縮したものだと感じる。
いくつもある多様な日本人のルーツの一つとして、アウトリガーを付けた大型丸木船に乗ってポリネシアやミクロネシアから
島々を伝って日本列島に渡って来た人々がいるが、彼らは大地のパワーに満ちたタロイモなど芋類を長期の航海の保存食料として載せていたそうだ。


箱には無駄な空間はなく きっちりと多様な野菜がパックされていた。ありがとうございます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
本ブログに最初にムラサキ山芋が登場したのは2011年のこちらです。☟は2013年12月23日掲載。
ムラサキヤマイモの旨さには参りました。

6年使っていた炊飯器が不調になったので、新しくT社製の炊飯器に買い替えました。硬さや柔らかさなど設定の範囲が広く、何日か試行錯誤してようやく
好みの炊き上げの設定が確定したので、満を持して国東半島は平川農園の「ムラサキヤマイモ」で「とろろご飯」と相成りました。

最初すり鉢で始めましたが、芋の密度?が高いために作業が進まなく、やはり例年のようにおろし器を出してきました。
おろし器で下してからすり鉢に移しますが、何しろ粘りが凄くて移すのに苦労します。
(自然光で写ったおろし器から落としているムラサキ色が実際の色です。電燈の光で撮影した画像は白っぽく写ってしまいました)
おろし器にへばりついたのは、爪楊枝で掻き取りました。
トロロをもっと滑らかにするために、すりこ木で仕上すりをします。何とかおろし器から移して出汁と共によく摺りましたが、
普通の山芋の何倍もの力と時間がかかります。
ようやく完成です。
炊きあがったご飯にかけて頂きました。う~ん、と唸ったまま二人で黙々と噛みしめました。まさに比類なき旨さです。
同じく平川農園産のキャベツは噛みしめると昔のキャベツの味がします。味にも厚みがあるという感じです。
今回は大きな方の芋の半分を使ったので、これから残った半分と小さいムラサキヤマイモとあと2回か3回楽しみが
待っています。それにしても「ムラサキヤマイモ」の芋とは思えない粘りと味に今回も感歎しました。

佐藤さんとは1966 年の4月に、当時大阪の淀屋橋にあった本社の入社式で出会ってからの付き合いだから
既に56年を閲したことになる。佐藤さんは四国の工場の独身寮の時代に同期入社の生田さんから絵画の道に誘われたそうだ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2018年6月18日のアカデミー展掲載エントリー
会場は御徒町駅南口を出るとすぐのMontBellの4階だった。

友人の佐藤君の作品。小品だが存在感を放っていて気持ちが鎮まる版画だった。

作家と作品
作品の完成までのプロセスや使用された技法や団体の歴史などの解説を伺った。特に毎週見ているNHKの日曜美術館で前に放映された
英国のダイアナ妃の執務室に飾られていた日本の木版画の作家がこの団体の創設者だという話には驚いた。
帰りは一駅秋葉原駅まで歩いた。AKB48劇場の前はかなりの人で賑わっていた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ダイアナ妃の執務室には吉田博の版画が飾られていた。

吉田博の作品






吉田 博は、もともと水彩画・油彩画の画家でアメリカではある程度成功をおさめていましたが、49歳で木版画の道へ進みます。
その作風は、水面に写る船の影のゆらめき、山頂に朝日があたる一瞬の光、水の流れや光のうつろいなど、驚くほど繊細に表しています。
吉田 博の版画の特色として、平均30版以上といわれる多色刷り、細部での亜鉛凸版の使用、大判木版画などがあげられます。
なかでも帆船シリーズに代表される、同じ版木を用いて色を替えて刷る時間や気候の変化を表した同版色替の技法は大きな特色のひとつです。