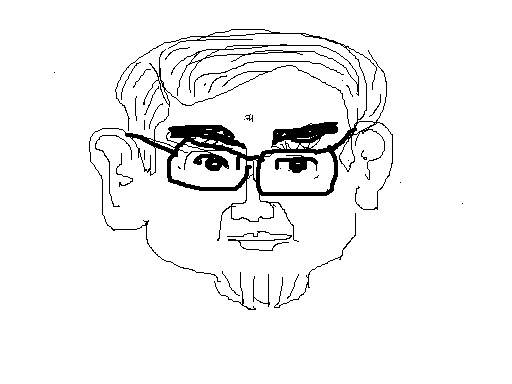2005年1月11日の夜、何年かぶりでNHKの「プロジェクトX」を見ました。
自分が大阪勤務時代、10年間通勤駅として利用したJR東海道線の六甲道駅復旧工事がテーマと新聞に紹介記事が出ていたからです。
地上の星 / 中島みゆき [公式]
1)「プロジェクトX」はだいぶ前に「新潟のコシヒカリ」をテーマにした番組を見てからは、身内にご縁があった古野電気さんの
「漁船用魚群探知機の開発」の回を見たくらいで、後は殆どまともに見たことがありません。
「コシヒカリ」の開発のプロセスをテーマにした回は、開発者の苦労やプロセス自身は面白かったのですが、
番組の構成とナレーションのシナリオに驚きました。
この回は「善玉」の開発者に対し、立ちはだかる障壁として「悪玉」に時の新潟県知事を配し、完全な勧善懲悪ドラマに仕立てられていました。
何度も何度も大写しされ、全てに邪魔をし続けたかのように表現される悪代官ヅラそのものの当時の知事さんが、だんだん気の毒になってきました。
もう亡くなれていたようですが、遺族の方々はとても正視出来ないだろう内容でした。構成には、なんのヒネリもわずかなエスプリもありませんでした。
日本各地に、NHKの放送内容は絶対間違いないと思っている日本人がまだまだ多いのに、こんな取り上げられ方をして、
もし奥さんなど遺族が新潟に住んでおられたらお気の毒と思いました。そんな配慮は微塵も伺えませんでした。
このとき「プロジェクトX」も、番組の創生期に汗を流したスタッフが去って、
安定して視聴率を取れるようになってから担当した第二世代の連中が、人気の上にあぐらをかいて傲慢で楽な方法で作りだしたなあと思いました。
2)もともとこの番組は、対象がどんなに素晴らしい開発や社会的功績のあるプロジェクトであっても、ラジオ番組ではなくテレビ番組ですから
「映像」が入手出来ない場合は番組化出来ないという大きな制約があります。
つまり、成るか成らないかわからないままプロジェクトに専念し、記録写真やスナップ写真が残っていなければ、
その事柄の価値とは無関係に番組として取り上げられないのです。
おそらく「プロジェクトX」という番組の企画を発案し、実現した初期の製作者とそのスタッフは、持ち込まれるネタではなく、
自ら全国を走り回って対象を探し、しかも選別し吟味して製作していたような気がします。
番組スタート時に見ていた私は、文句をつける余裕も無く、♪風の中のすばる~と「地上の星」が流れだし、「ヘッドライト・テールライト」の
エンデイングが消えていく時間まで、この番組にじっと身を浸らせてもらっていたような気がします。
3)今回の<「鉄道分断 突貫作戦 奇跡の74日間」~阪神・淡路大震災~>を見ていたら、自分が経験した「JRも阪急、阪神も甲子園あたりで不通になったため、
始めは代替バスで一番近い駅まで行くしかなかった。通勤ルートは毎日変わった。最寄りのJR六甲道駅は地震の瞬間に崩壊して東海道線がここで長いあいだ断絶した。
阪神青木まで2時間ほど歩いた事もあった。」頃を思い出しました。 (阪神淡路大震災の体験記click)
ここまで大変な工事だったことは、この番組を見るまで知りませんでした。
映像的には、震災で崩壊した駅のシーンは、当時を思い出してあまり見たくはなかったのですが、今も乗り降りする駅がこんなんだったんだと、
自分が今は記憶から当時の情景を押しのけていることにも気がつきました。
そして最後の完成試験で、上下逢わせて4軌道のレール上を各2両連結の機関車が4台同時にスタートし、
平行走行して、桁のタワミをチエックする場面は迫力がありました。
当時我々に聞こえてきたのは、東海道線がここでブチ切られ、日本列島全国輸送の大動脈が機能しなくなったことから、
また戦争突発に備え、国家として威信をかけて金に糸目をつけない突貫工事にかかったという話でした。
この24時間昼夜を問わない、金に糸目をつけないお上の工事のため、重機や建設資材、工事人員がこの工事現場に独占され、
阪急や阪神のような私鉄では、六甲道駅が復旧するまで工事の着手も出来ないということでした。
確かに阪急と阪神の復旧工事は大幅に遅れました。ただ利用者にとっては大阪と神戸の間のいわゆる阪神間には阪神,JR、阪急という
3本の路線が平行して走っているため、どれか一本が復旧すれば何とかなるという面がありました。この震災の後、復旧費用がかさんだこと、
乗客の減少などで両私鉄のバランスシートが一挙に劣化したことはまた別の話としてあります。
今回の番組のシナリオは、工事業者の奥村組が提供した工事記録ビデオと写真類をメインに構成されたためか、
余震をかいくぐり短時間で大変な工事を貫徹したという美談仕立てに終わり、番組制作者の固有の視点が初めから終わりまで感じられませんでしたし、
近辺の住民からの感謝と暖かい応援という添え物の時間も結構長く感じられました。
なんか作る方に「泣かせるノン作ったやろ、人間の思いやりの気持ちを思い起こそう」という、上からさとしてくれるような傲慢さがあるのを少し感じました。
ほぼ5年間、同じコンセプトのドキュメンタリー番組を作り続けるのはしんどい。
毎週毎週、企画当時のレベルを維持するのは、ネタ切れもあり、もう無理なんだろうとも思いました。
浮かれ節(講談の前身)のイントロではありませんが、テレビは、
「・・・これじゃからとて皆様方、現場見てきてやるのやおまへん、昔作者が暗い行燈のその陰で書いて残した筆のあと、筆に狸の毛がまじる。
嘘かほんまか知らんけど、本当らしゅうにやりますさかいに聞く皆様もその通り、たとえ嘘じゃと思うても本当らしゅうに聞いてもらわにゃ仕様がない、
一生懸命に勤めまするで、しばらくの間お遊びを給わる。」なんだと思います。
テレビが普及しだした頃に大宅壮一という人が、テレビのことを「電気紙芝居」と言いましたが、作る方もかっこつけずにそう思って作り、
見るほうもそう思って見れば、テレビも「なかなかおもろいもんではないかいなア・・・・」
この年の12月にこの番組は終了し、最後の番組に【中島みゆき】さんがライブで登場してエンディング曲を歌った。
2005年1月12日記
ヘッドライト・テールライト 中島みゆき【cover】