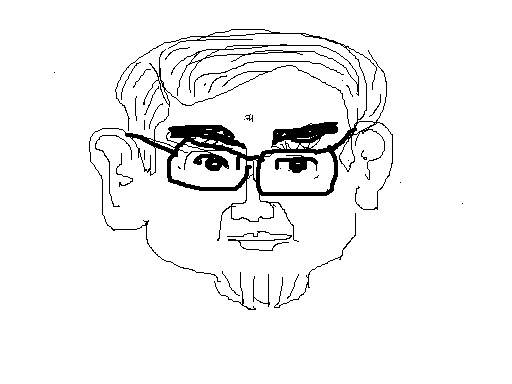少しでも長生きさせる医療が続いている理由
佐々木 淳(以下、佐々木):実は病院で亡くなる方で、悲しい状態で死を迎えるケースは少なくありません。入院先で、あなたはこの病気だからお風呂には入れません、
こういう状態だからご飯は食べられません、家にも帰れませんなどと言われて、本人としては、残された時間をこんなふうに過ごしたいと願っていても、
それがかなえられることは、あまりない。
最期の時まで病院で医療を受けるというのは、自分の生活が医師に支配されるということでもあるんです。
井手:医療を施すことで、少しでも長生きさせる。それが第一なんですね。
佐々木:多くの医師は、患者さんを1分でも1秒でも長く生かそうとしますから、患者さんが自力ではもう動けなくなっても、点滴と酸素投与で生かされるということが起きます。
医師自身は、そんなことしたくはないと思っていても、治療を中止したら家族から訴えられるかもしれない。あるいは、点滴をすれば食事ができない患者さんも、
もう少し長く生きられるかもしれない。そんなふうに治療が行われるということが結構長く続いてきました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
井手:患者さんだって、「自分の死」を選びたいはず。でもそれに抗えば、結果は自己責任という話になってしまいますよね。
佐々木:そうですね。ただ最近は、患者さんの側から、自分たちが受けたいのはそういう医療じゃないと、声が上がるようになってきています。
医師の側からも、実は自分たちもやりたくないと意思表示をするようになってきた。こうした話し合いの中で、望まれない医療は徐々に減ってきています。
患者さんの命の終わりが近づいてきて、医療によってもその状況を変えられないなら、われわれがやるべきことは、無理に命を延ばすことでも縮めることでもなく、
その人がもっている本来の時間を、できるだけいい形で過ごしていただくことだと思うんです。私の仕事は在宅医療ですが、
そこで重要なのは、最後までその人が望む生活が続けられるようにお手伝いすることなんですね。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
人生をどう「下山」するか
井手:3世代同居が激減して、人間が年を取ること、愛する人が死んでいくことを、子どものときに体験できない人が増えてますものね。
佐々木:おばあちゃんの体が弱ってきて、寝ている時間が長くなっていき、ご飯を食べず、水も飲まなくなって、だんだんと呼吸が弱くなっていく。
これは老衰という当たり前のプロセスですが、初めて目にすると、点滴したほうがいいのでは、とか、何か治療が必要なんじゃないかと思ってしまう。
人間がどう成長していくかは誰もが知っていますし、人生の高みを目指すための情報はたくさんある。
ですが、人生をどう「下山」すればいいのかという問いは、後回しにされている印象です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
人は地域の中で生きている
佐々木:そうですね。それで言うと、社会の中に居場所とか役割があると、それが生きがいにつながっていくと思うので、コミュニティーの役割もとても大きいと思っています。
こうした議論では、お年寄りが人間として扱われていないんですね。その人が、それまで培ってきた人間関係から暴力的にいきなり切り離されてしまうわけですから。
こうして佐々木さんのお話をうかがっていても、あるいはソーシャルワーカーの仲間たちから話を聞いても、地域の中で人は生きているという当たり前の
事実をとても大事にしていることが伝わってきます。僕はそこにすごく共感するんですよね。
全文 クリック☟




























 楽屋ネタ。
楽屋ネタ。