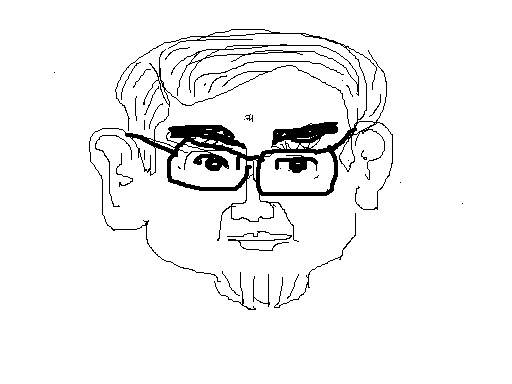日本政府が入国制限を決断できなかった本当の理由
外国人がいないと業務が回らない!あぶり出された日本社会の実態
<iframe class="hatena-bookmark-button-frame" title="このエントリーをはてなブックマークに追加" width="86" height="20" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
政府は1月13日になってようやく重い腰を上げ、これまで続けてきた入国緩和政策を一時停止すると発表したが、決断が遅すぎたというのが大半の国民の見解だろう。
政府が入国制限に消極的であることはハッキリしているが、なぜ入国を制限したくないのかという理由については「経済優先」といった抽象的な理由だけで報じられることが多かった。確かに、外国との行き来があった方が経済的には望ましいだろうが、とりあえずモノの輸出入が存続していれば、経済活動の大半は維持できる。感染拡大のリスクを考えれば、天秤にかけるような話ではないだろう。
あらゆるリスクを引き受けてでも、緩和策を維持する必要性は薄く、その意味ではメディアの報道も「なぜ?」という国民の疑問を解消する内容とは言い難かった。一部の論者は中国や韓国など、特定の国を名指しした上で、政府がこうした国々に対して遠慮していると厳しく批判していた。だが、政府がこれらの国に遠慮し、あえて入国制限を実施しないというのは少々考えにくい。
特定の国のせいにすることは、ストーリーとしては分かりやすいのだろうが、このロジックはあまりにも短絡的で幼稚だ。政府が明確に理由を示していない以上、推測するしか方法はないが、統計から判断する限り、政府が入国制限に消極的な理由はハッキリしている。
<iframe id="google_ads_iframe_/6213853/pc_inread_0" title="3rd party ad content" name="google_ads_iframe_/6213853/pc_inread_0" width="1" height="1" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" data-google-container-id="a" data-load-complete="true"></iframe>
ビジネス上の往来の実態は技能実習
出入国在留管理庁の統計によると、一連の入国緩和措置を使って12月(11月30日から12月27日)に入国した外国人のうち、もっとも数が多かったのは中国人で1万5109人だった。次いで多かったのはベトナム人(1万4432人)、その次はインドネシア人(2991人)となっている。入国者の総数は約4万5000人なので、この3カ国で全体の70%を占めていることが分かる。
入国者の資格を見ると、ベトナム人のうち65%が、インドネシア人のうち62%が技能実習となっていた。中国人は留学というケースも多く、技能実習は全体の4割程度だが、それでも比率はかなり高い。つまり緩和措置で入国した人の7割は3カ国に集中しており、しかもその大半は技能実習生である。
ここまで来れば、もはや詳しく説明する必要はないだろう。
ビジネス上の往来というのは、いわゆる国際的なビジネスではなく、入国制限の緩和は、低賃金労働に従事する外国人を確保する目的であったことが分かる。中国や韓国に遠慮しているのではなく、国内産業の事情で入国制限を実施できなかったというのが真相である。
外国人技能実習制度は、新興国の外国人を対象に日本の企業で働きながら専門的な技術や知識を習得するための制度である。だが現実には、安い賃金で外国人労働者を雇用する制度として機能しており、一部の事業者は、賃金の未払いや過重労働、劣悪な宿舎など、労働法制を守っていないと指摘されている。
日本は外国人労働者の受け入れについて「高度な専門知識を持つ人材に限る」としており、単純労働者は受け入れないというのが従来からの方針だった。国内世論も外国人労働者を拒絶する風潮が根強かったが、これはあくまで建前に過ぎない。企業の現場では単純労働に従事する外国人がいないと業務が回らないというのが現実となっており、政府は矛盾した状況に対応するため、技能実習という制度を設け、あくまでも“実習”という名目で単純労働に従事する外国人を受け入れてきた。