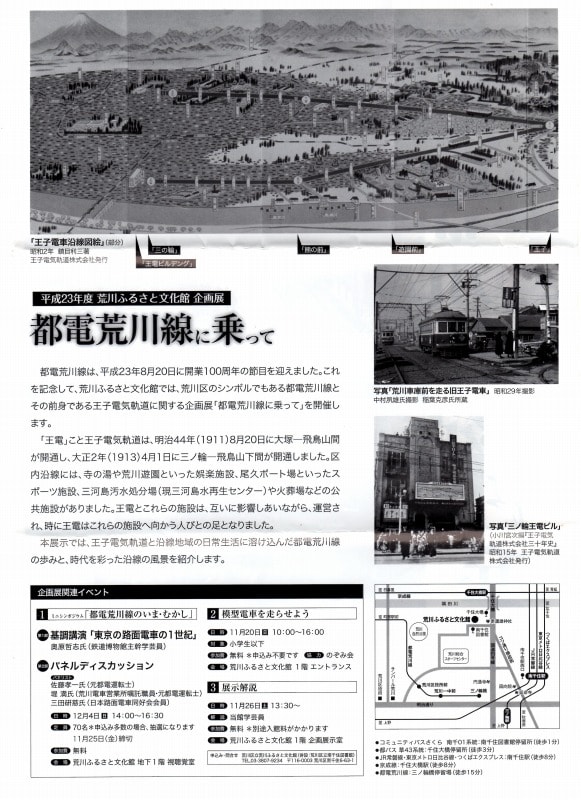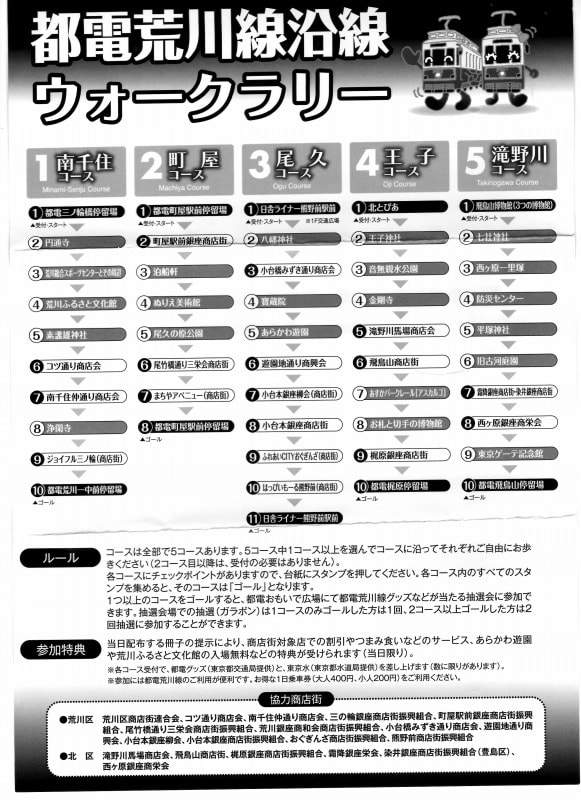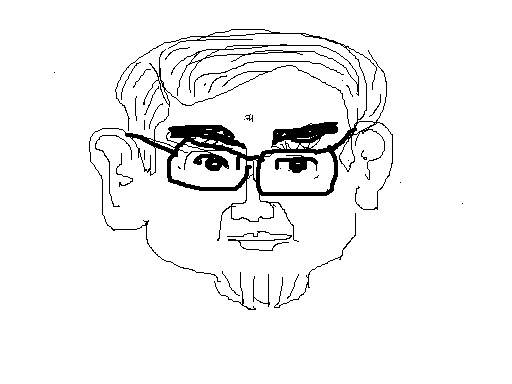翌日、11人のうち希望者の5人が阪急六甲駅から、記念の催しがある六甲台に上がりました。
いい天気でした。45年前と同じように神戸の街並みが眼下に広がっていました。
ただ前にはなかった人口島のポートアイランドと六甲アイランドが景観を変えています。
そして、阪神淡路大震災で亡くなった留学生を含む学生の慰霊碑がキャンパスに建立されていました。
記念式典の司会は卒業生の一人、NHK大阪の住田アナウンサーでした。
また構内には俳人の山口誓子さんの記念館が出来ていました。
画像の真ん中をクリックしてスタートし、拡大アイコンをクリックして大画面でご覧ください。
いい天気でした。45年前と同じように神戸の街並みが眼下に広がっていました。
ただ前にはなかった人口島のポートアイランドと六甲アイランドが景観を変えています。
そして、阪神淡路大震災で亡くなった留学生を含む学生の慰霊碑がキャンパスに建立されていました。
記念式典の司会は卒業生の一人、NHK大阪の住田アナウンサーでした。
また構内には俳人の山口誓子さんの記念館が出来ていました。
画像の真ん中をクリックしてスタートし、拡大アイコンをクリックして大画面でご覧ください。