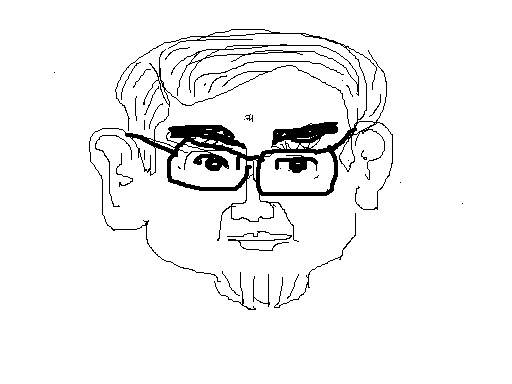両国の江戸東京博物館のダヴィンチ展を見た後、ずっとご一緒した森哲雄さんと両国から錦糸町へ、地下鉄半蔵門線に乗り変えて二駅、曳船駅で下車して駅の目の前の「七七」に入りました。
店内はそう広くありませんがゆったりした雰囲気の店でした。クジラを売りにしている店でおいしく楽しみました。
サシミ

竜田揚げ

ベーコン

煮込み

イカ焼きなども。

この店は吉田類のテレビ番組「居酒屋放浪記」で知りました。
店名 七々
ジャンル 居酒屋
TEL・予約 03-3610-0882
住所 東京都墨田区東向島2-16-16 1F
交通手段 曳舟駅から72m
営業時間 17:00 ~ 00:00
夜10時以降入店可、日曜営業
定休日 第3水曜
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
昭和20年代当時は家でカツを食べるなんていうことはありませんでした。
当然外食などという事は全くありませんから、おそらくカツと言うのは小学校の給食で鯨のカツを食べたのが初めてだったでしょう。
小学校3年生までの九州の若松市二島の島郷小学校ではまだ給食は脱脂粉乳のミルクとコッペパンくらいでしたから、
鯨のカツが出たのは尼崎市の塚口小学校か四日市の納屋小学校かのどちらかだと思います。
硬い硬い肉のカツに早くにかけれらたソースがへばりついている。それでもこんな旨い物があるのかと思って食べました。
最近は調査捕鯨の鯨の肉があまって、結構鯨肉がスーパーなどにも出回っているので、時々家でも作ってもらいますが、喜んで食べるのは私だけなのが寂しい。
また、居酒屋のメニューに鯨関係があればついオーダーしてしまいます。
後に東京勤務のおり、鯨肉の旨さの話をしたら関東の人は誰も乗ってきませんでした。あんな不味いものというのです。
あるとき漁業関係にいた人に聞いたら、古代から鯨をよく食べてきたのは西日本で、しかも鯨も和歌山の太地のように西日本各地でよく取れていた。
戦後、全国に鯨肉が流通するときも「鯨の美味しいところ」は西日本で販売し、東日本は肉にしてから日数が経つ上に、あまりいい肉はいかなかったと聞きました。
それであんな不味いものと言う理由がわかりました。当時の貨車やトラック輸送ではそのハンデイもあったと思います。
いずれにせよ私にとってはこれからも憧れの一品であり続けます。
2006年9月6日 「阿智胡地亭の非日乗」掲載