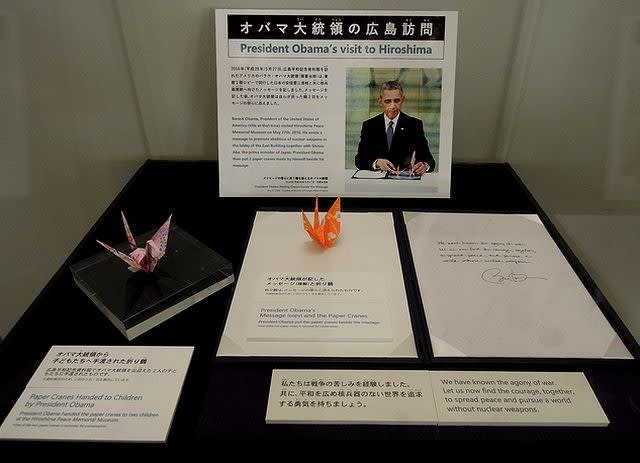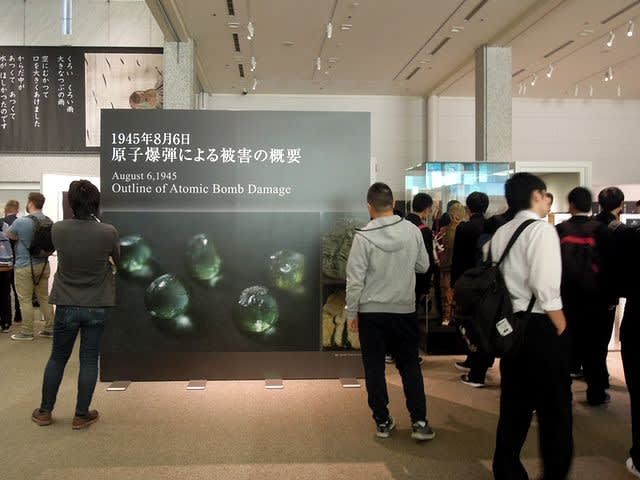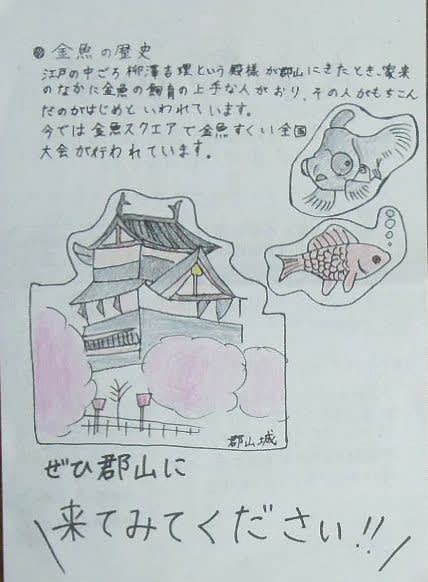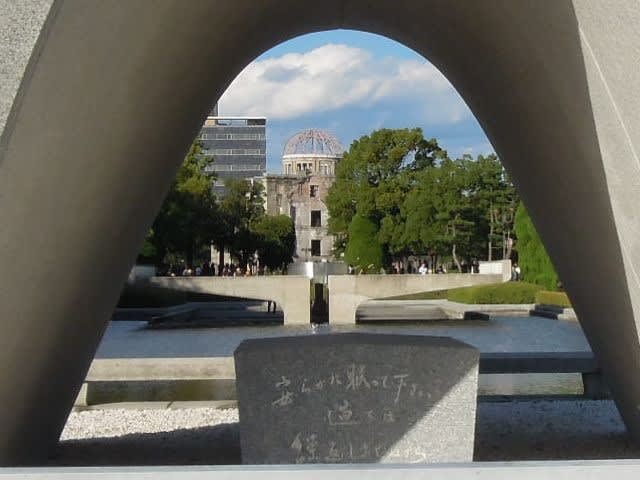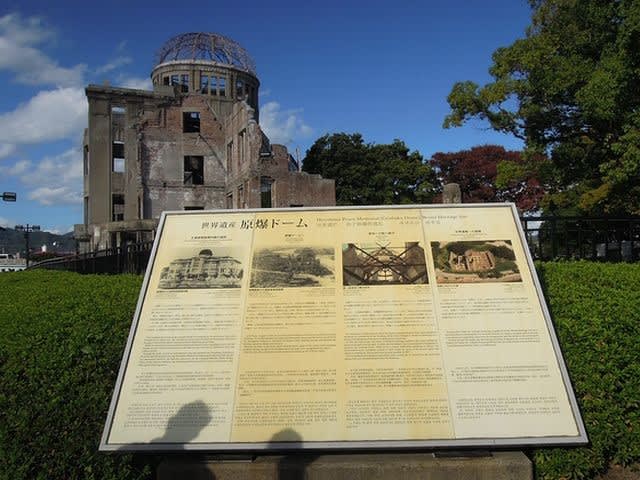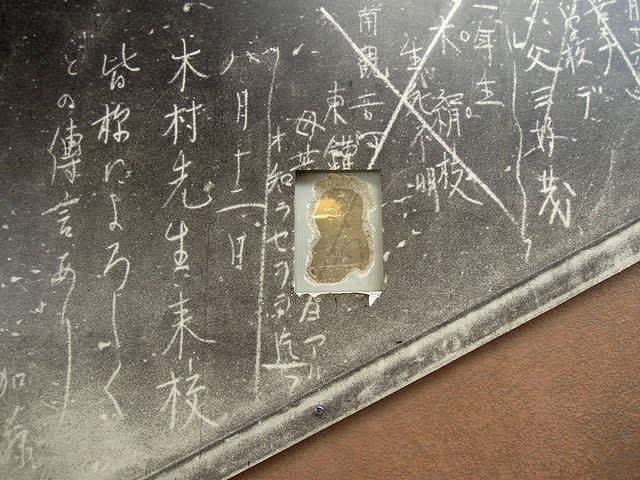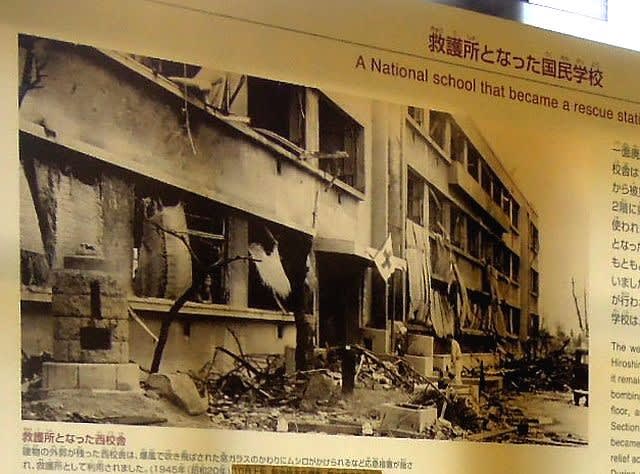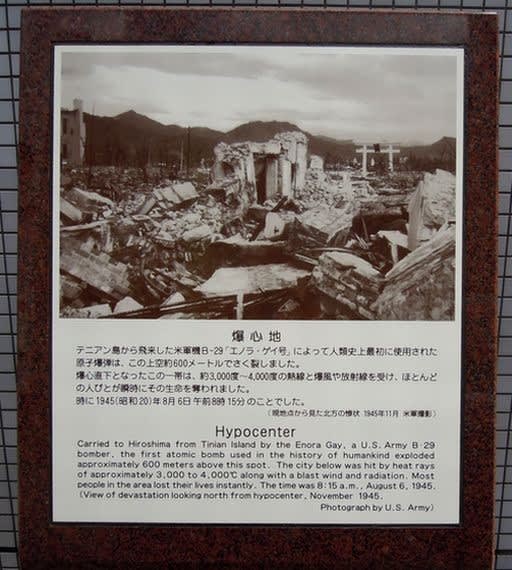JR宮島フェリーに乗って宮島へ

大鳥居が見えてきました。

私たちが乗ってきた「みせん丸」

平和記念公園で会った奈良の子供たちも
宮島に行くと言っていたので
この宮島のどこかにいるのでしょうね。

厳島神社を横目にして

五重塔を通り過ぎ、
宮島ロープウェイ乗り場「紅葉谷駅」に向かっています。

厳島神社の裏門に「尻上がりの狛犬」があります。

友人が声を掛けてくれなければ見過ごしてしまいそうでした。

お尻があがっていることから「尻上がりで縁起が良い」と言われています。

ロープウェイは「紅葉谷駅」から、獅子岩駅に向かっています。
まだ紅葉には早いですが、弥山の原生林や瀬戸内海を望む。