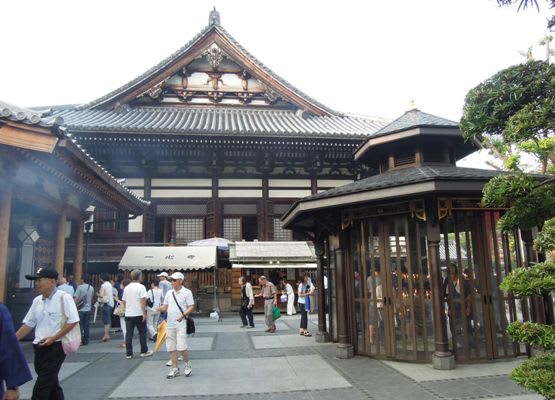新型肺炎で有名に・・・中国「武漢市」ってどんな街?(20/01/23)
中国の衛生当局は、症状が出ていない潜伏期間でもウイルスが他人に感染すると指摘しています。
新型コロナウイルスによる肺炎の感染が世界的に広がるなか、フィリピン当局は中国の武漢から到着した500人近い観光客を送還することを決めました。アメリカ政府、韓国、フランス政府などは、体調不良が無くても武漢から帰国した人は検査と経過観察のために最長2週間にわたり臨時の居住スペースに隔離する方針です。
日本では、新型コロナウイルスの感染が武漢からだと知りながら武漢からの旅行者を受け入れ、チャーター機の第1便で29日に武漢市から帰国した日本人のうち、ウイルス検査も受けず身勝手にも帰宅した2人がいました。その身勝手な2人が「検査受けたい」と申し出たそうです。その記事は・・・こちら
武漢からの旅行者を受け入れ、帰国者の身勝手な行動が許される日本政府の対応に失望です。奈良・三重・大阪・京都・東京でも感染が確認され、国内で確認された感染者はあわせて14人になったと発表されました。
中国の衛生当局は、症状が出ていない潜伏期間でもウイルスが他人に感染すると指摘しています。
新型コロナウイルスによる肺炎の感染が世界的に広がるなか、フィリピン当局は中国の武漢から到着した500人近い観光客を送還することを決めました。アメリカ政府、韓国、フランス政府などは、体調不良が無くても武漢から帰国した人は検査と経過観察のために最長2週間にわたり臨時の居住スペースに隔離する方針です。
日本では、新型コロナウイルスの感染が武漢からだと知りながら武漢からの旅行者を受け入れ、チャーター機の第1便で29日に武漢市から帰国した日本人のうち、ウイルス検査も受けず身勝手にも帰宅した2人がいました。その身勝手な2人が「検査受けたい」と申し出たそうです。その記事は・・・こちら
武漢からの旅行者を受け入れ、帰国者の身勝手な行動が許される日本政府の対応に失望です。奈良・三重・大阪・京都・東京でも感染が確認され、国内で確認された感染者はあわせて14人になったと発表されました。