2020年11月20日に「津の田ミート エミル高槻店」が、オープンしているので
阪急高槻市駅の近くへ行った時に見てきました。(^^ゞ
津の田咖喱 エミル高槻店

カレーのボリュームが選べるようです。
少なめ:ライス150g 多め:ライス250g
普 通:ライス200g 大盛:ライス300g
※大盛まで無料サービス

カレーは全種類、テイクアウト出来るようです。
容器代などで+50円
津の田ミート エミル高槻店

隣のお店も「津の田」です。

こちらは、ステーキ、ハンバーグ のお店でした。
ハンバーガセット・カツサンドセット・オムライスセットなども
テイクアウト出来るようです・・・(^^ゞ
大阪府高槻市城北町2丁目1−18 阪急高槻駅 構内2階
電話番号 072-661-1189 事前予約:090-1591ー0272 がおススメ
阪急高槻市駅の近くへ行った時に見てきました。(^^ゞ
津の田咖喱 エミル高槻店

カレーのボリュームが選べるようです。
少なめ:ライス150g 多め:ライス250g
普 通:ライス200g 大盛:ライス300g
※大盛まで無料サービス

カレーは全種類、テイクアウト出来るようです。
容器代などで+50円
津の田ミート エミル高槻店

隣のお店も「津の田」です。

こちらは、ステーキ、ハンバーグ のお店でした。
ハンバーガセット・カツサンドセット・オムライスセットなども
テイクアウト出来るようです・・・(^^ゞ
大阪府高槻市城北町2丁目1−18 阪急高槻駅 構内2階
電話番号 072-661-1189 事前予約:090-1591ー0272 がおススメ
































































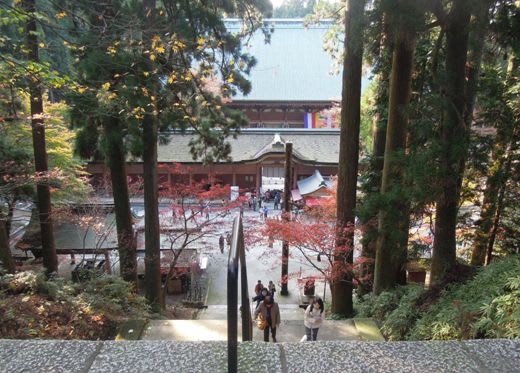



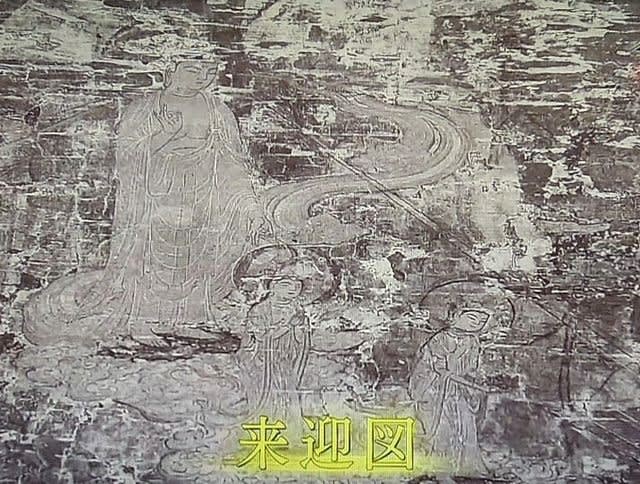





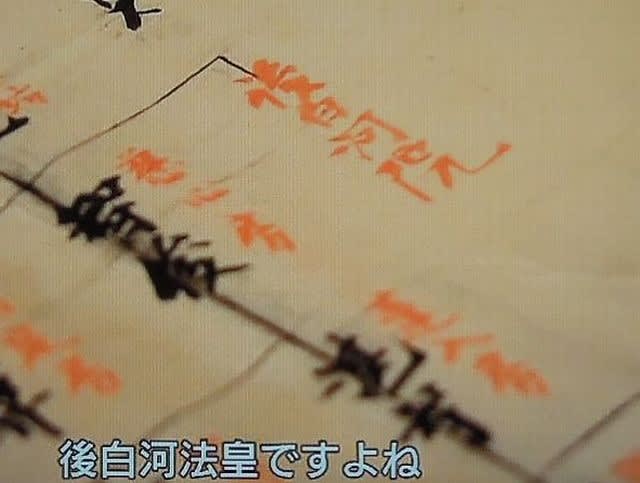











 が運ばれてきました。
が運ばれてきました。




















